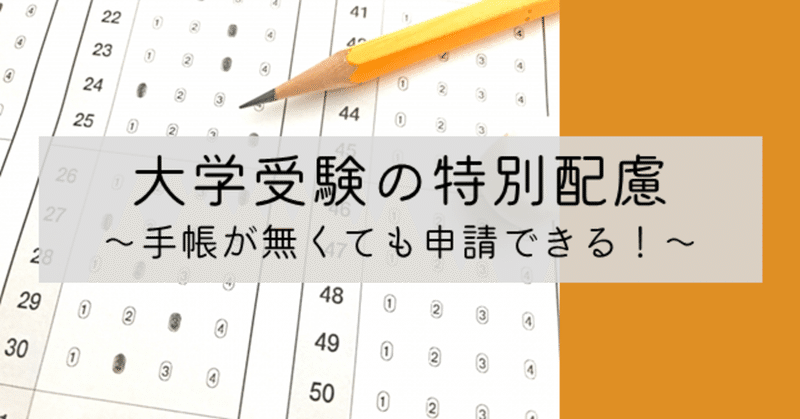
大学受験の特別配慮~手帳が無くても申請できる!~
以前はてなブログで書いた記事と同じ内容です。
noteにすべての記事をまとめたいと思い、再投稿しました~。
ちょうど大学受験の合格発表が終わるころではないでしょうか?
年の離れた弟が大学受験を終え、私も受験から入学までのバタバタを思い出しています。
様々な思いを胸に、大学を目指して頑張る受験。
受験生は不安を感じる場面もあるかもしれません。
ということで、今回は6年前に経験した【大学受験の特別配慮】についてまとめます。
障害者手帳が無くても、いつも(恒常的に)症状が出てなくても大丈夫です。
心や体に不安があって、大学受験受けられるかな…と心配な方、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。
※あくまで6年前の個人的な経験です。詳しいことは各大学などの情報をご確認ください。
▼▼この記事で分かること▼▼
・病気をしながら、どうやって受験勉強するのか
・受験時に特別配慮を受けるための流れ
▼0.受験時の私の症状
私の病気・障害については前回の記事にまとめていますので、もしよかったら読んでみてください。
症状が時間を経て変わるので、高校3年生18歳のときの主な症状をざっくりとまとめます。
①自分の意志に反して、手足・顔・首などが震えたり動いたりする
②体(手足)が硬直する→細かい書く作業ができない
③体が脱力する→歩いたり、持ったりできない
④強い倦怠感
これらの症状は常に出ているわけではなく、ランダムなタイミングで発作的に出ます。
予兆はなんとなく感じられるときもあるし、突然発作が起こってしまうときもあります。
★そして、当時は障害者手帳を取得していませんでした。
▼1.受験勉強
移動に向いてなかったので、ほとんど家で勉強してました!
東〇ハイスクールの映像授業の受講を家で完結できるよう認めてもらい(基本的には通塾が勧められます)、大好きな英語だけ週に1回別の塾に通っていました。
あとは参考書や問題集でカバー。
参考書を読むのが好きだったのと、インドア派だったことで何とかなりました。
ただ、最後の方は参考書もめくれず、ほぼ寝たきりだったので英語のニュースを聞くことしかできず、この時ばかりはちょっぴり焦りました。
でも、単語を1ワードでも多く覚えるとか、ちょっとの積み重ねが焦りを解消してくれるし、受験当日の自分を救ってくれます。
▼2.特別配慮の申請
★受験の願書を出すときに特別配慮の申請をします。
そのあと面接や配慮内容の打ち合わせをした受験先がほとんどだったと記憶しています。
試験会場の担当者の方と、自分の病気がどんなものなのか・病院の先生はどういう見立てをしているのか・困りごとは何か・必要な配慮は何か…ということを打ち合わせます。
受験先によっては、症状を聞いたうえで一度協議して私の症状にマッチする配慮を考えてくださったところもありました。
事前に私からは移動の配慮とマークシートの配慮をお願いしました。
私は発作が出ると手が動かしづらく、マークシートを塗ることができなかったので、しっかり塗らなくてもいいように準備してもらいました。(具体的な配慮は受験先によって違うので、後ほどご紹介します。)
移動に関しては、大学構内に受験生以外が入れない場合、両親が介助するわけにもいかず、歩けなくなったときは補助してもらうようお願いしました。
▼3.会場までの移動
受験の1か月前くらいからは、ほとんど体が言うことを聞いてくれず、自力で受験会場までたどり着くことは不可能でした。
ですので、受験校をなるべく少なく抑えて、両親にタクシーや車で送り迎えをしてもらっていました。(この時かかったお金のことを考えると、本当に悔しいし申し訳ない思いです…)
受験開始時間に遅れるといけないので、朝6時くらいには家を出ていたと思います。
そして、受験会場の入り口まで母が介助してくれて、受験が終わったらまた迎えにきて一緒に帰る。
約1か月その生活を続けてくれた母は本当に大変だったと思います。感謝しています。
私自身は、不安でパニックにならないようにルーティーンを守ることに精一杯でした。
このタイミングでこの音楽を聴く、会場に入ったらトイレの場所をまず確認する、休憩中に食べるものは毎回同じ(ラ〇チパックさん、ありがとう!笑)、試験開始何分前にトイレに行く…
この時は体の症状が辛すぎて、あまり心の方に目が向かなかったのですが、今こうして書き出すと結構心もキてたな~と思います。
心のしんどさを自覚しすぎないように、ルーティンを守ることを一生懸命やっていたのかもしれません。
▼4.いざ、試験を受ける!
受験先ごとに書いていきます。
①センター試験
今はもう「センター試験」ではありませんが…
移動が難しかったので、あまり多くの受験校を受けると消耗してしまうため、併願校受験はセンター利用を大いに使いました。
弟に聞いた話では、今は共通テスト利用で合格するハードルが上がっているらしく(受験が必要な教科数など)、なかなかたくさん併願するのは難しいとのこと…。なんかいい方法ないかな。
【移動について】
受験校舎のすぐ近くまで母が入ることができたので、移動の合理的配慮はありません。
【会場について】
1人部屋でした!!
(おそらく私が受けた会場で特別配慮申請をした人がほかにいなかったから。)
私1人につき試験監督2人だったので、めちゃくちゃ緊張しましたし、気まずかったです笑。
センター試験は学校ごとに受けるので学校行事的な雰囲気がありますが、そういう思い出は作れませんでした。トホホ…
【マークシートについて】
1問につき、タテ3cm×ヨコ4cmくらいの記入欄が設けられていて、そこにチェックマークを書けばOKという形でした。
ですので、通常マークシートは1~2枚ですが、1問の記入欄が大きい分、10枚くらいだったような。
こんなでっかいマークシートあるんや~!と感動しました。
②私立大学A
事前にとても丁寧に面接をして配慮を考えてくださいました。
「受験当日、発作が出ると手を動かしづらいけれど、発作が全く出ないこともある。発作が急に来ることあるので予測できない」と伝えると、
「どっちになってもいいように準備しておきます!」とスーパーオーダーメイド特別配慮!!
具体的にはこんな感じ。
・発作が出た時⇒パソコン打ち込みで完結する問題(漢字の書き取りを他の問題にする)
・発作が出なかった時⇒普通に紙で受けてもいいよ~
受験前から時間と労力を割いてくださったおかげで当日安心して臨めました。
【移動について】
受験会場に着くと、合理的配慮が必要な一人の受験生につき一人のサポートスタッフさんがついてくださいました。その大学の大学院生のお姉さんでした。
偶然高校の卒業生だと知って、嬉しくて緊張がほぐれたのを覚えています。
【会場について】
1人部屋でした。
センター試験で経験していたので、前よりは緊張しませんでした。
【マークシートについて】
最初に書いた通り、「パソコン持ち込み可+パソコン用問題準備」という対応でした。
せっかく用意してくださったのですが、このときは体調がよく、通常の問題を通常のマークシートを使って解きました。
③私立大学B
第一志望で、複数の学部を受けました。体調は最高潮に悪かったです。
【移動について】
リサーチ不足だったのですが、教室近くまで母に介助してもらえると思い込んでいて配慮をお願いしませんでした。
(記憶がここだけ抜けている…打ち合わせについても思い出せない…)
会場の入り口までしか母は入れず、スタッフの学生さんにも「ここまでです!」と言われてしまったので、そこからは一人で歩きました。
発作は出ていましたが、歩ける程度の足の状態でよかったです。
【会場について】
別室受験ではありましたが、特別配慮が必要な受験生何人かが集められて、小教室で受験するという形でした。
教室には私のほかに2人の受験生がいました。
車椅子の方や(おそらく)聴覚障害がある方が一緒だったと記憶しています。
受験時間の終了は、口頭アナウンスと紙でのお知らせでした。
色んな合理的配慮が集まっている空間をこの時初めて体験しました。
これがインクルーシブかあ。
【マークシートについて】
通常のマークシートにチェックマークを記入すればOKという配慮でした。
何とかそれでも大丈夫だったのですが、硬直の発作が強く出ていたので、豆粒大の小さな記入欄に書き込むのはそれなりに大変でした。
▼5.まとめ:配慮の申請時にしっかりと伝えるのがポイント!
こうして思い出すと、本当にいい経験だったなあと思います。
この経験を通して分かったのは
・きちんと説明すれば、合理的配慮をしてもらえる!(こともある)
・自分はこの体が普通になってるけど、説明しないと伝わらない!
・説明することがスタート地点!
ということでした。
もちろん、説明しても伝わらないことたくさんあります。
高校時代も大学時代も社会人になってからも、理解してもらえなかったり、全然配慮してもらえなかったりしたこともあります。
でも、10じゃなくても0より1のほうがいいかなと思います。
だから丁寧に説明することをこれからも続けていきたいです。
私はセンター試験+私立大学しか受けていないですし、私立文系ということで限定的な体験にはなりますが、困りごとがあっても、そしてそれを公的に証明する障害者手帳がなくても大学受験では配慮があるということを知るきっかけになればと思います。
そして、少しでも安心して大学受験に臨める人が増えると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
