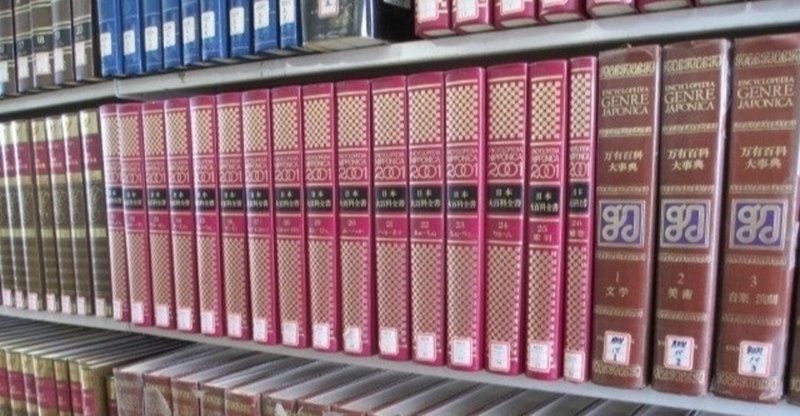
映画『博士と狂人 The Professor and the Madman』(2019)の感想
ファルハド・サフィニア(P・B・シェムラン)監督の『博士と狂人 the Professor and the Madman』を映画館で観てきた。
個人的には、今年鑑賞した映画で、暫定一位である。
理由は、学ぶこと、知ることに対する「肯定」が、明確に描かれていたからである。観終わったあと、思わず走り出したくなるような映画だった。
イギリスのオックスフォード英英辞典といえば、英語学習の経験があれば、聞いたことがあるだろう。学習が進めば、和英・英和辞典から、英英辞典への移行を促されるものである。
そのお馴染みのオックスフォード大学の英英辞典の誕生(製作)秘話が、映画化されている。
なぜ、辞書を作らなければなかったのか。急務であった理由は、大英帝国(植民地支配)によって、第二言語、外国語として、英語を学ぶ人たちが急増したことが要因である。
劇中では「女王様の言葉が全世界で話されるのだ」と高らかに宣言される。その大英帝国の植民地支配の残滓として、今日においても、英語は世界共通語であり、みなそれぞれの「訛り(母語)」とミックスされ、英語は世界のあらゆる場所で使われ、それぞれの場所で変化を繰り返している。それは驚くべき、驚異的な事象である。ひとつの言語が世界に伝播し、それを解することができる人々がいる。そのすさまじさ、便利さと不自由さを知っているのは、英語母語話者ならではの経験といえるかもしれない。また、彼らの傲慢さも、そこに起因している。その結果、彼らが外国語を学ぶ切実さが失われてしまったという側面があることは否定できない。(かたくなに英語を話すアメリカ人のほうが、かたくなにフランス語しか話さないフランス人より実際多いだろう)
ただ、「辞書作り」という地味で気の遠くなるような膨大な作業を実際にする人々は、ナショナリズムや大英帝国の思惑とは、少し離れたところにいる。彼らを突き動かすのは、徹底的に調べ上げて言葉のルーツを突き止めたい、という欲求である。それは、英語で書かれた文献はもちろんのこと、ラテン語、ドイツ語、フランス語、インド・ヨーロッパ語族のものも含め、遡らなければならない。頭がおかしくなりそうな作業である。ただ、それをやってのけた人々がいるからこそ、今『オックスフォード 英英辞典』というものが存在しているのである。
たとえば、『広辞苑』には出典が明記されており、普段の言葉を知るには、情報が多すぎるのだが、「これは源氏物語から使われているのか」と文化の厚みを感じることができる。言語、あるいは辞書による言葉の定義は、国家の運用に必要なものなのだ。
そして、辞書作りを行ったのが、中央にいる人々ではなく周辺から来た人々であったことも興味深い。編集責任者であるジェームズ・マレー(メル・ギブソン)は、スコットランド人で、British Englishを話す人物ではないし、博士号の学位も取得していない。語学の天才ではあるが、学歴は心許ない。
もう一人の主人公のマイナー(ショーン・ペン)は、アメリカ人の軍医(外科医)である。彼も、British Englishを話す人物ではないが、辞書の編纂に大きく関わっていく。そして、皮肉なことに狂人(Madman)であるマイナーは、ドクター(医師、博士)の資格を持っている。
アウトサイダーにいる人が、社会や物事を変えていく力を持てるのは、彼ら自身が周縁に追いやられていることを知っているからである。彼らは自分たちの無力さを知っているからこそ、それを補うべく、真摯に「学ぶ」のである。それは、学びの本質ではないだろうか。我々は、生まれたままでは、字を読むことも、何かを知ることもできない。言語というルールを習得し、世界を広げていく。誰しも、はじめは謙虚であるはずなのだが、さまざまな言い訳をして、学ぶことをやめてしまう人も、少なからずいる。
マイナー医師は、自分が殺害してしまった男性の妻が文盲であることを知り、文字を教えていく。そのなかで、「人間の脳は、この世界より広い」と説く。被害者遺族である彼女は、加害男性であるマイナー医師に心を開き、慕うようになる。その気持ちはわからないでもなかった。
文字を学び、読めるようになったことにより、彼女の世界は文字通り大きく広がったのである。人に教えてもらわなくとも、自分で情報を拾える。文字がわかるふりをしなくてもいい。文字を理解したあとの彼女の世界は鮮烈に輝いたのではないだろうか。そして、母親が文字を理解したことで、子どもたちも、高いレベルの教育を受けられるチャンスが広がる。わかる喜び、知る喜びは確実にある。それを教えてくれた人を愛するようになっても、なんら不思議ではない。マイナー医師は、金銭以上の贈り物を彼女に送ったのである。
物語の終盤、マレー博士の妻は、夫の人生を象徴する言葉として「この上ない勤勉を」というフレーズをあげる。「学び」とは、本来あなたや私を別の場所に連れて行ってくれるものである。私たちは、受験勉強や資格の勉強に汲々とすることで、学ぶことを疎ましく思ったり、損得勘定や時間コストにとらわれ、即物的な見方しかできなくなってしまったりする。
なぜ、学ぶのか。それは新しいことを知り、昨日と少し違う自分になるためだと思う。急激な変化ではなく、日々少しずつ変化していく。新しいことを知る、それだけで、幼少時はうれしかったはずである。先人たちが学んできたように、私たちも学び、次の世代にバトンを渡すのだ。その形は千差万別で、学校や職場のみならず、ありとあらゆるコミュニティで、日々無意識に実践されている。
学び続けなければ、と素直に思える作品であった。
そして、辞書作りの過程はコミカルでもある。「16世紀から17世紀の文献がありません。どうしましょう」と愚痴る場面は傍目にはほほえましく映る。
獄中(精神療養施設)にいるマイナー医師が出す手紙を投函していた(切手をなめていた)と言う看守に対して、マレー博士が「あなたの舌(mother tongue)に感謝します」と述べる。
"mother tongue"とは、母語、つまりBritish Englishを指すのだろう。なかなかしゃれたやりとりである。残念ながら、私は英語に堪能ではないので、この映画の台詞に隠された遊びや工夫が全然わかっていないと思う。それが心残りではあるが、仕事を遂行したいという執念と、とことん調べあげ、新しいことを知る、その喜びが素朴に描かれていて、私は虚を突かれた。
面倒くさがらずに、どんどん学んでゆこう。皮が一枚ぺらっと剥けた感じがするくらい、前向きな気持ちにさせてくれる映画だった。もう一度観に行きたいし、原作本も買ったので、これから読むつもりである。
ただ、ひとつだけ疑問なのは、最後にマレー博士が辞書編纂メンバーと一緒にいる写真が映されるのだが、そこには女性スタッフが二人いたのである。だが、映画の中の辞書編纂チームには男性しかいなかった。単なるアシスタントであったのだとしても、あの写真の女性二人を映画のなかに存在させてほしかったなと思う。(もしかしたら、現実には何か問題があり、話がややこしくなるため、意図的に登場させなかった可能性もあるので、これから原作を読んで確かめたい)
そして、実は、メル・ギブソンは、『パッション』『アポカリプト』に加え、私生活もヤバい人という印象が強く、食わず嫌いしていたのだが、頭のおかしい人を演じるにはこの人以上の適任者はいないのかもしれない、と思えた。
マイナー医師だけでなく、マレー博士も狂人であり、この映画のタイトルはおそらくダブルミーニングなのだろう。二人とも博士であり狂人なのだ。その二つを両立させることは、それほど難しいことではない。
チップをいただけたら、さらに頑張れそうな気がします(笑)とはいえ、読んでいただけるだけで、ありがたいです。またのご来店をお待ちしております!
