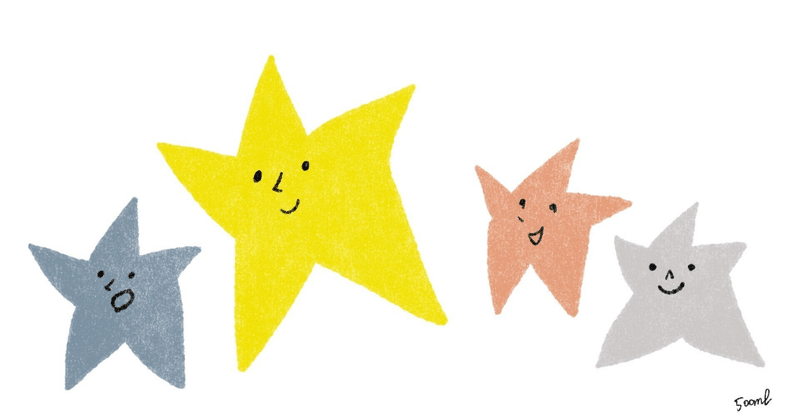
「何者かになりたい自分」と「何者にもなれない自分」、そして「何者にもなりたくない自分」
「何者かになりたい」とか「何者にもなれなかった」という表現をよく耳にする。
「何者かになりたい」とは?
「何者かになりたい」という願望、欲求には以下のようなことが含意されていると、わたしは考えている。
・仕事での自己実現
・自分の能力や個性、特徴を思う存分発揮したい
・他者から一目置かれたい
・社会に認められたい
・有名人になってちやほやされたい、モテたい
・多くの人から羨ましがられたい(羨望を浴びたい)
・確かな居場所がほしい
・誰かから必要とされたい
・自分の意のままになるような空間がほしい
・孤独から逃れたい
・愛されたい(他者を愛することを許されたい)
・常に仕事のある状態で暇を持て余したくない
・貧困から遠く離れたい
・経済的成功を収めて、人より抜きん出たい
・安定した生活を送りたい
・家族に豊かな生活をもたらしたい
思い浮かぶままに書いてみたが、全部似たような意味のことばかりだ。すべてにおいて他者が関わってくる。マズローの欲求5段階説があるが、段階ではなく、5つの欲求はすべてぐちゃぐちゃに絡み合うのではないかと思っている。
つまり、「何者かになる」が意味するところは、社会のなかで、どういう立ち位置になるのか、どのように見られるのか、といった他者のまなざしを多分に含んでいる。つまり、他者がいなくなれば、意味を失ってしまう。他者からの承認がほしくてほしくてたまらない。でも、それは人生において学んできた他者のまなざし、社会的評価というものを自己学習して、自ら作った基準でもある。誰もが「自己採点表」を持っているのかもしれない。
リドリー・スコット監督の映画『オデッセイ』のマット・デイモンのように火星での一人暮らしが始まれば、「社会ってなに?」となり、個体として生き延びることだけが目標となる。「他者を失う」という前提がないことは、人類の希望であり、絶望という気がしている。他者は必ずそこにいる。人間が社会的な動物であるがゆえの苦しみ、というやつだ。
他者のまなざし、他人は地獄
たとえば、二人の哲学者がいる。
一人は某国立大学の教授で、著作も多く、研究業績も目覚ましく、研究室に入りたい学生は後を絶たない。海外の学会やシンポジウムにも年に何度も招待される。テレビ番組の司会者をやったり、メディアへの登場回数も多く、一般人の認知度も高い。年収も二千万円ぐらいある。
もう一人は風呂なし四畳半の木造アパートで哲学的な思索に耽っている。家族も友達もおらず、日雇いの肉体労働で週に何度か働き、なんとか生活を成り立たせている。教育を受けたことはない。ある日、哲学の面白さに気が付き、本をひたすら読んでいる。口下手で、書くトレーニングも受けたことがないので、肝心のアウトプットができない。しかし、ぐるぐると、誰よりも考え続けている。そのことを知っているのは、本人だけ。
どちらの哲学者になりたいか自由に選んでいいよ、と言われたら、大半の人は前者を選ぶのではないか。前者は、他者が欲しい社会的地位、年収、人気、人望などを持っている。後者は持たざる者だ。孤独で、自由なのは時間だけで、すべてが不安定だ。
もちろん、前者は「他者のまなざし」、いわゆる「評価」に常にさらされている。(先日、お亡くなりになった社会学者の見田宗介が指摘した「まなざしの地獄」は誰にでも起こり得る)
前者は「あいつは終わっている」「古臭い」などと学会で陰口を言われたり、SNSで業績も知らぬ一般人に「顔が微妙www」と嘲笑され、学生から「あの日の先生のゼミでのご発言はアカハラにあたると思われ、再考願いたい」などのメールが来たりする。ストレスフルだが、世捨て人のように暮らしたくはないし、今の地位も手放せない。フランスの思想家のサルトルは「地獄とは他人だ」と述べているが、「何者かである」人は、少なからず地獄の中を生きている。超然として見えても、そのような演技をしていたとしても、常に晒されている、という感覚があるはずだ。「何者かになる」って結構大変だ。
一方の後者は、そもそも人に知られておらず、所属しているコミュニティも狭いので、悪口を言われることもそれほどない。「評価」も、哲学を仕事にしているわけではないので、批判を受けることもない。栄光がないだけ、失望もない。自己完結しているので、社会の中での位置づけを心配することもないし、持っていないので失うこともない。もちろん、孤独は果てしないが、自由だ。
二人とも、哲学者であることは間違いない。前者はアウトプットにに丈ており、社会における手続きを踏んで、今の地位を得た人だ。後者はインプットばかりで、社会の手続きがあることは知っているがやり方がわからず、自分の世界を生きている。そもそも、積極的に社会の中で目立とう、とはしない生き方もある。
「何者かになりたい人」はどこにいる?
「何者かになりたい」人の多くは、この前者と後者の中間にいるのではないか、と思われる。分野は違えど、各々のジャンルにおける階段の上り方はある。それを若いうちに認知でき、最短距離で進める人ほど、成功にたどりつける。社会資本、文化資本といった親から継承されるものの有無によっても左右されるところであり、だからこそ、みんな苦しくなる。
「実力の違いなんて大してないはずなのに、あいつはなんで高給取りの専門分野の第一人者で、こっちはずっと薄給で無名なのだ。不公平だ!」というふうになる。
わたしも、生来の天才や天才的に努力できる人もいることは知っている。培ってきた実力が大事であることも認める。だが、結構「運次第」ではないか、運も大きな要素ではないかと思っている。
自分自身、「運がよかった」と肯定的に思える過去と、そうではない過去が半々ぐらいなのだ。
「何者にもなれなかった自分」との対峙
「何者にもなれなかった自分」は、運も、才能も、実力も、コネもなく、ルックスがイマイチだから駄目だった。そう考えてしまっても、おかしくない。成功した人も、成功していない人も、自分の置かれている立場が、どういった経緯で、どのような要因によって、もたらされたものなのか、はっきりとはわからないし、わかっていない。
さまざまな人々のいろいろな意志が関わり、混ざり合った結果が今である。だからこそ、理由を明らかにすることは不可能なのだ。しかし、生存者バイアスによって、成功した人は、成功するまでの道のりとして、汗と涙と苦渋の日々を物語化して語ったりするので、「自分が成功しているとは思えない人々」は劣等感が煽られたりする。汗と涙と苦渋の日々は、成功していない人も経験しているのだから。
もしかしたら、「成功者」は、単に上の人に気に入られただけの人、親が有名人だったから、とかのつまらない要因で有名になっているだけだったりするかもしれない。確かに、世の中は不公平だが、「剝奪感」に苛まれる時間は、要らない時間という気もする。
ポイントは、「自分が成功しているとは思えない人々」である。これは圧倒的な主観でもある。
そして、「成功」の基準なんて、朝令暮改で、時代とともにいくらでも変容する。今あるプラットフォーム(Youtube,Twitter,TikTok,インスタ,noteなど)がルールを変更したり、なくなれば、収入減が絶たれてしまう人もいる。それだけ、薄氷を踏むような、あるいは吹けば飛ぶような基盤を頼りに暮らしているのが現代人なのだろう。
仕事や職業は永遠ではない
わたしは、かつての「電話交換手」や「タイプライター」といったその当時の専門職の「花形」だった人たちについて考えたりする。彼らは、好奇心旺盛で、新しいものに臆せず、バリバリ仕事をこなしていたはずだ。仕事の手際が信じられないほどよい人もいただろう。それらの能力が「才能」「実力」と呼ばれたこともあったはずだ。
しかし、技術革新によって、あっけなく、職業自体が消失してしまった。
一人で車を組み立てられる才能だって存在したはずだが、今の社会では必要とされないだろうし、一人では作れない仕組みになっている。
「何者かになる」の心許なさは、社会の情勢によって、一瞬で変化してしまう点にある。崩壊はいつやってくるのかわからない。決して確固たる才能、生来の能力や努力の賜物で「何者かになる」のではない。かなり流動性が高く、約束されたものなど何もない。もちろん、実力と努力は否定しない。しかし、Googleが検索アルゴリズムを変えただけで、収入が大変動する。ルール変更によって、いとも簡単に揺らぐ「才能」を「才能」と呼ぶことはできるのだろうか。
これは波乗りだ。よい波が来るかどうか、海と風によって決まるので、個人でコントロールできるものではない。もちろん、台風の日に海に行かないとか、それぐらいの判断は個人に委ねられていると思うが、それぐらいしかない。
「仕事」や「人」が、ある日突然世の中に必要とされたり、もてはやされたり、脚光を浴びることもある。一方、唐突に「不要」であると烙印を押されたりする。タイピストとしての才能の素晴らしさは損なわれることがないのに、「不要」と他者からジャッジされてしまう。
何らかの成功を手に入れたとしても、それは時の流れとともに忘れ去られる。あるいは、数年後、誰かの専売特許は、代替可能なものになり、AIで自動化され、数秒で終わるタスクになっている可能性もゼロではない。
CD時代と配信時代の歌手
若い頃、スターになって、スターでい続けることは難しい。盛者必衰。歌手を例に考える。CDの売れていた時代に歌手になった人と、配信時代の人では、成功の定義も、収入の多寡もまるで違うだろう。でも、配信時代の人たちの収入の少なさは、彼らの才能とは無関係だ。
二十年ぐらい前、わたしはインディーズのアーティストを紹介するラジオ番組を聞いていて、「あれ? 別にプロと遜色ないじゃん」と思ったことを鮮明に覚えている。もちろん、華があるとか、ないとか、ルックスの問題とか、メジャーデビューできない、あえてメジャーデビューしなかったなど理由はいろいろあると思う。ただ、純粋に「才能」を比較しても、メジャーとインディーズにそれほど大きな差はないと感じた。
日本の音楽市場で成功できた人たちは、肯定的なフィードバックを受け続け、生き残れたに過ぎない。インディーズバンドで才能があり、プロフェッショナルな人々は多いが、誰もが成功できるわけではない。成否をわけるもの、それがわかればプロモーターもレコード会社も、苦労しない。成功の理由と失敗の理由は、誰にもわからない。
それは、社会や世の中が、常に、うつろい、たゆたうものだからだ。「巡り合わせ」はある。しかし、人脈に四苦八苦するのは本末転倒な気もする。そして、人間は、理屈や論理ではなく、「感情」や「欲望」で動く。予測できないことのほうが、圧倒的に多い。
何者にもなりたくない理由
現代人は「何者かになる」ことを夢見ながら、それと同時に「何者かになる」面倒くささも知っている。ブレーキを踏んで「何者かになる」ことを拒んだ人、逃げた人もいるはずだ。(誰もが何者かにならなければ食えない時代になっているのだとしたら、それこそ本当に地獄だ。)
「何者にもなりたくない人」は、見えにくい。野心や野望がなく、「何者にもならず、平穏無事に暮らせれば、それでいいのよ」という人もたくさんいる。そう、「何者かになる」ことが幸福に直結しないことぐらい、みんな知っている。
人間社会には同調圧力があり、「出る杭は打たれる」なんてことわざがある。それをもじった「出過ぎた杭は打たれない」などという派生ことわざもあるが、現実は「出過ぎた杭は抜かれる」だとわたしは思っている。「何者にもなりたくない」という欲望は、当然のものだ。叩かれたり、引きずり降ろされるのに耐えられる人ばかりではない。
思わず「何者かになってしまう人」もいる
有名著名人でなくとも、「イジメ、不倫、略奪愛、失踪、借金、強盗、殺人」とかの物騒な言葉で形容され、ドラマチックに生きている市井の人々もいる。そのような人生が小説や映画になったりして、図らずも経済的成功を収める人を見ては「わたしの考える成功って、そういうのじゃないのよね」と不遜にも考えてしまう。
一番最悪なのは「有名で日常生活が不自由なのに、収入が少なくて生活ができない」というパターンかもしれない。残念ながら、知名度と収入は比例しない。
わたしの生き方を振り返ってみる
「何者かになりたい自分」と「何者にもなれない自分(何者にもなれなかった自分)」は対立しているが、「何者にもなりたくない自分」はそこから少し離れたところにいる。
わたしは、十代の頃から、この三つの自分を闘わせていたような気がする。この三つの自分は共存し得る。疲労の要因の一つでもある。野心のある自分(「何者かになりたい自分」)を否定したくないし、慎ましくわきまえる自分(「何者にもなりたくない自分」)を無条件に全肯定もしたくない。
ただ、自己否定の権化である「何者にもなれない自分」と対話するのは本当に疲れる。あいつはイチゼロ、白黒思考なので、いつも攻撃的で困る。
「他者」という軸から、少し距離を置けるのは「何者にもなりたくない自分」だ。教室の中で、目立たず、埋没していたい、という子どものときの感覚に似ている。しかし、この考え方にも、ある種の自意識過剰さがある。
個人は不条理な世界と闘えない
少し話の角度を変えよう。「戦争」や「感染症」に家族の命を奪われ、生活の基盤を失った人がいる。圧倒的な不条理で、個人にできたことなど、何もない。因果関係などない。
(陰謀論でつじつまを合わせして、きれいなストーリーに納得などしたくない。)
この世は理不尽だ。誰の命の積み重ねも、いつ終わるのは誰も知らない。
わたしたちは、そのような世界で暮らしている。運がいいの悪いのか、生き延びている。だからこそ、「自分」が存在している場所から、世界を観察し続けるほかないのだと今は思っている。
だから「何者かになる」というこだわりは、生きる上で、邪魔な余分な要素になるおそれもある。
そうは言いつつも、何者かになれたと喜んだり、何者にもなれず苦しんだり、何者にもなりたくないと社会からちょっと距離を置く、といったことを行きつ戻りつ、自分の中に去来させながら、わたしはこれからも生きていくのだと思う。
時代の流れ、経済情勢、技術革新、人々の趣味嗜好の変化、戦争、感染症といった理不尽は、いつもそこにある。椅子取りゲームが好きな人、そうでない人、どちらも生きていかねばならない。だから、「何者にもなれない自分」「何者にもなれなかった自分」を責めなくていい。あなたの欲しいものを持っている誰かが目障りでイライラすることもあるだろうが、その人だって、それほど幸福を満喫しているわけではない。目立つ人は、否応なく、常に「評価」されている。絶賛ではなく、罵倒の方が多いことも少なくない。それはあなたもすでに理解しているはずだ。
現実的な理想
わたしの理想の暮らしは、「あたたかい家庭、愛する人がいて、愛されて、誰も知らない無名の大富豪になって、平穏無事に贅沢三昧して暮らすこと」だ。(無理だよ。金持ちは、たかられるものだ笑)
現実的なことを言えば、毎日わくわくしながら、生きている人が一番の成功者かなとも思う。
(そんなことをここ数日考えていたら、長文になってしまった。加筆・修正を加えたら、6,000字を越えた。葛藤を楽しんでいこうではないか。あちこちにいく思考をまとめることはセルフセラピーにもなる。)
チップをいただけたら、さらに頑張れそうな気がします(笑)とはいえ、読んでいただけるだけで、ありがたいです。またのご来店をお待ちしております!
