
#1 太宰治全部読む |一作目にして晩年
私は、太宰治の作品を全部読むことにした。
太宰治を全部読むと、人はどのような感情を抱くのか。身をもって確かめることにした。
これから始まる、長い文学の旅路。
ワクワクすると同時に、太宰治という癖のある作家の本をひたすら読むということに不安もある。日常生活に支障が出ないことを祈りつつ、出発することにしよう。
太宰治|晩年
太宰治全部読む、1冊目は『晩年』である。
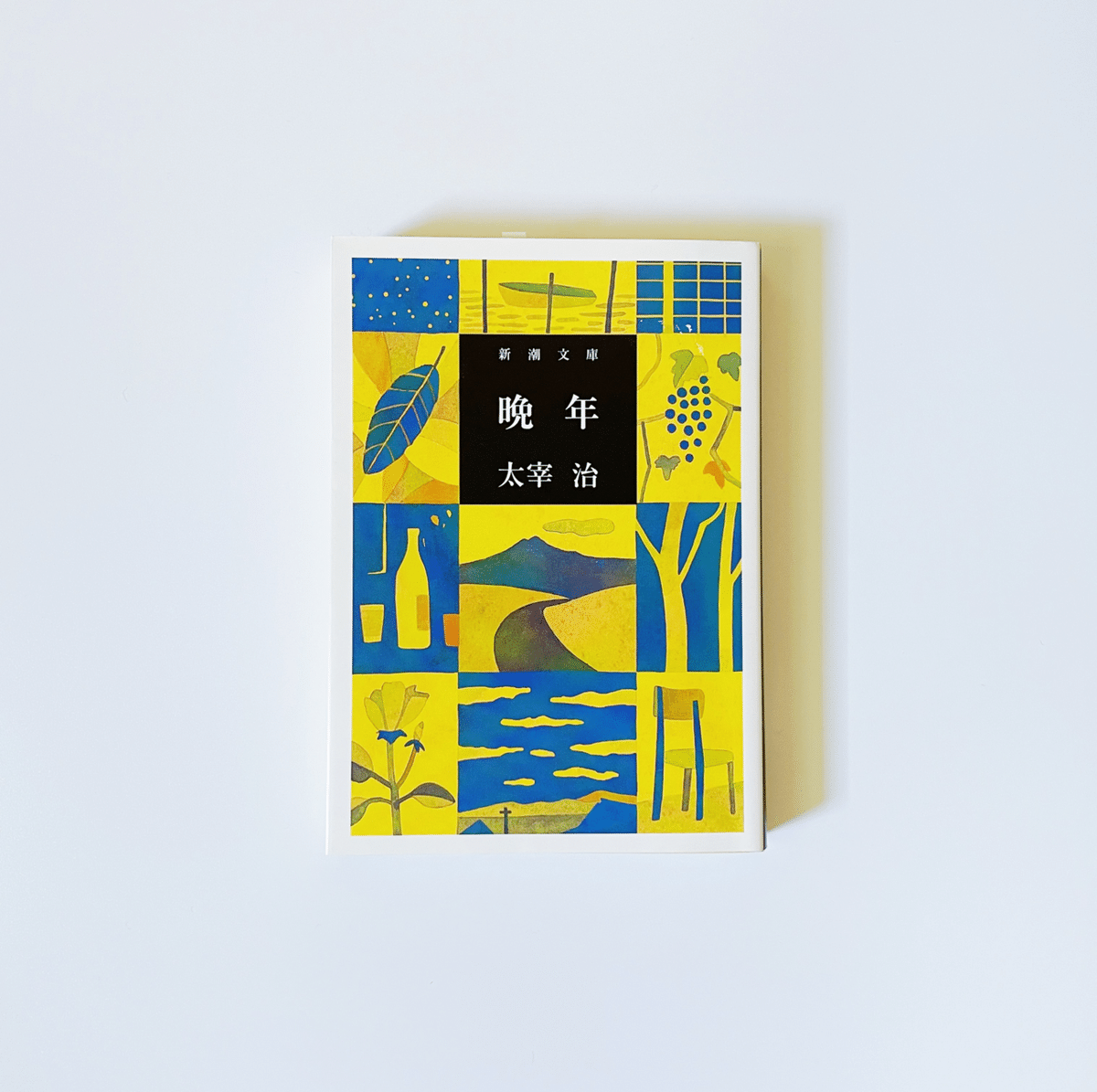
妻の裏切りを知らされ、共産主義運動から脱落し、心中から生き残った著者が、自殺を前提に遺書のつもりで書き綴った処女作品集。"撰ばれてあることの 恍惚と不安と 二つ我にあり"というヴェルレーヌのエピグラフで始まる『葉』以下、自己の幼・少年時代を感受性豊かに描いた処女作『思い出』、心中事件前後の内面を前衛的手法で告白した『道化の華』など15編より成る。
『晩年』と聞くと、太宰が晩年に書いた作品であると勘違いしてしまうが、それは太宰トラップである。当時27歳の太宰が、自殺を前提に遺書のつもりで執筆した小説、それらをまとめた第一作品集が『晩年』だ。
それにしても、遺書のつもりで書いた短編集に「晩年」という題をつけるところに、太宰の隠し切れない才能が漏れ出てしまっている。
巻末の解説に、太宰本人が『晩年』について語る文章が載っていた。これから太宰治全部読むを始めるにあたり、すごく胸を打つ文章だった。まずはその引用から、太宰治作品を読む旅を始めよう。
「私はこの短編集の一冊のために、十箇年を棒に振った。まる十箇年、市民と同じさわやかな朝めしを食わなかった。私は、この本一冊のために、身の置きどころを見失い、たえず自尊心を傷つけられて世のなかの寒風に吹きまくられ、そうして、うろうろ歩きまわっていた。
(中略)
舌を焼き、胸を焦がし、わが身を、とうてい恢復できぬまでにわざと損じた。百篇にあまる小説を、破り棄てた。原稿用紙五万枚。そうして残ってのは、辛うじて、これだけである。これだけ。
(中略)
けれども、私は信じて居る。この短編集、『晩年』は、年々歳々、いよいよ色濃く、きみの眼に、きみの胸に滲透して行くにちがいないということを。私はこの本一冊を創るためにのみ生れた。
(中略)
さもあらばあれ、『晩年』一冊、君のその両手の垢で黒く光って来るまで、繰り返し繰り返し愛読されることを思うと、ああ、私は幸福だ。」(「文芸雑誌」昭和十一年一月号)
葉
新潮文庫で太宰治を順番に全て読もうと決めた人は、『晩年』の「葉」という短編から、その世界に足を踏み入れることになる。注目すべきは、最初の一文。「葉」の冒頭は、これからの旅路の命運を占う重要な一文である。
死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目が織りこめられていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。
ここでもう、読者は全員太宰に心を掴まれるわけである。素晴らしい冒頭だ。死のうと思っていた→夏まで生きていようと思ったの流れが良すぎる。
「葉」は、太宰が物書きになる前に書いた、様々なボツ小説の断片を寄せ集めたものと考えられる。太宰の脳内世界に誘われる、不思議な読み心地のパッチワークだ。
思い出
自身の幼少期・少年期を回顧する自叙伝的小説。幼い頃の太宰に会うことができる、これまた、太宰治全部読むの序盤にふさわしい作品である。
読んでいると、太宰の人間性の根源に触れることができる。特に私が好きだったのは、太宰がファッションのこだわりについて熱く語る場面だ。太宰は幼い頃から、不可侵の自己世界を有していたことがわかる。
私は早くから服装に関心を持っていたのである。シャツの袖口にはボタンが附いていないと承知できなかった。白いフランネルのシャツを好んだ。襦袢の襟も白くなければいけなかった。えりもとからその白襟を一分か二分かのぞかせるように注意した。
(中略)
私はそのようなおしゃれを、人に感附かれぬようにひそかにやった。
(中略)
私は、かえって服装に無関心であるように振舞い、しかもそれは或る程度まで成功したように思う。
魚服記
北国の山で暮らす少女が、滝壺に飛び込んで鮒に変身するという、なんとも不思議なお話である。太宰の故郷・津軽の自然描写と、童話的な世界観が融合している。
列車
これが、初めて「太宰治」の筆名で書いた小説とのこと。この作品も、冒頭が良い。機関車の歴史の説明から入り、その機関車に乗って去りゆく友を送り出すエピソードに、自然と繋がっていく。
地球図
江戸時代、キリスト教布教のためにローマから来た宣教師シロオテと、彼を審問する新井白石ら日本人のお話。シロオテから聞く世界各地の珍しい土産話は、当時の日本人にとって、まるで冒険小説を読むかのような、未知の感覚だったのだろう。
猿ヶ島
ちょっと伊坂幸太郎っぽさを感じた短編。太宰の一風変わった着眼点が光る。序盤から終盤にかけての切り替えが見事。猿の視点を通じて、人間を批評する太宰。
雀こ
津軽弁で書かれた詩。津軽弁は難しい。ずおん。
道化の花
太宰が女性と入水自殺を図った事件を題材とする小説。彼の内面が書き綴られている。
主人公・大庭葉蔵の物語の所々に、太宰自身であるところの「僕」からメタ的にツッコミが入り、小説が中断される。小説を書いている「僕(=太宰)」の、言い訳めいた心境や注釈、メタ発言が面白く、唯一無二の読み心地である。
なにもかもさらけ出す。ほんとうは、僕はこの小説の一齣一齣の描写の間に、僕という男の顔を出させて、言わでものことひとくさり述べさせたのにも、ずるい考えがあってのことなのだ。僕は、それを読者に気づかせずに、あの僕でもって、こっそり特異なニュアンスを作品にもりたかったのである。それは日本にまだないハイカラな作風であると自惚れていた。しかし、敗北した。いや、僕はこの敗北の告白をも、この小説のプランのなかにかぞえていた筈である。できれば僕は、もうすこしあとでそれを言いたかった。いや、この言葉をさえ、僕ははじめから用意していたような気がする。ああ、もう僕を信ずるな。僕の言うことをひとことも信ずるな。
猿面冠者
ひとつの小説を書き上げるのは難しいのだということを、太宰らしいユーモアで、小説に仕立てている。猿面冠者とは、完璧さを求めて筆が進まない、物書きの滑稽な様子を表しているのだろうか。
逆光
第1回芥川賞の候補作になった短編。個人的に、『晩年』の中で1番好きな小説だった。
4つの掌編から構成されており、それぞれの掌編は登場人物も場面もバラバラである。通して読むと、人間とはなんとままならない存在なのだろうと思う。
彼は昔の彼ならず
無職で怠け者の青扇という男に部屋を貸す大家の視点から、嘘ばかり吐いて女に溺れる、ダメ男のどうしようもない日々を描く。
青扇は、太宰自身だろうか。だとすると、自身を客観視して小説化するのがうますぎる。そして最後の一文に、ドキリとさせられる。
ロマネスク
仙術太郎、喧嘩次郎兵衛、嘘の三郎の3人の変わり者が登場。全員変わり者だが、憎めないやつだ。
別々の掌編かと思いきや、最後に3人が居酒屋で一堂に会する場面は、シリーズものの歴代主人公たちが集結した時のような感動があった。
玩具
断片的に蘇る、幼少期の記憶。私たちが幼少期を思い出すときも、この小説のように、断片を繋ぎ合わせるような感覚に近いだろう。記憶を思い起こす内的な作業を、リアルに描いている。
陰火
逆光同様に、4編の全く関連性のない掌編から成る作品。ストーリーも教訓もない、淡々とした掌編だが、やっぱりなんだか良い。太宰自身は、こんな中身のない小説は駄作だ、とか思っていそうだが……。
めくら草紙
太宰がパビナール中毒にかかっていた時期に書かれたと言われる。乱れた文体、断片のつぎはぎ、そしてその中に潜む暗いユーモア。ここから、『二十世紀旗手』の作品などに繋がっていくのだろうか——。
雑文めいた感想を並べてしまったが、『晩年』を読んで、太宰治がどんな人物なのか、ぼんやりとした輪郭が見えてきた気がする。
いや、実はそんな輪郭は幻想で、太宰に巧妙に騙されているような気もする。つまるところ、『晩年』を読んだだけでは太宰の真髄は掴めなかったが、それでも太宰作品の読み方は少しわかった。
太宰の小説には、鬱とユーモアが絶妙なバランスで混在している。この感覚は、これまで私が読んできた他のどの作家の作品にもなかった。
考えてみれば、鬱々とした気分と他者に向けたユーモア精神をあわせ持つのは、人間として当たり前のことだ。その二面性が極端に混在し、全く違和感がないことが、太宰作品の特異性なのかもしれない。これから様々な太宰作品を読んでいく中で、彼の真髄を探っていこうと思う。
↓「全部読む」シリーズの続きはこちらから!
↓本に関するおすすめ記事をまとめています。
↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。
↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
