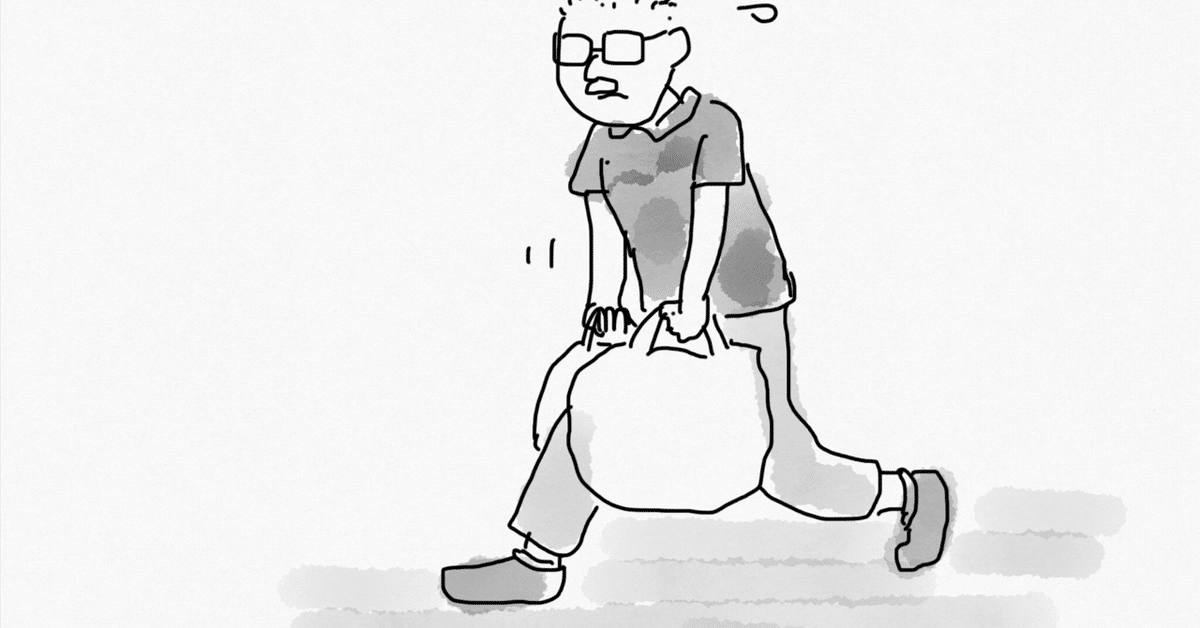
ネガティヴリストによる指針
ここではネガティヴリストという考え方を元に、教育実践の多様性を考えていきます。ネガティヴリストというのは、「〜をしないようにしよう」という事柄を集めたリストです。ネガティヴリストの対義語は「ポジティブリスト」ですね。これは逆に「〜をしよう」というリストです。教育現場には「〜をするべき」とか「〜をしたら学力が向上する」という言説がとても多いので、ポジティブリストの方が馴染み深いかもしれません。
ポジティブリストの方が実践者としては気が楽なのかもしれません。「教育というのは正解が無い」とよく言われます。そんな不確かさが付きまとう教育実践の中で「〜をしよう」とか「〜をしていたら大丈夫」というポジティブリスト的言説は心強いです。なぜなら、「とりあえずは、それをしておけばいい」と「頼る」ことができるからです。特に小学校教員は、10以上の教科を一人で教えることもありますので、一つ一つの教科についての専門性を高めることはかなり困難です。すると、ある教員が、若い頃に仕入れた「ポジティブリスト」を後生大事に抱えておくことは不思議ではありません。そして、教育は、その効果が検証されることもありませんので、その若い頃に仕入れたポジティブリストの効果や意味が見直されることも少ないのです。
例えば、「学級経営の基本は規律である」というのはポジティブリスト的考えですね。規律があればそれで良いのであれば、その方法は「恐怖による管理」でも良くなります。実際、「学級の荒れ」ということに対しての忌避感が強まっている現場からすれば、「荒れるくらいなら、多少の恐怖政治は必要悪である」と考える教員は多いです。もちろん、「恐怖による管理」以外の手法もありそうですが、「規律」という言葉からは、子供たちの「教師の想定外の行動」は許容されないでしょうから、どのような手法に頼ったとしても、結局は「教師の顔色を忖度する子供たち」というのが規律を求める学級の末路になることは明白でしょう。
一方、「子供たちへの威圧的な言動は慎まないといけない」というのはネガティヴリストです。管理的な教育への批判が叫ばれていますが、実際問題として、30人を超える子供たちに一斉に指導をしていくのならば、多少は語気を強める場面もあるのかもしれませんが、先ほどの命題はそれを「するな」と要請してきます。では、どうすれば良いのでしょうか。これがネガティヴリストの難しいところであり、かつ、おもしろいところでもあるのです。「明確な答え」が無いからこそ「考える」ことが常に求められるわけです。
例えば、僕だったら「権威に服従するようなことを子供たちに教えたくない」という考えから、「信頼関係構築」と「言葉の丁寧さ」を意識して子供たちと関わることで、指示を聞いてもらいたいと思って実践しています。ポジティブリスト的に言うならば「まずは子供たちと信頼関係を築きましょう」とか「教師の言葉遣いから子供たちは影響を受けるので丁寧に語りましょう」とかになるでしょうか。しかし、これがまさに「言葉で教育実践を説明することの難しさ」だと感じるのですが、言葉で説明しようとすると、どうしても「説明されていること」に意識が向いてしまいます。これはどういうことでしょうか。つまり、「子供たちと信頼関係を構築するため」にしていることをいくら言葉で列挙してみたところで「言葉に汲み尽くされない部分」はわからないのです。何を当たり前のことを言っているんだと思われたかもしれませんが、教育実践においては「明確な正解」が無い以上、どれだけ言葉を尽くして語ったとしても「言い足りない部分」と「表現し得ない部分」が出てきてしまうのです。
それは、僕の教育実践が僕の特徴や性格を通してなされているからとも言い換えられますし、僕が経験してきたことや、読んできた書物も踏まえないと理解できない部分でもあるとも言えます。教育実践とは「自分の全人格でぶつかっていく営み」であるならば、これはメチャクチャなことでもありません。昭和の教育実践家である斎藤喜博は、子供たちの授業中の議論を「闘い」と表現していました。斎藤喜博も学級の子供たちもまさに「死ぬ気で」調べてきて授業に臨んでいた姿が斎藤喜博の書物には活写されています。
だとすれば、ポジティブリストには扱いに対して慎重にならないといけない部分があることもわかると思います。教育書を読んで、ある教育実践に感銘を受けて、自分の学級で実践してみたけど、思い通りに成果が上がらないという事例は現場にはたくさんありますが、これこそまさに先ほどのまでの内容を見事に表しています。
教育実践は、科学実験とは異なるのです。条件が整備された研究室で行う実験であれば「再現性」はあります。というか、科学の強みはその「再現性」です。世界中の研究室で研究が行われるのは、それぞれの研究室での発見が、別の研究室でも再現できるからこそです。だから、科学研究は「集団の営み」足り得るのです。一方、教育はどこまでも「個別的かつ具体的」です。ある教室の成功事例をいくら研究しても、別の教室では失敗することだって何も不思議ではありません。数多くのファクターによって結果は容易に変化する「複雑系」なのです。
最近の教育言説は「科学的」になってきたと感じます。もちろん、教育にまったく「再現性」が無いとも言いませんが、あまり教育を科学的にな視点で眺めていたら、それこそ「目の前の子供たち」への関心がなくなってしまうのではないかと危惧してしまうのです。科学がこれだけの権威を獲得できたのは、科学が「社会を豊か」にしてきたからですね。しかし、科学では「教育を豊か」にすることは難しいです。画一的な手法が教育の世界を支配した世界は、どう考えてもディストピアでしかありません。教育には多様性が必要であることを否定できる人は、歴史を勉強しなおした方がよいでしょう。国よる統一的なイデオロギーに従って、ナチスがしたことや、文化大革命で起こったことは負の歴史です。
ネガティヴリストであれば、教師は常に「答えへの道のり」に対して「悩む」ことができます。これは楽な道のりではありません。ただでさえ多忙を極める教師のみなさんに「悩む」ことを要請するわけですから。でも、そもそも教育は簡単では無いのです。
ネガティヴリストは、教師を「悩ませ」ます。それを僕はここで「葛藤」表現したいと思います。僕はこの「葛藤」こそが教師の資質能力開発に対しては有効であると信じているのです。教育実践をするときには常に「これでいいのかな…」という葛藤を持つ教師は、常に「開かれている」とも言えます。これはどういうことでしょうか。ポジティブリスト的な「正解」を手にしている教師には「葛藤」がありません。常に頼るべき「経典」があり、そこには「正解」が記されているという考えこそがポジティブリストの信仰なのです。だから、その教師の思考は「閉鎖系」になります。つまり完結している。別の可能性を考慮に入れにくい状態である。これを僕は「閉じられている」と表現したいと思います。「答えを持つ者」と「未だ答えを持たざる者」では、可能性への「開かれ」に有意な差が生まれることでしょう。そして、教育実践においては教師の「開かれ」度が重要になってくるのです。なぜなら、教師が日々接している子供たちは「理解不能な他者」なのですから。
