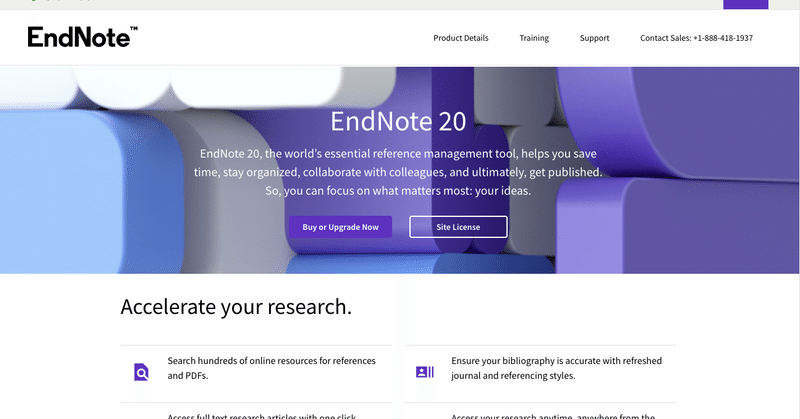
天国から地獄。そして地獄から天国へ〜【これぞSaaSだからこそできるサービス・・・な顧客体験をした話】
立場上、いろいろな学術論文を読むことが多く、そうした論文を管理するためのツールとして、Mendeley だとか EndNoteだとかいくつかのツールがを選択肢として使っていた。で、以前は Mendeley 派だったが、最近は文献管理ツールとしては EndNote のほうを使い出している。
EndNoteのソフトウェアは、有料版はウン万円するのだけれど、ここはきっちりしたものを使いたかったので、エイヤッと支払ってしばらく使ってみていた。
ところが、ここしばらく、EndNoteを立ち上げるとフリーズしたり全然webのほうとSyncしなかったりと、何百もの文献リストがまともに使えない状況になり、「死んだ・・・もう・・・」という感じで生きた心地がしなかった。
で、あーでもないこうでもないと試していると、昨日・今日とEndNoteサイドから突然、登録しているメアドに対して、
「トラブル起こってないか?こちらではそっちのEndNoteがこうこうこういう風になってるように認識している。もしトラブル中なら、こうしてこうしてこうしたらリカバーできるはずだよ」
とメールが届いた。
これ、こちらから問い合わせて返事が来たわけではなく、あちらがこちらのトラブルを察知して連絡くれたわけだ。
SaaS/Cloudサービスのメリットは、ユーザー側の利用状況、そしてトラブルもわかること。ユーザー側のトラブルが検知できると言うことは、ユーザーの問い合わせによる reactive な対応ではなく、ユーザーが困ってくることを検知したら proactive に対応することができる。
なんて素敵なユーザー体験。
兼ねてから、
「DXよりも重要なのはCX」
「DX=CX」
と、デジタルトランスフォーメーションは顧客体験向上のためにやるべし、とか、デジタルトランスフォーメーションは顧客体験とイコールである、とほうぼうで言ってるわけですが、今回のこの EndNote 体験はまさにそれだったわけです。
デジタル、ネットにつながるということは、こういう「servitization」が可能になるということであり、けっして単純に「モノからコト」とか「モノからサービスへ」ということではない。
むしろ僕が経験したのは、EndNoteが「モノ」なのではなく、それが「サービス」そのものなのであり、EndNoteのソフトウェアというのは、その「サービス」を体現するためのツールでしかないということなのだ、ということではないかな、と。Service-dominant logic の視点で見れば、そういう風に解釈ができるわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
