
体験小説「チロル会音楽部 ~ ロック青春記」第19回*ザ・レイク登場!
高校入学を待つ春休み、バンド仲間の行動範囲が急に広がって行った。
鹿児島の繁華街天文館商店街の中に、当時オープンしたばかりのロック喫茶《コロネット》に出入りするようになり、社会人の先輩バンドや、ダンスホール《ヒルトン》で演奏していたプロのミュージシャンとも交流するようになる。
自分たちもライブに参加させてもらうことも度々あった。コロネットで知り合ったブロード・ビーン・ブルース・バンドという先輩バンドなどとセッションし、楽し気に演奏する姿を、僕はただ指をくわえて見ているばかりだった。ギターは肩から下げて気楽に持ち運べるが、キーボードはそういうわけにいかない。
そのブロード・ビーン・ブルース・バンドが、彼らの地元出水市で単独コンサートを開いたときは、鈍行列車に乗って、はるばる見に行った。
公民館を会場にしたそのコンサートで「遠いところから来たお客様」と紹介され、数曲披露させてもらった。
グランド・ファンク・レイルロードの『ハートブレイカー』を演奏した時、末原君がギターソロの場面で、両膝を床に着け状態を反らせて熱演し、拍手喝采されている姿が、心底羨ましかった。
一度だけ、コロネットのライブで、アップライトピアノが準備されたことがあり、ここぞとばかり、勇んで熱演したのだが、マイクで音を拾ってもギターやドラムの音にかき消され、なかなか聞こえない。ムキになって鍵盤を叩きまくり、爪がはがれて血まみれになった。
それを見た末原君が、「カッコいい!」などと気楽にのたまっていたが、誰も気づかないような出血など、ただ痛いばっかしでへの役にも立ちはしなかった。
** ** **
1971年。
この年から海外アーティストの来日公演が急激に増えてゆく。
伝説となったグランド・ファンク・レイルロードの雷雨の中での後楽園ライブを始め、BS&T、シカゴ、フリー、ピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、エルトン・ジョン等。
前年が、ドノヴァン、ジョン・メイオールくらいだったのと比べるとえらい違いだった。
そういった変化の波を感じ取っていた僕らは、自分たちの力をより大きな場で試したくなり、ヤマハ主催の《ライト・ミュージック・コンテスト》にチャレンジすることにした。
翌年に《ポピュラー・ソング・コンテスト》が開始されているので、コピー曲でも参加できたコンテストの最終回だったことになる。
会場は県医師会館。
アンプもドラムもキーボードも主催者側によって準備される。
大きな会場で、十分な機材を使って大音量を出せるという、その条件だけでも大満足だ。しかも、準備されるキーボードは、ヤマハYC-30。リボン・コントローラーが装備されているのが特徴で、いつもため息交じりにカタログを見つめていた憧れの機種だ。その楽器に実際に触れられると思うだけで、胸が高鳴った。
ひとつだけ困った問題が起こっていた。鹿屋から合流したドラムの川原君が、高校進学後、剣道部の活動で忙しく、バンドへの参加が困難になっていた。
そんな折、鮫島君が、通い始めたばかりの高校にドラムが叩ける先輩がいるという情報を得た。加入したブラスバンドで、共にフルート担当だった2年生の中間和之君。彼とは、後に、キース・エマソンの新バンドEL&Pのコピーバンドを組むことになる。
鮫島君にしても、中間君にしても、ブラスバンドに加入していたのはほんお僅かの期間に過ぎず、後で考えると、まるで鮫島君に知り合うためだけに入部したようなものだったと、中間君が述懐している。
コンテストへの参加メンバーは、ボーカル・南貞則、ギター・末原康志、ベース・鮫島秀樹、ドラム・中間和之、そしてキーボードはもちろん僕だ。参加曲は、中間君の提案によるステッペン・ウルフの『ワイルドで行こう』。他にもいくつか候補曲があったが、南君が歌いやすくて楽器編成が自分たちにピッタリということで決定。
バンド名は、「ザ・レイク」。これは鮫島君の発案だった。
** ** **
いよいよその日がやって来た。
第5回ヤマハ・ライトミュージック・コンテスト、鹿児島県大会。
天気の良い日曜日だった。西鹿児島駅からほど近い県医師会館に、ジーンズを履いたティーンエイジャーたちが、自転車に乗って集合した。
僕は、キース・エマーソンがよく鎖のブレスレットを右手に付けていたのを真似て、手作りしたものを装着。それが、気分を盛り上げるためのお守りのような効果を発揮し、アドレナリンが泉のように湧き上がってくるのを感じていた。
参加者を集めての事前打ち合わせで、「アンプのボリュームはいじらないこと」という指示が出された。つまみは最大値10のうち「4」に固定される。
「ボリューム4じゃ、迫力出ないね」
「がっかりだね」
「なんでそんな設定にしたんだろう?」
「ロックのことを良く知らないんじゃない?」
「せっかくの大きな会場で、苦情の心配もないんだし、思いっきりやりたいよね」
「この中ではオレたちが一番年下だし、顔ぶれを見てもどうせ予選落ちするんだから、結果なんか気にしないで、好きなようにやろう」
「そうだね。せっかく大勢の人が見てくれるのに、あとで悔いが残るのはいやだよ」
「よし、ボリュームを上げよう」
「思いっきり最大ね」
「でも、その場でバレたら、すぐに戻されるぞ」
「あわてずに、できるだけ自然な動作でやらんといかん」
「それと、演奏が終わったら、元に戻しとかんとね」
ロックにとっては、大音量こそ命。せっかくの大舞台で中途半端に事を終わらせるなんて、考えられないことだった。
反骨精神旺盛で、人を驚かすことが大好きなティーン・エイジャーたちである。
― わくわくするぜ! ―
僕らは、すでに「コンテスト参加者」の立場をかなぐり捨て、入賞などそっちのけの、凶暴な「サウンド・テロリスト」と化していた。
さあ、出番がやってきた。
前の出演バンドの終了を今か今かと待ちかまえ、そして僕らはステージへと向かった。計画実行へ向けて、はやる気持ちを抑え、わざとゆっくりと歩く。
― 素知らぬ顔をして、できるだけ自然な動作で・・・ ―
高鳴る胸を押し隠し、自分に言い聞かせながら、さりげない動作でアンプのボリュームを最大に上げた。
司会者が、バンド名と演奏曲を告げている。爆発の瞬間が、刻一刻と近づいてくる。会場にいる誰もが、そんなことを知る由もない。
ドラムの中間君が、スティックで合図を出す。
演奏スタート☆!
その途端、録音技師はぶったまげてヘッドフォンをはずした。
ギターの大音量とドラムの爆音が、花火のようにはじけ飛ぶ。
鮫島君のベースに導かれ、南君のドスの効いた声が響き渡る。
アンプの大音量に負けじと、中間君のスティックさばきにも力が入り、
トップシンバルがやけに軽く、ひらひらと動きまくるのが不思議なほどだ。
バッキングに回っている間、キーボードのフット・ボリュームはある程度絞っておいた。
― Born to be wild!
Born to be wild!
キーボード・ソロが近づく・・・
― 来た!
フットボリュームを踏み切る。
― ぎゅわーーー! ―
鍵盤の端から端まで、思いっきりの高速グリッサンド。そして目一杯の高速で指を動かし、目立つことに全身全霊を注いだ。
憧れのリボンコントローラーも使いまくる。
ウィ~~ン
チョワワ~~~~オ
ミュインミュイ~~ン!
髪を振り乱して、もう無我夢中である。
そして、めでたく無事演奏終了。
いや、録音技師にとっては、無事どころではなかったのだが・・・。
ステージを去る前に は、ふたたび素知らぬ顔で、アンプのつまみを元の位置に戻しておいた。
** ** **
この日の審査は、異常に長引いた。
どのくらい待っただろう・・・。
とにかく普通じゃなかった。
1時間以上、いや、もっと?。
散々待たされ、そして審査結果の発表が始まった。
開催者の指示を無視し、反則行為を行った小僧たち。
どうせ入、賞など端からあり得ない。
と思っていたが、
ひとつ、またひとつと入賞バンド名が呼ばれてゆき、めぼしい名前は、ほぼ出揃ってしまった。
― あれ? ほかに呼ばれそうなバンドって、あったっけ?
もしかして・・・、
もしかする?? ―
そして、最終宣告の時がやってきた。
「では、優勝者の発表です。
湖のように無限の可能性を秘めた・・・」
その言葉に、全身が鳥肌立った。
「ザ・レイクです」
バンド名が告げられると、僕らは全員大声をあげステージに向けて走り出していた。
** ** **
チロル会音楽部結成から3年弱。映画音楽の『駅馬車』などを演奏していたことを思えば、よくぞここまで成長したものである。
周囲とのトラブルに悩まされ、居場所のない閉塞感に囚われていた僕らが、初めてストレートに認められ、自分たちの力が世間にも通用するんだという手応えを、初めて掴んだ瞬間だった。
** ** **
コンテストからほどなく、鹿児島のラジオ局南日本放送の番組で、特集が組まれることになった。
聴取者参加の公開番組30分をフルに使って、コンテスト優勝バンドの演奏のみを紹介するという企画。そのために僕らはスタジオに呼ばれ、5曲を演奏した。
ローリングストーンズの「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」、「グランド・ファンク・レイルロード」の「ハートブレイカー」、テン・イヤーズ・アフターの「バッド・シーン」、ザ・ナイスの「夢を追って」、そしてコンテスト参加曲「ワイルドで行こう」。
** ** **
その番組とは別に、コンテスト当日の演奏が、あるラジオ番組で紹介された。当日を振り返りながら、1曲ずつ聴いていたのだが、僕らの演奏だけは、コンテスト当日の演奏ではなく、後日スタジオで録音されたものに差し替えられていた。考えて見れば、当日の録音などまともに収録できたはずがない。録音技師がぶったまげてヘッドフォンを外したぐらいだから・・・。
この一連の流れを改めて振り返ると、コンテストの日、審査が異常に長引いた原因が何だったのか、想像がつく。
レイクの音を録りなおす事後策までが、議論の的になっていた可能性が高い。
後年、会場で聞いていた人から聞いた話だが、僕らの演奏だけが、始まった瞬間から、全く次元が違っていたという。
結果など端から気にせず、規定違反を犯すドキドキ感もプラスに作用し、爆発的エネルギーに繋がった。たぶん、審査員の心にも、響くものがあったのだと思う。
博多開催の九州大会に参加する前、審査に加わった南日本放送のディレクターから、しっかりと念を押された。
「今度は、絶対アンプのボリュームをいじっちゃダメだよ。九州大会では、それだけで失格になるからね」
県大会で失格にならなかったのも、ほぼあり得ないような極めて異例の措置だったのではないか・・・。やんちゃ坊主たちの、傍若無人の暴挙で周りを散々振り回した挙句、それでも知恵を絞ってバックアップしてくれた温情。当時は、それに全く気付いていなかった。
「湖のように無限の可能性を秘めた」という、あのアナウンサーの素敵な言葉が、その後どれほど大きな励みになったことか・・・。
あの瞬間のことは、今でも忘れられない。

左から、鮫島秀樹・中間和之・めどう・南貞則・末原康志
県大会当日、県医師会館前にて
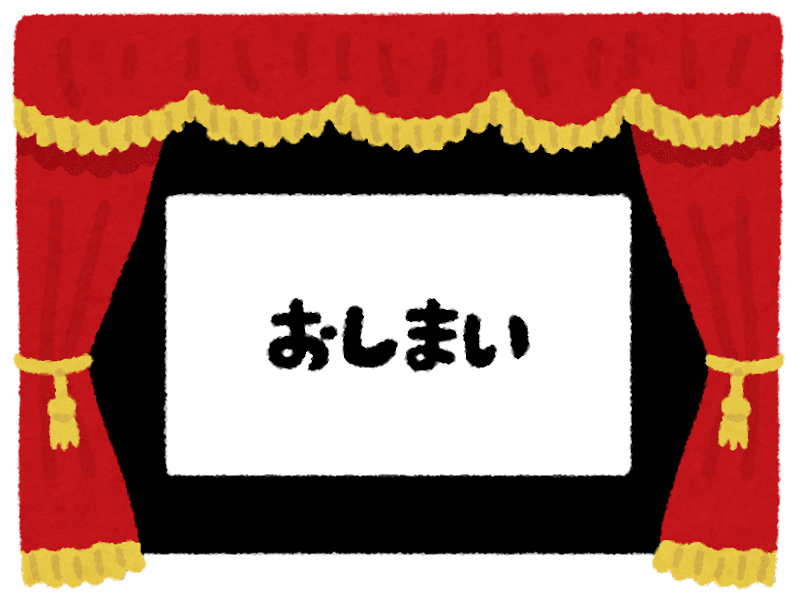
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
