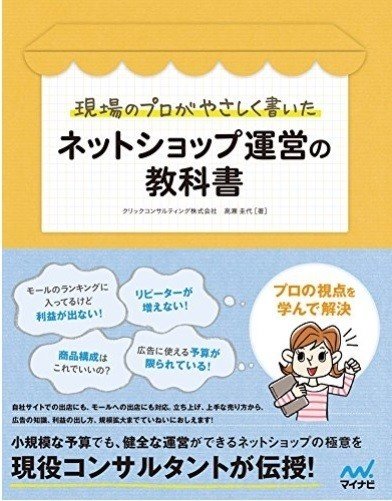ゼロから学ぶECビジネス ECビジネスは儲からない!?編
おはようございます。ドドル・カンマネ あおけんです。
このnoteにはマガジンという記事をまとめる機能があるようなので、試しに僕の転職関連の記事(4本)をまとめましたので、興味がある方はこちらからどうぞ。あらすじは↓です。
日系企業で16年、40代後半のサラリーマンが外資の日本代表になるまでの話をまとめました。
さて昨日に引き続きECビジネスをもう少し掘ってみたいと思います。昨日の投稿では、ECビジネスの輪郭をひとつのチャートにまとめて俯瞰を試みました。

ECビジネスは儲からない!?
そして今日は実際ECプレイヤーの目線にたってネットのショップ運営について学んでみたいと思います。今日参考にしたのは、クリックコンサルティングという中小企業のネットショップ運営支援をしている会社の高瀬代表のこちらの本です。
この本で注目したのは「ネット通販=お金がかかる」という覚悟、というチャプターです。実店舗を持たなくてよい通販はお金をかけずに儲けられると思っている人が多いと思いますが実際は違うようです。

お客さんをリスティング広告やモール内広告などで呼んできて、実際に購入してもらうにはひとりあたり3~5,000円の広告費がかかり、そのお客さんの売上単価は3~5,000円ということ。なんか変ですね。
仮に製品を2,500円で仕入れて5,000円で売っていて(送料はいったん考えず)、お客さんをひとり獲得するのに5,000円かかったとすると粗利だけでマイナス2,500円。純粋にここで赤字。ここには店舗構築、運営コストは含まれていません。売れば売るほど損をする、という構造です。厳しい。
結果、”初年度利益を出すことに重点を置きすぎるお店ほど撤退するケースが多い”とのこと。次がその負の思考ループです。

事業は実際には利益を生まなければどんなに素晴らしいコンセプトでも世の中に必要とされていない、という位置づけがされ、強制終了となってしまいます。実店舗を準備しなくてもよいECビジネスは低コスト体質のような錯覚がありますが、実際は顧客獲得単価がものすごくかさむビジネスということになりますね。
逆にいうとその顧客獲得のための広告で現在世界を支配しているのがGoogleであり、Facebookということになります。
初回のユーザ獲得時は基本粗利ベースで赤字を覚悟しなければならないモデルということは、一度来てもらったお客さんに2回目以降は”追加コスト”を発生させずに購入をしてもらい、何回かその状況を作ることでようやくひとりのユーザから利益を生み出せるようになります。
そのため、メルマガなどを通じでヘビーユーザになってもらうように企業努力を行っていくことが収益率を上げる上で最も大事なポイントとなり、このリピート率をどう上げるか、というリテンション施策がECビジネスの肝と言えそうです。
この本の著者はこのチャプターで次のようなコメントをしています。
成功するお店は2~3年で黒字を出す計画で運営されるパターンが多いですし、そのくらいの資金を投入できる覚悟がないと難しいと思われます。
1年目は投資、2年目で収支トントン、3年目で黒字、1年目のマイナスを取り戻す、くらいが一般的な流れ。2~3年の回収計画が必要と思われます。
そんな覚悟が必要なビジネスだったんですね。EC事業者さんは皆さん、この覚悟を決めてビジネスをしてらっしゃるわけです。やはり学ぶことは大事です。
コストの話
なんとなくのコスト感を掴みたいというのは事業開発畑でやってきた人間のサガ(性)。この本の中に商品タイプ別のモールに払う費用をまとめている事例があったので、その情報を下のチャートにまとめてみました。

商品タイプを分けるのは、その商品の性質によってマーケティングの仕方が変わるから。ここでは便宜上2種類のタイプの商品でそのコスト構造を見ています。
1.型番商品:
ナショナルブランドの製品のようにみんなが認知していて、指名買いが起こるもの。欲しいテレビを型番を頼りにモールで検索するようなイメージで、当然ユーザの商品に対する認知と購買欲求は高いですが、その分ライバルも多く価格競争になりがちです。
2.オリジナル商品
例えば完全食のパスタやパンを作っているBase Foodのように自分たちでしか作れないようなオリジナルな商品を売る場合の事例。認知が低いので、どんな商品なのか、なぜそれが良いのかを広く知ってもらうために広告費がかさむ傾向にあります。
型番商品の場合、モールへの費用拠出は、売上の8.5%。売上月商400万円であれば34万円です。オリジナル商品と比較してもベースでかかる費用は売上の7%程度(28万円/34万円)で、あとはポイント付与分です。認知があるものを価格競争を乗り越えて売る、なので、モールの検索機能を活用し集客をして売り切るモデルになりそうです。
ドラッグストアが日用品を薄利で安く提供することで集客し、薬で儲ける、ということをやるように型番商品を客寄せとして、他の粗利の高い商品を追加で売るなどのバランス感覚も必要になってくる気がしますね。
一方、オリジナル商品はベースの7%に加え、ポイントで売上比6%、広告費が15%の計28%がモールへの拠出費用となっています。月商400万円の場合、112万円となり、売上の1/4以上がモールへの拠出で消えることになります。
前チャプターであったように、創業時売上と広告費が同じところからスタートして、その後月商400万円超えてもオリジナル商品の場合、売上の1/4以上の費用をモール側に払うということが結構リアリティのあるコスト構造であることがわかってきました。
Google、FB、Amazon、楽天など胴元ビジネスが常にECビジネスの成長をドライブしながらも、逆に収益を圧迫する存在であることがおぼろげながら見えてきたところで本日のお話はおしまいです。
次回もまた違った切り口からECビジネスを掘ってみたいと思います。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
それでは、今日もよい一日を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?