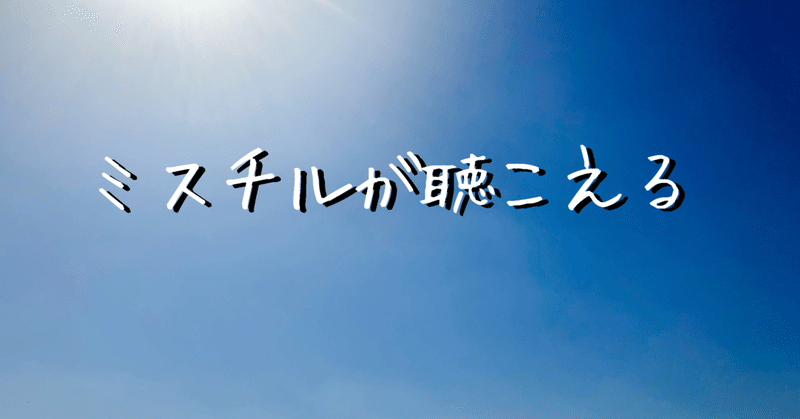
虹の彼方へ (短編小説『ミスチルが聴こえる』)
健くんは雨上がりの空を見上げて、「虹だ!」と叫んだ。私はあまりにも遠い存在に、あまり関心を持つことができなくて、「そうだね」と素っ気ない返事をしてしまった。
「風花、虹嫌い?」
「嫌いじゃないけど、遠いなって思って」
「遠い? 僕には近くに見えるよ」
「どうして?」
「僕、虹を渡ることができるんだ!」
私には、意味不明な言葉。健くんって、変な人。
「風花は虹を渡ることができないの?」
「できないよ。どうやって渡るの?」
「簡単だよ。あの虹を、頭の中で描けばいいんだ」
「頭で描く?」
「そう。頭で描いて、虹を渡るんだ。楽しいよ」
小学生の私でも、健くんの想像が幼稚だと思ってしまった。
「変なの」
そんなふうに、私は健くんを突き放してしまった。
土砂降りだった雨がピタリと止んで、空には煌めきすら広がっている。私はその隅に、小さな虹のかけらを見かけた。そういえば、小さい頃に同級生だった健くんが「虹を渡れる」って言っていたっけ。あの頃は馬鹿にしていたけど、大人になった私は健くんの想像力が羨ましく思えた。
「やってみるか」
私は目を瞑って、小さな虹に乗る自分を思い浮かべた。赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色、緑色、青色、紫色。どの色も、自分らしさを存分に出していて、誇らしげにしている。私は、どの色にもなれない無個性な人間。
健くんは、今何色になったのだろうか。まだ、虹を渡っているのだろうか。
健くんとは小学生以来一度も会っていないから、彼がどんな姿になって、どんな顔をして生きているのか、私にはわからない。それでも、何となく虹を渡っている健くんがいてほしいと願ってしまう。純粋だったあの頃を、忘れてほしくないから。
「虹を渡るって、案外良いかも」
私は、虹の彼方まで歩きたいと思う。現実だけが人生じゃない。とんでもない理想だって、人生に彩りを与えてくれる。健くんは、多分そんなことを私に言いたかったのかもしれない。
「ありがとう、健くん」
虹はすっかり消えてしまったけど、私の心には永遠に残り続けている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
