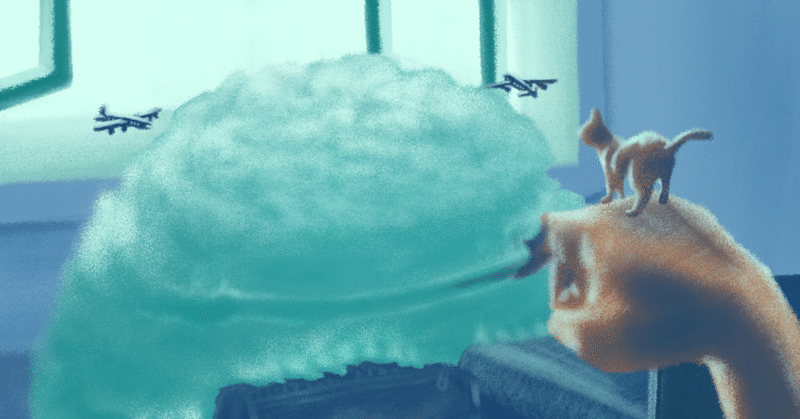
日本が注力する線状降水帯予測について調べてみた
2024年5月2週目は東日本全域で雨が降りました。日本列島に沿った低気圧が発生しましたが、今回は雨量が少なくて済みました。これが7月頃になると短時間で大雨が降る線状降水帯が発生し、甚大な被害を受ける地域が毎年出てきます。
気象庁ではこの線状降水帯の予測強化を目指したと取り組みを行っています。調べてみたらへぇ〜と思ったので少しご紹介します。

予測強化の取り組み
24年3月からスパコン「富嶽」を利用したNAPS11稼働開始
気象庁は以前からスパコン自体は使用していたのですが、24年3月から、より高性能なマシンでNAPS11(11世代型の数値解析予報システム)の稼働を開始しました。
24年5月から線状降水帯の事前予測結果の公開開始
実は22年からNAPS10による線状降水帯の予測を行っていました。
しかし今年5月からNAPS11の稼働が開始し、気象庁は線状降水帯の予測結果を発生の30分前に公開するようになりました。まだ発展途上の技術ですが、今年の夏これがどの位活躍するのか期待したいです。
そしてこれが2027年には2〜3時間短縮を目標としています。結構すごい。
観測強化の取り組み
予測精度を上げるために、予測アルゴリズムだけでなく観測情報を増やしたり精度を上げる取り組みも行っています。
各種観測機器の強化
以下の観測基地の強化の取り組みを行っています。
・アメダスへの湿度観測追加 令和5年度は159地点に整備予定。
・気象レーダーの更新強化 令和5年度は沖縄・松江・新潟・名瀬を二重偏波レーダーに更新(沖縄は4月、松江は6月、新潟は11月にそれぞれ更新済み)
・洋上の水蒸気等の観測の強化 機動的な気象観測を担う海洋気象観測船「凌風丸」の竣工(令和5年度末)。
・マイクロ波放射計の整備 令和4年度までに西日本 太平洋南側沿岸域の17箇所に設置完了。
・次期気象衛星ひまわり10号の運用
ひまわり10号に関して以下で取り上げます
ひまわり10号設計開始
現在稼働している気象観測衛星ひまわり9号は、令和11 年度で運用終了の予定です。今年から10号の設計を開始、令和10年に打ち上げの予定です。
この10号には搭載するのはI3harris社のイメージセンサーです。
I3harris社は米国、韓国も御用達の会社です。8号・9号に搭載していたのは当時最先端のイメージセンサーを実証実験も兼ねて、ひまわり専用にカスタマイズして搭載していました。しかし今回はI3harris社で打ち上げている衛星(ABI、GEOS-R)に使われているものと同規格のセンサーを搭載する予定です。
赤外サウンダー
この赤外サウンダーというのは、イメージセンサーの事だと私は理解しています。
今までと違うのは遠赤外領域の波長の感度が高いこと。雲の分子をすり抜けてセンサーに届いた遠赤外領域の光を受信できるので、今まで撮影できなかった夜間の雲下の画像も取得できるようになる予定です。赤外サウンダーが搭載される以外、まだ具体的な改良点は公表されていませんが、精度は向上することを期待したいです。
おわりに
いかがだったでしょうか。日本では線状降水帯の予測に非常に力を入れていることがわかりました。
ちなみに米国についても調べたところ、噴火やひょうの予測に力をいれていたり、緑色特化のセンサーで地上のクロロフィル量を測定したり、偏光センサーで雲や霧の濃度を測定したりと、日本と大分異なっていたため機会があれば調べてみたいです。
少し長文でしたが、最後までご覧頂きありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
