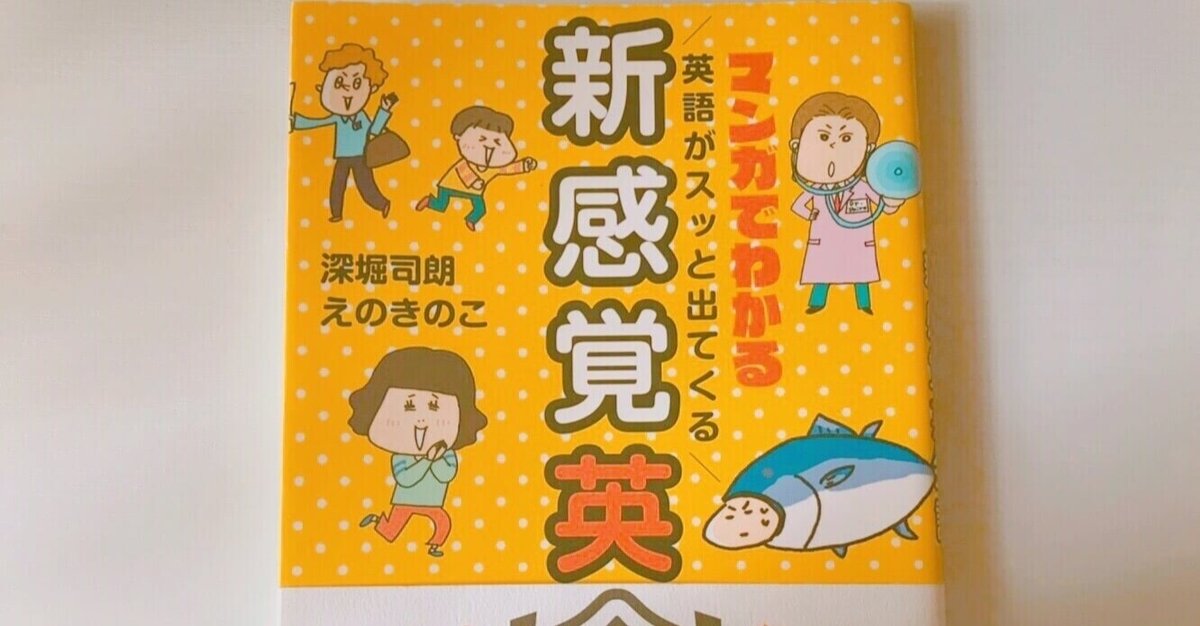
「マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話」の書評📚
今回は、英語初心者向けに、漫画のレビュー(書評)を書いてみる。
「マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話」
っていう本なんだけどね。知ってる?
これ、漫画形式なんだけど、内容的には学校英語をけなしつつ、ネイティブの英会話を習得するための秘訣が159ページにまたがって描かれている。
形式がマンガなので、堅苦しい雰囲気ではなく、あくまでやわらかい雰囲気で、そこまでガチ(本格的)な本ではない。笑
結論から言えば、この漫画を読んだだけでは英語を話せない。
でも、英語を話せるようになりたい人には、重要なことが書かれている。
昔から英語に強いニガテ意識を持っていて、中学英語で挫折・・・。
そんな著者も、英語の必要性を実感して、聞き流し英語教材とか買ってみるものの全然ダメで、どうしようと困っていたところに、Shiro氏が登場して、そのまま英語の極意を伝えていくっていうストーリーである。
ぼくもザッと一通り読んでみたんだけど、面白いなって感じる部分がいくつかあったから、この漫画から得た学びをきみにも共有していくよ^^
マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話
著者:深掘司郎 / えのきのこ
発行者:高橋秀雄
発行所:高橋書店
住所:〒112-0013 東京都文京区音羽1-26-1
お問い合わせ:
03-3943-4529(内容・不良品)
03-3943-4525(在庫・注文)
![]()
📚 「マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話」の面白いところ
ぼくは現時点でいちおう、「英検準1級」という半端な実力を持っているんだけど、このマンガを読んで学べたことがたくさんあるので、そのアウトプットがてら、この本の面白いところをきみにも紹介していきます。
🌷「とりあえずSVだけ言えばOK」的な発想
英会話では特に、日本語にとらわれて「長いセンテンス」を言いがちなんだけど、でも実際には短い会話を繋げていくだけで、ある程度の会話は成立する。
困ったらとりあえずS(主語)とV(動詞)だけをパパっと言ってしまえば、あとはネイティブが細かい質問を訪ねてくれるから、それにこたえる形で会話を繋げていけばいいという発想が解説されていた。
たとえば「昨日、自宅に帰る途中でコンビニの近くを歩いていたら、女装した男性が店から出てきてビックリした」ってことを英語で伝えたい。
そんな時はとりあえず
"I saw a man."(私は男性を見た)
とだけ言えばいいらしい。
その後で、男性を描写する時に
"The man was wearing a mini skirt"(その男性はミニスカートを穿いていた)
と、後付けで説明する。
そこまで言えば、相手のネイティブが面白がってきみの見た何かを確認すべく、"So, you saw a man dressed like a woman at a convenience store on your way home last night?" とか言ってくれるので、"Yes!!!! That's right!!!!" とか相槌を打てばいいっていうお話ですね。
🌷「主語ではなく動詞から英文を作れ」的な発想
たとえば「テストがよくできた」って言いたい場合、この文の主語は何になると思う?
「が~」って付いてるから「テスト!」って答えたくなるかもしれないけど、実はよくできたのは「テスト」ではなく「わたし」だよね。
なので、英語的な発想だと、"The test does well" じゃなくて、"I did well on the exam" って感じの文になるということです。
英語ができる人って、普段から無意識でこういう技術を駆使してるわけだね。
まあ他にも色んな「英語を話すコツ」がマンガでうまく解説されていたんで、気になったら読んでみると良いかもしれない。
まとめると、だいたいこんな感じ。
~~~ Japanglishの特徴 ~~~
🍅 無理やり一文で話そうとする
🍅 話が漠然としている
🍅 やたらbe動詞を使う
🍅 脳内で日本語を英訳してから話す
🍅 言葉で感情を表現しない
Japanglishってのは「日本人英語」のことだけど、まあ理論だけで勉強をしてしまうと、日本人の発想でどうしてもモノを考えてしまうんだ。実際には英語圏特有の発想とか感覚があって、そこをいかに理解できるかが英会話の鍵となることが多い。
上記の特徴はどれも「あるある」ってぼくも思ったから、日本人の英語学習者なら誰もが通る道だと思ってくれていいだろう。
だから著者のShiro氏はそこに警鐘を鳴らしていて、「日本語に頼らない英語を身に付けよう」という主張をしているんやね。
![]()
📚 日本語にとらわれずに英語を話す発想を持つ
「息子のサッカーの夏合宿」の話って、英語でなんて言えばいいと思う❓
夏= summer
合= together
宿= stay
だから、"Summer together stay!!" みたいな発想にはならないよね。
なぜならそんな言葉は英語圏には存在しないから。笑
これはぼくも普段から口を酸っぱくして言ってることだけど、日本語と英語を無理やり「一対一対応」させようとすると、いろいろとおかしい点が出てきてしまうのが、英語の特徴なんだ。
だからこの著者のShiro氏は、いっそのこと「日本語を英語に訳すのをやめなさい!」と言ってる。
日本語を無理やり英語に訳そうとするのではなく、「夏合宿」という言葉のイメージから感覚を取り出して、3~4コマのイメージを頭に思い浮かべ、それを英語で読み上げるようなイメージで話すと良いって話ね。
たとえば「今年の夏、静岡でサッカーの夏合宿に行った」場合、
My son went to Shizuoka this summer.
(息子が今年の夏、静岡に行きました)
He practiced soccer every day.
(彼はサッカーを毎日練習しました)
It was hard, but he had a good time!
(大変だったけど良い時間を過ごせました)
って感じで、「夏合宿」を3つの要素に分解すれば、シンプルな英語でもネイティブに通じる英会話ができるってことだ。これは素晴らしい。
![]()
📚 ネイティブが使わない英語表現
Shiro氏が言うには、学校でぼくらが習った英語の中には、ネイティブがほとんど使わないような表現も混じっているとのこと。
たとえば "so-so" っていう表現を、ぼくらは中学生の時に学校で学んだはずだ。「まあまあ」って意味だけど、実際にネイティブが使うのは "not bad" とか "not so bad" になる。
また、"such" もぼくらは学校で習ったけど、ネイティブはこれをあまり使わず、どちらかっていうと "like" を好んで使う傾向があるらしい。
ちなみにこの "like" は「~が好き」って意味じゃなくて、「~のような」って意味の前置詞だから、一応知っておいてね。
他にも「美味しい」って言いたい時に、ぼくらは "delicious" って英単語を習ったと思うけど、実際にはこれもネイティブは滅多に使うものではなく、普段は "it's good" くらいの軽いニュアンスで済ませるらしい。
まあ確かに、そんな美味い食べ物って、滅多に出会いませんやね🍛🍝
こういう事例を挙げられると、確かに学校英語がいかに変な知識が多いかってのがよく分かる気がする。。。
私立のお嬢様学校とかだとまた違うんだろうけど、一般の田舎の公立中学では、まだまだ古い知識に囚われてる人も多いだろうね。
![]()
📚 「マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話」のツッコミどころ
最後に、このマンガを読んでみてぼくが思ったツッコミどころがいくつかあるので、それを共有して今回の書評終わりにする。
日本語に頼らない英会話を目指すからか、「日本語が書かれている辞書は使うな!英英辞典を使うべき」っていう主張があったのだけど、これはぼくは個人的には微妙だと思った。
英語上級者であれば、英英辞典を使いこなせるだろーけど、ぼくが高校1年の時の英語教師に同じことを言われて買ったLongmanは、結局1~2回しか使わず、本棚の奥でホコリを被ることになった(笑)
だってさ、英語を英語のまま理解できるのって、ぶっちゃけ「上級者だけ」じゃん。
ぼくはある程度、上級者の部類に入ってるから、「英語を英語のまま理解」することもできるんだけど、自分がもし初心者の段階でコレ言われたら、さすがに受け付けないだろーな・・・って思った。
まあ著者のShiro氏自身、過去に学校で習った英語がアメリカで使い物にならなかったらしいので、それに対する嫌な思い出を自分の教えに反映させているんだろうと思う。
ただ、ぼくの意見としては、学校英語を過剰に批判しても、初心者が英語を話せるようになるわけではないので、あまり最初から無茶なことはやらない方がいいと思うんですわ。
だってさ、仕事とか人間関係でも、必ずしも面白おかしいことばっかりじゃないよね。
ある程度、退屈な時間とか、無意味そうに思える時間を費やして、それにある程度耐えて先に進み続けるからこそ、ハイレベルな関係性が得られるわけで・・・。
ネイティブ感覚を理解して、英語を使いこなせるようになると、確かに楽しいことは多いんだけど、その領域に達するまでは、やっぱり我慢してコツコツ地道に努力することが必要になる。
だから最初のうちは、英語を日本語で理解しても別に良いと思うんだ。
いきなり英語を英語のまま理解しようとすると、確実に混乱する。
Shiro氏のやり方は、英語中級者以上向けだと思うね。ある程度、英語を理解して使える人なら、参考になると思う。
ぼくは今、彼の英語教材の "Nativebuster" で、英語の「上級レベルの基礎」を深く学び直しているんだけど、いいねぇ~~やっぱり。
ただ、初心者が彼の教えを受けて、どこまで吸収できるかは分からないので、そこは自己責任で調べてみると良いと思うぜ。
![]()
📚 「マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話」の評判
さて、この漫画のレビューがいくつかあったので、ここに載せておきます。やっぱりマンガだからか、みんな読みやすいみたいだね。
【マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話/深堀 司朗他】日本人が英語を学習する前に知っておいたほうがよいことがたくさん書いてある。特に「話すこと」に関して。これを読んだからすぐにどうこ… → https://t.co/FylgVvqQuk #bookmeter
— Shingosa- (@sing_osa) February 20, 2019
語学を学ぶことは、その背景にある文化や考え方を柔軟に受け入れることである、というのが印象に残りました。
— Kenyou@ESO (@hiroma_BB) July 23, 2017
.
マンガでわかる 英語がスッと出てくる新感覚英会話 深堀 司朗 https://t.co/x9cLzKifdW via @amazonJP#英会話
💡日本語と英語の違いを理解した上での基礎力をつける事の重要さを教えてくれます。
同著者による目からうろこの英会話も読んでいます。両著とも基礎が大事なことを英語と日本語の違いを説明しながら教えてくれているので分かり易いです。また基礎は初心者のうちだけ重要なのではなく中級?上級者になろうとも大切な事なんだとも思いました。ちょうどアスリートが、心肺能力、筋力、体の柔軟性を維持するためにランニング、ウエイトトレーニング、ストレッチ等を続けていることに例えられるかもしれません。日常のルーティンに組み込まれていると一番効果が出るかも知れませんね。通勤電車の中でとかで。
💡言ってることはわかるんだけど…
「英語がわかるようになる」「英語やり直し」系の書籍を何冊も読んでみましたが、内容的にはそれとあまり変わりがなかったように思います。作者の場合、先生がいて、身近にアウトプットできる場があるから、得た知識を体験することで強化できるんじゃないかと思いました。
![]()
📚 まとめ
ぼく個人の意見だけど、「学校英語のカリキュラムがダメ」なんじゃなくて、「学校で習うべき英語をきちんと理解していない日本人が多い」から、日本人は英語を話せないままの人が多いんだと思う。
つまり多くの人は、「学校で学ぶ知識を理解していないのに、やたらと学校を批判する」という、なんとも謎な立場をとっているのだ……。
Shiro氏みたいに、「一通り理解した上で批判する」ならまだしも、そうでないのに批判しても自分のタメにならないから、そこらへんは気を付けなければいけないね。
一つの教えだけにとらわれることなく、幅広く色んな題材から学んでみるのがいいと思った。特に読書とか漫画とか、サラッと読める系のものは。
ぼくは英文法を中心として初心者向けに英語を教えている立場なので、最初はとにかく「文法」をマスターした方がいいと思ってる派だ。
だって周りを見渡しても、文法をやらずに英語を極めた人って皆無だし。
受験でやった英文法を批判してる英会話講師は多いけど、実際その人たちもなんやかんやで英文法のトレーニングに取り組んだ過去を持ってる。
これはほぼ例外はないので、信じて良いと思う。
特にちょっとした通訳とか翻訳をできるようになりたい人であれば、「日本語と英語の両方で」考えるようにするといいんじゃないかなと思う。
このnoteでは英語初心者向けに、なるべくモチベーションを高めて英語の壁をガンガン乗り切ろうぜって話をしてるから、他の記事も読んでみてね!
【次の記事】
▷ 英語の勉強本をいくら読んでも、英語は話せるようにならない!?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
