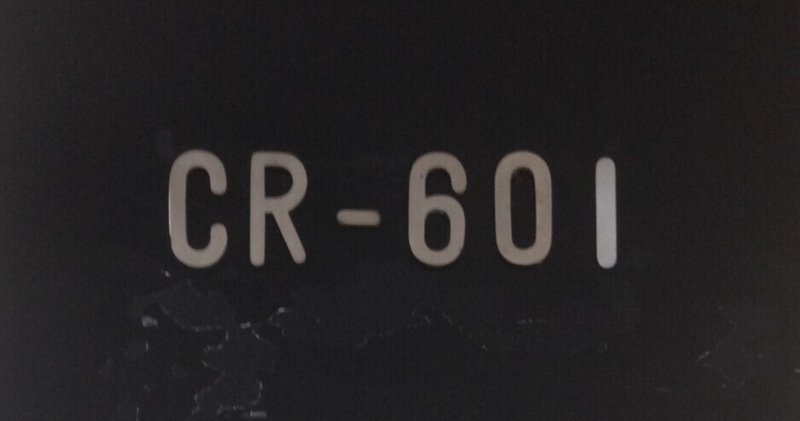
胸の燃料を焚きつけろ─青春アドベンチャー「走れ歌鉄!」
タイトル画像はセリフ収録したNHKのスタジオのドア。黒地に白文字で「CR-601」の部屋番号。機関車の車体みたい。
聴いてすぐClubhouse感想会
作品を作ったからにはたくさんの人に届けたいので、映画がDVDになるのも番組が再放送されるのも本が重版されるのも、うれしい。
2016年の2月にNHK FMの連続ラジオドラマ枠「青春アドベンチャー」で放送された「走れ歌鉄!」全10話が再放送されると聞いたときも、もちろん喜んだ。
あらためて、はじめまして、歌鉄!
5年前は存在しなかったClubhouseで盛り上げルームをやることにした。戦争孤児のシドウを演じた大浦千佳さんを誘った。
初日と2日目は放送前の21:00にルームを開いて「前説」の後、それぞれが21:15-30の放送を聴いてから再集合していたが、3日目からは「各自で聴いて21:30集合」にした。
ルームに間に合うように、毎日リアルタイムで放送を聴いた。もしルームをやらなかったら、聴き逃し配信をまとめて聴く日もあったと思う。
出演者のクレジットを読み上げ始めた辺りでルームを開け、21:30過ぎから感想を聞く。家族に出したおかずの感想をその場で聞くぐらいの時差のなさ。
集まってくれたのは、ほぼ「膝枕リレー」で知り合った人たち。「膝マメのコバ」こと小羽勝也さん。「膝枕」だけでなく「わにのだんす」も朗読、さらには合体版も披露してくれているきぃくんママさん。夫婦で59膝目を朗読された全盲女優の美月めぐみさんと鈴木橙輔さん。膝枕外伝作家のやまねたけしさん、サトジュンさん。膝枕営業トップセールスのkana kaedeさん。Miho.Fさん、堀部由香里さん、桜井ういよさん、河崎卓也さん、宮村麻未さん、さんがつ亭しょこらさん、かわいいねこさん、金井将明さん、などなど。
膝枕リレーも歌鉄も走るよどこまでも。
聴いてすぐ分かち合う。これがすごく楽しかった。「浮浪児の歌」を耳コピで口ずさむ人あり、「明日はどうなる?」の予想をする人あり。
わたしは鉄道の豆知識や戦後の鉄道事情やせっせと教えてくれた鉄道通の友人からのメモを掘り起こして紹介し、大浦さんは歌の特訓のエピソードや役や収録のときの思い出を語ってくれた。
演出の小見山佳典さんは、5日目と最終回に参加。「今日はこちらのルームです」とアドレスを連日送ったところ、アカウントを取ってくれた。小見山さんが「希望ではなく勇気の物語に」と最初に方向性を示してくれたメールも披露した。
膝枕erの桜井ういよさんが歌鉄アイコンを作ってくれた。集まった人たちが次々と着替えてくれ、ルームが青空色になった。

歌鉄ロスのなか、今さら番宣note
8月13日に最終回が放送され、2日経った終戦の日。放送前に書くつもりだった「歌鉄」紹介noteを放送後の今頃になって書いている。
今さらなのだけど、まだ間に合う。配信期間1週間のらじるらじるでの聴き逃し配信が残っている。一番早く消える6話は8/16(月)21:30まで。一番長く聴ける10話は8/20(金)21:30まで。
6話から10話は感想会での「次回どうなる?」予想が日に日に盛り上がった。「西の港の新聞記者がもう一度登場するのでは?」「果たして歌合戦に出られるのか?」「アゲインはマリを追いかけて来るのか?」「機関士のじいちゃんは歌うのか?」などなど。
9話が終わった時点で、最終回でどうやって風呂敷を畳むのか、記憶が曖昧だった。聴いてみて、そうだったかと思い出し、いい終わり方じゃないかと感じ入った。
「燃やしても燃やしてもなくならない燃料」という言葉が出てくる。それは心の中、胸の奥から湧いて来るもの。愚痴もため息も涙も歌になり、燃料になる。コロナ禍が1年半あまり続き、気持ちがすり減ることが多い今、5年前に書いたセリフに励まされた。
15分だけ聴ける人は最終回だけでも、ぜひ。75分聴ける人はぜひ6話から。
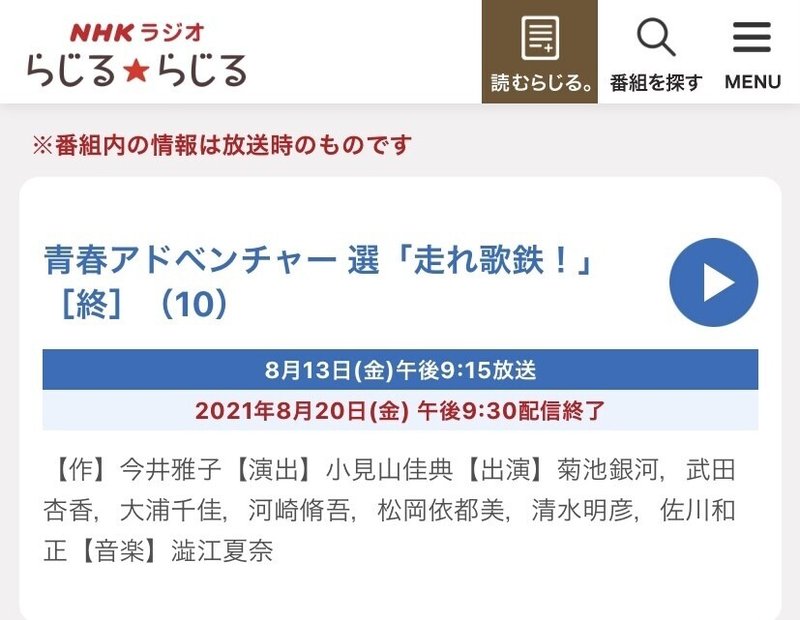
自称「書き鉄」が書いた鉄ミュージカル
「走れ歌鉄!」の成り立ちについては当時の日記をどうぞ。
✏︎初放送時2016年2月1日(月) の日記はじめ✏︎
NHK FM青春アドベンチャーで初めてのオリジナル連続ラジオドラマを書きました。
タイトルは「走れ歌鉄!」
青春アドベンチャーの枠でデビュー間もない頃に「不思議屋旅行代理店」というオムニバスドラマの第1回「ランゲルハンス島の謎」と第10回「過去に架ける虹」を書かせていただいてから幾星霜、2005年に稲生平太郎さん原作の「アクアリウムの夜」(全10回)を、一昨年には岡田淳さん原作の「びりっかすの神様」(全5回)を脚色させていただきましたが、全編オリジナルは初めて。
1話15分×10回。原作なしの150分オリジナルは、思った以上に大変でしたが、聴くとあっという間です(笑)
演出の小見山佳典さんに「青春アドベンチャーやりませんか」と声をかけていただいて、パッと思い浮かんだのが「鉄道もの」。そこからの連想で「戦後に戦争孤児たちが自分たちで機関車を走らせる」という物語が膨らんでいきました。
戦後70年の昨年夏から冬にかけて、何冊もの資料を読み、そこで知ったたくさんの戦争孤児たちの壮絶な体験や悲痛な想いを受け止め、登場人物たちに宿らせていきました。
都で行われる歌合戦を目指す、という設定も早くからできていました。歌、ドレミファソラシド、という連想で、浮浪児と呼ばれていた孤児たちにはレン、シドウ、ソウタ、ソラ、と名づけました。
東の都で空襲に遭い、両親をなくして妹と生き別れになり、おばあちゃんのいる西の港に逃れて来たら、そこでも空襲に遭って身寄りがいなくなってしまったレン(菊池銀河)が主人公。東の都にいたときは大陸国の音楽に親しみ、大陸語も少し話せます。
レンの歌が大好きな妹分のソラ(清水詩音)には、レンの妹ユリ(川原琴響)の面影が。
収容所から逃げてきたソウタ(河崎脩吾)は、いつもおなかをすかせていて、機敏で利発なシドウ(大浦千佳)はレンには頼もしい存在。
浮浪児たちが出会う「見た目は異人の子、でもしゃべるのは大陸国の言葉ではなくてコテコテの西の港の言葉」な少女マリ(武田杏香)は、レンの天敵、占領軍のマケイン大佐(清水明彦)の娘。
レンに歌合戦への出場をすすめるのは、国民学校時代の受け持ちだったミチコ先生(松岡依都美)。
レンたちが出会う元機関士の日出男(斉藤暁)は、子どもだからと甘やかすことなく、レンたちに厳しくカマ焚きを教えます。
そして、警察なのか、鉄道省の人間なのか、レンたちの様子をうかがう謎の男(佐川和正)が……。
戦後復興に取り残された子どもたちも、進める側の大人たちも、それぞれに戦争が影を落としています。
ファンタジーでミュージカルという形にして、「戦争孤児の愚痴も涙も歌にして、走れ機関車どこまでも!」と作品のキャッチコピーをつけましたが、実際の愚痴や涙はきっとこんな甘いものではなかったでしょう。そのことをわきまえつつも、愚痴や涙を歌にして突き進む子どもたちを、その子どもたちに衝き動かされる大人たちを描きたい、と思いました。
澁江夏奈さんが脚本から書き起こしてくださった音楽が全編を彩り、歌も次々と。音楽収録のときにM30まであって驚きましたが、繰り返し登場する歌も含め、毎回何曲かの歌が登場します。作詞は「真夜中のアンデルセン」「天使とジャンプ」、昨年からエフエム甲府で月一回放送している連続ラジオドラマ「甲府広告」でも手がけていますが、楽しいです!
歌詞が音楽に彩られ、歌となる、その過程がこれまた楽しいです!
「愚痴も涙も歌にして」は人生の悲喜こもごもから吐息のようにセリフを吐き出す脚本家の心意気にも通じるかもしれません。
効果音作りも熱いです。「音で見せる」ラジオドラマの魅力を紹介する記事を発見しました(奇しくも歌鉄演出の小見山さんがインタビューに答えています)が、NHKの音作りの本気さがうかがえると思います。
歌鉄の音響効果、石川恭男さんは、鉄道にも造詣が深い方。石炭の音を作るためにSLを走らせている鉄道会社に問い合わせ、石炭を調達されたようです。石炭をくべる音、石炭の山を踏み越える音の臨場感にも耳を澄ませてみてください。
とにもかくにも初めてのオリジナル青春アドベンチャー、ぜひぜひ聴いてくださいませ。
✏︎初放送時2016年2月1日(月) の日記終わり✏︎
企画開発を始めたのが2015年の5月。「走れ歌鉄!」の原型になる最初のプロットを書いたのが7月。
このときのタイトルは「うた鉄589km」。
589kmというのは、劇中で移動する線路の長さ。乗り換え案内で測ったのだが、ブレーンになってくれた鉄道通の友人からは「当時ですと◯◯◯キロになるかと思います」と指摘があった。演出の小見山さんの提案で、のちに「走れ歌鉄!」になった。
ここから脚本を起こし、改訂を重ねるなかで、出だしもラストも中のエピソードも、ガラッと変わった。設定もプロット初稿では日本の神戸から東京へ向かうことになっていて、実在の土地の話になっている。聴き逃し配信があるうちに、ぜひプロットと放送版を比べてほしい。
「うた鉄589km」(仮題)プロット初稿 2015/7/10今井雅子
プロローグ。
昭和二十年十二月の暮れ。東京の警察署の取調室。関西弁の少年・レンが取り調べを受けている。
「きみたちのために動員された警察官、五十五名、報道記者八十七名、野次馬数えきれず……。とんでもないことをしてくれたもんだ。さて、どこから話してもらおうか」
取り調べに供述する形で、レンたちが起こした前代未聞の事件が語られる。
事件の一か月前、昭和二十年十一月が終わる頃の神戸。八月に戦争が終わり、三か月。米兵のジープを子どもたちが「ギブミーチョコレート」と追いかけていた。
大人も子どももおなかを空かせていた。レンもいつもおなかが鳴っていた。けれど、米兵に媚びるのだけは、イヤだった。ヤツらは横柄で、ヤツらの大きな体の足下にかがんで靴を磨いていると、敗戦の事実を突きつけられるようで卑屈な気持ちになった。
とくに気に入らないのが「アゲイン」のヤツだ。レンがきっちり磨き上げても、まだ磨き残しがあると身振りを交えた英語で訴え、「Again」とやり直しを命じるのだ。アゲインの姿が見えると憂鬱な気分になるが、彼は嫌がらせのようにいつもレンの前に立つ。靴磨きは他にいくらでもいるのに。「Hey,Kid」とレンを呼ぶアゲインの馬鹿にしたような響きも大嫌いだった。
レンの仲間は、ソウタ、シドウの男子二人と、ミドリ、ソラの女子二人。この街で生まれ育ち、戦争で親を亡くした戦争孤児たちだ。最年長のレンは十一歳、最年少のソラは六歳。
五人は、裏社会に生きる「親方」に拾われ、寝食を共にしていた。闇市の隅で、ひたすら靴を磨いた。稼ぎはすべて親方に巻き上げられ、ご飯はお情け程度。体はくたくたなのに空腹で眠れない。けれど、他に行く場所はなく、生きる術も知らず、親方の言うなりにするしかなかった。
そんな五人の憂さ晴らしは、親方の悪口やどん底の暮らしを笑う歌を作って披露しあうことだった。音楽の心得がある者はいない。自分が作った歌を仲間が面白がってくれる。一緒に歌えば、元気が出る。それが楽しかった。歌っている間は、空腹を忘れられたが、歌い終わると、腹が減った。
ある日、落ちていた新聞の中に「少年少女」「歌」の文字をソラが見つける。一番年上で長男格のレンが「第一回少年少女歌合戦」の「参加者募集広告」と書かれていると教えた。少年少女が一緒に歌うというのも戦後らしい新しい風を感じさせた。
大会は大晦日。その数日前に行われる予選を勝ち抜いた十組が本番に出場でき、優勝者には賞金が出る。靴磨きで稼いでいる何千倍もの金額だ。
「これに出て、自由になろ!」と盛り上がる五人。だが、予選と本番の会場は東京。東京に行けるお金があるのなら、とっくに親方のところから逃げ出している。それでも諦めるのは惜しい。なんとか東京へ行く手はないか……。
「こっそり乗り込んで無銭乗車や」と一人が言う。
「ズルはあかん、縁起が悪い。事情を話して乗せてもらお」
一同を代表してレンが最寄り駅の駅長に頼みに行った。駅長は靴磨きの常連で、仕事熱心なレンの顔を覚えていた。乗せてやれるものなら乗せてやりたいが、ムリだと駅長は言い、レンをホームへ案内する。買い出しの大きな荷物を持った大人で車両ははちきれんばかり。タダの客を乗せてやる余裕はない。
「自分で走らせるしかないな」と駅長。空いている機関車があれば、それに貨車でも一両つければ五人を運べる。だが、戦争で機関車はことごとく傷つき、生き残った機関車はフル稼働しているのだった。
そこに、がら空きの機関車が近づいて来る。
保存状態はすこぶる良く、他の列車のようにくたびれていない。車体の腹には白い帯がペンキで引いてあった。
「あれは?」とレンが指差すと「連合軍専用列車や」と駅長が教えてくれた。戦争を生き延びて状態のいい機関車は優先的に米軍に回され、彼らの国内輸送に使われているのだという。
「あれに乗せてもらう!」と駆け出すレンを駅長が追いかける。
一般の日本人が連合軍専用列車に近づくことは許されていない。駅長の制止を振りほどき、レンは機関車の前に躍り出ると、「シューポリッシュ? エニバディ?」と闇市で覚えた片言の英語で靴磨きの営業を始めた。
「靴磨きはいらないが、こいつを磨いてくれ」と米軍の一人が身振りで伝えた。機関車を磨けというのだ。レンは仲間達を呼んできて、一緒に機関車を磨く。靴以外のものを磨けるのは何だか楽しい。靴は小さいけど、機関車はでっかい。靴磨きはうつむきっぱなしだけど、機関車磨きは上を向く。
磨き上げられた車体に米軍は満足するが、「お礼に東京まで連れて行ってほしい」というレンたちの訴えは笑い飛ばされた。レンたちは東京で人生を変えるつもりだが、米軍たちにはその切実さが伝わらなかったらしい。
「東京には連れて行けないが、これをやるよ」と缶詰をいくつかくれた。レンたちが見たこともない高級食材だが、素直に喜べない。東京へ行けると思ったから、張り切って磨いたのに……とピカピカの車体が恨めしかった。持ち帰った缶詰は、あっさり親方に見つかって、巻き上げられてしまった。
何とか東京へ行く方法はないものか……。靴を磨きながらレンたちは考え続けた。米兵の「アゲイン」は今日もレンを指名し、靴を磨かせ、ダメ出しする。いじめて憂さ晴らしをしているのだろう。レンが生意気そうだからターゲットにしているのかもしれない。レンも仕返しのように意地になってピカピカに磨いてやった。
レンが未練がましく最寄り駅の線路脇から東京方面へ向かう列車を眺めていると、若い駅員が呼び止めた。レンと同い年くらいの少年だ。レンが駅長と話していたのを聞いて、事情はわかっていた。
「こっから少し離れたとこに軍需工場があってな、そこが専用の引き込み線を作って工場内の物資を機関車で運んでたんや」と若い駅員が耳打ちした。工場は空襲で焼けたが、機関車と貨車を納めていた倉庫は爆撃を逃れている。もしかしたら、今も機関車と貨車が眠っているかもしれない……。
真夜中、親方が酒を飲んでぐっすり眠っている隙に、レンたちは軍需工場跡に侵入する。そこには機関車と貨車が眠っていた。
「何をしてる!」と五人を照らし出したのは、年老いた元機関士の正太郎。戦争中は工場内の機関車を正太郎が運転し、車両の手入れもしていた。戦争が終わり、正太郎も機関車も仕事を失った。だが、家も家族も失った正太郎は、他に行くところがなく、ここに留まっているのだった。
「自分たちで機関車を走らせて東京へ行きたい」とレンが打ち明けると、「何しに東京行くんや?」と正太郎。歌合戦だと答えると、「歌ってみい」と言う。いつも靴磨きて歌っている歌を五人が歌うと、「へったくそやなあ。予選落ちに決まってる」と正太郎。「けど、おもろい」と笑ってくれる。
「これから練習します! この機関車と貨車を使わせてください!」とレン。
「これが走れると思うか?」と正太郎は鼻で笑う。
戦争が終わってから、ほったらかし。すっかりサビついて埃をかぶっているし、油も差してない。
「それやったら、ぼくらが磨きます!」
「好きにしい」と正太郎に言われ、機関車を磨きだす五人。連合軍機関車を磨いた後だから、要領が良くなっている。自分たちを東京へ運んでくれる機関車だと思うと、力もこもる。空腹も眠気も忘れて、一生懸命磨いた。いつしか歌がこぼれる。いつもは親方の悪口だけど、今日は楽しい陽気な歌だ。
レンたちが靴磨きに使っている布は、列車の座席の座面を覆う布をはぎ取ったものだ。戦中戦後のどさくさに紛れて、ならず者たちは列車内から盗めるものは何でも盗んだ。親方は座面をはいで、商売道具を盗み出したのだ。列車にあった布で列車を磨く。なんだかおかしくて愉快だ。
すっかりピカピカに磨き上げられた機関車と貨車を見て、ほうと感心する正太郎。もうすぐ日が昇る。朝になって親方が目を覚まして、五人がいなくなっていたら大騒ぎするだろう。だが、「親方の元には戻らん。この機関車で今から東京に行く」とレン。
「アホ、磨いただけで走れるかいな。燃料がないと走れんやろ」と正太郎。それはレンたちも同じ。空腹を思い出しておなかが鳴る。米兵にもらった缶詰は親方に巻き上げられたし、昨日はろくなものを口に入れてなかった。
「まずはあんたらの燃料補給や」と正太郎が食料を分けてくれる。口は悪いがいい人らしい。
「今日のとこは一旦帰り」と正太郎に言われ、レンたちは親方が目を覚ます前に寝床へ戻る。
翌朝早くからいつものように靴磨きに出かける五人。ほとんど眠っていないのに、体が軽い。木枯らしが吹き荒れているのに、体はほかほかしている。親方にこき使われるのもあと少しの辛抱だと思えば、辛い仕事にも耐えられた。
親方の目を盗んで最寄り駅へ向かったレンは、機関車を走らせる石炭を分けてほしいと持ちかける。工場跡に今も機関車と貨車が眠っていることを駅長は知らなかった。レンたちが駅長を工場跡に連れて行き、ぴかぴかになった機関車と貨車を見せると、駅長は驚いた。
「この機関車を自分らで走らせて、東京行く! 石炭をください!」
熱意にほだされた駅長は協力に応じると言ってくれる。
レンは工場跡に眠っている機関車の情報を提供してくれた同年代の駅員に礼を言う。駅員は、時々聞こえるレンたちの歌に励まされていたのだと打ち明ける。
「きみたちの歌は上手じゃないけど、元気が出る。ラジオで聞けたらいいな」と若い駅員。
歌合戦の本番はラジオで放送されるのだ。親切に報いるためにも、予選を勝ち抜いて本選で歌いたい、と決意を新たにするレンたち。
「これでいよいよ東京へ行ける!」と張り切って最寄り駅から軍需工場跡まで石炭を運ぶ五人。だが、石炭を運び終えると、正太郎は「ごくろうさん」と冷たく告げ、五人を追い返す。
「機関車と貨車を貸してくれるんとちゃうん?」とレンたちが食い下がると、
「そんな約束してへん。あんたらが勝手に磨いて、勝手に石炭運んで来たんや」と正太郎。
この機関車と貨車をどこかに売りさばいて一儲けしようと思っていたが、腰も痛いし力も出ない。そこに飛んで火に入る夏の虫のごとく五人が現れて、手伝いを申し出て、しめたと思ったのだと正太郎は開き直る。
「騙された!」とレンたちが悔しがっているところに「見つけたぞ」と親方の声。靴磨きをさぼって工場跡に通っていたのがバレてしまったのだ。東京で行われる少年少女歌合戦に出たい、そのために自分たちで蒸気機関車を走らせたい、と打ち明け、親方に暇乞いをするレン。あとの四人も頭を下げる。
「なにを寝ぼけたこと言うてるんや。そんなもん無理に決まってる」と一蹴する親方。
だが、「決めつけるんはまだ早いんちゃうか」と正太郎が口をはさむ。
「普通はムリかもしらん。けど、この鋼の正太郎が仕込んだら、こいつらかて靴磨きよりはでっかいことしよるかもしらん」
親方の挑発に乗る形で、はからずも正太郎が協力を申し出る形になった。
「一週間以内にこの子らがこの機関車を操れるようになったら、この子らの勝ち。もし、できんかったら、この子らを返す。それでどうや?」と賭けを持ちかける正太郎。
親方が去った後で礼を言う五人。
「あんたらのためやない。こいつのためや。こいつかてもういっぺん走りたいやろ」と機関車をなでる正太郎。「戦争中は磨いたる間ぁもなかった。すすだらけで、さんざんこき使っといて。やっと戦争が終わったらお払い箱て、そらかわいそうやで」
自分は戦時中の栄養失調もあり、すっかり体が弱ってしまった。機関車の揺れに耐える体力もない。だが、口はまだ達者。指示を出すことはできる。
「あんたらと同じ夢、見よやないか」
ぐずぐずしている時間はない。期限は一週間。
正太郎の猛特訓が始まる。まずは火おこし。
「石炭のくべかたが大事や。蒸気をうまく上げるんや。煙やなくて蒸気や。いかにうまくかまをたくか。頃合いを見るんや」
絶妙な頃合いは、何度もやって体に叩き込むしかない。だが、歌合戦の日は迫っている。レンたち五人は正太郎の教えを歌にして、歌いながら手を動かす。すると、歌のリズムでタイミングをはかることができて、正太郎も驚くほど腕を上げていくのだった。
一週間後、親方と約束した期限の日。親方の目の前で五人は、自分たちだけで機関車を発進させ、工場内の引き込み線を走らせる。賭けに負けた親方は、これまでの養育費を支払えと図々しいことを言う。
「養育費代わりに、親方に捧げる歌を歌います」
五人が歌いだしたのは、親方の悪口を歌い込んだもの。親方は怒り出すが、五人は機関車を走らせて逃げ、飛び乗った正太郎の手引きで工場の奥へ逃げ込む。
親方は捨て台詞を吐き、そこらじゅうのものを蹴っ飛ばして去って行く。レン以外の四人はバンザイをするが、レンはちょっぴり心が痛む。こき使われてはいたが、今日まで生きて来られたのは親方のおかげなのだ。
「お前らでこいつを走らせられたとして、問題はどうやって走り続けるかや」と正太郎。これは工場専用の小型機関車なので、くべられる石炭の量も少ない。一度石炭をくべても、せいぜい百キロ行くかどうか。国鉄の機関車は200キロくらい平気で行くから、一度の補給量で走れる距離は半分以下。
「つまり、東京に着くまでに、なんべんも補給を受け続けなあかん、いうことや」
石炭は積めるだけ積んだとして、水は積み込める量に限度がある。揺れればこぼれてしまう。
沿線で水を補給してくれる協力者を募らなくてはならない。
正太郎と五人は地図を広げ、補給駅の候補を考える。
「こいつにまずい水は飲ませたない」と正太郎。
「機関車に水の味がわかるん?」と首をかしげる五人。
「アホたれ、お前らよりこいつのほうがよっぽど舌は肥えとるわ!」と正太郎。
水はカルシウム分の少ない軟水に限る。カルシウム分が多いとボイラー内の管内に結晶が出来てしまい熱伝達が著しく落ちるのだ。
「それに、せっかく東京まで行くんやし、こいつに日本各地の名水を飲ませたりたいやないか」と地図に目を走らせる正太郎。かわいい子に旅をさせる親のようだ。
正太郎は「うまい水」を基準に神戸から東京までの間の七つの補給駅候補を選んだ。それらの駅に協力を頼むにはどうすればいいか。勝手に機関車を走らせるのだから、国鉄の代表にかけあうわけにはいかない。細いツテを頼って、それぞれの駅に話をつけるしかない。
最寄り駅の駅長に相談すると、二つ隣の大きな駅の駅長が顔広いから、そっちに相談をと言われる。
「こういうんは最初が肝心や。こっちの熱意を見せることや」と正太郎。
その熱意とは、「決まってるやろ。お前らの歌を聞かすんや」
最寄り駅の駅長からの紹介状を携え、歩いて十数キロ先の二つ隣駅の駅長を訪ねる五人。
「聞いてください」と「機関車操縦の歌」を歌う。うまい下手はともかく面白いと駅長は喜んでくれ、歌合戦出場を応援すると言ってくれる。
「東京までは面倒見きれんけど、ここの駅の駅長はよう知ってる」
駅長は最初の補給ポイント、出発駅から九十キロ先の駅を指差した。その駅長に手紙を書き、石炭と水の補給と、さらに先の駅での補給駅に協力を頼んでもらえないか聞いてくれるという。
伝言がつながり、七か所ある補給ポイントのうち五か所までは協力を取りつけられた。小田原辺りまでは行けそうだが、その先は約束されていない。それでも何とかなるようなツキを五人は感じていた。機関車などないと言われたところから始まって、機関車が見つかり、操縦法法を覚え、石炭を差し出してくれる協力者が最寄り駅とあと五駅も見つかったのだ。天が味方してくれているような心強さがあった。
工場跡から最寄り駅までの引き込み線には、列車が走らなくなった数か月の間に雑草が生い茂っていた。下手すると列車が脱線してしまう。草むしりをして道を作らなくてはならなかった。手はかじかみ、あかぎれが割れて血が出る。それでも苦にはならなかった。
歌合戦予選は十二月二十九日。その五日前の二十四日に神戸を発つことになった。東京まで順調に行けば、二十四時間走り通しで丸二日。だが、途中で何が起こるかわからない。余裕を持って早めに出発することにした。
戦後の混乱でダイヤが乱れているおかげで、時刻表にない機関車をどさくさに紛れて走らせることは可能だった。だが、旅客車が走る線路を貨車が走っていると、さすがに目についてしまう。
「連合軍専用列車のフリをしたらどやろ?」と誰かが思いつき、それはいい考えだとなり、白いペンキで帯を描こうとするのを正太郎が止める。
「連合軍専用列車はもっと立派な車両や。一発でニセモンやてバレてまうわ」
堂々と走ってれば怪しまれへんもんやと正太郎に言われ、それもそうかとうなずく五人だった。
出発当日。まず工場内引き込み線から最寄り駅へ向かい、そこで積めるだけの石炭と水を積み込んだ。機関車のことを最初にレンに教えてくれた若い駅員が、差し入れにさつまいもをどっさりくれた。隣の駅へ行くまでの線路が空くのをじっと待ってから出発した。
「お前らに教えることはもうない」と正太郎は機関車を降りる。
「行ってまうん?」と不安がる五人。
何かあった場合の連絡手段は「手紙を巻いた石を線路に投げろ」と正太郎。
隣どうしの駅は電話がつながっているから、石を拾った駅員が隣の駅に連絡してくれる。運が良ければだが。
「それでもどうしようもなくなったら、この封筒を開けろ」と正太郎はレンに封筒を託した。
行ってきます代わりの汽笛を鳴らし、機関車が走り出した。まず、めざすのは、九十キロ先の最初の補給駅だ。貨車には屋根がない。風は冷たいが気持ちいい。風に吹かれ、罐(かま)で焼いた焼き芋をかじり、機関車の唸りに負けない大声で歌を練習する。夜になれば、星空が見える。雨が降れば、シートを広げて雨をしのげばいい。親方の元でずっと我慢を強いられていた五人にとって、自由の味は格別だった。五人で体を寄せ合って温め合った。興奮して、なかなか寝つけない。このまま東京まで寝なくても平気さと言いながら、一人ずつ眠りに落ちていくのだった。
小さな機関車が子どもだけを乗せた貨車一両を引っ張って通過して行くのを見て、途中駅のホームや線路脇の通行人は「あれは何だ?」と不思議がって指差した。
「ぼくら、東京で歌合戦に出るんや!」とレンたちは高らかに宣言した。この線路は東京に続いている。新しい未来に続いている。東京に行けること、行けば歌合戦に出れること、出れば優勝できることを信じられるおめでたさがレンたちの強さだった。
補給駅では石炭と水の他に差し入れやあたたかい励ましの言葉をもらえた。だが、五人の歌を聞くと「それで歌合戦に出れるのか?」と反応は芳しくなかった。元気が取り柄、特別賞くらいにはなるさと明るく送り出してもらった。
急病人を次の駅まで運ぶなどの小さなアクシデントはあったが、旅は順調に続いた。
名古屋駅まで来ると、貨物車が旅客車の線路を走っているのを見とがめた駅員が機関車を停めた。貨車に乗っているのは子どもたちばかり五人。何事か、こんな機関車を通すわけにはいかない、ここで線路を降りろと騒ぎになった。
「親はどこだ?」「機関車はどこで盗んだ?」「警察に突き出すぞ!」と息巻く駅員たち。
だが、ここまで来て引き返すわけにはいかない。無理矢理制止をふりほどいて発車しようか、いやそれも危険だ。
「わが国の鉄道は、このような子どもの暴走を許すわけにはいかない!」と奥から出て来た駅長が言った。
「なら、アメリカだったら許してくれるのか?」とレン。
ちょうど名古屋駅に停車中の連合軍専用列車が目に留まったのだ。以前列車を磨いたとき、お礼に缶詰を気前良くくれた米兵の顔が思い浮かんだ。彼らは子どもだからと言って見下したりはしない。子どもであっても、個人として認めてくれた。車体をぴかぴかに磨いたレンたちの腕前を買ってくれた。
駅員たちが止めるのも聞かず、停車中の連合軍専用列車に駆け寄るレンたち。身振り手振りを交え、地図を広げて「あそこに停まっている機関車で東京まで行きたい。神戸から走ってきたのに、ここで降りろと言われて困っている。ヘルプミー!」と訴えた。
片言の英語は通じなかったが、熱意は伝わったようで、米兵たちは面倒くさそうに専用列車を降りて、レンたちの機関車を見に来る。
「こんなちっぽけな貨物用機関車見たことがない!」
「子どもたちだけで神戸から来たなんてクレイジーすぎる!」
「お前ら面白いな。気に入った」
口々にそんなことを言って、レンたちの肩を叩いたり、写真を撮ったりする米兵たち。彼らと英語ができる駅員の間でやりとりがあった後、駅員が日本語に要約して告げた。
「東京まではまだまだ長い。事故でもあっては大変だから、特別に連合軍専用列車に乗せてやると言っている」
五人のうちレン以外は「やった!」と喜ぶが、レンは「それじゃ意味がない」と断る。何のためにこの機関車を磨き、操縦法を覚え、石炭や水のアテを探し、ここまで走ってきたのか。ここで米兵に甘えては、正太郎をはじめ、皆からの厚意を台なしにしてしまう。
「レンだって最初は連合軍専用列車に乗せてもらおうとしていたじゃないか」と他の四人が言う。それはそうだ。だけど、これは自分たちの未来をつかむ旅なんだ。自分たちの力で東京まで行かなくてはダメなんだ。そうは言いつつ、たくさんの人の力を借りている。結局のところ、レンはアメリカに頼りたくないだけなのかもしれない。
アゲインの顔が思い浮かんでいた。彼の足下にひざまずき、何度もやり直しをさせられた屈辱。連合軍専用列車に乗せてもらうことは、レンにとっては魂を売ることなのだ。そこに、見覚えのある赤ら顔が近づいてきた。まさかのアゲインとこんな場所で再会するとは!アゲインは連合軍専用列車の運行を管理する任務に就いていたのだった。アゲインが来ると、米兵たちが敬礼をした。アゲインは偉い人らしい。アゲインはレンの顔を見たが、表情は変わらない。レンのことなど覚えていないようだ。
「こいつらの汚い靴で連合軍専用列車を汚させる必要はない。事故に遭おうが知ったことではない。好きに走らせろ」
アゲインの英語を駅員が日本語に直した。アゲインの命令には誰も逆らえないようだった。レンたちの機関車は堂々と名古屋駅を通過できることになった。相変わらず憎たらしいが、アゲインの意地悪が今回はレンたちにとっては吉と出た。
走り出そうとする機関車にアゲインが近づき、「Hey,Kid」とレンに声をかけた。アゲインはレンを覚えていたのだ。アゲインは英語で何かをまくしたてた。「シューポリッシュ」「キッド」が聞き取れた。「キッド」と言うとき、自分を指差し、背丈が小さいことを表す身振りをした。最後にアゲインは「メリークリスマス」と右手を差し出した。レンが戸惑いながら手を差し出すと、アゲインはレンの手を力強く握った。レンは初めてアゲインが笑うのを見た。
「俺も子どもの頃は靴を磨いていたんだ」
きっとそう言ったのだろうと、機関車が走り出してから、レンは意味を汲み取った。アゲインは靴磨きの先輩だったのだ。だから、あんなに厳しかったのだ。でも、今はえらい人になっている。お前たちも、いつかきっといいことがあるぞとアゲインは言いたかったのかもしれない。連合軍専用列車に乗せてくれなかったのは、意地悪ではなく、レンたちがやりたいように計らってくれたのだ。
「なんだ、いいヤツだったんだ」
こぼれそうな涙を思わず靴磨き布で拭いたら、顔が真っ黒になった。その顔を見て、仲間が笑った。「笑うなよ」と言うと、また涙があふれた。神戸の闇市でひたすら靴を磨いていた日々が今はすっかり遠く思える。いつまでも続くトンネルの中にいるようだった。今、風を受けて走っているのが嘘みたいだ。ひょっとしたら、親方が俺たちに厳しかったのも、何か思うところがあったのかもしれない。いや、あいつはただ俺たちをこき使っていただけか……。でも、少なくとも、あの辛い日々があったから、十二月の冷たい風だって気持ちいいって思えるんだ……。そう思ったら、また涙が止まらなくなった。
五つ目の補給駅で、六つ目の補給駅への交渉を頼んだが、拒まれた。レンたちの機関車に手を貸さないようにという指令が名古屋駅から回っているらしい。名古屋駅はアゲインの口ききで通過できたが、国鉄は当然面白く思っていない。機関車を兵糧攻めにして止めるつもりなのだ。正太郎の指定のおいしい水にこだわっている場合ではない。どこでもいいから補給してくれる駅を探さなくてはならない。だが、国鉄を敵に回してしまった今、どこに駅に停車するのも危険だった。
「燃やせるもんがある限り機関車は走り続ける」という正太郎の言葉を思い出すレン。
石炭の代わりに、貨車の棚を壊して、放り込んだ。だが、燃やせるものは尽き、水も間もなく尽きてしまいそうだ。石炭と水が尽きれば、機関車は止まってしまう。
「山で薪を取ろう! 川で水を汲もう!」
そうだ、駅でなくても燃料と水は手に入る!
途中駅の引き込み線で一時停車し、見張りを一人残して、二人は山へ、二人は海へ。緊急事態が発生すれば汽笛を鳴らすことになっていた。
とそのとき、汽笛が鳴った。あわてて薪組と水組が引き返すと、近所の人たちからふかしたてのまんじゅうの差し入れがあった。
「薪と水を積めるだけ積んで、走れるところまで行こう」
新しい気持ちで出発する五人。また新しい歌が生まれた。
しばらく行った先の駅を通過するとき、駅員が旗を振っていた。機関車を止めると、「次の駅で迂回してください」と言う。大きな駅のためダイヤが詰まっていてなかなか線路が空かないので、貨物用の線路に回ったほうがいい。ルートが複雑なので自分が同乗して指示をすると言う。ここにも名古屋駅からの連絡は来ているはずだ。
「罠では?」と疑う者もあったが、一か八かで駅員を乗せ、迂回する。機関車は無事にその大きな駅を通過できた。レンたち五人は駅員を信用する。
だが、駅員が機関車のことをよくわかっていないことをレンが怪しむ。実は男は鉄道省のお役人で、名古屋駅からレンたちの機関車の通報を受け、レンたちを止めるために待ち受けていたのだった。
「きみたちには、次の駅で降りてもらう。きみたちにこんなことをされては困るのだ」と告げる役人。
国民が一丸となって戦後復興に取り組むなか、機関車を盗んで走らせるなど言語道断だと言う役人。盗んだのではない、この機関車を管理していた元機関士から借りたのだとレンたちは主張するが、「そんなバカなことをする大人がいるわけない」と聞き入れてもらえない。
「もし困ったことがあったら、この封筒を開けろ」
正太郎の言葉を思い出したレンが、正太郎に託した封筒を開ける。そこには、正太郎からの手紙が入っていた。難しい漢字がいっぱいあるので、役人に読んでもらうことになった。手紙には、面と向かっては恥ずかしくて言えないから、と正太郎の感謝の気持ちが綴られていた。
「お前らが孤児になったんは、戦争を止めれんかったわしら大人にも責任がある。空襲で家は焼け、妻と娘たちが死んだ。工場も焼けた。自分だけは倉庫にいて、機関車と一緒に助かった。戦争が終わっても、なあんもやる気が起きんかった。あの倉庫で、死ぬのを待っていたようなもんや。あそこはわしと機関車の、でっかい墓場やった。空襲で、なんでみんなと一緒に死ねんかったんやろて悔やんどった。そんなわしの前にお前らが突然現れて、歌合戦に出たいちゅうて、人の機関車を勝手に磨いたり石炭を運んだり石炭をくべたり、えらいにぎやかになった。機関車が生き返った。わしはこのために、生かされとったんやてわかった。最後にええ夢を見た。わしはもう身よりもおらん。機関車はお前らにやる。機関車は戦争中、人を殺すためのもんばっかし運ばされとった。あと何年走れるかわからんけど、あいつが走れる限り、人を喜ばせるもん運ばしたってな」
手紙を持つ鉄道省役人の手が震えた。
「私の任務は戦後復興を押し進めること。であれば、進むのみだ!」
「そんなことしてええん?」と子どもたちのほうがうろたえる。おそらく処分がくだされるだろう。だが、戦争を生き延びて授かったおまけの命だ。信じた道を突き進んで、この身分を失うことになっても惜しくはない、と役人はきっぱり言う。
次の駅のホームで数十人体制の警察が待ち受けているのが見えた。
「速度を上げろ!」と役人。
速度を落として停車するはずだった機関車が素通りするのをぽかんと見送る警察官たち。
「ようし、このまま東京まで突っ走るぞ!」
五人が歌いだす。機関車が汽笛を鳴らす。速度を上げて、機関車は東京を目指した。
エピローグ。東京の警察署での取り調べが続いている。ラジオから流れる歌合戦本番の生放送。
「出たかったな」とレンがぼやく。
「予選が終わるまで取り調べを待ってやったんだ。感謝しろ」と警察官。
つかまったおかげで、食事には困らない。年越し蕎麦にもありつける。
他の四人も別々に取り調べを受けているが、皆、布団の上で寝られて喜んでいるという。
「で、ぼくたち、どうなるんですか?」
「何かを盗んだわけじゃない。国鉄からも被害届は出ていない。しいていえば、お騒がせ罪だな」
五人の顔が大きく写った新聞を見せる警察官。
《神戸から東京へ うたごえ鉄道589キロの旅》と見出しが躍る。
「歌合戦なんか出なくたって、お前達五人はすっかり英雄だ」
新聞の片隅に、神戸の親方の写真を見つけるレン。「五人の育ての親」として紹介され、孤児のレンたちを引き取った苦労話が美談になっている。写真の親方の得意げな顔を見て、レンが大笑いする。
「何がおかしいんだ?」と警察官が訝しむが、レンの笑いは止まらない。笑い過ぎて、涙が出てくる。いろんなものを失ってきた。辛い目にもたくさんあった。でも、そのすべてが今の自分を作っている気がする。何もかもにありがとうを言いたい気分だった。
(終わり)
目に留めていただき、ありがとうございます。わたしが物書きでいられるのは、面白がってくださる方々のおかげです。
