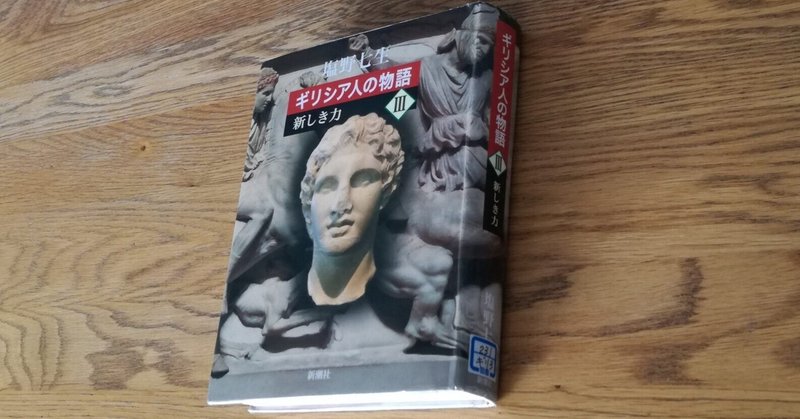
【読書録35】著者への感謝とともに ~塩野七生 「ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力」を読んで~
本書では、ペロポネソス戦役後のギリシアを描く。
ペロポネソス戦役後、アテネの凋落は続く。
勝者であったスパルタもその保守性から、覇権を握るにはいたらない。
そのような中出てきた「新しき力」がマケドニアであった。
王・フィリッポスの下、脱皮するマケドニア。そして、フィリッポス暗殺の後、その息子、アレクサンドロスは王を継ぐ。20歳のことである。
アレクサンドロス
学問上の師は、あのアリストテレス。生涯の書は、「イーリアス」。ギリシア式の教育を受け、同世代の仲間と、スパルタ式の軍事教育を受ける。
その同世代の仲間である「コンパニオン」たちとパルメニオンを筆頭にした父の時代からの高官たちとともに東征に乗り出すことになる。
初陣のころから自らが先頭になって敵陣に突っ込んでいく「ダイヤの切っ先」スタイルは変わらず、戦傷は癒えることがない。
東征に乗り出し、グラニコスの会戦、イッソスの会戦、ティロス攻防戦、ガウガメラの会戦、ヒタスペスの会戦と負け知らず。
イッソスの会戦では、3万の兵を率いて15万のペルシアを打ち破る。
そしてついには、ギリシアにとって長年の脅威であった大国・ペルシアを滅亡に導く。
「ローマ人の物語」のユリウス・カエサルにしても、後に「大王」と呼ばれる本書のアレクサンドロスにしても、著者に「天才」を描かせたら右に出る者はいない。その姿は、躍動的で活き活きとしており魅力的である。
「愛すべきインコシエンテ」(=愛すべき向こう見ず)とも形容されるアレクサンドロスであるが、斥候や兵站の重視の仕方、短期決戦により味方の被害を最小にする戦い方、戦勝後の占領体制の築き方などまさに「天才」である。
一方で、酒席でのクレイトスの殺害などの若気の至りとしか言いようがないエピソードも描かれる。古代の名将のなかでも圧倒的に若いのである。
ユリウス・カエサルにとってのルビコン川が、アレクサンドロスには、「ゴルディオンの結び目」であろうが、その時の年齢からか、快活さを感じさせる。
ゴルディオンの結び目は、今なおヨーロッパで「複雑な問題の解決には、断固とした意志と、明快で単純で果断に対処するのが、最も有効な方法になる」という教訓を残しているという
そしてその生涯は、32歳の時に病により終えることになる。
21歳の歳にヨーロッパを後にアジアに来て以来、一度もマケドニアにもギリシアにも帰らないまま、メソポタミア地方のバビロンで死を迎える。
著者はいう。
なぜ、彼だけが後の人々から、「大王」と呼ばれることになったのか。
なぜ、キリスト教の聖人でもないのに、今でもキリスト教徒の親は子に、アレクサンドロス(英語ならばアレクサンダー、略称ならばアレックス)という名をつける人が絶えないのか。
その理由はただ単に、広大な地域の征服者であったからか。
それとも、他にも、愛する息子にこの名を与えるに充分な、理由があるのか。
なぜアレクサンドロスは、二千三百年が過ぎた今でも、こうも人々から愛されつづけているのか。
本書を読めば、その理由がわかるような気がする。
「歴史エッセイ」の終わり
そして著者・塩野七生は、本書で「調べ、考え、それを基にして歴史を再構築していく」という手法で記述する「歴史エッセイ」を終わりにするという。
本書の最後は、歴史エッセイを終わりにする著者から読者へのメッセージで締めくくられる。
新潮社の粕谷一希との「翻訳文化の岩波に抗して、僕たちは国産で行こう」という誓いのエピソードには、涙が出てくる。
その後、50年におよぶ作家としての活動で数多くの名著を記すことになる。
そして本書をこう締める
ほんとうにありがとう。これまで私が書きつづけてこれたのも、あなた方がいてくれたからでした。
(中略)
最後にもう一度、ほんとうにありがとう。イタリア語ならば「グラツィエ・ミッレ」。つまり、「一千回もありがとう。」
2017年・秋 ローマにて
塩野七生
「ローマ人の物語」を中心とした素晴らしく、また骨太な著作群を読者であるわれわれに与えてくれた著者にこちらこそ本当にありがとうと言いたい。
本書やローマ人の物語は、今後また読み返すことになるであろう。そして、その他の著作も今後、読み進めていくことになるであろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
