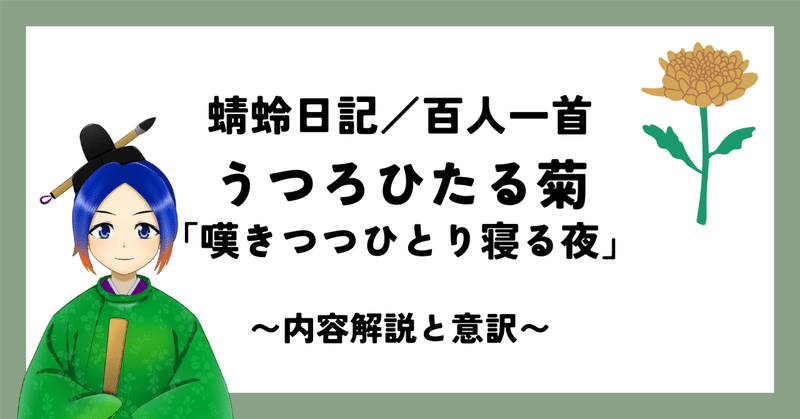
【古文解説】うつろひたる菊「嘆きつつひとり寝る夜」〈蜻蛉日記・百人一首〉内容意訳|万葉授業
こんにちは!
ばーちゃる古典オタクのよろづ萩葉です。
今回は蜻蛉日記より、「うつろいたる菊(嘆きつつひとり寝る夜)」の内容を解説をします。
蜻蛉日記とは
平安時代の女流作家・藤原道綱母によって書かれた日記。
藤原道綱母の本名はわかっていないが、更級日記の作者・菅原孝標女の叔母にあたる。
浮気性の夫との結婚生活を思い出しながら書いた回顧録。
原文
さて、九月ばかりになりて、出でにたるほどに、箱のあるを手まさぐりに開けて見れば、人のもと遣らむとしける文あり。あさましさに、見てけりとだに知られむと思ひて、書きつく。
うたがはしほかに渡せるふみ見ればここやとだえにならむとすらむ
など思ふほどに、むべなう、十月つごもりがたに、三夜しきりて見えぬ時あり。つれなうて、「しばしこころみるほどに」など、気色あり。
これより、夕さりつかた、「内裏の方ふたがりけり」とて出づるに、心得で、人をつけて見すれば、「町の小路なるそこそこになむ、とまり給ひぬる」とて来たり。さればよと、いみじう心憂しと思へども、言はむやうも知らであるほどに、二日三日ばかりありて、暁がたに門をたたく時あり。さなめりと思ふに、憂くて、開けさせねば、例の家とおぼしきところにものしたり。つとめて、なほもあらじと思ひて、
嘆きつつひとり寝る夜のあくる間はいかに久しきものとかは知る
と、例よりはひきつくろひて書きて、うつろひたる菊にさしたり。返り言、「あくるまでもこころみむとしつれど、とみなる召し使ひの来あひたりつればなむ。いと理なりつるは。
げにやげに冬の夜ならぬ真木の戸も遅くあくるはわびしかりけり」
さても、いとあやしかりつるほどに、ことなしびたり。しばしは、忍びたるさまに、「内裏に」など言ひつつぞあるべきを、いとどしう心づきなく思ふことぞ、限りなきや。
和歌
うたがはしほかに渡せるふみ見れば
ここやとだえにならむとすらむ
疑わしい。他の女へ渡す手紙を見ると、私の家に通うのは途絶えてしまうのでしょうか。
「はし」と「橋」、「ふみ」と「文」と「踏み」が掛詞
「とだえの橋」…陸奥の歌枕
「とだえ」「渡せる」「踏み」…「橋」の縁語
嘆きつつひとり寝る夜のあくる間は
いかに久しきものとかは知る
嘆きながら独りで寝る夜が明けるまでの時間がいかに長いか、あなたは知っているのだろうか、いや知らないでしょう。
この和歌は百人一首にも収録されている。
「つつ」…反復・継続の接続助詞
「かは」…反語
げにやげに冬の夜ならぬ真木の戸も
遅くあくるはわびしかりけり
本当に、冬の長い夜が明けるのを待つのはつらいものだが、冬の夜でもない真木の戸が開かないのはつらいことです。
「嘆きつつ」の和歌に対する返歌。
真木の戸…杉や檜などでつくった立派な戸。
「あくる」…「夜が明ける」と「戸が開く」の掛詞
意訳
西暦955年の8月末に、作者と藤原兼家との間に道綱が生まれた。
その少し後のこと。
そうして、9月頃になって、兼家様が出て行ったときに箱が置いてあるのを見つけた。
なんとなく開けてみると、他の女に宛てた手紙が入っていた。
驚いて、見たことだけでも知らせようと思って、手紙の隅に和歌を書きつけた。
うたがはしほかに渡せるふみ見れば
ここやとだえにならむとすらむ
疑わしい。他の女へ渡す手紙を見ると、私の家に通うのは途絶えてしまうのでしょうか。
すると案の定、10月末になると3日連続で来ない時があった。
兼家様は平然として
「しばらくあなたの気持ちを試しているうちに3日も経ってしまった」
などと怪しい態度を見せる。
夕方頃、私の家から「宮中が禁忌の方向だから方違えに出かけるよ」といって出て行った。
信用できないので使用人に尾行させると、
「町の小路にあるどこそこに、車を止めました」
と言って帰ってきた。
思ったとおりだ、と嫌な気持ちになったけれど、
何と言って良いかわからないでいると、
2日3日ほど経って、夜明け前に門を叩く音がした。
兼家様が来たと思ったけれど、つらくて門を開けさせなかった。
すると兼家様は例の女の家と思われるところに行ってしまった。
翌朝、このままでは良くないと思って、
嘆きつつひとり寝る夜のあくる間は
いかに久しきものとかは知る
嘆きながら独りで寝る夜が明けるまでの時間がいかに長いか、あなたはご存知ないのでしょう。
と、いつもよりは体裁を整えて書いて、色褪せている菊に挿して送った。
兼家様からは、
「夜が明けるまで様子を見ようと思ったけど、急用を伝える召使いが来たので帰ってしまった。あなたが怒るのは当然だ。
げにやげに冬の夜ならぬ真木の戸も
遅くあくるはわびしかりけり
本当に、長い冬の夜でもない真木の戸でも、開けないのはつらいことです」
と返事が来た。
それにしても、不思議なほど素知らぬふりをしている。
しばらくは「宮中へ行ってくる」などと嘘を言ってバレないように通うのが当然だろうに、ますます不愉快であることこの上ない。
解説
この時代は一夫多妻が認められていますので、このような夫婦はたくさんいました。
それでもやっぱり、夫の不倫に怒る女性も多かったのでしょう。
ちなみにこの兼家は、あの藤原道長たち兄弟の父親です。
道綱母が兼家を怒る気持ちはもっともですが…
その不倫のおかげで道長たちの時代が来ると考えると、
何とも言えない気持ちになりますね。
動画
ご覧いただきありがとうございました🖌️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
