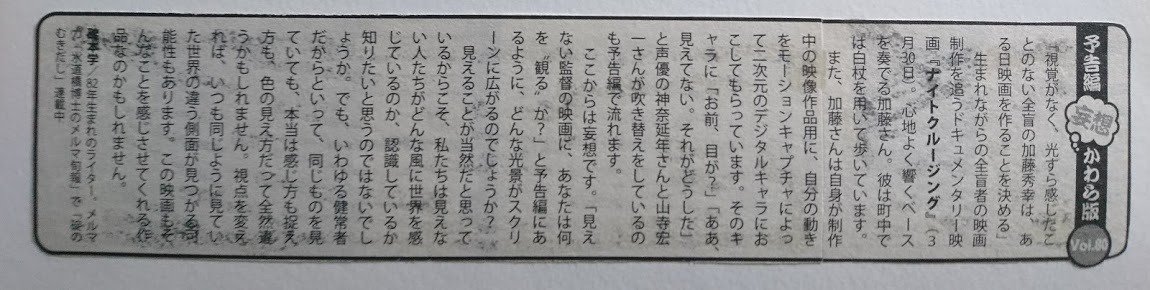『ナイトクルージング』
全盲のミュージシャン・加藤秀幸が映画制作に挑む姿を追った「INNERVISION インナーヴィジョン」の佐々木誠監督が、同作から引き続き加藤の映画制作過程に迫ったドキュメンタリー。生まれつき視覚がなく、光を感じたことのない加藤が、ある日、映画を作ることを決意。加藤はSF短編映画「ゴーストヴィジョン」を制作するさまざまな過程を通して、顔や色の実体、2Dで表現することなど、視覚から見た世界を知っていく。同時に、映画制作に携わるスタッフたちも、加藤を通して視覚のない世界に触れる。そんな見えない加藤と見えるスタッフたちが、互いのイメージを共有しながら映画が作られていく過程を追った。(映画.comより)
「視覚がなく、光すら感じたことのない全盲の加藤秀幸は、ある日映画を作ることを決める」
生まれながらの全盲者の映画制作を追うドキュメンタリー映画『ナイトクルージング』(3月30日)。心地よく響くベースを奏でる加藤さん。彼は町中では白杖を用いて歩いています。
また、加藤さんは制作中の自身の映像作品用に、自分の動きをモーションキャプチャによって二次元のデジタルキャラにおこしてもらっています。そのキャラに「お前、目が?」「ああ、見えてない。それがどうした」と声優の神奈延年さんと山寺宏一さんが吹き替えをしているのも予告編で見ることができます。
ここからは妄想です。「見えない監督の映画に、あなたは何を“観る”か?」と予告編にあるように、どんな光景がスクリーンに広がるのでしょうか?
見えることが当然だと思っているからこそ、私たちは見えない人たちがどんな風に世界を感じているのか、認識しているか知りたいと思うのではないでしょうか。でも、いわゆる健常者だからといって、同じものを見ていても、本当は感じ方も捉え方も、色の見え方だって全然違うかもしれません。視点を変えれば、いつも同じように見ていた世界の違う側面が見つかる可能性もあります。この映画もそんなことを感じさせてくれる作品なのかもしれません。
↑は『週刊ポスト』3月25日発売号に掲載された「予告編妄想かわら版」で『ナイトクルージング』を取り上げたものです。
僕のこの連載は映画の予告編だけを見て、オチとかを妄想したものを書くというある種謎のものとなっていて、本当の終わり方とか当てないように気をつけながら(いいシーンってラストあたりにあることが多く、わりと予告編の頭にあったりする)書いています。地味に週刊連載で80回越えているので、毎週一本ずつ取り上げるため予告編をわりと気にしてチェックするようになりました。この『ナイトクルージング』も最初の特報ぐらいの時に見て、劇場公開されたら観に行こうかなと思ったのでした。
予告編がつまらない映画はどう考えてもつまんないです。だって、本編や本編にはもしかしたら使われていないかもしれないが、予告編に使われる映像も含めて、撮影したものしか予告編には使えないからです。予告編はいいとこだけをまとめたものになるので、それがつまんない時点で二時間おもしろいわけがない、ということです。
編集能力によって予告編は見事なものもあります。予告編はおもしろそう、おもしろかったのに本編を見るとつまらないことも確かにあります。この辺りは予告編を作る人のセンスと本編を編集する人が違ったりすることもあるのかもしれないなと思います。
公開されて観に行こうかなと思っていたら、今日は【上映後トークショー】登壇者:青羊(けもの/シンガーソングライター)、鈴木沓子(ライター、翻訳家)、加藤秀幸(主演)、佐々木誠(本作監督))だったのでラッキー。アップリンク渋谷にて『ナイトクルージング』を鑑賞してきました。
『ナイトクルージング』は加藤さんが映画制作したSF短編映画『ゴーストヴィジョン』の創作過程を佐々木誠監督が撮影したドキュメンタリーという形になっている。同時に『ゴーストヴィジョン』も作中で流れていく。この作品にはノンフィクションとフィクションを行き来することで映像が多層になっている。こう書くと複雑な感じを受ける人もいるかもしれないが、実はこういった作品は観ていてもストレスは感じない。
同じくアップリンクで公開されていた『シスターフッド』もドキュメンタリーと劇映画パートがあった。現実と虚構というものどちらかだけ、という時代ではないということもあるのだと思う。
「ポストトゥルース」の時代には真実であろうが虚実であろうが、創作であろうが現実であろうが、個人の感情に訴えるものの方が強い影響力を持っている。つまり今の時代に適した表現のひとつとして考えることもできるかもしれない。
この映画において「視覚がなく、光すら感じたことのない全盲の加藤秀幸は、ある日映画を作ることを決める」というのが一番大きな軸であり、観客の興味の大部分を占めるところだと思う。僕はそういう興味で観たいと思った。
実際に作品を観ていく中で感じたことは、目が見える、見えないということに関わらず、人が他者と関わりながらなにかを作るという過程はスリリングであり、埋まらない距離やイメージをどう伝えるのか、補えるのか、またはそれは不可能なのかということを見せつけられる点だろう。これがすごくおもしろい。
映画、映像というものは視覚表現であり、加藤さんと一緒に『ゴーストヴィジョン』を作る人たちは見えるのが当たり前な人たちだ。だからこそ、映像として説明できるものやある種の言語的な感覚については、暗黙の了解のようなもので今まで仕事ができていたし、やってきていた。しかし、加藤さんと映画作りを始めた途端、見たらわかるでしょ、という感覚的なものが通用しない。彼らは目の見えない加藤さんに言葉や触覚を用いて、映像を説明したり、アイデアをどう映像にしていくかということを伝えていく。
おそらく、彼らは加藤さんと仕事をしたことで意識していなかったものに目が向くようになったのではないだろうか。そして、コミュニケーションをする中で、なあなあの関係ではなく、ひとつひとつを話し合い、意見を交わして形を決めていくというプロセスをすることになったのだと思う。普段からそういうことをしていない、と言いたいわけではない。
目に見えるという共通の条件のもとでは疑問視されず、話にすら挙がらないことが、加藤さんとの仕事ではすごく大事な比重をしめたはずだ。神は細部に宿るという。加藤さんとのやりとりで今までとは違う細部を見つけていたように思える。だからこそ、映画の中で加藤さんとやりとりする人たちは、なにかを発見したように目を輝かせ、同時に伝えたいのに言語化してこなかったことに自信をなくして、少しずつ互いのイメージを近づけていく。そこにはやはり信頼というものが芽生えたように僕には見えた。
映像や映画というビジュアルの仕事だけではなく、様々な仕事における他者と自分とのやりとりについて考えさせられる。だから、これは芸術を扱ったドキュメンタリーでありながら、仕事論としても見ることができる。そこで大きいのはコミュニケーションとはなにか? ということだろう。つまり自分とは違う誰かとイメージを共有する際に必要なもの、五感のすべてがそのツールになる。
目が見えている人は視覚情報に頼っている。読書は文章を読む、見るという行為だ。聖書がグーテンベルグの活版印刷技術によって世界で一番読まれる書物となったが、それ以前に紙が貴重な時代にも紙に文章は書かれていた。遡れば、人は石に文字や記号を刻んだ。洞窟の壁画に絵を書いた。
20世紀は映像の世紀だった。新聞からラジオへ、ラジオから映画にテレビへ。そしてインターネットへとメディアは進化し、大衆はそれによって操作もされた。新聞もラジオも映画も戦争に利用された。だからこそ、メディアに関わる人間、様々なエンターテインメントや創作に関わる人間はそのことを知っておかないといけない。なぜなら、人々はたやすく操られ、自分たちが関わるものが操るツールにされてしまう自覚がなければ、やはり簡単に大きな力に操られてしまうからだ。当然ながらインターネットも同じことだ。で、操られまくってるこの有様、そうそれが現代。
僕は映画の専門学校に二十歳の時に上京し2年通っていたが、誰もそんなことは教えてくれなかったし、カリキュラムにもなかった。個人の考えとしては映像や音楽、アートという創作に関係する学校では、まずメディアと創作がたのしいものだけではなく、いかに危険なものとなるか、そしてその歴史を教えることからやったほうがいいと思う。だから、歴史修正主義者や差別主義者が跋扈する事態になる。その辺りのことは最近書いた『ブラック・クランズマン』や『レクイエムとしての90年代グランジ・オルタナティブが鳴り響く『キャプテン・マーベル』、そして20年代へのフェミニズムと差別主義者』に書いてます。
話を映画に戻すと、上映後に「けもの」の青羊さんが言われていたが、加藤さんがまずおもしろい存在である。このことが一番の魅力になっているのは間違いない。しかも、ドキュメンターなのに加藤さんの今までとかほぼ触れてないからブラックボックスになっていて、ミュージシャンでもある加藤さんが映像作りを始めたというところからなのでバックボーンがわからないまま進む。加藤さんがどういう人間なのかというのは映像作りに関する人たちとのやりとりの中で、彼のキャラクターが徐々に伝わってくる。人間味が溢れているというと褒め言葉なのかわからないが、自分の持っているイメージをいかに伝えるか、共有してもらうかについて言葉を費やし、相手の話をじっくりと聞いた上で自分の疑問や意見、同意を伝える。時折、めんどくさいなあって顔もしていてチャーミングだ。
ドキュメンタリーで映し出される人(対象者)は例えば、観客や見る側が感情移入できなくてもいいと思う。興味本位で見る人のほうが多いだろう。その時、自分とは違うよなって対象者が急に見せる仕草や言葉、態度に知らぬ間に共感を覚える。そういうものが他者と自分をつなぐものであり、僕たちが世界(他者性)へ興味を持つフックとなっていく。
『ゴーストヴィジョン』に関しては、僕は物足りないというのが正直な感想。それぞれに撮り方や表現方法を変えているのは観ていて楽しい。同時にそれはその作る過程を見ているからということもあると思う。答え合わせになっているというのもあるかもしれない。あれだけ意見を交わして細部を決めていった映像がこれなのだ、とわかる。わかるからたのしい。『ゴーストヴィジョン』は最初に映像がなく音だけで流される。戸惑いもありつつ、音に集中して映画を「観る」ところから映画は始まる。そして、加藤さんは出来上がった映像を観ることはできないから、完成した映像が本当に作りたかったものなのか確かめようはない。シュレーディンガーの猫みたいな状況になる。最後の猫ってそういう意味なんじゃないかな、パンフとかにあの猫の意味書いてあるみたいなアナウンスされてたけど、ごめんなさい、読んでないのであってるかわからない。
その個人の中にある異なる像(イメージ)が、「幽霊」という目に見えないとされる存在を脳内だったり心の中に浮上(視覚)させるという、創作過程も含んだ作品がSF短編映画『ゴーストヴィジョン』ということだったんじゃないかな、そして、それをさらに撮り続ける佐々木誠監督の視線と編集によって、「身体性」を持たされてドキュメンタリー映画という実態を持った。これは創作に関するコミュニケーションを映し出しながら、芸術という五感、それを越える第六感について観た人が感じる、考えるきっかけになっている作品だと思う。こういう作品は映画館でいろんな人がいる中で観る方がより五感が敏感になるのでいいと思う。
トークの最後にはけもの(青羊)×加藤秀幸『めたもるセブン』を披露してもらいました。聴けてよかった。