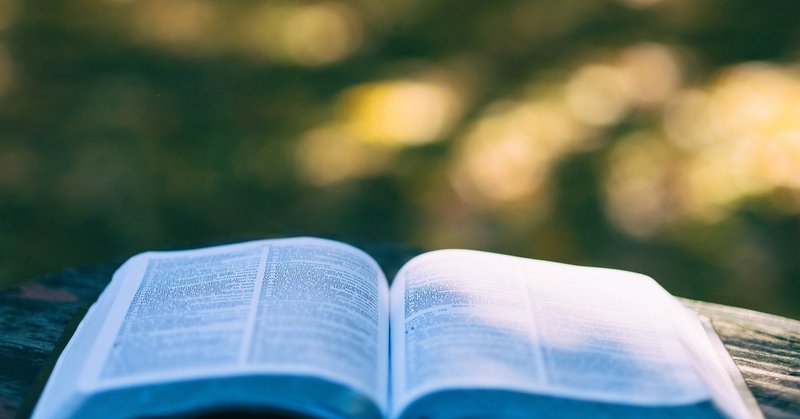
新卒銀行員の課題図書(1/3)
今回は、入社時におすすめされた10冊の本を読んで思ったことや考えたことなどを書いていこうと思います。
長くなってしまうので3パートに分けて書いていこうと思います。
まず一冊目はこちらの本です。
図解 ワイン一年生
初めから銀行員も新卒も関係ない本の紹介です。
こちらの本は、実際の品種の特性そのままに擬人化した、個性豊かなブドウたちの特徴を漫画で楽しく知ることができる一冊です。
全くワインのことは知らない。という方でも、マンガなので気軽に読み進めることができますし、実際に飲んでいるときにもつい、これはあのキャラクターの味かな?などと考えてしまうようになり、ワインをより楽しく、気軽に楽しむことができるように感じさせてくれると思います。
ワインに詳しい方でも、「確かにこのブドウの品種はこんなキャラクターかもしれないな」と、記憶にあるワインの味と照らし合わせながら読んでみるても楽しんでいただけるかと思います。
社会人にワインの知識が必要かといわれると、私自身まだ実感はしていませんが、社会人云々を抜きにして、ワインの知識を教養として身に着けたいと思う方にとっての入門書としておすすめです。
続いての本はこちらです。
アルゴリズム フェアネス
この本を読むまでは、「アルゴリズム」と聞いてもプログラミングのコードの定型文かな?とあいまいな理解しかしていませんでした。しかし、読み終えるころには、この世界がどれだけアルゴリズムの上に成り立っているのかということを実感させられました。
アルゴリズムは私たちにたくさんの自由をもたらせてくれますが、ただそれを利用するだけだと支配される側の人間になってしまいます。
例えば、私たちの生活に身近に存在しているアルゴリズムに、「おすすめ機能」があげられます。動画サイトのおすすめ動画を延々と見続けてしまうことや、通販サイトのおすすめの商品を、対してほしくもなかったのに買ってしまい、後悔してしまったことはありませんか?
見たい動画や商品を自分の意志で探す、といった行為までアルゴリズムは代わりに行ってくれるので、私たちにとってはついつい便利で使ってしまうこの機能ですが、私たちから「考え、判断する」ということを放棄させてしまうということもしっかりと理解することが大切です。
アルゴリズムに使われるのではなく、アルゴリズムを理解し、使う側になることが必要であり、そのためにはどうすればいいのか。
今後、データが私たちの生活をより便利にし、ますますアルゴリズムに支配される機会が増えていく中で、どのようにアルゴリズムと付き合っていく必要があるか。
デジタル時代を生きる私たちに必要な知識を学ぶことができる一冊です。
最後に紹介するのはこちらの本です。
ビジネスモデル・ジェネレーション
本書は、ビジネスモデルを新しく作成したいと思う全ての方に、ビジネスモデルを作るうえで必要な考え方を提供してくれる一冊です。
私ははじめ、ビジネスモデルは起業の時に使うものなのに、なぜ新卒の私が読むのだろう?と思っていたのですが決してそんなことはなく、ビジネスに携わるだれが読んでも業務に生かすことができる内容となっています。例えば、
何か新しいことをして価値を生み出したい。
今の私の仕事は何の意味があるんだろう。
こんな風に考えたことはありませんか?私自身働いていて何度も考えていることでもあります。
この本では、こうした思いを形にするうえで必要な具体的なツールがふんだんに盛り込まれており実際の企業の例に当て込んで開設されているため、私と同じような疑問を持つ方には何かしらの解決策を提示してくれます。
特に、本書で紹介されているビジネスモデルキャンバスは、ビジネス全体を俯瞰して見ることができるため、新しくビジネスを企画するときや、現在の業務の改善点を見つけるときなどに重宝するツールとなっています。
今の業務を書き起こすことで、これまでにない発見ができるかもしれません。
今回は以上です。
見ていただきありがとうございます。
