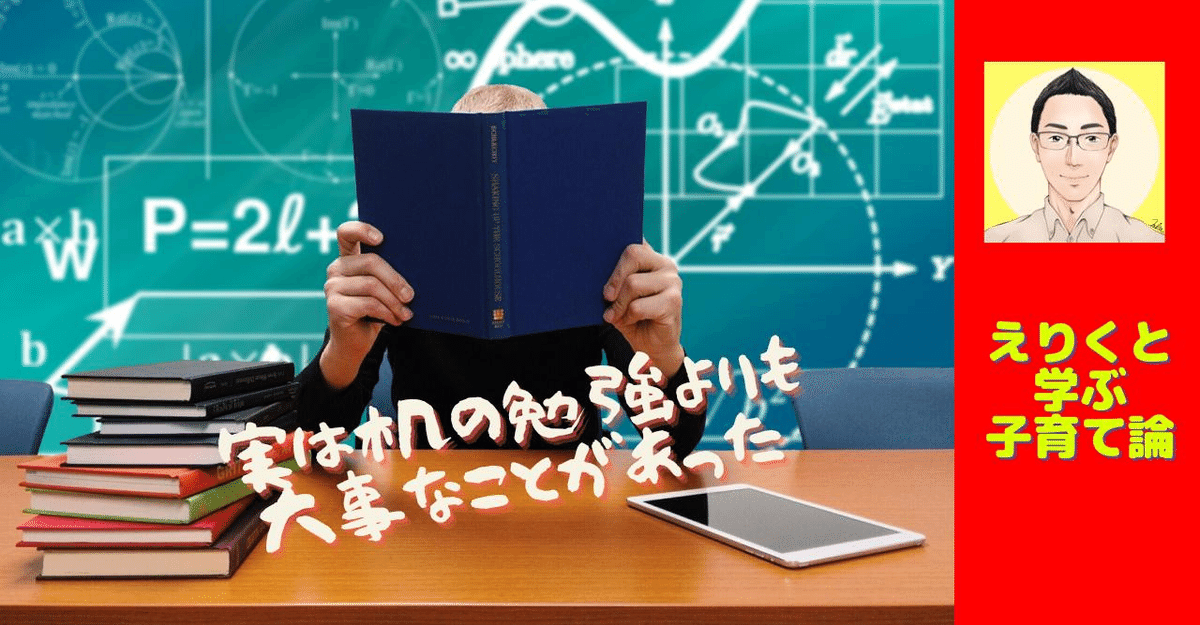
実は机の勉強より大事なことがあった
こんにちは、えりくです。
学校に行ったら嫌でもやらなくてははならない勉強。
子どもの頃を思い出してください。
親に「勉強しなさい」って言われませんでした?
誰もが経験あると思います。
なぜ勉強が大事とされてきたと思います?
それは学歴社会だったからです。
1960年代~2000年くらいまでは学歴社会が当たり前とされてきました。
しかし、時代の流れや進化と共に、あまり知られていませんがその考え方はだんだん変わってきたのです。
今回は今の教育現場や保育現場の実態も踏まえて、「実は机の勉強より大切なことがあった」ということをお話します。
目次
1.時代の流れに沿って感覚を変えていこう
2.机の上の勉強よりも大事なのは、ずばりこれ
3.これからを生きる子どもたちのために
4.まとめ

1.時代の流れに沿って感覚を変えていこう
子どもの頃の小学校の授業を思い出してみてください。
先生が前に出てチョークで黒板に記入し、教え込まれるという授業でした。(チョーク&トーク方式と呼ばれています)
しかし、最近では教育方法も変わってきました。
それはなぜかというと2000年以降、ICT化やAIが進んできて、コンピューターがすべてをやってくれる時代となり、当たり前にやってきた学習よりも自分たちで知識を習得することが大切となってきたのです。
これからはセンター試験の結果で大学に行ったり、学歴重視で就職をするという「認知能力」よりも、忍耐力・協調性・社会性などの「非認知能力」が大事になると言われてきています。
さらにAIやICT化が進んできて、今まであった職業の7割がこの10年でなくなるとも言われています。
こうした状況の中で、学歴社会だったものが社会適応能力(生きる力)が重要視されるようになったのです。
そんな背景の中で、学校教育もこれから変化していきます。
先生の一方的授業はなくなっていき、「主体的に仲間と対話しながら深い学び合い」をしていく授業になっていくのです。
これは平成29年に告示された小学校学習指導要領にも記載されています。
例えば、昔の理科の実験を考えてみてください。
魚の解剖をする時に先生に言われた手順通りにやりましたよね。
これからの時代を生き抜くためには、解剖とはなにか、解剖に必要な物はなにか、なんのために解剖は必要なのか、どうすればうまく解剖が出来るかなどを仲間と対話を重ねながら進めていくのです。
こうして仲間と対話を繰り返しながら学び合う力が、社会に出た時に必要な力となるのです。
時代の流れと共に学習スタイルも変化してきているわけですね。
今までは勉強しなさいという言葉が家庭でも言われてきましたが、これからは自分で調べなさいとかもっと考えなさいという言葉が主流になっていくかもしれませんね。

2.机の勉強より大切なものは、ずばりこれ
机の勉強も大事な部分はもちろんあります。
しかし、iPadや携帯で調べたいことは大体、検索できるようになりました。
掛け算の九九、漢字、単語の意味などすべてが簡単に調べることが出来るようになりました。
では机の上での勉強よりも大事なものは何か。
それはずばり「体験」です。
ここでも子どもの頃を思い出してみてください。
小学校の頃、友だちと日が暮れるまであそんだ経験はありませんか。
何もない空き地や河原などで、玩具がなくてもあそびを生み出していませんでしたか。
実はこの体験に大きな学びがあったのです。
玩具がなくてもどうやってあそぶかを考えてみたり、友だちとの対話をしながらあそびを考え発展させたりしていましたよね。
こうした体験がこれからの社会を生きる子どもたちにとっては大きな力となるのです。
では、学校の勉強は必要なくなるの?
そんなことはありません。
学習指導要領に乗っ取ったカリキュラムの中にも体験学習や考える場面、社会に出て必要な力は盛り込まれています。
家庭での子育ての中でバーチャルな体験ではなく、実体験を重ねていくことを意識出来れば、将来役立つ力の習得につながっていくわけなんですね。
ではどのように体験できる環境を作れば良いのか。
子どもが興味を持ったことを一緒にやってみたり、調べてみたり、さらには実物を見に行ったり触ってみることで子どもの興味関心は広がっていくわけです。
ここで習得された意欲が学習へとつながっていくのですね。
少し意識するだけで子どもの大きな成長につながっていきます。
おすすめは自然体験です。
自然の中では豊かな感性が育まれたり、考える機会が多くもてたり、挑戦する機会もたくさんもてます。
自然のある場所で思う存分、子どもとあそんでみてはいかがでしょうか。
主体的な行動が増えていき、考える機会が増え、学習となっていきますよ。

3.これからを生きる子どもたちのために
最近では公園に行っても〇歳以上と規制がかかる遊具が増えました。
安心・安全が重視されるようになってきているのです。
こういう規制をかけるから公園でYouTubeを見る子どもが増えるわけです。
あそぶ場所がないんです。
あそぶ機会が減るということは、考える機会が失われているのです。
環境がなければ意図的に作るしかない。
子どもとの体験を増やしていくことできっと子育てがもっと楽しくなっていくのです。
これからの時代を背負う子どもたちに残していけるものを考えていきたいですよね。
子どもが真ん中の社会を一緒に作っていきましょう。

4.まとめ
時代の流れと共に大事にすべきことが変わってきました。
教育の在り方、学習の仕方も変化してきました。
しかし、これから大事にすべきことは明確です。
体験を増やして、感じたり考えたりしながら深い学びを経験出来るようにしていきましょう。
身近にいる大人も一緒に楽しんじゃうことが、子育てを楽しむポイントにもなっていきます。
悩みはたくさんあるとは思いますが一人にならず、何かあればすぐに相談してくださいね。
また、知りたいこと、疑問に思うことがあればご連絡くださいね。
https://lin.ee/TXSxe26
次回もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
