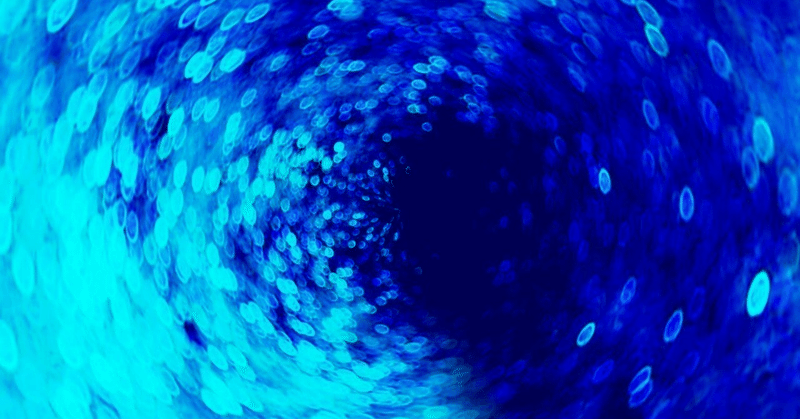
バイオフィリア的な未来(異質で反対の存在と融けあうということ)
これからの未来を築く上で大切なことは「人間中心から生命中心への転換」ではないだろうか。
日々流れてくるニュースで目にする光景、耳にする声、公私での人間関係、ヨガや楽器を通して自分とつながる身体経験。これらにとどまらない様々な物事の集積が混沌とした状態で自分の中で渦を巻いていた。
ふと手にしたいくつかの書籍に記されていた言葉の数々が、「生命」という中心軸を与え、混沌としていた状況に流れと秩序をもたらした。それも徐々にではなく瞬時に、である。
書店に足を運び、棚に並べられた書籍のタイトルを流れるように目で追ってゆく。ふと気になった本をおもむろに手に取り、パラパラとめくってゆく中で「無性に気になる」言葉が目に飛び込んでくる。答えを探しているというよりも、自分の中に渦巻く混沌をに流れをもたらし得る足場としての問いを考える触媒を探している。そんな感覚だ。
「生命中心への転換」の必要性を感じたきっかけの一つは、精神分析学者・社会心理学者であるエーリッヒ・フロムが記した『悪について』という本だ。原題は『The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil』であり、そのまま意味を取ると「人間の心:善と悪の特徴・性質」となるだろうか。
本書から印象的な言葉をいくつか引いてみたい。
生命を守り死と闘う性質は、バイオフィリア的な性向のもっとも基本的な形態であり、すべての生き物に共通している。生命を維持し、死と闘うことは、生へ向かう原動力の一面にすぎない。もう一つ、もっとポジティブな面がある。生きているものは、まとまって一つになろうとする性質がある。異質で反対の存在と融合して、組織的に成長しようとするのである。統合して一つになって成長するのは、すべての生命プロセスの特徴であり、それは細胞レベルだけでなく、感情や思考にも当てはまる。
「異質で反対の存在と融合して、組織的に成長しようとする」という言葉に開かれた未来の可能性を見た気がした。
共同体としての社会において、人は「他者」と向き合わなければならない。分かり合えないかもしれなくても何とか互いを理解しようとする。結果的に距離をおくことになったとしても。
一定の距離をおいた関係も一つの関係である。距離をゼロに縮めることだけが、異質なものと一つになる方法ではない。時間とともに自分も他者も変化してゆく中で、適切な距離感を測り、調整しながら自他区別から自他未分の関係へと移行してゆく。
その調整過程においては時に衝突や対立を起こすかもしれないけれど、何かしらの状態に移行する。とするならば、その移行過程はどのような原理で生じ、行き着く先はどのように決まるのだろう。
「生命とは何か?」という問いと向き合いたくなったのは、そのような素朴な疑問から。そして、たとえば「平和」という言葉は本当のところ何を意味するのだろう。平和という言葉にはどこか温かくてやわらかなニュアンスを伴うけれど、その印象によって覆い隠されてしまっている何かがあるのではないだろうか。生命の視点で平和を捉えてみると何が見えてくるだろう。気づけば、最近はそんなことばかりを考えている。
バイオフィリアの全容がよく表れるのは、その生産的な性向においてである。生を全身全霊で愛する人は、あらゆる領域での生のプロセスと成長に惹きつけられる。現状を維持するより新しいものを組み立てることを好む。驚異を感じる力があり、古いものの確証を得て安心するよりも、何か新しいものを発見することを好む。確実なものより人生の冒険を愛する。生への接し方は機械的というより機能的である。部分だけではなく全体を、概要ではなく構造を見る。彼は愛、理性、自らの範によって、かたちをつくり影響を与えることを望む。力を使用したり、物事を分断したり、官僚的なやり方で人をモノのように支配することによってではない。単純な興奮ではなく、生とその発露のすべてを愛する。
「生を全身全霊で愛する人は、あらゆる領域での生のプロセスと成長に惹きつけられる」というフレーズから感じるのは「止まらずに動き続けている」ということだ。「囚われないこと」とも言えるのかもしれない。
イギリスの哲学者フランシス・ベーコンは、人の偏見や先入観を「四つのイドラ」と表現した。その四つは「認知、経験、伝聞、権威」であるけれど、たとえば人の目に見える光の波長や聴こえる音域には一定の幅があるから、人の目では見えない世界や聞こえない音の世界が存在している。
今でこそ自然科学が明らかにしてきた数々の原理や法則を応用することで、目に見えない世界や聞こえない世界を想像したり、あるいは構成することができるようになった。それは偏見や先入観を乗り越えて、異質なる世界との対話を始め、一つになってゆく機会であるかもしれない。
バイオフィリアの倫理は、独自の善悪の倫理を持つ。善は生に寄与するすべてのものであり、悪は死に寄与するすべてのものだ。善とは、生を尊ぶことであり、生や成長、拡大を高めるものすべてである。悪とは、生を抑圧し、その幅を狭め、ずたずたに切り裂くものすべてである。喜びは美徳であり、悲しみは罪である。(中略)バイオフィリア的な人の道義とは、無理に悪を慎み、善をなすことではない。(中略)バイオフィリア的な良心を刺激するのは、その生と喜びへの引力なのである。その道徳的な努力は、自己のなかの生を愛する側面を強化することにある。この理由から、バイオフィリア的な人間は悔恨と罪悪にとどまることはない。それらは結局のところ、自己嫌悪と悲しみの側面にすぎない。その人はすぐに生に目を向け、善をなそうとする。
「その道徳的な努力は、自己のなかの生を愛する側面を強化することにある」
人には、バイオフィリア(生を愛する性向)とネクロフィリア(死を愛する性向)の両方が内在している。どちらの側面が強調されるのかは、その人を取り巻く環境との関係性において決まってくる。
生命はそれ自身で閉じておらず、自身を取り巻く環境との相互作用や交換を行い続ける中で自らの存在を維持していて、言うなれば流れの中にある渦のようなもの。立ち現れては大きくなり、小さくなって消えてゆく。
人間社会における共同体もまた立ち現れては大きくなり、小さくなって消えてゆく生命体として捉えることができるかもしれない。これまで人類が生命と向き合ってきた中で蓄積されてきた叡智を足場としながら、その叡智を時に拡張しながら、未来を考えてゆく時が来ているように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
