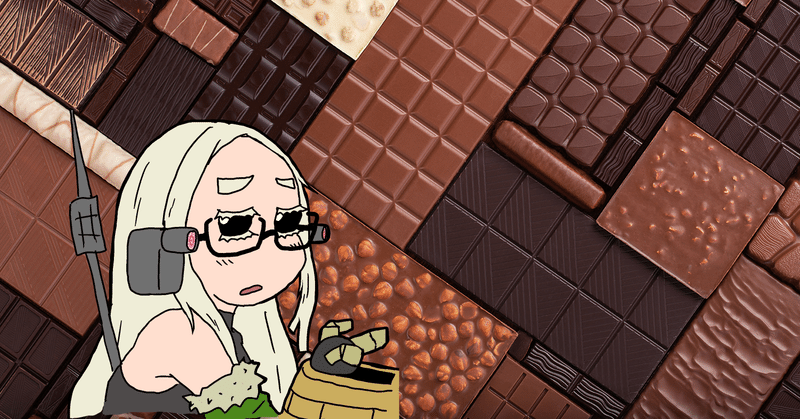
マシーナリーとも子EX 〜徳のバレンタイン篇〜
2045年、2月、池袋……。駅と直結したふたつの百貨店は、厚着をした人類でごった返ししていた! 隙間が見えないほどの人類密度! だが買い物に沸く人類たちはやがて轟音と共に四方へ吹き飛んだ。中心に大爆発が起きたのだ! シンギュラリティのサイボーグ、マシーナリーとも子のグレネードランチャー によって!
「不用心だねえ人類って生き物はよ。サイボーグに殺されるとわかってても買い物したさに外出するんだもんなぁ〜。おい、爆発半径外の人類逃すなよ吉村」
「あいよー」
砲撃から逃げる人類をエアバースト吉村がひとりずつ掴んでは殴る! 賑やかな百貨店は一転地獄の様相となった! だがそう感じるのはあなたが人間だからだ。これはサイボーグにとっては至って日常的な光景であり、そこに残酷さは微塵もない。このことは理解された上で読み進められたい。
殺戮を終えたあと、マシーナリーとも子はふと奇妙なことに気づいた。
「なあ……なんか変じゃねぇ〜か?」
「なにが?」
「殺した人類が女ばっかだぜ……。男は店員だけみたいだ」
「そんなもんじゃねーの? 百貨店の客層ってだいたい女だろ」
「付き添いや子どもだっているだろ? でも今日は100%だぜ……あ?」
「なに?」
「あの垂れ幕見ろ……なんだぁ?」
「「バレンタイン??」」
***
「あら、あなたたちバレンタインも知らないの? ネットリテラシーが低いわね」
とも子と吉村はその昼、昼食を共にしたネットリテラシーたか子に聞いてみた。百貨店に女性を密集させたあの垂れ幕の意味がわからなかったのだ。たか子は腕のチェーンソーで器用にポークリブを切り分けながら答えた。
「人類の女性が、2月14日に意中の人類にチョコレートを贈るイベント。それがバレンタインよ」
「イチュウ? イチュウってなに?」
「愛してるってことだよ。ねぇー、たか子さん」
「わからん。感情がないから」
「じゃああそこにいた人類は全員恋人やダンナに贈るためのチョコを買いに来てたのか」
「そうとも限らないわね。チョコを買う理由は伴侶以外にも子どもや親戚というのもあり得るでしょうし、義理チョコという文化もあります」
「義理チョコ?」
「友人や同僚にチョコを贈る文化よ」
「そんなもんまであるんだ。そこまでする必要ってある? わかんねぇなぁ〜」
「おそらく……単なるコミュニケーション以上に、彼女らにはそうした理由が必要なのでしょう」
「理由? 理由ってなんの?」
「チョコを買う理由よ」
吉村ははぁ~? と眉毛を下げた。
「そんなもん、いります? ただ好きに買って食えばいいじゃないですか」
「わかってないわね。そういう理由があればこそ、必要以上にチョコを買えるのよ。チョコレートというのは非常に豊富なバリエーションが存在します。マシーナリーとも子、あなたみたいに年中コンビニの麦チョコを食べているサイボーグには及びもつかないでしょうが、それはそれは深い沼なのよ。チョコレートドリンクでできた沼はね」
「そーなの?」
「そしてチョコレート特需のバレンタインでは、各ブランド趣向を凝らしたハイエンドなチョコ、変わったチョコが店頭に並ぶの。一部ではバレンタイン時期の百貨店はチョコの博覧会、チョコのコミケと言われているわ。要するに彼女たちはチョコのオタクなのよ」
「なるほどねえ」
「そこまで言われると興味が出てくるなあ……。買いに行く?」
「悪くねえな。……ってかたか子、いやに詳しくない? それもネットリテラシーか?」
「ふむ……興味があるのなら、まああなたたちに会わせてもいいかもしれないわね」
「?」
たか子は最後のポークリブをマフラーの中に放り込むと、ファンネルに携帯通信端末を操作させた。
***
とも子と吉村、たか子が支部の入り口前に立つ。たか子が呼んだ、チョコに詳しい客が今日訪れるのだという。
「そろそろね……。あっ、あれだ」
「あれって……もしかしてあれか?」
駅の方からこちらに向かって、奇妙な四角いものがえっちらおっちらと歩いてくるのが見える。四角いものはマシーナリーとも子が両腕を広げた長さより多少大きいくらいの幅で、高さは足からお腹くらいまでの大きさだろうか。そんなことを考えていると、その四角いものを支えているようにヒューマノイドタイプのシルエットが下方にあることに気づく。
「あれはなにかを……背負ってるのかな?」
「手伝ったほうがいいのか?」
「いいわよ。いつものことだから」
その四角いものを背負った影は、やがてたか子に気づいたのか腕を大きく振ってきた。たか子も軽くチェーンソーを振って返事とする。
「……やっぱサイボーグか」
「ボンジュールたか子。なぁわかってるだろ? 今自分は忙しいんだ」
「作るスピードはいつも通りでしょう。じゃあ問題ないわ。私にはいくつも借りがあるのを忘れてはいないでしょうね矢野」
「だからこうして文句を言いつつも来たんだろ」
たか子から矢野、と呼ばれたサイボーグは文句を垂れながらも背負った四角い物体……それはキッチンだった……に、さらに背中から生えた4本のアームを伸ばし忙しなく動かしていた。
「ねえたか子さん、もしかして……」
「ええそうよ。彼女はファイナルメモリー矢野……。チョコレートのテンパリングで擬似徳を得るサイボーグよ」
「テンパリング???」
「えーと……マシーナリーとも子とエアバースト吉村……でいいのかな」
矢野と呼ばれたサイボーグが長いコック帽を脱ぎながら話す。
「バレンタインに興味があるんだって?」
「うんまぁ……興味があるというか」
「変わった風習だなぁーってな。チョコレートもまあ、ロボ並に好きだし?」
「実はね、バレンタインを始めたのは私なんだよ」
とも子と吉村が固まる。
「お前が?」
「そう。正しくは、この国でバレンタインデーにチョコを贈るという習慣を流布したのが私さ」
「な、なんでそんなことしたの? それもシンギュラリティのため?」
「いや……これはどちらかというと私のためで、組織のためではない。もちろん、組織の目指す乱数に影響しないようキチンと正式な認可を取って調査も進めた上でだが……」
「どういうこと?」
とも子と吉村の頭に疑問符が次々と生まれては消えていった。それを見てたか子はニヤニヤと笑った。
「それからは私が説明しましょう……。彼女はその徳の生じさせ方故にチョコレートを大量に作る必要があります。その、チョコレートが無駄になることに彼女は耐えられなかったのよ。当時はまだバレンタインは無く、この国のチョコレートの消費量も今に比べると微々たるものでした」
矢野は目を閉じ腕を組んでウンウンと頷く。当時を懐かしむように。
「どうすればいいか考えた結果、根本的にこの国のチョコレート消費量を増やそうとしたのね。そうして私の任務とともに戦後の日本に飛び、バレンタインのチョコ交換を普及させたのよ」
「たか子はその後任務を終えて帰ったが、私はその後日本に残り続けた。コツコツとこの国にチョコレートの文化を継承させ続けてきたんだ」
「へぇーっ、大変な任務だなあ」
吉村は素直に感心した。戦後といえばおよそ100年ほど前だ。1世紀にも渡り仕事し続けるなんて自分にはとてもできない。
「まあ、結果けっこうこの国の歴史は変わってしまったのだけどね……。あなた達もチョコレートは食べるでしょう」
「まあ……」
「日本のチョコレート企業はいくつかありますが、その9割は矢野の息がかかってるのよ」
「はい?」
矢野が腕時計を確かめる。
「ああ、実はこの誘いに応じたのもたか子への義理はもちろんだが池袋方面にビジネスの用事があってね……。よかったら君たちもくるかい」
***
一同は東池袋にある高層ビル入った。いくつも会社が入ったビルにありがちなように、下層に総合ロビーがあり、駅の改札のようなものが設置され警備員が物々しく立っている。が、そのうちのひとりに矢野が腕をヒラヒラとさせると警備員は会釈し、改札の扉を開けるのだった。顔パスなのだ。
「このビルには業界2位のメーカーが入っている……。彼らは1位を引きずり落とそうと必死でね。そのための新商品開発に呼ばれてるというわけさ」
矢野はめんどくさそうに懐から粒状のチョコを取り出すとガリガリと噛み砕いた。
「ストレスを緩和する成分が練り込まれたチョコだ。食うかい?」
「じゃあもらう……。でもさ、さっき聞いた話だとその業界1位のメーカーってのも」
「そう、私が商品開発してるのさ」
もらったチョコを噛み砕きながらとも子は呆れた。なんでそんなことになってるんだと。とも子の心情を察した様に矢野は続ける。
「まあしょうがないのさ。私も、負けてるのは営業力とかその辺だと思うとは伝えているんだけどね。彼らは大ヒットチョコレートの一発逆転性に賭けているのさ」
エレベーターに乗り、47階のボタンを押して矢野は続ける。
「最初はどうしてもできてしまうチョコレートをなんとか消費するためのバレンタインデーだった。だが人類ってのは金の匂いのするものにはすぐに吸い寄せられてくる。作戦を開始して1年もしないうちにいろんな企業から声をかけられたよ。当時はアメリカから持ち込まれたチョコレートの魅力は強烈なものだったからね」
「ギブミーチョコレートってやつね」
返しながら吉村が矢野に向かって手のひらを上にする。
「ああ悪い悪い、とも子にしかあげてなかったね。たか子もいるかい?」
「いらない。感情がないから」
「うまいぜ」
「いいと言うに」
矢野は吉村にボロボロと3、4個のチョコを手渡す。
「もちろん全国で流通させるようなチョコレートを私だけで開発するのは不可能だ。百貨店の売り場を埋めることくらいはできるけどね。だからメーカー相手には商品開発の手伝いをするのが主な役割だった。他にも大量生産のための工場の設計とか、管理のための施設の考案とか色々したがね」
「めちゃめちゃしてんなあ」
「気づけばこの国で私のノウハウが活かされてないチョコは存在しないような状態になった。この国のチョコレートの母は今や私なんだよ」
「でもさ、ちょっと不思議だよな」
チンとエレベーターが鳴り、目的階へ着いたことを告げる。
「アタシ達がどこまで認識できてるかわかんねーけど、矢野さんが過去に行くまでこの国のチョコレートの歴史は違ってたわけだろ? その場合、どんなチョコレートが売ってたんだ?」
「なーに簡単さ。輸入食品店でちょっとクセのある海外のチョコ売ってるだろ? あれが細々と売られてたのさ」
「なるほど」
吉村は一応の合点をする。矢野がたどり着いた先のドアを開けると、そこは会議室だった。数名いたスーツ姿の人類が起立し、頭を下げる。
「先生! この度はご足労をおかけして……」
「いいよいいよ。いつものことだから今更……。友達を連れてきたんだけど構わないかな?」
「そ、それは勿論……」
矢野は背中に抱えていたキッチンを床に下ろす。キッチンは矢野の腰から丈夫な二軸アームで繋がっており、スムーズに上げ下ろしができるようだった。キッチンの中央には半円状の凹みがあり、そこに矢野の身体がすっぽりと収まる。その姿はチョコレートのパティシエというより天ぷら屋を彷彿とさせた。
「さて、じゃあ商品開発もいいけどウォーミングアップがてら普通にチョコレートを作ってみようか。とも子と吉村に見せてあげよう」
「おーっす」
「別におもしれーからいいけど、なんで社会科見学みたいな流れになってるんだっけ?」
「アンタ達がバレンタインのチョコに興味があるって言ったからでしょーが」
たか子は不満げにふんふんと鼻息を鳴らす。彼女に感情はなかった。
「いや、別に買いに行って食えれば満足だったんだけど。料理とかお菓子作るところ見るの好きだからいいけどさ」
「まあ他のサイボーグの徳の積み方を学ぶのも仕事のうちよ。とくに吉村。あなたはもっと真面目に徳の積むべきだわ。よく見ておくのね」
「へーい」
矢野は慣れた手つきでチョコレートを刻み、同時に背中から生えたアームを伸ばして湯を沸かす。
「まずはチョコレートを湯煎しながらかき混ぜて溶かす。このとき、沸騰したお湯を使ってはいけないよ。チョコの風味が飛んでしまうからね。温度は50度から55度を保つのが肝要だ」
「めんどくせーな」
「いやいや、これからもっと面倒くさいよ。このまま固めるんじゃなく、また冷やして、温めてを繰り返すんだ」
言いながら矢野は今度は氷水を用意し、チョコレートが入ったボウルをつけた。
「こうすることでチョコの結晶が安定し、美しい光沢となめらかな舌触りが生まれるんだ。これをテンパリングと言う」
「チョコなんて溶かして固めるだけだろと思ってたけど案外めんどくさいんすねぇー」
「あとは型に入れてもう一度冷やせば美しいチョコレートが……何!?」
矢野が悲鳴を上げた。
「どーした?」
不思議に思ってとも子が覗き込むと、固まったチョコレートはツヤがなく、表面に泡のようなマーブル模様が浮かび上がっていた。
「ば、バカなこれは……テンパリングを失敗している!?」
矢野の顔が青くなる。そしてそれは周りの社員たちも一緒だ。
「矢野さんがテンパリングをミスるなんて……」
「珍しいよな」
「大丈夫かな?」
とも子と吉村はその様子を不思議そうに眺めていた。たか子は矢野と同様に冷や汗をかいている。
「矢野が……テンパリングを失敗?」
「なあたか子、それってそんなに大変なことかあ?」
「マズいわね。テンパリングはチョコレートの品質を決めるのにもっとも大事な工程。年末な温度調整が必要な、基本かつ難易度の高い技術よ。それを失敗するということは矢野の技術が怪しまれるということ……。ただ一度の失敗でもね。ましてや矢野はテンパリングで擬似徳を得るサイボーグなのよ。見なさい、彼女のショックを受けた顔を」
矢野は冷や汗を顔中にかき、息を荒くしていた。腕が震えあがり、手にしていたゴムヘラを床に落とす!
「擬似徳というのはね……徳の高い行動をしたと言う気持ちなのよ。だから大丈夫だという気持ちで動いている。いま、彼女はその気持ちが揺らいでいる。この意味がわかる?」
「……ヘタするとこのまま矢野は死ぬ?」
「最悪な場合はそれもあり得るわ」
「お、おい矢野さん! 今のはちょっとしたうっかりミスだろ! もう一度やってみたらできるって!」
倒れかけた矢野の肩を吉村が抱え上げて助ける。矢野はぶつぶつと小さな声でつぶやいていた。
「私の温度管理は完璧だった……。なぜ? なぜ失敗したんだ……」
「矢野さん!」
そのとき部屋のドアが勢いよく開かれ、血相を変えた社員が飛び込んできた。
「大変です! 工場が……チョコレート工場が!」
「なんだ、どうした!?」
「で、できあがったチョコレートが……すべてテンパリングを失敗しているんです!」
「なにぃ!?」
***
読んだ人は気が向いたら「100円くらいの価値はあったな」「この1000円で昼飯でも食いな」てきにおひねりをくれるとよろこびます
