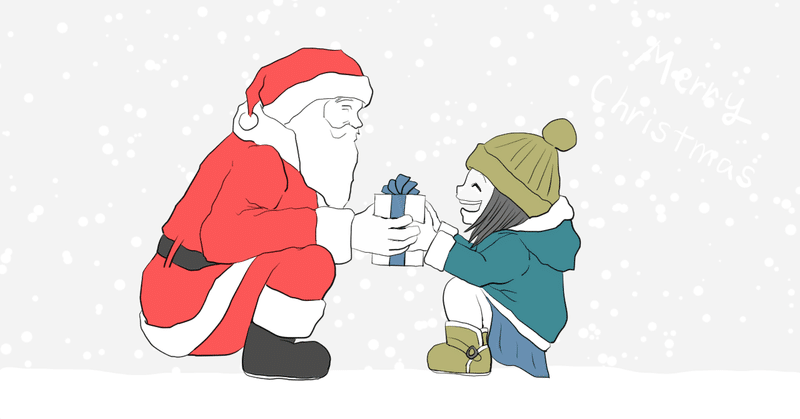
無償の愛、の誤解(世界は贈与でできている/近内悠太)
贈与=私たちが必要としているにもかかわらずお金で買うことのできないものおよびその移動、と定義したとき、私たちはその「お金で買えないもの」の正体がよく分かっていない。
贈与の原理が分かっていないから、大切な人との関係を見誤るのだ。
こう主張する著者が、贈与の原理とそれを正しく語る言葉を明らかにすることで、世界の成り立ちを解く一冊。
名画『ペイ・フォワード』や、『テルマエ・ロマエ』のルシウスを「贈与のメッセンジャー」として解説するなど例が分かりやすく、「なるほど、あれも贈与だったのか」という気づきに満ちた作品だった。
「無償の愛」の誤解
この世の贈与には全て先行する贈与があり、「私は受け取ってしまった」という被贈与感、つまり「負い目」に起動されて、贈与は次々と渡されていく。
親は愛という形で子に贈与をするが、これを「無償の愛」とする表現は誤解を生む。
贈与の宛先である子からの見返りを期待しない、という点では正しいが、それは「無から生まれる愛」ではなく、先行した贈与(親がその親から受け取った愛)があるからだ。
「育ててもらえるだけの根拠も理由もないのに愛されてしまった」という感覚が、子に「負債」を負わせ、負い目を相殺するための返礼、つまり「反対給付の義務」が生じる。その義務に突き動かされた、返礼相手が異なる贈与、これが「無償の愛」の正体なのだ。
親が孫を望む理由もここにある。
親は「子が再び他者を愛することのできる主体になった」ことによって、贈与が正しく完了したと認識できるからだ。
映画『ペイ・フォワード』に見る贈与の困難さ
恵まれない家庭で育った少年・トレバーは、社会の授業で「世界を変える方法を考え、実行してみよう」という課題に対し、善い行いを受けたら3人にパスをするという「ペイ・フォワード運動」を思いつく。街中に贈与のフローが広がっていく感動的な物語だが、結末はトレバーが殺されるというショッキングなもの。
なぜ、この結末が必要だったかというと、不幸なトレバーが贈与を受け取ることなく贈与を開始してしまったからだ。「被贈与の負い目」がないトレバーには、贈与のフローを生み出す力が存在しない。その力の空白を埋め合わせるために必要だったのが、トレバーの命だったのだ。
つまりこの映画は、贈与の失敗の物語なのである。
呪いの言葉
「お前のことを思って言ってるんだよ」をいう言葉は呪いだ。
未来の利益の回収を予定している贈与は贈与ではなく、「渡す」「受け取る」の間に時間差があるだけのただの交換であり、打算にもとづく行為だ。等価交換を贈与と言い張るこの行為は偽善であり、自己欺瞞である。
プレヒストリーなき贈与は必ず疲弊し、トレバーのような「自己犠牲」を生む。
贈与になるか偽善になるか、あるいは自己犠牲になるかは、それ以前に贈与を受け取っているか否かによる。
ギブ&テイクの限界点
仕事上の知り合いと友人関係になりにくいのは、互いを手段として扱うからだ。そして私たちは、自分のことを手段として扱う人を信頼することができない。ギブ&テイクという交換的な人間関係に信頼は存在せず、裏を返せば信頼は贈与の中からしか生じない。
贈与は、それが贈与だと知られてはいけない
「これは贈与だ、お前はこれを受け取れ」と明示的に語られる贈与は呪いへと転じ、受取人の自由を奪う。手渡される瞬間に返礼の義務を生み出してしまい、見返りを求めない贈与から「交換」へと変貌するからだ。
そして、交換するものを持たない場合、負い目に押しつぶされ呪いにかかってしまう。
『鶴の恩返し』の部屋を覗いてはならない理由もここにある。
贈与者は名乗ってはならず、贈与はそれが贈与と知られない場合に限り、正しく贈与となる。しかし、ずっと気づかれない贈与はそもそも贈与として存在しない。
「あれは贈与だった」と過去時制によって把握される贈与こそ、贈与の名にふさわしい。私たちは受取人としての想像力を発揮するしかない。
資本主義のすきまを埋める
私たちが仕事のやりがいを見失ったり、生きる意味を自問したりしてしまう理由は、それが「交換」に根差したものだからだ。
歴史を学び、手に入れた知識や知見そのものが贈与であることに気づき、その知見から世界を眺めたとき、いかに世界が贈与に満ちているかを悟る。それができた人はメッセンジャーとなり、他者へと何かを手渡す使命を帯びる。仕事のやりがいや生きる意味の獲得は目的ではなく、贈与の結果として返ってくるものなのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
