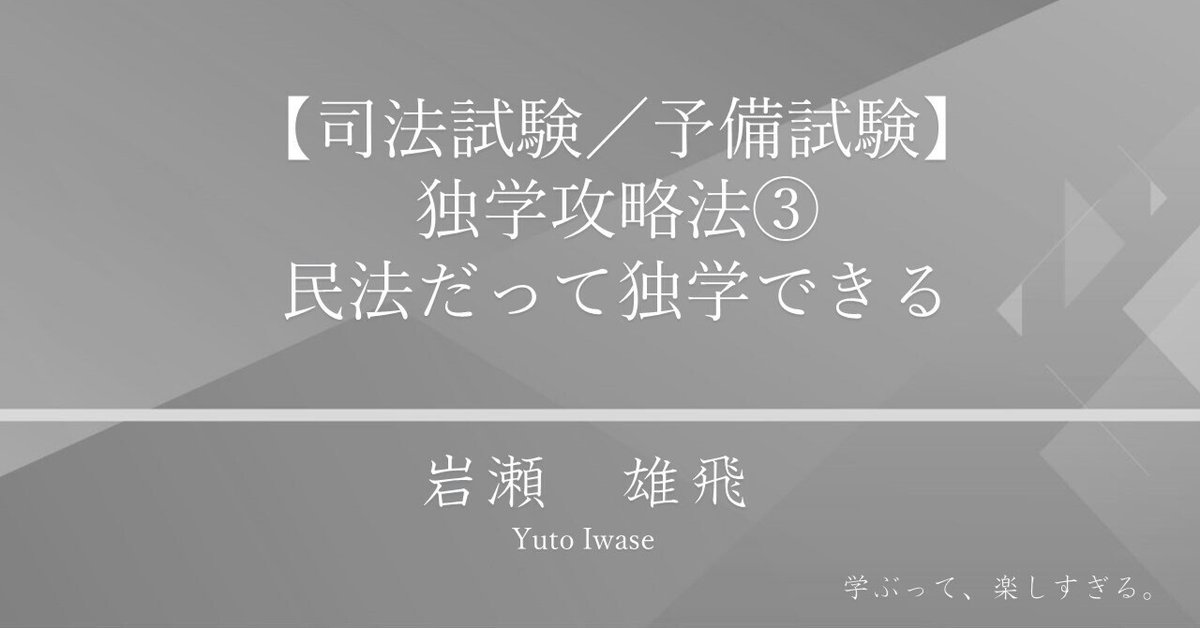
【司法試験/予備試験】独学攻略法③~民法だって独学できる
「学ぶって、楽しすぎる。」-弁護士の岩瀬雄飛です。
本noteでは学ぶことの面白さや学習のノウハウ等を発信するとともに、自分が学んだことの記録を発信しています。
今日のテーマは「民法の勉強法(初学者)」。
前回までのnoteでは、司法試験・予備試験合格を目指すために、まず刑法から始め、その後は刑事訴訟法を学ぶ、すなわち刑事系科目を一通り終えることを提言した(前回までのnoteは以下参照)。刑事系の学習を終えたら、次はいよいよ民法である。
(1)刑事系の次に民法を学ぶべき理由
刑事系の次に民法を学ぶべき理由は「消去法」になる。刑事系以外の科目には、公法系の「憲法」「行政法」、民事系の「民法」「民事訴訟法」「商法(会社法)」、そして選択科目がある。しかし、選択科目については予備試験の短答試験には用意されていないため、予備試験経由で司法試験を受ける人は一旦後回しになる。
まず、「民事訴訟法」と「行政法」は除外される。この2科目は内容が小難しく、学習に取り組みづらい。また、周りの受験生も苦手であるので、頭ひとつ抜けるだけでA判定がとれる。私自身の経験をいうと、行政法はどちらかというと苦手であったがAであった(民事訴訟法は得意だったので周りの受験生に差をつけた自負がある)。
「憲法」は司法試験・予備試験に合格するレベル、すなわち深入りしなければそこまで学習量が多いわけではない。しかし、抽象的であったり堅苦しい内容が多かったりするため、前に進んでいる気がしない。そのため、勉強の前半戦である現段階においては、モチベーション維持の観点からお勧めできない。
「商法(会社法)」は、特に社会人で会社勤め等をしている人にとっては民法に代わる選択肢として考えられる。なじみがある分学習がしやすいであろう。
以上から、「民法」又は「商法(会社法)」が刑事系の次に学ぶ科目として候補に挙がるが、特におすすめは「民法」である。
(2)「民法」の学習はまずマインドから
まず意識してほしいのは、民法は学習量が多いということである(刑法・刑事訴訟法の合計と同等かそれ以上である)。そのため、挫折してしまったり、とりあえず量をこなすために、よく分からないまま「本を読み進めているだけ」「短答試験の問題を解き続けているだけ」の学習をしてしまったりする人が少なくない。このような事態を避けるため、まずは、民法を学習する上での心構えを身に着けてほしい。
①民法「1科目」ではなく「民法①~⑥」の6つととらえる
「民法」は大きく6つに分けられる。①総則、②物権、③債権、④契約、⑤不法行為、⑥親族・相続である(民法自体もこの6つのカテゴリーで、この順番ごとに並んでいる)。
仕事でもそうだが、ひとつの大きいタスクをこなそうとするとやる気が起きず、また、途中で挫折しやすくなる。そこで細かいタスクに分解し、ひとつひとつdoneしていくことをお勧めする。
②民法を得意にする必要はない
「民法」は、「あなた」を含め多くの受験生が最終的になんとなくは答案を書けるようになる。他方で、そのような科目で差をつけることは難しい。そのため、民法を得意科目に育て他の受験生と差をつけようと思う必要はない(この戦略はまさに「策士、策に溺れる」である)。思うように学習が進まなくとも、「最終的にはなんとなく答案が書けるようになる」「得意にする必要はない」と開き直って、挫折を回避することで十分である。
(3)民法を「何を使って」「どのように」「どの期間」勉強すべきか
何を使って
民法の学習の基本戦略も、刑事系同様、「基本書を1章読む→その章の短答試験を解く→基本書を読み直す」である。
まず基本書を読む。しかし、民法の基本書選びは正解がない。民法については、多くの教授が出版している一方、少なくとも私が知る限り「決定版」と言われるものはない。私が使用していたのはロースクールの各クラスの教授が指定したものであったが、(おそらく印税のために)自分が執筆したものを指定されることが多かった。
そのため、ここでは『LEGAL QUEST』(有斐閣)シリーズを挙げておく(以下のリンクはⅠ総則だがⅥまである)。中身だと上記のとおりどの基本書がよいと断定することが難しいため、商法・民事訴訟法・刑事訴訟法と同じシリーズで勉強する方が勝手が分かっているという意味、すなわち学習効率を考慮した。
どのように
刑事系同様、「①各章ごとに読んで、内容を理解する→②短答試験を解く→③基本書を読み直す」を章ごとに繰り返すことで確固たる知識をつけてほしい。詳細は本note冒頭のリンクから刑事系のnoteを参照してほしい。
ここでおそらく気になるのは①総則、②物権、③債権、④契約、⑤不法行為、⑥親族・相続のどれから手を付けるべきか、という点であろう。私のお勧めは、相性や難易度等を考慮してA「①総則・⑥親族・相続」→B「②物権・⑤不法行為」→C「③債権・④契約」である。
なお、1単元ずつ進めていく方が理論上は効果的である。仕事でもマルチタスクよりもシングルタスクの方が、仕事効率が高いことは分かっている。1単元ずつ進める場合は、①→②→⑤→⑥→③→④を提言する。
しかし、学習モチベーション維持の観点からは異なる分野の学習を並行して行うべきであると考える。ひとつの分野だけ学習するのは飽きるからである。
Aセットは、①総則と⑥親族・相続である。総則の中で特に重要な分野は「錯誤」等の「意思表示」と「代理」であるが、「後見」など⑥の親族・相続と一部リンクする内容も含まれるため、このセットにしている。
また、⑥は民法学習のスタートに適している。⑥は司法試験・予備試験とも論文での重要度は高くないが、短答試験では毎年複数問出題される。どちらかというと理解よりも知識の学習になり短答試験メインであるから学習がしやすい。加えて、婚姻、離婚、相続、遺言等、なじみがある内容であるためやはり学習がしやすい。
Bセットは、②物権と⑤不法行為である。この2つは特にシナジーがあるわけではないが、②の物権がそれなりにハードであるため、学習量が少なく(民法だけなら20条文くらいである)、かつ、イメージがしやすく学習がしやすい⑤不法行為をセットにしている。
Cセットは、③債権と④契約である。契約をバラしたものが債権であるため、この2つの相性がよいのは当然である(例えば、売買契約は代金請求権と対象物の引渡請求権の2つに分解される)。
しかし、Cセットは、AセットやBセットに比べると学習量が多く、内容も難しい。そのため、民法学習の仕上げとして最後にスケジューリングした。
どれくらい
民法の学習は時間がかかる。そのため、A→B→Cを各1か月のトータル3か月で勉強し終えることをお勧めする。
なお、このときに刑事系の復習も怠らないようにしてほしい。定期的に記憶のメンテナンスをしないとせっかく覚えたことも忘れてしまう。
例えば、朝起きた直後のウォーミングアップで刑事系の短答試験を解いたり、覚えた定義の確認を行ったりすることをお勧めする。もっとも、時間をかけすぎると肝心の民法の学習をする時間が無くなってしまうので、ウォーミングアップは20分から30分にとどめたい。なお、朝の勉強については以下のnoteも参考にしてほしい。
終わりに
民法は論文試験では他の科目と同じ配点にもかかわらず学習量が多い。しかし、単元に分割することで学習の心理的ハードルが低くなると思う。民法学習は富士山のように高い山ではあるが、1号ずつの到達を目標にして、挫折することなく山頂にたどり着いてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
