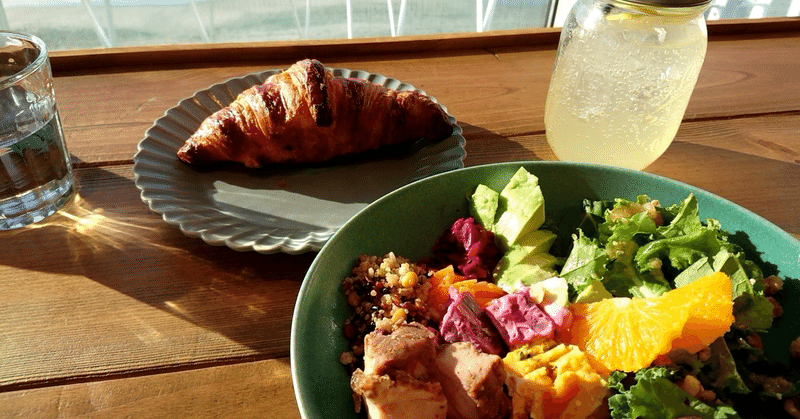
煩悩と静謐
ずっと昔のお話です。あるところに名のない女がいました。女は長い間、夫から有形無形の苦しみを与えられ、自分はそれに耐えることを義務づけられているに違いないと考えて生きていました。
彼女がはじめて夫となる若者に出会ったとき、若者はとても親切で礼儀正しくさえありました。若者のとび色の瞳に見据えられた時、彼女は生まれてはじめて体の芯を触られた気がしていました。体の芯に楔を打たれ、その楔が彼女の心と体を震わせ湿らせ動けなくするのです。それが幼い官能であることに怯えた彼女は、若者との出会いはなにかしらの聖なるものだと考えるように努めました。若者の栗色の髪はきちんと整えられ、あるいは時にわずかに乱れ独特な波を打っていました。髪のそのスタイルは、若者がお洒落で頼もしく好ましい存在であることを彼女の乙女心に雄弁に語っていたのでした。一方で目の前にいる若者の魂は激しい野心を持て余していることも彼女は見抜いていました。なぜなら彼は「そのうちなにか大きなことをするつもりだ」といくぶん鼻につく横柄な態度で彼女に訴えたからです。その野心は平和で居心地のよい家庭には似つかわしくないと彼女は感じ取ったのでした。
それでも結局彼女は若者と結婚することに決めました。若者のとび色の瞳から逃れることは出来ないと彼女の身体が判断したのでした。それほどにとび色の瞳は妖しく美しく若い女の心と体をすっかり痺れさせてしまったのでした。やがてふたりの間に可愛らしい女の子の赤ちゃんが生まれましたが、新米の母親は、同時に毎晩夫の帰りを狭い部屋で待つせつない妻になりました。夫はその部屋にはたいてい寄り付かず、いつも妻が知らないどこかをふわふわとさまよっているのでした。若い母親は一輪の花もない灰色の部屋の中で生まれてまもない赤ちゃんを抱き、夫の帰りをただただ待つしよりほかに生きる術がなかったのです。
時間はときに残酷なものです。苦しみと惨めさと痛みとが若い母親の人生に付きまとうことになりました。まれに部屋に戻ると、夫は小さな子供の眼の前で、妻を無視し侮辱し嘲り、あるいは何度も妻の痩せ細った青白い頬を男の逞しい手のひらで繰り返し殴るのでした。夫は暴力と同情心とを交互に用いて妻を思いのままに支配しました。夫は妻に言いました。
「俺はこの世にあるものをなんでも高値で売りさばくことだ出来るんだ。田舎には無数の哀れで無知な奴らがいる、俺は奴らの家から家へと渡り歩いて、聖書を売り、義足を売り、可愛い娘がいれば赤いサテンのリボンで髪を飾ってやる、そうすれば娘たちは簡単にうっすらと毛の生えた両脚を開いてくれるからね」
外から帰ると夫は妻が赤子を抱くその部屋で深々と酒を呑み、酔っ払い、しゃがれた声でなにかしら世の中に対する恨み言を並べ、そのうちなんともだらしない姿態のまま床にはりつき、眠ってしまうのでした。三日、あるいは四日間を同じように過ごし、夫はまたどこかへと去ってゆく、さよならの一言もなく彼女の前からあっさりと消えてしまうのでした。
あるとき、妻は近所にある西洋風の食堂に働きに出ることにしました。夫には家にお金を入れるという概念がほぼ備わってないことを悟ったからです。小さな娘との最低限の、けれども心をつくした穏やかな暮らしをなんとか守ろうと妻は社会に出て働くことを選んだのです。
食堂はそんなに流行っていませんでした。ふたりか三人の客が肩をすぼめて酒を呑み、しわくちゃの新聞に顔をうずめるくらいです。手が空くと店の主人は耐えられるぎりぎりの大音量で古いラジオを聴き始め、その気になるとたった一人の従業員であるウェイトレスにいい加減な音楽の知識を披露するのが癖になっていました。蛍光灯のおぼろな灯りのもと、数匹のハエが意味なく飛び交い鈍い音をたてていました。店の主人とウェイトレスは古いラジオから流れる古い音楽を浴び、客が訪れるのをただ待っていたのです。
しかしこの古ぼけた食堂には奇妙な客が集っていたことも事実です。若い絵描きがいました。彼の作品の中には作者である彼自身気づいていない祈りの音が明らかに低く響いているのですが、それに気付くにはあまりに彼は若すぎました。曲がった腰で店のテーブルのいくつかに手をついて、店じゅうをふらふらさまよう老婦人がいました。老婦人は丸い朱色の舌先で彼女の乾燥したうわ唇をべろべろ舐めるのが癖になっていました。中年の男がいました。この男はなんでも社会主義を標榜する政党の一員だというのです。男は周りにいる見知らぬ人々に向かって、今、外国でどのような切迫した政争、あるいは流血の戦が起こっているかを何かにとりつかれたように熱心に早口で論ずるのですが、誰一人彼の話を理解しようとする人間はいませんでした。
風のように夜のように沈黙のように熱風のように愛のように、時間はさらさらと過ぎていきます。
あるとき、食堂のウェイトレスは自分が50歳であることに気づきびっくりしました。彼女は自分以外の人間のいくつかの人生を見聞きしてきました。あの腰の曲がった老婦人はある朝、動かないちっぽけな遺体となって発見されました。ピンク色のネグリジェに包まれた老婦人の遺体は豪華なベッドに横たわり、流行りの若い役者が微笑んでいる雑誌のページを胸に抱いていたということです。若い絵描きはオレンジ色の薔薇の花を一輪食堂のウェイトレスに差し出した夜以降、食堂に姿を見せなくなりました。中年の社会主義者は遥か遠い国に赴き兵士になったとのうわさがしばらくありましたが、そのうち誰もが彼を思い出さなくなりました。
他人の人生についてあれこれ思いわずらうのはなんとも愉快なものでした、けれど、ウェイトレスは自分がどのように娘を育ててきたのかについては何もかも忘れてしまったように思えてなりません。だから彼女は心に決めました。自分で自分のこれまでの日々を認めたのです。
「わたしはしなければならないことをすべて果たしてきた。娘が飢えることのないよう十分な食事を与えてきた、暖かい毛布を切らすこともなかった、毎晩娘の小さな体を抱きしめ、いつだって娘に微笑みかけることを忘れなかった」
ある夏の日、ウェイトレスの娘は若い海兵隊員に恋をしてやがて、彼女は海兵隊員の可愛らしい妻になることを決めました。男の両腕に腰を包まれ頬を染めることを知った娘がさよならを告げにきた朝、50歳の母親は娘の身体を抱き寄せ、強く抱きしめ、若い娘の頬に繰り返しキスしたのでした。
さて。50歳を過ぎたウェイトレスの夫、かつてとび色の瞳と波打つ髪で女たちの心と身体を狂わせた男は、彼の人生において何ひとつ大きなことを成すことはありませんでした。長い月日は彼のちっぽけなプライドをすべてこなごなに砕いたのです。やがて夫は奇妙なことを口走るようになりました。神を見た、神に出会った、あるいはこの世界の謎と目的を突き止めたなど。妻は夫の頭のネジが少しばかり緩んでしまった、あるいは単純に夫は狂ってしまったのだと思いましたが、自分には夫のさまよえる魂を救うことなど出来ないのだということも、彼女はきちんと理解していたのでした。
そうしてまた時が経ち、夫は、寡黙な老人になり、いつでも妻の横で眠るようになりました。老人は朝も昼も夜も本当によく眠るのです。ソファやベッドに身体を横たえると、瞬く間に深い寝息を立て始めるのです。妻は眠ることがあまり上手ではありません。天井を眺め、壁紙の模様のひとつひとつを数え、それでもなかなか寝付けないのです。いつしか妻は眠るのをあきらめ、スケッチブックと鉛筆を手にするようになりました。手慰みに眠る夫の顔を描いてみようと思いついたのです。よく見ると眠る夫はいつもわずかな微笑を浮かべているようでした。妻は長い人生が夫に与えたであろう苦しみや嘆きを画用紙に描き出そうとしたに違いありません。けれど、妻が何度鉛筆を動かしても、鉛筆が描き起こす夫の寝顔には明らかな微笑がまるで必然のようにまとわりつき、妻はその微笑の圧倒的な静謐さにただただ心奪われるしかありませんでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

