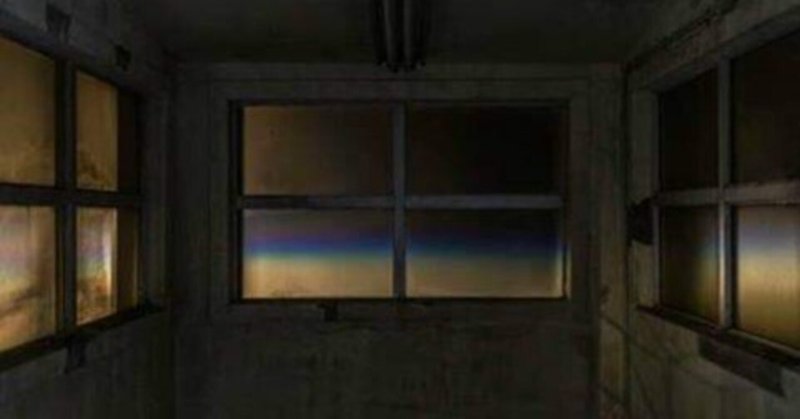
《「東京藝大に行ってます(笑)」》2022/11
▼「東京藝大にいってます(笑)」
ご挨拶させていただく時に、そんな冗談を言うことがあるのですが、自分の複数ある名刺の中のひとつに、”藝大RAM”バージョンがあります。
RAMとは、Research for Arts and Media-projectの略で、東京藝術大学・大学院の映像研究科(メディア映像専攻)が主催している、アーティストを中心にした社会人向けのノンディグリー教育プログラムで、2014年度から現在まで(2017年度は休止)、文化庁による「大学における文化芸術推進事業」助成を受けて開催されています。
私は2018年度に応募して参加、その後、現在(2022年度)まで継続して参加しています。
「RAMってどんなプログラムなんですか?」とよく聞かれるのですが、一言で答えるのが難しい有機体でいつも困っています(笑)
▼藝大RAMとは
RAM自体の定義も移ろっています。2014年度からは「リサーチ型アートプロジェクトのための人材育成事業」、2018年度からは、「メディアプロジェクトを構想する映像ドキュメンタリスト育成事業」と、2021年度からは「インターメディア型プロジェクト・ベースド・ラーニング実践プログラム」と銘打たれて開催されてきました。
自分は、2018年度の要項にあった、「メディアプロジェクトを構想する映像ドキュメンタリスト育成事業」「ポストドキュメンタリー、その芸術実践を目指して」というテーマに惹きつけられて応募しました。
その要項には、対象者として「同時代の表現行為を実践的に問い直そうとするアーティスト、演出家、研究者、エンジニア、プロデューサー、編集者、プロジェクトマネージャーなど」と記されています。定員は20人ほど。倍率は高いときは6~7倍とのことなので、エントリーシートはけっこうしっかり書かなくてはいけないかもです。
▼RAM参加メンバーにはこんな人も…
2018年度以降の運営体制は、東京藝大映像研究科の桂英史教授と高山明准教授がプロデューサーを、助教の和田信太郎さんがディレクターをつとめています。
メンバーは、映像、映画、パフォーマンス、詩、演劇、写真など様々な背景を持つアーティストを中心に、研究者やキュレーターなどが参加しています。
参加者や事務局スタッフなどで、これまで自分がご一緒させて頂いた方の名前の一部をあげさせていただくと、、
・青柳菜摘さん(アーティスト)
・佐藤朋子さん(アーティスト)
・潘逸舟さん(美術家)
・草野なつかさん(映像作家)
・岩根愛さん(写真家)
・三野新さん(写真家/舞台作家)
・カニエ・ナハさん(詩人)
・小宮麻吏奈さん(アーティスト)
・飯岡幸子さん(映像作家/撮影監督)
・トモトシさん(アーティスト)
・ジョイス・ラムさん(アーティスト/編集者)
・今福龍太さん(文化人類学者/批評家※シニアフェローという特別な立場で)
など、なかなか!な方々が参加されています。
▼RAMで行われるプログラムは?
プログラムの柱としては、
・アーティストやキュレーターによる「オープンレクチャー」
・フィールドワーク的に地域を訪ね、リサーチや即興的な作品制作を行う「フィールドサーヴェイ」。自分が参加したのは、台湾、奄美大島、仙台、三浦半島などでした。
・ビューイング;アート作品の展示をキュレーターの解説なども合わせて詳細に分析する「ビューイング」
・参加者の活動や進行中のプロジェクトをシェアして、発展の契機にする「リサーチラボ」
・展示や上映会など、成果発表展を行う「RAMプラクティス」。会場は、藝大の横浜中華街校舎や渋谷ユーロライブ、東京芸大附属図書館のギャラリーなどで開催されました。
・新進アーティストを中心とした、ゼミ的な有機的な学びと制作の場が7つ同時並行した年も。(これが実施された2019年度は、月に10回以上のプログラムがあるのでは?というとても濃い年でした)
また、事務局が企画するプログラム以外にも、
・参加者からの提案でプロジェクトを立てて実践することも可能
という枠組みでした。
映像研究科メディア映像専攻の大学院などとも連携しながら、様々な背景を持つアーティストや研究者の思考に触れ、コンテンポラリーアートの実践を体感できる貴重な機会になっています。
▼今年度のプログラムは?新規参加者の募集は?
毎年7月~翌年度3月までが活動のベースになることが多いのですが、その年によって、プログラムやスケジュールには(かなり)違いがあります。
大胆に柔軟に変わるプログラム、突発的に立ち上がるプロジェクトは、いい意味で大学が主催しているとは思えないほどの機動性があります。
基本的には、毎年、新しく「研修生(受講生)」を募集する方向なのですが、昨年度は、新規の募集がなく、2018年度以降の参加者をベースにした活動が行われていました。
今年度、8月下旬に募集を開始する!とのことだったのですが、、、、
現在のTOPページはティザーサイト状態です(2022年11月時点)
http://geidai-ram.jp/

過去の活動内容がわかるサイトはこちらです。(2022年11月時点ではTOPページからのリンクが外れているようです)
http://geidai-ram.jp/ram2018wp/

▼藝大の大学院で映像や現代アートを学ぶには
RAMと合わせて、よく聞かれるのが、東京藝大で、映像や現代アートに関する大学院はどこにあるのか?です。
自分のような”外部”の人間には、本当に分かりづらかったです(汗)。主に、本部のある上野キャンパス以外に点在しています。
・取手;
先端芸術表現科・先端芸術表現専攻(通称先端)
美術研究科・グローバルアートプラクティス専攻(通称GAP)
※GAPの授業は英語で行われ、海外の美術大学との共同カリキュラムも多いです。
・北千住;
国際芸術創造研究科・アートプロデュース専攻(通称GA)
※GAはキュレーターやアートプロデュースについての専攻。脳科学者の中野信子さんが博士課程後期にいらっしゃいますね!
・横浜(馬車道);
映像研究科・映画専攻
※ご存知、濱口竜介監督の母校ですね!
・横浜(元町中華街);
映像研究科・メディア映像専攻
※RAMの主催はこちら。映像、写真、演劇パフォーマンス、メディア・アートなどを中心に
・横浜(万国橋);
映像研究科・アニメーション専攻
東京藝大の大学院で、社会人が定時で働きながら学ぶのはなかなか厳しいものがあると思いますが、RAMは対象が社会人(主にアーティストや研究者)ですし、対応できる部分も多いと思います。
RAMのような長期の教育プログラム以外でも、各大学院でも、一般公開のトーク・上映会や、授業の特別公開など開かれた企画をやっていて、かなり濃厚で貴重なものも多いです。
興味がある方は、各専攻や教員の方のSNSなどをチェックしてみてくださいー。
#####
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
