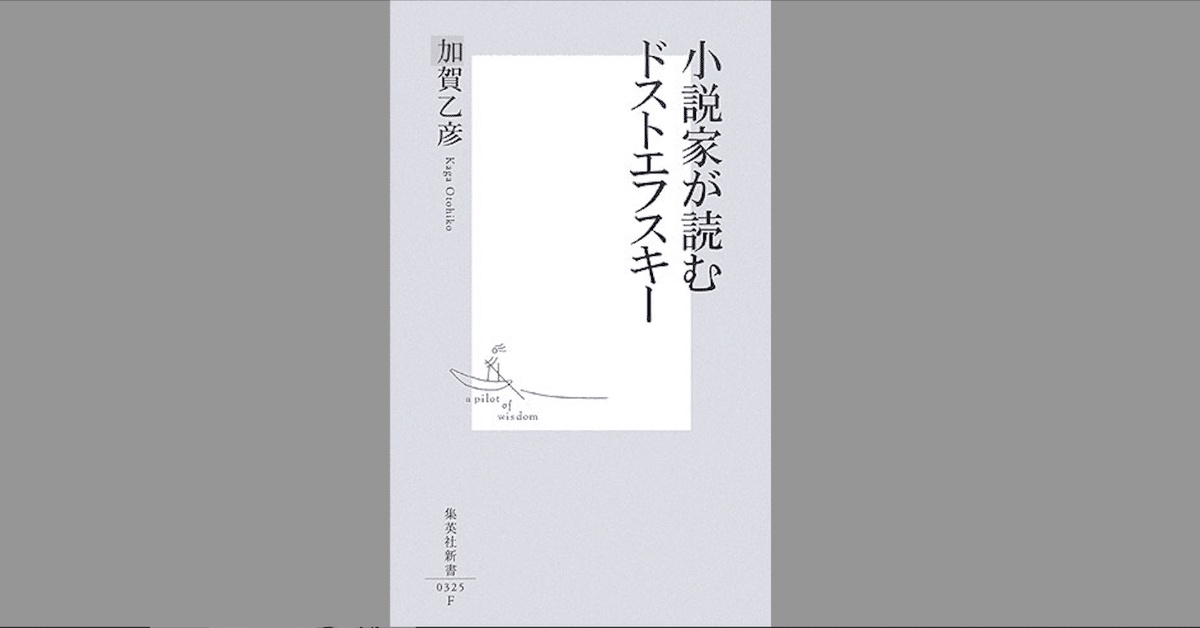
小説家が読むドストエフスキー
加賀乙彦の『宣告』
加賀乙彦の『宣告』という長編小説の舞台は、拘置所のなかでもゼロ番区と呼ばれる、死刑や無期懲役刑が確定した囚人ばかりが収容されている区画である。
法務大臣が死刑の執行を命じるまで死刑囚はそこで何年も待つことになるが、実際にその宣告が本人に伝えられるのは24時間前と決まっている。
死刑囚はたいていが処刑への恐怖から拘禁ノイローゼになり、看守の足音を聞くだけで「お迎え」を連想して極度の緊張状態に陥る。
主人公には眩暈で立てなくなる症状が出るが、夜な夜な床を転げまわって叫ぶ者もいれば、一心不乱に声を張りあげて読経する者もいる。
『宣告』ではそんな死刑囚たちの凄惨な生の実態が、拘置所の医官である精神科医の冷静な視線を交えて描かれる。
加賀自身が拘置所で勤務した経験があり、正田昭や若松善紀など実在の死刑囚がモデルになっているという。
とはいえ、加賀の『死刑囚の記録』という多くの死刑囚と面接した経験を書いた著書と較べると、『宣告』の世界が現実とは別物の虚構として打ち立てられていることが分かる。
「私たちの未来に確実におこる出来事は死だけである。とすれば、死刑囚と私たちとは、時間のあり方の本質においては同じだと考えられないか」と加賀は言う。
『宣告』はゼロ番区という限定された空間を描きつつも、私たちが住む外側の世界の本質を映し出す鏡ともなっており、加賀の文学的な動機に内側から強く支えられている。
『死の家の記録』
『宣告』を書くときに加賀乙彦の頭にあったのは、むろんドストエフスキーの『死の家の記録』であっただろう。
広く知られるように、ドストエフスキーはペトラシェフスキー事件で死刑を宣告され、刑の執行直前に恩赦によってシベリア流刑を言い渡された。
聖書一冊を懐中にオムスク要塞監獄に着き、そこで4年間徒刑囚として服役したが、その間に獄中で見聞したことが『死の家の記録』という凄まじい小説に結実した。
最初の構想では監獄の記録だけではなく、妻殺しの苦悩を抱えた男の物語になる予定であったが、いつしかその主題が脱落して監獄の記録とそこの住人たちに関する一連のスケッチだけが残った。
そのことが逆に効を奏したのか、ロシア・リアリズムの伝統に連なる緻密な観察に基づく作品として、当時のロシア文学者や批評家から高く評価されたという。
しかし、本書を「書き手の側からドストエフスキーを読み直す」試みとして書いた、加賀乙彦の見方はそれとは少し違っている。
『死の家の記録』は10年間監獄に入っていた人間の手記という設定だが、実際のドストエフスキーは4年間拘禁されて、その後の5年間はシベリアの小さな町で兵役を務めながら小説を書いていた。
つまり、自分の4年間の監獄体験をそのまま書いたのではなく、体験を最も力強く読者に伝えるにはどうしたらよいかを5年ほど考えながら虚構化して書き進めていった。
加賀がそこから導き出すのは「フィクションのほうが、本当のことを書いたよりも遥かに真実を伝える文学になる」という確信である。
また、『宣告』という小説の「閉ざされた場所の時間」の描出に苦悩した書き手ならではの視点にも独自性がある。
『死の家の記録』は監獄での10年を描いているが、よく読むと最初のひと月がすごく長く、最初の一年が過ぎるまでに小説全体の約5分の4の分量が使われている。
閉ざされた空間を描く工夫として、最初を濃密に書いて必要な人物を出しておき、後で物語が進む節目で人物たちを再登場させていかないと、読み手が長い時間の経過を実感できない、と加賀が指摘しているところが非常に興味深い。
ラザロの復活
病跡学的な見地から書かれた前著『ドストエフスキイ』との最大の違いは、本書が加賀乙彦のキリスト教受洗の後に書かれたという点であろう。
「キリスト教の知見からドストエフスキーを読み直す」という新たな観点が加わっているのである。
『死の家の記録』で主人公の大切な聖書を盗む人物が出てくるが、実際は盗まれずにドストエフスキーは監獄で聖書だけを読んでいた。
そんな人間が書いた『罪と罰』を、江川卓や小林秀雄のように信仰の観点を抜きにして読解するのはおかしいと加賀は言う。
では、ラスコーリニコフは犯行を告白する場面で、なぜ聖書のラザロの復活の部分をソーニャに読ませるのか。
「ヨハネ福音書」の十二章一節は腐って臭いを発していたラザロの死骸が生き返る場面である。
加賀の考えでは「死んだ人間が復活するなんて信じられない人は、キリスト教者にはなれない」のだから、死者の復活はキリスト教信仰のなかでは躓きの石である。
同時に、この部分はドストエフスキーが流刑中に何度も読んで涙を流した箇所であり、彼は『罪と罰』の核心部分でラザロの復活を延々と引用した。
ラザロの復活が人間の魂が一度死んで、また生き返ることの象徴としてあるからこそ、死刑執行の直前に許されたドストエフスキーにとっては感動的だったのであり、『宣告』の書き手がこだわる部分でもあるのだろう。
本書ではあまり触れられていないが、『死の家の記録』の大きな魅力の一つとして「ロシアの民衆」の生き生きとした姿が挙げられる。
これら囚人の一人一人が原型となり、後のラスコーリニコフやスタヴローギンに発展していったことは定説である。
だが一口にシベリアの監獄の住人といっても、その構成員はロシア貴族からチェチェン人、東欧系ユダヤ人、タタール人まで多種多様である。
死の家には酒が飲まれ、毒舌合戦があり、囚人芝居が催され、ユダヤ人が金貸しを営む濃縮した生の世界がある。
加賀がパスカルの言葉を借りて言うように「人間はすべて死刑囚であって神にいつ殺されるかわからない」のであれば、個の消滅まで限りある時間を十全に生きたいと願うのもまた私たち死刑囚であろう。
『宣告』が長尺を読ませるのは、登場する死刑囚が短く苦しくも充溢した生をいきているからで、それこそ加賀が他ならぬドストエフスキーから受け取ったものではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
