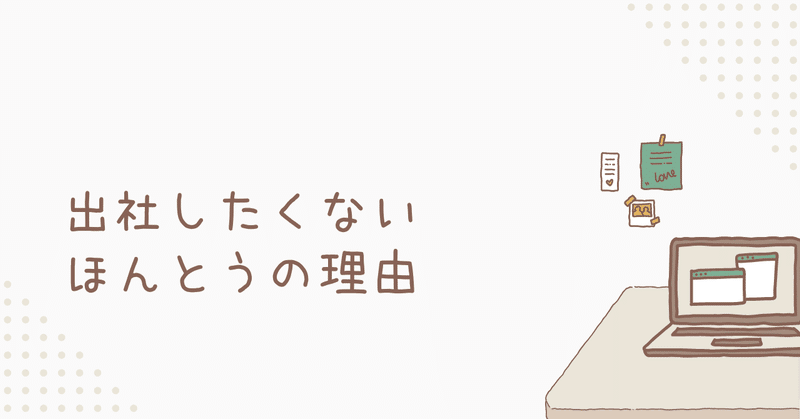
出社したくないほんとうの理由
はじめに
野村総研が今年2月に公表した「2022年の日米欧のテレワーク状況と将来展望」によれば、日本のテレワーク実施率は19.0%と調査対象8カ国中最低となっている。調査時期が2022年7〜8月なので、コロナがほぼ収束した現在では、この数字はさらに低下している(=出社率が上昇している)ものと思われる。いわゆる「オフィス回帰(リターン・トゥ・オフィス)」の動きが鮮明となっている。
コロナ禍においては「働きかたのニューノーマル(新常態)」ともてはやされ、コロナ収束後も定着するかと思われたリモートワークだが、コロナがほぼ収束してしまうとやはり元の木阿弥、なんやかんや言っても日本人は会社が好きなのかなあ。と思ったのでちょいと調べてみた。
日本人は仕事が(会社が)きらい?
6月14日付の日本経済新聞の記事によれば、従業員の仕事への熱意や会社への帰属意識などを示す指標である「ワーク・エンゲージメント」において、日本は世界最低のレベルなのだそうだ。
どうやら、日本人の多くは世界的に見てもかなりいやいや仕事しているということらしい。ワーク・エンゲージメントと生産性には正の相関があるとされており、エンゲージメントの低さが日本の生産性の低さ(OECD38カ国中27位)の理由のひとつとなっている可能性もある。
一方、ザイマックス不動産総合研究所はこのワーク・エンゲージメントとオフィスワーカーの働く場所との関係を調査している。これによればワーク・エンゲージメントの大きさは
ハイブリッドワーカー>完全テレワーカー>完全出社ワーカー
の順になっており、完全出社ワーカーがもっとも低いという結果となっている。
フルに会社で働く人ほどワーク・エンゲージメントは低いということだとすると、コロナが収束したから会社に戻れ、出社せよと会社が掛け声をかければかけるほど、社員の会社に対する熱意や愛着は低下し、生産性も下がるということなのだろうか。
そんな「楽しくないオフィス」をなんとかせんといかんということで、最近トレンドなのが「出社したくなるオフィス」だ。
出社したくないほんとうの理由
しかし、オフィスに行くとワーク・エンゲージメントが下がるというのは、そういう問題じゃないんじゃないの? エンゲーシーメントが下がる最大の理由は実は職場の人間関係なんじゃないかと思うんだよね。
チューリヒ生命が毎年実施している「ビジネスパーソンが抱えるストレスに関する調査」でも「上司との人間関係」「上司・部下以外の社内の人間関係」「同僚との人間関係」など社内の人間関係がストレスの原因の上位にランクインしている。これはオフィスのアメニティをどうこうしたぐらいで解決するような問題じゃないと思うんだよね。だって、オフィスに卓球台やらビリヤード台を置いたところで、嫌な上司(や部下や同僚)と卓球なんぞやれば、そりゃよけいストレス溜まりますがな。

で、こうした人間関係のストレスをもたらしているいちばんの要因は、日本企業では一般的な「メンバーシップ型雇用」にあるのではないかと私は考える。濱口桂一郎氏(2021)によれば、メンバーシップ型雇用とは、雇用契約上、職務や勤務地が特定されておらず、どんな仕事をするか・どんな職務に就くかは使用者の命令によって定まるような雇用形態を言う。濱口さんはそれを「日本の雇用契約は、その都度遂行すべき特定の職務が書き込まれる空白の石板である」と端的に表現している。
メンバーシップ型では「職務が個々の社員に特定されていない」。ではどうなっているかというと、課とか係とかグループといった「チーム」に包括的に(=ざっくりと)職務がアサインされているケースが多い(集団的職場編成)。
チームに職務が割り振られているということは、自分の仕事が片付いてもチームの他のメンバーの仕事が終わっていなければ自分だけさっさと帰るわけにいかず、他のメンバーの仕事を手伝ったりするためについつい長時間労働になる。有給休暇の取得率が低いのも同様で、「みんなが忙しい時に自分だけ休むわけにいかない」という心理が働くからだ。パワハラも同根だ。職務があいまいだと上司の指示もあいまいになり、責任の所在もあいまいになる。そのあいまいさがチーム内で立場が弱い者への批判や叱責、責任転嫁といったかたちで吹き出すという構図だ。
【参考】 佐藤健司(2021)「日本企業における人間関係:メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の視点から」
では、このようなメンバーシップ型雇用の中でテレワークをするとどうなるか。職務が特定されていないということは、チームの上司や部下との間での職務の分担や調整を状況に応じて頻繁に行う必要があるということだが、そのためには対面のコミュニケーションのほうがスムーズだ。だから日本では「会社より在宅のほうが仕事がはかどる」と考える人が他国より際立って少ないのだ。

さらに「近接性バイアス」という問題もある。近接性バイアス(proximity bias)とは、日常的に物理的な距離が近かったり直接対面で接する時間が長かったりするほど、その相手を優遇して好意的な関係を持ちたいと思う心理的傾向のことだ。よく時代劇に出てくる「ういやつじゃ、ちこうよれ(愛い奴じゃ、近う寄れ」」というセリフがあるが、逆もまたしかりでやっぱり「近う寄る」奴は「愛い奴」なのだ。いやあ、これは「あるある」でしょう。だから、上司に気に入られる(あるいは上司に嫌われない)ためには在宅じゃなくて出社したほうがいい、ということになるわけだ。
同質集団における「対面コミュニケーション」の意味
というようなことを言うと「いやいや欧米企業だって、ましてやGAFAMのようなテック企業だって、コロナ後は出社しろと社員に言ってるじゃないか」という反論が出てくる。たしかに以下のような報道もある。
米IT(情報技術)大手ではアップルやアマゾン・ドット・コムもコロナが収束した後に週3日出勤を原則とする方針を打ち出した。企業がオフィス回帰を進めるなか、現状維持を望む働き手との綱引きも激しくなっている。米プルデンシャル・ファイナンシャルの3月の調査でも在宅勤務者の42%がテレワークを継続できなければ転職すると答えた。
ここでおもしろいのは上記引用の後半「企業と働き手が出社をめぐって綱引き」というくだりだ。他にも「攻防」「せめぎ合い」みたいな表現でも報道されているが、欧米では企業が「出社しろ」と言っても「はい、わかりました」と簡単に言うことをきくわけではないようで、この点は日本とはえらい違いだ(このあたりもジョブ型とメンバーシップ型という雇用形態の違いに起因しているのだろうが)。
まあ、それはさておき、たしかに、対面コミュニケーションの重要性として「イノベーションに不可欠な偶発的な議論」とか「社内でふと出会った仲間との情報交換」といったセレンディピティの重要性を主張する向きは多いし、私も一般論としてはそれを否定するものではない。しかし、それは日本企業においてもあてはまるのか、と言えばそれははなはだ疑問だと思っている。というのは、日本企業の多くはそもそも社員の同質性が極めて高いからだ。
日本はほぼ単一民族・単一言語の国家である。しかも、日本の企業社会はいまだに男性中心の社会であり、外国人の雇用もまだまだ進んでいない。崩れつつあるとはいえ終身雇用制もいまだに根強く残っているため転職者も少なく、入社以来「同じ釜の飯」を食ってきた仲間たちが職場の大半を占めている。そして、相も変わらず「新卒一括採用」が主流で、しかも依然として特定の大学卒業者を中心に採用する「学歴フィルター」も大手企業ほど健在である。さらに言えば、そうした有名大学への入学者に占める地方出身者の比率も低下している。つまり、日本の企業は依然として、似たような環境で育ち、似たようなレベルの大学を卒業した、主として日本人の男性が、入社以来ずっと同じ会社で働いているという、極めて同質的な集団であり、その多様性は極めて低いと言わざるをえない。
このような同質性の高い集団におけるコミュニケーションは、ともすれば似たような意見が集団内を飛び交うため結果として偏った考え方が増長される「エコー・チェンバー(共鳴室)現象」に陥る可能性が高い 。つまり、同質的な集団の中ではそもそもセレンディピティ(異質なものとの偶然の出会い)は起こりにくいので、対面コミュニケーションが必ずしもクリエイティビティを高める方向に働くとは限らないということだ。
そう言えば、ふた昔ほど前、オフィスのタバコ部屋(喫煙スペース)が、他部署の人との偶然の出会いや何気ない会話を通じた情報交換の場となっているという話があったが、これは裏を返せばタバコ部屋ぐらいしかセレンディップな社内横断的コミュニケーションの場がなかったということでもあるわけで。
それに、考えてみれば、対面コミュニケーションがクリエイティビティの源泉なのだとしたら、コロナ以前から社員同士が同じオフィスで(あるいは昼飯も夜の飲み会も土日のゴルフも含めて)長時間顔を突き合わせている日本企業はもっとイノベーティブであってもおかしくないはずじゃないか。結局のところ、日本企業における対面コミュニケーションというのは、近接性バイアスを強化しているだけなんじゃないかという気がしなくもなく。
なお、対面コミュニケーションとイノベーションの関係については、当の米国でもThe New York Timesからこんなミもフタもない論考が出ているので一応ご参考まで。
ということで、リモートワーク(あるいは出社と在宅のハイブリッドワーク)
はジョブ型雇用とは相性が良さそうだが、メンバーシップ型雇用との相性については問題なきにしもあらずの感がある。日本企業でもコロナを契機にジョブ型雇用に切り替える企業も出てきているようだが、メンバーシップ型の雇用スタイルは維持したままで、働き方だけをハイブリッドワークにするとそれはそれでまた別の問題が出てくるような気がしてならない。
□□□□□□
最後までお読みいただきありがとうございます。もしよろしければnoteの「スキ」(ハートのボタン)を押してもらえると、今後の励みになります!。noteのアカウントがなくても押せますので、よろしくお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

