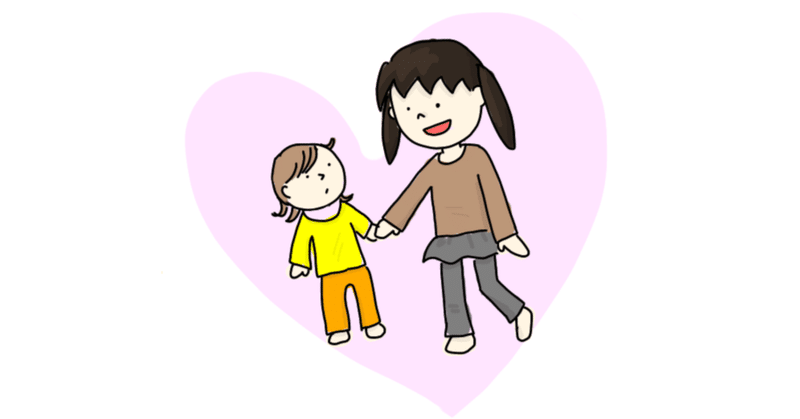
里親に親権がないことの不都合
【 自己紹介 】
プロフィールページはこちら
このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、600日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。
法律に関する記事は既にたくさん書いていますので、興味のある方は、こちらにテーマ別で整理していますので、興味のあるテーマを選んでご覧ください。
【 今日のトピック:里親の親権 】
昨日のブログの続きです(昨日のブログのリンクは一番下にあります↓)。
さて、昨日は、里親には親権がないことについて説明しました。
児童相談所では、虐待を受けたりした子どもの処遇について、施設入所だったり里親委託だったりを日々決めています。
施設入所や里親委託は、「措置」という行政処分として行われています。
こういった「措置」がとられると、子どもは、実際に施設や里親宅で暮らすようになるので、身の回りの世話(法的には「監護」と呼ばれます)は、施設職員や里親が行うことになります。
「親権」には、「監護」と「財産管理」の2つの側面があって、普通は、この2つを両方持っているのですが、この2つが分かれる場合があります。
その場合、「財産管理」の権限を持っている人が「親権者(法定代理人)」となります。
もう一方は、「財産管理」ができないので、「法定代理人」に該当しません。
「法定代理人」とは、代理人になれることが「法定」されている(=「法律上書かれている」)、という意味です。親権者が「法定代理人」である理由は、親権者が、子どもの代理人として契約などを結べることが民法に書かれているからです。
そして、「子どもの代理人として契約を結べる」は、財産管理権のほうに含まれます。
だから、監護権と財産管理権が分かれた場合に、法定代理人たる親権者というのは、財産管理権を持っているほう、ということになるのです。
これを里親について考えると、里親委託された場合、里親に監護権、実親に財産管理権が分かれることになります。
だから、実親が法定代理人たる親権者、ということになり、里親は監護権者なのです。
これがどういった困りごとになるかというと、例えば、子どもがアパートを借りる場合です。
来年(2022年)以降は、民法上の成人年齢が18歳に引き下げられるので、高校を卒業して大学入学に合わせてアパートを借りる場合には、未成年ではなくなっているので、親権者の同意がなくても、アパートの賃貸借契約を結ぶことができます(未成年だと、親権者の同意がない契約は後から白紙にされる危険があるので、契約相手は親権者の同意を求めるのですが、成人であれば、親権者が後から取り消すこともありませんし、もちろん、本人が取り消すこともできません)。
しかし、中卒で一人暮らしを始める場合は、そうはいきません。
中卒だと、本人はまだ15歳です。成人年齢が引き下げられた後も、15歳は未成年なので、アパートの賃貸借契約を結ぶ場合は、親権者の同意がないと、契約させてくれません。
里親さんも、子どもが自分の人生を自分で決めて、中卒で一人暮らしをしようとしているのなら、それを応援してあげたいでしょう。
しかし、アパートを借りる際に必要な親権者の同意を、里親は果たすことができません。
本当に残念なのですが、里親さんは、アパート賃貸借契約に同意することができません。この同意は、親権者に頼まなければなりません。
里親から親権者に連絡をとってもいいですし、子ども本人から親権者に連絡をとってもいいです。
ただ、里親や子どもとの連絡が途絶えている親権者もいます。その場合、どうすればいいのでしょうか。
それまでずっと連絡が途絶えていたのに、いざ親権者の協力が必要となったときに非協力的な態度をとられても困りますが、残念ながら、非協力的であったとしても、原則として、親権者の意向に従う必要があります。
中卒で一人暮らしさせるのを認めたくないと親権者が考えるのであれば、それに従うことになります。
ただ、親権者が子ども意向に反対する理由が、「子どもを困らせたい」などという、不当なものであれば、親権停止などの手続きによって、親権者から親権を一時的に奪うことも可能でしょう。
しかし、そんな不当な理由を親権者が明言することはまずありませんよね(笑)。
・中卒で一人暮らしするよりも、普通に高校に行って勉強したほうがいい
・その後大学に行ってせめて大卒の資格はあったほうがいい
という理由であれば、それをむげに否定することはできません。したがって、こういう、不当ではない理由で親権者が子どもの意向に反対する場合は、親権者の意向に従わざるを得ません。
長年にわたって里親に委託しておきながら、親権者の同意が必要な場面になった途端に子どもの意向に反対するなんて、「毒親だ!」とか「ひどい!」と思うかもしれませんが、長年にわたって里親に委託することのは悪いことではありません。
里親へ子どもを委託することは、完全に合法です。
しかも、里親委託は、親権者の同意なく実施することもできますが、基本的に親権者の事前同意を得ます。
つまり、親権者が里親委託に同意し、それによって里親委託が開始されることも完全に合法で、それが長期化したからといって、里親委託が違法となることもありません。
正直にいえば、里親委託によって親権者と分離された子どもには、非常に大きな悪影響が及ぼされるので、僕としては、堂々と「悪い!」と言いたいのですが、とはいえ、里親委託は間違いなく合法です。
・里親委託は合法
・里親委託が長期化するのも合法
・親権者の協力が必要な場面で親権者は子どもの意向に反対することも可能
「はあ・・・」といった感じなんですが、これが法律上決まっています。
しかし、親権者と連絡がつかないと、話が変わってきます。というのも、調査を尽くしても親権者の所在が判明せず、行方不明である場合、いつまでもアパートが借りられません。
親権者が子どもの意向に反対しているなら、諦めるほかありませんが、親権者の行方が不明の場合は、諦めることすらできず、宙ぶらりんになってしまいます。
この場合は、児童相談所長が親権者となります。
だから、児童相談所長が、親権者として、賃貸借契約に同意することができます。
児童相談所も、いつまでも親権者でいるわけではなく、子どもに未成年後見人が選任されるまでの暫定的な親権者です。
本来、親権者が行方不明の場合、未成年後見人が選任され、未成年後見人が親権者の代わりに、身の回りの世話(=監護)と、財産管理(契約の同意)をすることになります。
しかし、未成年後見人の選任には家庭裁判所での手続きが必要で、正式選任までに時間がかかるので、その間、親権者に空白が生じないよう、暫定的に親権者を誰か決めておく必要があって、そのために、児童福祉法が暫定的な親権者として、児童相談所長が指定されています。
ここからわかるのは、里親委託したって「親は親だ」、ということです。
確かに、身の回りの世話は、親以外でも可能ですが、自分を分娩した女性は誰なのか、誰の精子から自分が出来上がっているのか、という自分のルーツを知りたい気持ちはとても素朴なものであって、親は、この素朴な欲求に応える責任があります。
だって、子どもを作ったのですから。ひとりの命をこの世に生み出したのであれば、その子どもが自分のルーツを知るための責任を果たすのは、当然というほかありません。
親の存在を、「身の回りの世話をしてあげる」「衣食住を与えてあげる」というだけだと思っている親は、残念ながら「クソ」です。
親の価値(存在意義)は、そんなんじゃありません。
子どもにとって、親はかけがえがなくって、里親委託したところで、子どもに対する責任は消えない、という思想が、↑に書いた児童福祉法の条文には現れていると思います。
本来、子どもにとって、親とのアタッチメント形成は、その子の一生を左右するほどの重大な営みなので、子どもに合わせた形で、毎日それなりの時間を養育に割く必要があり、これが、幼少期にとって最も大切な親の役割です。
しかし、その役割が何らかの事情によって果たせなかったとしても、せめて、子どものルーツを知る欲求に応えてあげたり、実親として関係をキープしたりするのは、親として大切な義務です。
ひとりの命を生み出すことの重大さ、それに伴う親の責任というのを、毎日感じています。
それではまた明日!・・・↓
*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*
TwitterとFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。
昨日のブログはこちら↓
僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。
━━━━━━━━━━━━
※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。
毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。
サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!
