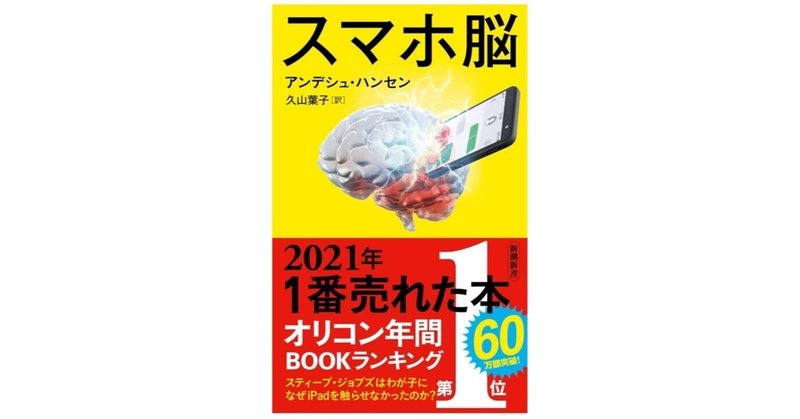
スマホ脳
「こんな方にオススメ」
・スマホやインターネットの利用時間を減らしたい人
・自分の脳の健康に関心がある人
・デジタルデトックスに興味がある人
スマホ脳の恐怖に打ち勝つ。
世界中で200万部突破のベストセラーが、ついに日本上陸!
教育大国スウェーデンを震撼させたスマホ脳の恐怖に、あなたはどう立ち向かうのか?
脳科学に基づいた、スマホとの健全な付き合い方を徹底解説。
本書は、スマホ脳の罠から抜け出し、真の幸福を手にするためのヒントが満載です。
①フェイスブック元CEO

できるだけ長い時間その人の注目を引いておくにはどうすればいい?
人間の心理の弱いところを突けばいいんだ。
ちょっとばかりドーパミンを注射してあげるんだよ。
②ドーパミンの役割

ドーパミンの最も重要な役割は私たちを元気にすることではなく、何に集中するかを選択させることだ。
たとえば、空腹時に食べ物を見ているだけでドーパミンの量が増える。
つまり、増えているのは食べている最中ではない。
食べて満足感を与えるのは「モルヒネ」である。
そして、スマホもドーパミンを増やす。
それが、チャットの通知が届くとスマホを見たい衝動にかられる理由である。
③マルチタスクの代償

人間はマルチタスクは苦手である。
マルチタスクとは、テレビを見ながらスマホを触るなど。
中にはスーパーマルチタスカーがいるが、人口の1~2%だと考えられている。
複数の作業を同時にやっているつもりで、実際にはこの作業からあの作業へと飛び回っているだけなら、確かに脳は効率よく働かない。
研究者はこんな結論を出した。
マルチタスクを頻繁にやる人は、集中力も作業記憶も低下する。
つまり、「脳が最適な状態では働らかなくなる」
④SNSを使うほど孤独に

なぜ孤独に落ち込むのだろうか。
それは、皆がどれほど幸せかという情報を大量に浴びせかけられて、自分は損をしている、孤独な人間だと感じてしまうからだ。
SNSが幸福感に与える影響を分析するとき、ヒエラルキーの中でのその人の位置は重要な要因だ。
他人と競争して負ける、特に地位が下がると、セロトニンが低下し、人は不安になり心の健康を損なう。
私が子供の頃は、自分を比べる相手はクラスメートくらいだった。
今の子供は、クラスメートがアップする写真に連続砲撃を受けるだけでない。
インスタグラマーが完璧に修正してアップした画像も見せられる。
そのせいで、「良い人生とはこうあるべきだ」という基準が手の届かない位置に設定されてしまい、その結果、自分は最下層にいると感じるようになる。
⑤SNSは使い方次第

SNSに時間を費やすからといって、全員の精神状態が悪くなるわけではない。
精神状態が「悪くなるような使い方」もある。
他人の写真を見るだけで、自分は写真をアップしないし議論にも参加しない消極的なユーザーは、積極的なユーザーよりも精神状態が悪くなりやすいそうだ。
SNSを社交生活をさらに引き立てる手段、友人や知人と連絡を保つための手段として利用している人の多くは、良い影響を受けることができる。
⑥子供のスマホ依存

子供にスマホを触らせる場合、
1日2時間を超えるスクリーンタイムはうつのリスクを高めている。
1日7時間以上使用する人はスクリーンタイムが短い人と比べると、うつと不安の症状が倍も多くみられることが分かった。
『まとめ』

スマホ中毒になる理由は、ドーパミンが分泌されることで、新しい情報が見たくなりスマホが手放せなくなる。
そして、マルチタスク(ながらスマホ)状態が続き、その結果集中力や記憶力の低下につながる。
SNSで鬱になる理由は、自分とその他大勢のインフルエンサーとの比較で自分が最下層にいると思ってしまうことで、セロトニンが低下し気分が沈む。
その点にもっと配慮すれば、私たちはより健康に、健全に生きられるはずだ。
最後までお読みいただきありがとうございました。 サポートも嬉しいですが「スキ」ボタンもとても励みになります!
