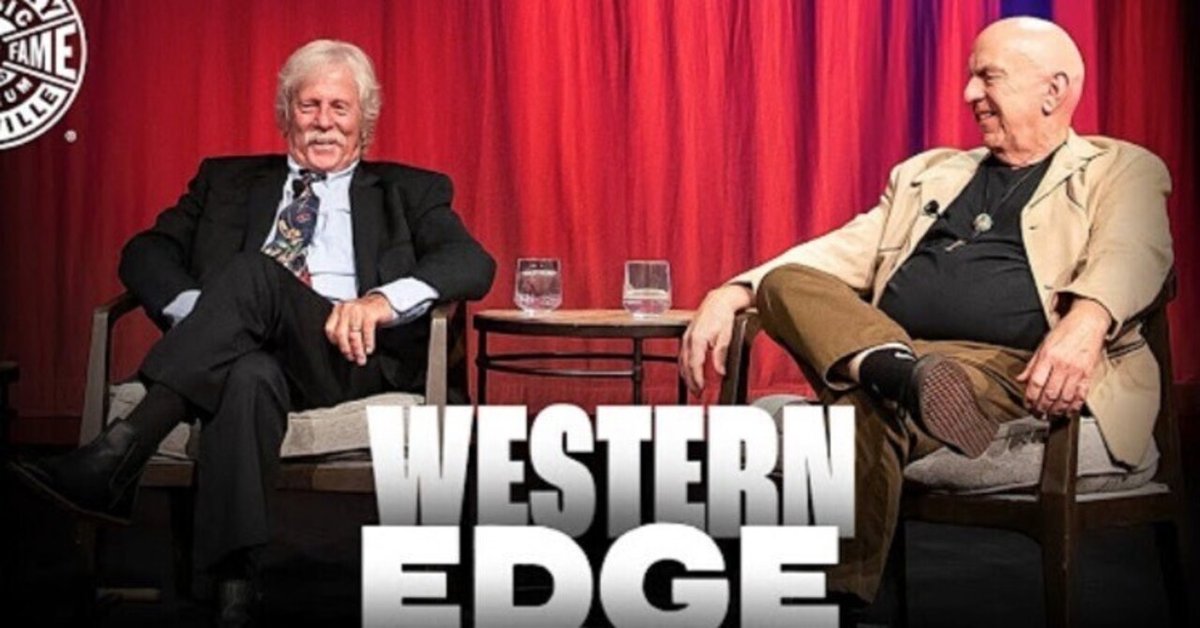
バーニー・レドン×クリス・ヒルマン:最新の対談動画で知ったいくつかのエピソード
先日、note仲間の音楽の杜さんが、フライング・ブリトー・ブラザーズのサードアルバムとディラード&クラークのファーストアルバムを相次いで紹介されていた。すると、まるでそれにタイミングを合わせたかのように、ある興味深い対談動画がカントリーミュージック名誉殿堂博物館のサイトにアップされた。フライング・ブリトー・ブラザーズでバンドメイトだったクリス・ヒルマンとバーニー・レドンの最近の対談だ。ご存じのように、クリス・ヒルマンはバーズのオリジナルメンバー、そして、バーニー・レドンはイーグルスのオリジナルメンバーだが、バーニーはブリトーズの前にはディラード&クラークに在籍していた。このようにLAのフォークロック〜カントリーロック萌芽期に共に重要な役割を果たしたふたりだが、彼らが互いに10代の頃からの旧知の中であることは、案外知られていない事実かもしれない。その辺りの話も含め、今回の記事では、この対談で披露されていた興味深いエピソードをいくつか紹介してみよう。
カントリーミュージック名誉殿堂博物館(Country Music Hall of Fame and Museum)は、その名の通り、カントリー音楽の歴史を今に伝える博物館だ。テネシー州ナッシュビルにあるこの博物館については以前の記事でも触れたことがあるが、現在、ここでは、60年代後半から70年代初頭にかけてのロサンゼルスのカントリーロックを取り上げた企画展「Western Edge: The Roots and Reverberations of Los Angeles Country-Rock」が開催されている(2025年5月まで)。同館では日頃からさまざまなショーやイベントが行われているが、今回ウェブサイトにアップされたこの対談は、開催中の企画展に沿ったイベントとして2023年10月14日に行われたものだ。

今回の対談で語られたことの多くは、2020年に出版されたクリス・ヒルマンの自伝『Time Between — My Life As A Byrd, Burrito Brother, And Beyond』でも触れられていた。この自伝については以前に連載形式で取り上げたので(下記)、今回は、どちらかと言えばバーニー・レドン主体で、私が初めてディテールを知ったエピソードや、二人の印象的な言葉などを紹介していこう。
フェスティバル・エクスプレス・ツアー
対談のステージは、司会者(博物館の出版物担当ディレクター)による二人の紹介の後、ヒルマンとレドンが共演していた時代の映像を流すところから始まる。1970年の夏に行われた「フェスティバル・エクスプレス」ツアーにフライング・ブリトー・ブラザーズが参加・出演したときの映像だ。曲はグラム・パーソンズ作の「Lazy Days」だが、グラムはこの年の初めに素行の悪さから解雇されており、バーニー・レドンがリードヴォーカルをとっている(この時点ではリック・ロバーツはまだ加入していない)
このツアーは、チャーター列車でカナダの東海岸から西海岸まで移動しながら、同国の複数都市を巡るという企画。その様子はフィルムクルーによって撮影されていたが、ツアーを企画した会社が倒産するなどしたため、フィルムは行方不明になっていた。それが、2000年代になって見つかり、リストアされて2003年に同名の映画になった。今回会場で流された映像もその映画からのものだ。ツアーに参加したのは、ブリトーズのほか、ジャニス・ジョプリン、グレイトフルデッド、ザ・バンド、バディ・ガイ、イアン&シルヴィア、デラニー&ボニーといった面々。ちょうどデッドがアコースティック志向のアルバム『Workingman's Dead』を発表した頃で、時代がサイケデリックなロックからルーツ志向のロックへと移る過渡期の記録として非常に興味深い内容だった。
ツアーの参加者についてふたりはうる覚えだったが、バーニーは「映画の中で一番好きなシーンは、運行途中の列車が酒屋に立ち寄るために停車し、出演者たちがみんなで酒瓶を列車に運び込むところ」と言って、聴衆を笑わせていた。
二人の出会い:スコッツヴィル・スクワレル・バーカーズ
対談では、司会者がまず二人の出会いについて尋ねる。それは、1963年サンディエゴでの話だ。当時高校を卒業してまなしのクリスはLAでアルバイト生活を送っていたが、生まれ育ったサンディエゴの旧友ゲイリー・カーとケニー・ワーツに誘われて、彼らが結成したばかりのブルーグラスバンド「スコッツヴィル・スクワレル・バーカーズ」にマンドリンで参加する。この経緯については、前述の私の記事でも簡単に紹介したが、当時高校生だったバーニーはこのバンドの徒弟のような存在で、クリスがバンドに参加する前から、他のメンバーたちと親しくしていたようだ。

左端のマンドリンがクリス・ヒルマン。その横のバンジョーがケニー・ワーツ、中央のドブロがラリー・マーレイ。今回の対談でバーニーは、主にMC担当のラリーはほとんどドブロは弾いていなかったと言って聴衆を笑わせていた。
バンドは、メンバーのラリー・マーレイが経営していた「ブルーギター」というギターショップの店内演奏から始まったもので、バーニーはその店に足繁く通う常連だった。バンジョー弾きだった彼は、バンドのバンジョー奏者ケニー・ワーツから多くを学んだという。半年ほどの活動の後、ケニーそして、ヴォーカルとギターのゲイリー・カーが徴兵に取られることになり、バーニーがケニーの後釜に収まるが、その後すぐにレドン一家がフロリダ州ゲインズヴィルに引っ越すことになり、グループは消滅してしまう。ちなみに、ケニー・ワーツは70年代初めに、フィドルのバイロン・バーラインらとプログレシッブなブルーグラスバンド、カントリーガゼットを結成。ガゼットは、当時、フライング・ブリトー・ブラザーズのツアーに同行して彼らと共演しており、ブリトーズの公式ライブアルバムにもその様子が収められている。ヒルマンが今回の対談で「スクワレル・バーカーズが源泉だった」と語っているように、60年代後半〜70年初頭のLAカントリーロック・コネクションの中でこのブルーグラス・グループの人脈が果たした役割は極めて大きい。
ふたりが楽器を始めた理由
次に司会者は、ふたりが楽器を始めた理由について尋ねている。まずは、バーニーの回答を引用してみよう。
レドン:
キングストン・トリオだ。デイヴ・ガードはカッコ良かったね。60年代の初め、彼らはビートルズみたいなもんだった。あんなふうになりたかったんだ。デイヴ・ガードが持っていたようなピート・シーガー風のネックの長いバンジョーに憧れていた人は何人もいたよ。それで始めたんだけど、15歳くらいの時かな。親父がフーテナニーに行かせてくれたんだ。地元のカトリック教会でのフートだったから、安全だってことでね。そこに、まだクリスが参加する前の4人編成のスクワレル・バーカーズが出てたんだ。すごく良かったよ。ラリーはすごく面白かったし。ジミー・マーティンの曲なんかをやっててね。それで、「一緒に遊んでもらえませんか」って感じで声を掛けたんだ。高校に行くバスの定期券で「ブルーギター」にも行けるってことがわかったんで、それから2年間はブルーギターに通ったんだ。高校の卒業証明書をもらったのは、後になってからだ(笑)
Transcription and translation by Lonesome Cowboy (以下同)
一方、クリス・ヒルマンは、マンドリンを始めた理由についてこう答えている。
ヒルマン:
ニュー・ロスト・シティ・ランブラーズを聞いたんだ。まだブルーグラスを聞く前で、オールドタイムなんかのストリングバンドの音楽を聞いてたんだ。マイク・シーガー(ピート・シーガーの異母兄弟)がギブソンのF5マンドリンを弾いていてね。「うわぁ、何だこれ?」と思ったね。すごく良かったんだ。それで、変なマンドリンを見つけてきて一生懸命練習した。それから、ビル・モンローのレコードを聞くようになった。当時はみんなレコードを聞いて練習してたよ。YouTubeなんていいものがなかったからね。回転数を落として、どんな音か拾おうとしてたんだ。
バーニーがカリフォルニアに戻った経緯
対談はヒルマンがブルーグラス・グループ「ザ・ゴールデンステート・ボーイズ」に参加したエピソードから、ザ・バーズ結成にいたる話へと展開する。その内容については前掲の記事で取り上げたものとほぼ同様なのでここでは割愛するが、面白かったのは、その頃フロリダにいたバーニーがバーズのレコードを初めて見たときの反応だ。
レドン:
突然ラジオから「タンバリンマン」が流れてきた。その次は「ターン、ターン、ターン」だ。それから(暫くして)レコード店にアルバムを見に行ったんだ。驚いたね。「ヒルマンじゃないか!」「くそっ!こんなとこにいてられねえぜ!」ってね。
バーニーがカリフォルニアに戻った経緯についてはこれまであまり詳しく知らなかったが、今回、彼は次のように説明している。
レドン:
ラリー・マーレイから手紙が来たんだ。「今、ハーツ&フラワーズというグループでキャピトル・レコードと契約してるんだ」ってね。ドラマーやベースがいないフォークポップトリオで、オリジナルメンバーのリック・クーナが脱けたんで、その後釜に入って、キャピトルからの2枚目を出すのを手伝ってくれないかって。「おいおい、キャピトルだって。(当時のキャピトルと言えば)、ビートルズ、キングストントリオ、ビーチボーイズ… 行く、行くっ!」って感じさ。
それで、カリフォルニアに行って、しばらくはラリーの家に居候してた。最初の週にキャピトルタワーに行って、プロデューサーのニック・ヴェネットに会ったんだ。ビーチ・ボーイズをキャピトルと契約させた人だよ。フランク・ザッパとも仕事してたし、当時は全てが共同体みたいなもんだった。彼がプロデュースしたり、契約してた人の中には、リンダ・ロンシュタットもいた。
数週間ほどのうちにレコードを作り始めた。それからヴェネットが他のレコーディングにも僕を使い始めるようになったんだ。ストーン・ポニーズとかね。そこからどんどん転がっていった。幸い、キャピトルと契約しているバンドの新メンバーってことで何処の馬の骨かわからない新人みたいに思われなかったから、受け入れられたんだ。一緒に仕事をした人たちの中には、ダートバンドもいたよ。68年だったかな。[この会場には、元ダートバンドのジョン・マキュエンもいた]


ハーツ&フラワーズは、メンバーのラリー・マーレイ自身が「マール・ハガード・ミーツ・サージェントペッパー」と称していたように、元々はカントリーの要素もあるバンドだったらしい。しかし、出来上がったレコードは、時にインド風メロディが顔を出すような、サイケデリック・フォークロックといった趣きで、フラワームーヴメント華やかし頃にLAで「作られた」時代の音を象徴していた。
プロデューサーのニック・ヴェネットは、ストーン・ポニーズの最大のヒット「Different Drum」(哀しきロックビート)も生んだ人だが、この曲も元々はもっとラグタイム調のゆったりした曲だったという。ハープシコードも持ち込んだヴェネットのアレンジに、ヴォーカルのリンダ・ロンシュタットはかなり閉口したという。(この時代のLA産コマーシャル・フォークロックには、ビーチ・ボーイズの『ペットサウンズ』の影響か、ハープシコードの音が結構目立つように思える)。バーニー・レドンはこの完成版の「Different Drum」にもギターで参加している)
このように、ハーツ&フラワーズのアルバム自体は、時代の空気感を感じる以外、特筆すべき作品とは言えないが、このグループのメンバーたちがその後のLAのカントリーロックシーンの礎になったことは無視できない。スコッツヴィル・スクワレル・バーカーズ出身のラレー・マーレイは、バーズがラストアルバムで取り上げた「Bugler」やリタ・クーリッジやスワンプウォーターが取り上げた「Mama Lou」などの佳曲を残しているし、自身唯一のソロアルバム『Sweet Country Suite』(1971年)もカントリーロックの好盤だ。また、オリジナルメンバーのリック・クーナは、エミルー・ハリスのデビュー作にバーニー・レドンとともにギターで参加しているほか、ジェニファー・ウォーンズが80年に中ヒットさせた「When The Feeling Comes Around」の作者でもある。ちなみに、ラレー・マーレイは、今回の博物館の展示でキュレーター役を務めたという。

左:ファースト『Now Is the Time for Hearts and Flowers』(1967年)
右:セカンド『Of Horses, Kids and Forgotten Women』(1968年)
セカンドの右端に立っているのが若き日のバーニー・レドン。
ディラード&クラーク結成にいたるエピソード
ハーツ&フラワーズ解散後、バーニーは、元バーズのジーン・クラークと元ディラーズのバンジョー奏者・ダグ・ディラードが結成した「ディラード&クラーク」に参加する。その当時、バーニーはダグ・ディラードの家に居候していたようだ。そのこと自体の経緯については今回特に語られなかったが、バンジョー奏者として優れた実績を残していたダグ・ディラードのもとに弟子入りした感じたったのだろう。ディラード&クラークのファースト『The Fantastic Expedition of Dillard & Clark』(1968年)では、後にイーグルスのファーストにも収められる「Train Leaves Here This Morning」のほか、多くの曲でバーニーが作者としてクレジットされているが、その経緯についてバーニーは次のように語っている。
レドン:
ダグと一緒にバンジョーのインストゥルメンタルを書いてたんだ。そこにジーンが来てハーモニカを吹いたりしてたんだけど、多作家のジーンは、次の日にはインストゥルメンタル2曲分の歌詞を持ってきた。その次の日にはまた2曲。そうしてブリッジを加えたりして、そんな感じで僕が作者としてクレジットされたんだ。(トム)ペティもそんな感じ(の多作家)だったよ。夕方のリハーサルから次の朝までに素晴らしい曲を3曲も書いてくるんだ。ディラード&クラークのファーストアルバムの曲は、全て2週間で出来たものなんだ。

ジーン・クラークの作詞能力については、クリス・ヒルマンが興味深い話をしていた。
ヒルマン:
何年か前に、デイヴィッド・クロスビーに聞いたことがあるんだ。「ジーンがフィクションの本を読んでるのを見たことがあるか?」って。「いや、お前は?」って言うから、「僕もないよ」って言ったんだけど。ジーンには優れた英文学の先生がいたんじゃないかって思うね。彼の作る詞は、本当に詩的で素晴らしいんだ。どこからか湧いてきたたように作るんだ。ボブ・ディランも、当初大いに賞賛していたよ。
これについて、バーニーがこう補足した。
レドン:
彼は動詞を最後に持ってくるんだ。言ってみれば、百年以上前にやっていたような古いやり方なんだ。いかしてるよね。
フライング・ブリトー・ブラザーズの演奏とカントリーロックの萌芽期
カントリーロックの歴史を語る際、クリス・ヒルマンがグラム・パーソンズをバーズのセッションに誘い、そこからエポックメイキングなアルバム『Sweetheart of the Rodeo』(ロデオの恋人)が生まれたこと。さらに、その後、フライング・ブリトー・ブラザーズの結成に至ったことは外せない話だ。その経緯については、今回語られたことと、ヒルマンの自伝に基づいて私が以前の記事で紹介したこととの間に大差はなかったが、自伝では触れられていなかったことでヒルマンが今回語ったことがひとつある。
それは、グラムがバーズとの初セッションで、バック・オウェンスの「Under Your Spell Again」を歌い、それを聞いて、クリスが自分と同じ仲間だと感じたという話。クリスもグラムも、バック・オウェンスやマール・ハガードなどのベイカーズフィールド・カントリーに対する共通項があることは周知の事実だが、このセッションで演奏された具体的曲名が出てきたことはなかなか興味深い。
バーニーがブリトーズに参加した最初のアルバムは、セカンド『Burrito Deluxe』(1970年)だ。このアルバムカバーは、メキシコ料理のブリトーにラメを施したような変な写真だが、アルバムカバーのフォトセッションに出向いたバーニーは、グラム・パーソンズが放射線防護服とビニールの手袋とブーツを持ってきたことに面食らったという(その写真は、表面には小さく、裏面に大きく使われている)。ベトナム戦争期の時代を象徴したエピソードとも言えるが、バーニーいわく、「ああいうのは、自分がバンドリーダーでないと、その時までわからないことだね」と言い、クリスは「止めさせておけば良かったことのひとつだ」と言って、会場の笑いを誘っていた。

グラム在籍時のブリトーズがライブバンドとして今ひとつだったことは、クリスの自伝からも今回の対談からも伺い知れる。なにしろ、グラムは、遅刻はするわ、酔ってステージに上がるはと、惨憺たる状況だったのだ。今回、クリスは次のように語っている。
ヒルマン:
今でもはっきり覚えているけど、当時J.D.サウザーと組んでいたグレン(・フライ)がトゥルバドールに僕ら(ブリトーズ)の演奏を見に来てたんだ。僕らのダラけた演奏を見て、グレンがどう考えていたかは分かっていたよ。「これは悪い見本、こんなふうにはやらないでおこう」ってね。その点、イーグルスは素晴らしかった。実にプロフェッショナルだったね。
ブリトーズの演奏については、バーニーもこんな話をしていた。
レドン:
マイケル・クラーク(のドラム)は前のめりで急ぎぎみだったんだ。だから、僕とクリスは、お互いマイケルの方を向いて、ギターネックをこんなふうに(上下に)動かして『ゆっくり、ゆっくり、曲のグルーブはこうだぞ』ってやってたんだ。
ブリトーズの演奏について自嘲気味だったヒルマンに対して、司会者が、軌道修正を図るようなうまい振りをしていた。一連の会話を再現してみよう。
司会者:
もうひとつ重要なポイントですけど、グレンは「やってはいけないこと」を見つけるためだけにあなたたちを見てたわけじゃなく、カントリーロックの側面にも注目してたわけですよね?
ヒルマン:
まあ、そういった作品に傾倒はしていたね。グレンとJ.D.のロングブランチ・ペニーホゥィッスルは。
レドン:
ブリトーズとかポコとか、カントリーロックのそういったいいバンドがいなかったら、イーグルスは生まれなかった。僕らだけじゃなくて、リック・ネルソンとか、ここに展示されてる人たちみんながそうだろ。あと、もうひとつは曲だ。僕らは自分達でも曲の作り方を覚えたけど、ジャクソン・ブラウンやJ.D.やジャック・テンプチンといった、外部のソングライターもいた。ファーストアルバムのために7人もソングライターがいたってことさ。[実際には、ファーストアルバムにはJ.D.の曲は収められてはいない]
話の流れで、クリスがこう続けた。
ヒルマン:
僕は、バンドとしてはポコが一番だとずっと思ってたよ。すごくタイトだったんだ。バーニーもそうだろ?
レドン:
特に初期の頃は、そうだね。
ヒルマン:
(ポコの)選曲に関しては必ずしも賛同しなかったけど。カントリーというより、僕にはちょっとポップすぎたからね。でも、演奏はとてもタイトでまとまってた。その点、僕ら(ブリトーズ)はだらしなかったよ。クスリばかりやってたしね。
司会者:
ハーモニーの点でも、ポコは素晴らしかったですね。その点はイーグルスも学んだんじゃないですか? カントリーロックの側面はブリトーズだけど、ポコのハーモニーは素晴らしかった。
レドン:
ポコはとてもエネルギッシュだったね。
ヒルマン:
あと、一番肝心なのは、曲だ。
レドン:
そうだね。曲が良くないと。
[中略]
レドン:
もうひとつ言うと、実は音楽だけでもないんだ。僕がLAで学んだことなんだけど、ヒットを飛ばして成功した周辺の人に聞いてみたんだ。「どうやった? どうしたらいい?」って。僕には分からなかったからね。それで分かったんだけど、必要なのは、いいレコード会社、いいマネージャー、いいプロモーターとマーケティング、それとうまくタイミングを掴むこと。そして、シラフで朝10時には仕事につけること。パーティーばっかりとかそんなんじゃない。プロとして完璧にビジネスに仕上げなきゃだめなんだ。
司会者:
その話の流れで言うと、あなたがデイヴィッド・ゲッフィンに「僕らと契約する気があるのか」みたいに迫ったんですよね。
レドン:
ああ、確かにそうだ。僕の嫌な面が出たね(笑)。[中略] ゲッフィンとどうやって繋がったかと言うとね。グレンとJ.D.のデュオはゲッフィンのマネジメント会社と契約してたんだけど、ゲッフィンはJ.D.だけを残してグレンを切ろうとしていたんだ。グレンは、ゲッフィンに興味を持ってもらおうと必死だった。それで、ドン・ヘンリー、ランディ・マイズナーと僕を集めたんだ。それで、ゲッフィンのところに行って「みんなで来たぜ」って。そうしたら、デイヴィッドが気に入ってくれたんだ(笑)それで契約してくれて、アトランティックが資金を出した自分のレーベルに入れてくれた。僕らは「アトランティックに入れてくれ」って頼んだんだけど、結果的には良かったよ。[中略]

イーグルス結成時のエピソード
「イーグルスは、リンダ・ロンシュタットのバックバンドから独立した」とよく言われるが、オリジナルメンバー4人が同時期にリンダのバックで演奏していたことは殆どない。71年当時、リンダのバックバンドの中核をなしていたのは、テキサス出身のスワンピーなカントリーロックバンド「シャイロ」のメンバーたちで、そのドラマーがドン・ヘンリーだった。

このバンドには、後に後期フライング・ブリトー・ブラザーズ〜マナサス〜サウザー・ヒルマン・フューレイ・バンドのメンバーとなるアル・パーキンス(steel)や、後にイーグルスの作品でピアノやアレンジで活躍し、カントリー系のプロデューサーからワーナーブラザーズ・ナッシュビルの社長となるジム・エド・ノーマン(key)も在籍していた。アルバムのプロデューサーは、同郷の先輩格だったケニー・ロジャース。
このシャイロと同じエイモスレコードのレーベルメイトだったロングブランチ・ペニーホゥィッスルのグレン・フライがそこに加わったような形が、リンダのバックバンドを構成していた。そんな中で自分たちのバンド結成を思い立ったドンとグレンに、リンダがバーニーを推薦したという話も聞いたことがあるが、今回のバーニーの話は少しニュアンスが異なる。
司会者:
リンダがあなたたち(イーグルスのメンバー)を一緒にしたんですよね?
レドン:
いや、他のメンバーたちは同じ時期に一緒にやり始めたと思うんだけど、僕はその時はクリスとやっていた。それで、ブリートーズを辞めたときにマッケーヴギターショップに行ったんだけど、そこの顔見知りの女性店員が「ドンとグレンが一緒にバンドを始めたらしいわよ。連絡してみたら」って言うんで、(彼らの)マネージャーだったジョン・ボイランに電話したんだ。ボイランがお金を出してくれてスタジオでリハーサルするって言うんで、リハーサルに行ったら、曲がとても良かった。それで、一緒にやりたいと思ったんだ。
確かに、71年に発表されたリンダのセルフタイトルのサードアルバムのクレジットを見ても、バーニーがグレンやドンと共演している曲は1曲もない。ランディ・マイズナーとの共演は1曲だけあるが、バーニーが入っている曲はハーブ・ペダースンとの共演が多い。
イーグルスは、デビューに際してイギリス人プロデューサーのグリン・ジョンズにプロデュースを任せているが、その経緯についてバーニーは次のように説明していた。
レドン:
さっき言ったように、チームとして最高の人たちを集めることが大切だろ。レコード会社とマネジメントはゲッフィンと契約できたから、今度はプロデューサーなんだけど、グレン・フライがグリン・ジョンズにプロデュースしてほしがったんだ。ストーンズとかツッペリンとかのロックをプロデュースしていたジョンズは、グレンの憧れだったからね。それで、グリンがコロラドまで僕らを見に来た。そしたら、彼は「辞めとくよ」って。「君らはみんなやってることがバラバラだ。レドンはカントリーの方を向いてるし、フライはロックの方を向いているし、リズムセクションはその間で板挟みになってるし」って。彼に聞いたら、そう説明してくれたよ。
それで、もう1回勉強して出直していいですかって言って、再度リハーサルを見てもらったんだけど、やっぱり「やらない」って。そこで、ランチに行こうってことになったんだけど、その時、僕らの中の誰かが言ったんだ。「今ハーモニーを付けたばっかりの曲があるんで、それを聞いてもらえませんか?」って。それで「Fair and Tender Lady」だったか何かのトラディショナルな曲をアコースティクギターと4声のハーモニーだけで演ったのを聞かせたんだ。そしたら、ジョンズは、「ああ、君らはヴォーカルバンドかぁ」って。それで彼は、ヴォーカルブレンドを中心に据えて制作したんだ。でも、いまだに彼は言ってるよ。「君らはロックンロールバンドじゃないね。僕は本物のロックンロールバンドを知ってるけど、君らとは違う」って。
そう言えば、ブートレッグなどで初期イーグルスのライブを聞くと、コンサートのオープニングにアカペラで「Fair and Tender Ladies」を歌い、それに続けて「Take It Easy」を演奏することがよくある。定番になっていたようだ。グリン・ジョンズによって悟らされたのかわからないが、当時はメンバーたちも自分達のウリはハーモニーだと認識していたのだろう。そして、この辺りのハーモニーには、彼ら(特にバーニー)のブルーグラス・ルーツが多分に感じられる。(ちなみに、ジャクソン・ブラウンも、初期のライブでは「Fair and Tender Ladies」と「Take It Easy」、そして「Our Lady of the Well」をメドレーにすることが多かった)
演奏者としてプロフェショナルに徹する姿勢
今回の対談でふたりが共に強調していたことがふたつある。ひとつは、曲の良さが大事ということ。特にバーニーは、メロディがないがしろにされている最近の状況に苦言を呈していた。そして、もうひとつ二人から共通して感じられたのは、プレイヤー(演奏者)としてプロに徹する姿勢だ。これについてバーニーは、イーグルスを始めたときのエピソードとしてこんな話をしていた。
レドン:
イーグルスを始めた時、僕らが決めたことのひとつは、プロフェッショナルであろうということだ。なぜかって言うと、バーズもそうだけど、当時のLAのグループの多くは元々フォークシンガーだったからね。幸運にも僕の場合、フロリダにいた時にトップ40のヒット曲を演るバンドで学生パーティなんかでも演奏してた。だから、エレクトリックギターのリズムパートなんかもこなせるようになった。リズムセクションのいるバンドでの経験があったんだ。
僕らが言ってたことのひとつは「最小公倍数」つまり「低俗な大衆嗜好」ってことだ。だから、僕らは、メンバーの誰かひとりがインフルに罹って、二人がお互いに喋らなかったら最高のショーができるってところまでリハーサルしたんだ(笑)。具体的にどのショーってわけじゃないけどね。それでうまくいったよ。重要なのは、僕らはもっとうまく出来たかもしれないけど、本当に最低だったわけじゃないってことなんだ。とにかく、プロフェッショナルを目指したんだ。
また、ヒルマンが、みんなが知っている話として、バーズのデビューシングル「Mr. Tambourine Man」とそのB面の演奏は、そのほとんどを通称「レッキングクルー」と呼ばれていた当時のLAの一流セッションマンたちが務めた話を紹介すると、バーニーは真面目な顔でこう言っていた。
レドン:
レッキグクルーはみんなのレコードで演奏していた素晴らしい人たちだけど、彼ら(バーズ)は最初のシングル以外、全部自分達で演奏していた。それが重要なんだ。
ヒルマンも、前述の通り、グラム・パーソンズのプロ意識のなさに辟易していた。フロリダの大農園の御曹司だったグラムには何もしなくても多額の資産があり、音楽という仕事と真剣に向き合う姿勢が欠如していたからだ。彼からは、こんな言葉も聞かれた。
ヒルマン:
僕とバーニーに共通しているのは、ふたりともロックスターになりたいなんて一度も思ったことがなかったということなんだ。僕らは、ふたりとも演奏者であり、バンドプレイヤーだった。いろんな意味で、それが僕らの救いになった。音楽を学んで、それを演奏する。それが全てだ。リムジンに乗りたいとか、そんなことじゃないんだ。
これに対して、バーニーはこう応えていた。
レドン:
そう、自分がスターだなんて、思わないこと。ただのギター奏者だってことだよ。
クリス・ヒルマンとバーニー・レドンは、ともにアメリカのロックの歴史を作ってきた偉大なバンドのメンバーだったにも関わらず、どちらかと言えば、それらのバンドの中では目立たない存在だった。ふたりとも、必ずしも世間一般に広く認知されているわけではない。グレン・フライやドン・ヘンリー、あるいはグラム・パーソンズやスティーヴン・スティルスといった、いわばスター性のある人たちの影で「脇役」に徹してきた人たちだ。しかし、こんなふうに純粋に音楽が好きで、それに向き合う人たちがいたからこそ、彼らが所属していたバンドが歴史に残るグループになったと思えるし、そういう彼らのミュージシャンシップにこそ、強く惹かれる。
最後に、そんな彼らのミュージシャンシップを示す好例として、クリスとバーニーが80年代初頭に組んでいたアコースティック・カルテットの映像リンクを張っておこう。ドブロはアル・パーキンス、ベースはエルヴィス・プレスリー・バンドのベーシストだったジェリー・シェフだ。
今回の対談の全編は、下記でご覧になれます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
