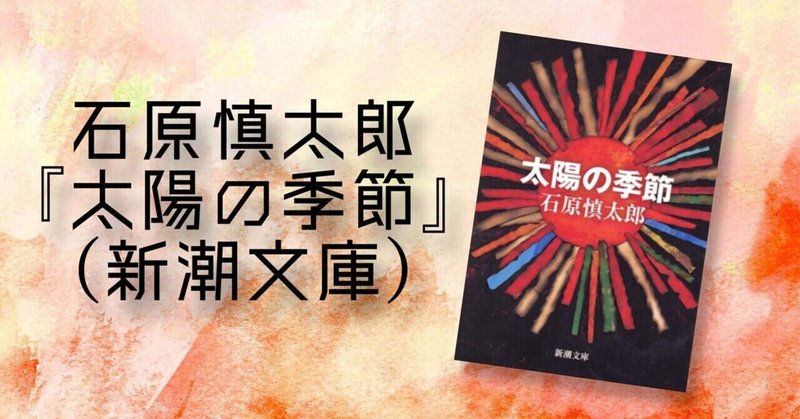
闘争としての恋愛の極北―石原慎太郎「太陽の季節」
女とは肉体の歓び以外のものではない。友とは取引の相手でしかない・・・退屈で窮屈な既成の価値や倫理にのびやかに反逆し、若き戦後世代の肉体と性を真正面から描いた「太陽の季節」。当時、最年少で芥川賞を受賞したデビュー作は戦後社会に新鮮な衝撃を与えた。
新潮文庫の裏表紙の紹介文はこのように評している。1955年、石原慎太郎が一橋大学在学中に執筆した本作は、新世代の若者のメルクマールとして迎えられた。奔放な戦後青年像は当時の選評も二分し、「攻撃的」「快楽主義的」な表層的な印象から「太陽族」という流行語も生まれた。
竜哉が強く英子に魅かれたのは、彼が拳闘に魅かれる気持と同じようなものがあった。
という有名な書き出しから物語は始まる。結論から一言で言えばここで描かれるのは、恋愛に形を借りたファム・ファタール(宿敵)=英子との闘争だ。恋はそのまま拳闘に重ねられ、それは効果的に作中に持ち込まれる。
主人公・竜哉は人を素直に愛することができない。どこかスカしていて、自分は他の奴とは違う、という自意識を持っている。事実、家も立派で腕っぷしも立つし器用。間違いなく女にモテてしまうタイプである。その主人公だからタチが悪いのだ。こいつは愛の言葉、優しい言葉ではなく、何かにつけ英子を試したり、嫉妬させたりすることで、裏返し的に相手の慕情を掻き立て、愛情を触知しようとする。英子も英子で、その誘いに乗ってしまう悪女的な側面を持つ。手ひどく精神をすり減らしながら、竜哉を盲目的に信じることで竜哉の悪辣な面をエスカレートさせている。
そうした救いようのない恋愛譚(?)のなかで、核となるのは、裏表紙にもあった「物質」という概念だと思う。この物語は、よりマクロに捉えるなら、新しい価値観としての「物質」への傾倒とも言えるものが、無惨にも敗れてゆく過程を描いているのではないか。
行為の内で自分を掴むと言うことは、それが抵抗される時に於いてこそ明確になるのではないか。少なくとも竜哉にはそう感じられる。それ故彼は精一杯やれるのだ。
これは竜哉がハマる二つのもの、拳闘と恋愛の双方にピッタリと当てはまるように書かれている。
この年頃の彼等にあっては、人間の持つ総ての感情は物質化してしまうのだ。最も大切な恋ですらがそうではなかったか。大体彼等の内で恋などという言葉は、常に戯画的な意味合いでしか使われたことがない。この言葉は多少くすぐったく、馬鹿々々しい余韻しか持ち得なかった。
明晰な分析だと思う。恋のイメージは現代に通じるものがある。登場する人物は、関係を取り結ぶ時、必ず物質を介在させているのは印象的だった。(後述)自らの衝動や思いをものに仮託すれば、率直さが失われるのは必定だ。
冒頭、拳闘を始めるまでのシーンでサンドバックを叩くところがある。ここでもそうした物質感、もっと言えば「抵抗」感が何気に描かれている。
思いきりサンドバックを叩いてみた。それは思ったより固く手応えがあった。彼はぞくっと身震いを感じる。
竜哉は恋愛にもこの「抵抗」の概念を導入してしまう。ここが「太陽の季節」が一部から嫌悪された点かと考えられる。それは、実際、英子をサンドバックとするものに近い。どこまで時代錯誤なんだ、という感じだが、仕方ない。愛する人を物質とみなし、自らの感情をも物質を通す。(兄に五千円で英子を売る、という衝撃の下衆さを見せる一幕もある!)極め付けは実際、63頁から英子は「玩具」に例えられていることだ。竜哉は「自分の好きな玩具を壊れるまで叩かなければ気のすまぬ子供」と表現され、彼の狼藉を語りが断罪し始めるのもこの辺りに顕著だ。
そして、というかまあそうだろうなと思ううちに、英子は壊れてしまう。壊されてしまう。そして、壊れることによって竜哉に復讐を果たしたのだ、と書いてある。これは裏を返さずとも、竜哉の物質的恋愛観の終着点であり、端的に言えば敗北である。
物語の終わり、パンチングバックの背後に竜哉は幻覚を見る。そして彼は「夢中でそれを殴りつけた」とある。ここは決定的な描写だ。物質とそれによる快楽で構成された幼児的小宇宙であった彼の世界は、英子が失われたことによって、非物質=幻覚の侵入する余地を生んだのである。本当の竜哉の物語はここから始まると言えるかもしれない。
この終盤をもって全体を振り返るならば、表層を撫でた「太陽族」の誤謬は明らかなものに思える。石原は戦後世代の新たな価値を提出しただけでなく、むしろその限界をも暗示していた。新世代の若者像と、その敗北/破滅を描いた石原の文体は、55年という現在から隔たったように見える戦後間も無くから、連綿として読めるほど鮮やかで古びない。
