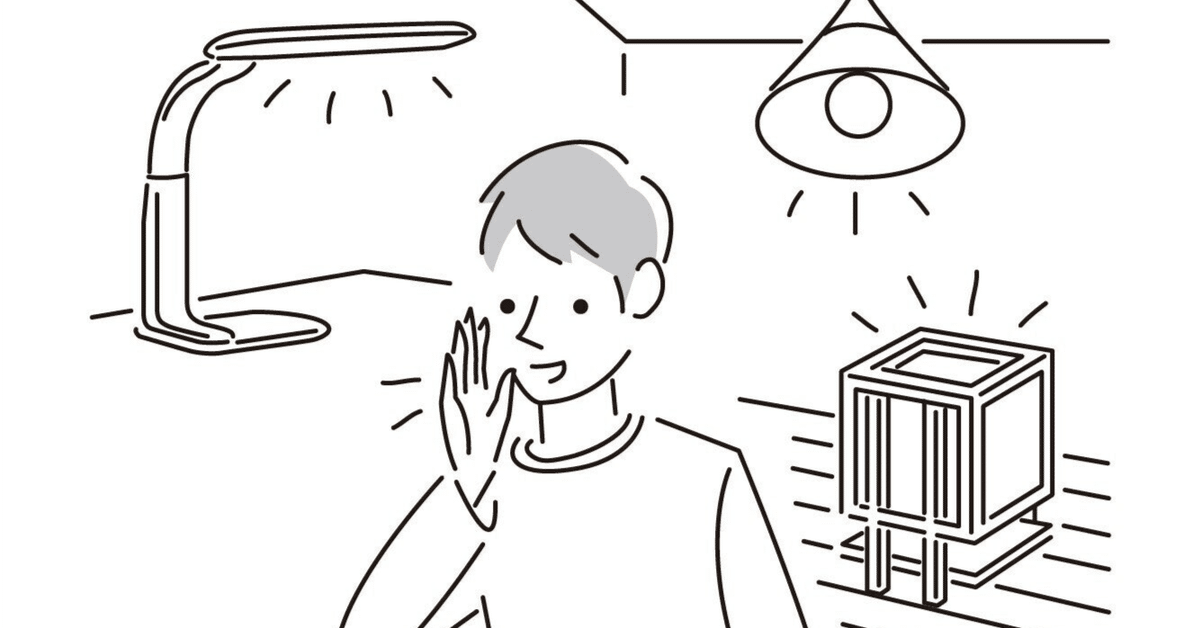
ボクのライフワーク 第3話
その晩、父親が帰ってきたので、この話をした。
「でね、5億は、とうさん、かあさんが好きに使って。残りはボクの分でいいでしょ。」
「そりゃ、サトシが稼いだお金だもんな。おとうさんたちは、サトシに感謝しないといけないな。」
「ありがとう、サトシ。」
「でも、黙っておいてね。」
「そりゃそうだろ。これがばれたら、大変なことになるもんな。」
「だけど、どんなパソコンなんだ?」
「それは内緒。」
「そっか。」
「だけど、これだけあれば、もっとゆったり生活できるよね。」
「そうだな、サトシのおかげだ。本当に感謝だな。」
「多分、使い切れないと思うけど、必要に応じて運用できるから。」
「わかった。ありがとうな。」
まあ、これでボクの親孝行は大半完了だ。
ボクにはあまり友達はいない。まあ、陰キャだからね。でも、ひとりだけ親しいヤツがいる。山本クンだ。実は彼もパソコンが好きだ。まあ、ボクほどではないけどね。でも、ボクの好きと、彼の好きは系統が違う。彼はハードではなく、ソフトが好きなんだ。それもゲームだ。何がそんなに面白いんだろうって思うよ。全然、ワクワクしない。
「山本クンは、ゲームばっかりだよな。」
「まあ、これほど面白いものはないよ。」
「ハード、いじくっている方が面白いよ。」
「いや、そこはオレの楽しみじゃないな。」
「そうか。何が面白いのかな?」
「じゃ、一度、ゲーム作ってくんない?」
「ゲームか。考えておくよ。」
ゲームだと、それなりのグラホがいるよな。トムのマシンなら、完璧なんだけどな。
「トム、高性能なグラホを作りたいんだけど、なんかアイディアくんない?」
「ありますよ。」
「どんな?」
「それは・・・」
ボクはトムのアイディアを紙に書いた。なるほど、じゃ作ってみるかな。ということで、おじさんの店に足を運んだ。
「おじさん、こんな部品ある?」
ボクは紙を見せた。
「お、いいねぇ。これはグラホを自作するのかな。」
「わかる?」
「ははは、ちょっと待っとけよ。」
奥に引っ込んで、しばらくすると、部品を持って現れた。
「これで作れんじゃないかな、はいよ。」
「おお、ちゃんとあるんだ。」
「いつも買っていってくれるから、2千円にまけとくわ。」
「ありがとう。」
ボクは、グラホ製作に足らない部品を手に家に帰った。トムに教わったように、グラホを改造した。一度、自分のパソコンに設置してみた。ボクはそんなにゲームはしないので、これの良さがわからない。とにかく、画像が普通に動いている程度にしか、見えない。
翌日、ボクはグラホを持って、学校へ行った。
「山本くん、スペシャルなグラホを製作したぞ。一度、使ってみてよ。」
「えっ、そうなの?楽しみだなあ。今晩、使ってみるよ。」
その晩、電話がかかってきた。
「あれ、すげーよ。」
「よかったな。」
「すげーなんてものじゃないぜ。」
「でも、ボク、ゲームしないから、よくわからんもん。」
「自分で作っといて、わからんとは淋しいやっちゃな。」
「まあ、楽しんでくれ。」
「ありがとうな。」
まあ、いずれにせよ、よかった。山本クンが楽しんでもらったら、OKだ。だが、このグラホとてつもない能力を持っていた。ボク自身、あまりグラホには興味がなかった。まあ、映ればいいかと思っていたくらいだったからね。
ボクは、学生だから、一応は勉強していたけれど、どうしても分からないところは、トムに聞いた。まあ、問題ないでしょう。そんなこんなで、大学へ行く必要性を感じていなかったが、両親の進めでもあったので、進学することにした。当然、費用は自分持ちだし、理系だ。
ボクは学費が安くなる国立に合格した。すべては、トムのおかげだったけどね。入ってしまえば、なんとかなると思っていた。ボクはコンピュータのハード・ソフトの勉強をあえて選んだ。自分が好きでやってきたことが、そのまま勉強になる。つまり、すべて理解しているし、分からないことはトムに聞くから、大学の授業は楽勝だった。あとは、学生生活をエンジョイするだけだ。大学へは家から通学できる。そんなに遠くない。理系だけあって、女子はほとんどいない。それがちょっと寂しいかな。まあ、そのうちできるだろ・・・と思う。
「ねえ、大学卒業したら、院に行ってもいい?」
「好きなようにしたらいいよ。」
だよな、両親は夫婦で、世界一周に出掛けるらしい。ボクに感謝していた。
「まあ、楽しんでいってらっしゃい。」
「サトシ、ありがとうね。」
半年は帰ってこない。いい気なもんだ。ということで、半年間、ボクはこの家の留守番をすることになった。その間にいろいろ製作して楽しんじゃおう。IoTってわかるだろうか。家の中のすべてのものにコンピュータ制御できる機器を取り付けたら、あとはトムが全部自動でやってくれるのだ。ボクはトムの言う通りに、いろんなところに、いろんなものを取り付けた。家中の電気はトムが全部制御してくれる。
冷蔵庫の中身は腐らせないように、栄養のバランスをとって、どんなものをつくるのか、教えてくれる。掃除は、掃除機を改造して、勝手に掃除してくれるようになった。カーテンの開け閉めもトムがしてくれるし、雨戸もだ。室内の空気清浄も、温度設定もトムがやってくれる。外の鍵の戸締りも完璧だ。家の内外のカメラもばっちりになった。怪しい人もしっかり映る。両親が帰ってきたら、びっくりするだろうな。一応、スマホからも操作できるようにしておいた。我が家は、ものすごくハイテクになった。
大学では、単位取得に悩むこともない。そのまま、院にいくことになった。そのあとの仕事はどうするか。研究と称して、大学に居残るのでもいいかと思っている。トムさえいれば、何もしなくてもいいけど、もし、そのトムがいなくなった場合を考えて、自分がちゃんと生活できるようにしておかなくちゃと思った。とは言え、院で勉強することなど、すでにトムに聞いて知っていることばかりだ。だから、これ以上、勉強することもないのだが、まあ、復習がてらやっているという感じだ。
「なあ、トム。」
「何ですか?」
「うちの両親のスマホと、いつでも接続できるようにしてくれないか?」
「簡単です、ついでに電源も空気充電できるようにしておきます。」
「ああ、頼むよ。」
これで、圏外なんてことはなくなる。どこにいるかもわかるし、ついでに健康状態も送信してもらった。これで、うちの両親が世界一周のどこにいて、健康状態もわかるようになった。
「トム、もしかして、回線業者なんかなしで、電話したり、ネット検索とか自由にできるんじゃないの?」
「サトシ、今頃何言ってるんですか?」
こいつは、たまに癇に障る。まあ、いいや。
「じゃ、両親のスマホもそうしといてくれる?」
「もう、してありますよ。」
「さよか。」
少々ムカつくけど、することはちゃんとしておいてくれるので、信頼できるのだ。両親は現在、大西洋を航行中みたいだ。健康状態も良好だから、楽しんでるんだろうな。
院に進学してから、ボクのいる研究室に、女の子が一人入ってきた。他の大学から、受験して入ってきたとのことだった。結構、機械いじりが好きらしい。半田も平気で扱う。プリント基板の扱いも慣れたもんだ。女の人では、なかなかいない。彼女は加藤早苗さんという。
「竹内クン、同じ研究なんでよろしくね。」
「よろしく。」
同じ研究室でも、3つの研究チームに分かれている。ボクのチームは彼女とふたりだけだ。あとのチームは3人で組んでいる。
「私、関西の大学から来たところなので、勝手がようわからんし、教えてな。」
「わかった。その都度、質問してくれたらいいよ。」
「ありがとぉ~、おおきに。」
なんか、関西弁が新鮮だ。3つのチームのうち、ボクのチームが一番高度なことをやっている。でも、トムに教わって、大半できているんだ。だから、一人で十分なんだけどな。
「この製作、大変ですよね。」
「ええまあ、そうですね。」
「どんなふうにやってみるんですか?」
「ある程度、仮定しているんで、問題ないかと。」
「どんな仮定なんですか?」
おっ、目が輝いている。これ、好きなんだな、この人。ボクは設計図面を見せた。加藤さんは、もう夢中みたいだ。電卓を叩きながら、ノートに計算式を書きながら、う~んとうなりながら、考え込んでいた。しばらくすると、ようやく納得したのか、こっちをみて、こう言った。
「すごいです。これが本当に可能なら、画期的です。」
「いけそうでしょ。」
「はい。あ、私に作らせて下さい。お願いします。」
「わかりました。私は確認しますね。」
「お願いします。」
だが、これにはトムから聞いていたことで、設計図面には起こしていないことがあるのだ。まあ、それが一番のキモなのだ。だから、加藤さんが製作するものとは別に、ボクが製作するものを用意しておいた。当然、加藤さんのでは、思った通りの動きはしない。それはわかっているんだ。
「あれ?なんでやろ?なんで、思った通りに動かへんのやろ?」
「うまくいかないの?」
「せやねん。あかんねん。原因がようわからへんねん。」
関西弁のオンパレードだ。ボクは少し笑ってしまった。
「何よ。何がおかしいん?」
「いや、その関西弁のオンパレードがおかしくって。」
「なんや、そっちのほうか。」
「これ、どう思う?」
「ん~、一応設計通りやね。」
「せやろ、間違ってないやろ?」
「だけど、肝心の魔法がかかってないみたいだね。」
「魔法?それなんや?」
「まあいいや、今日はこれまでにしょう。」
「あかんで、はよ教えてや。」
「自分で考えることも大切でしょ?」
「ん~、いけず。」
「まあ、いいでしょ。お腹減ってない?ご飯いこうか?」
「わかったわ。行く。」
ボクは、大学のときから行きつけのラーメン屋に行った。
「こんなとこに、ラーメン屋、あるんやな。」
「結構、おいしいよ。」
「そうなん、なら、ここでええわ。」
加藤さんは自分のことをずっとしゃべっていた。前の大学では、自分より賢い学生はいなくて、おもしろくなかったから、こっちの大学院へあえて受験したとのこと。すると自分と同じレベルの学生がいると聞いて、闘争心を燃やしていたらしい。それって、ボクのことなんだろうな。でも、あの設計図面を見て、理解できるということは、かなりのレベルだよな。
「だからな、こういう話を対等にできる人と知り合いになりたかってん。」
「ボク程度でいいんですか?」
「あんな設計図、書ける学生、おらへんよ。」
「そうかな。」
「あんた、結構すごいで。」
「ありがとう。」
大学院は大学と違って、交友関係は限られる。本当に研究室の中だけに限定されてしまうことがほとんどだ。普段は加藤さんと、研究室の大橋教授と前田助教の4人くらいとしか、話をすることはない。今の研究があんまり早く終わってしまわないように、加藤さんには当分四苦八苦しといてもらうのだ。
「なんで、うまいこといかんのやろ?あんたの言ってた魔法って何なん?」
「さあ、なんでしょうね。」
「ほんま、いけずやな。」
「がんばって、解いてみてね。」
「悔しいわ。絶対、やってやるさかい、みときぃや。」
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
