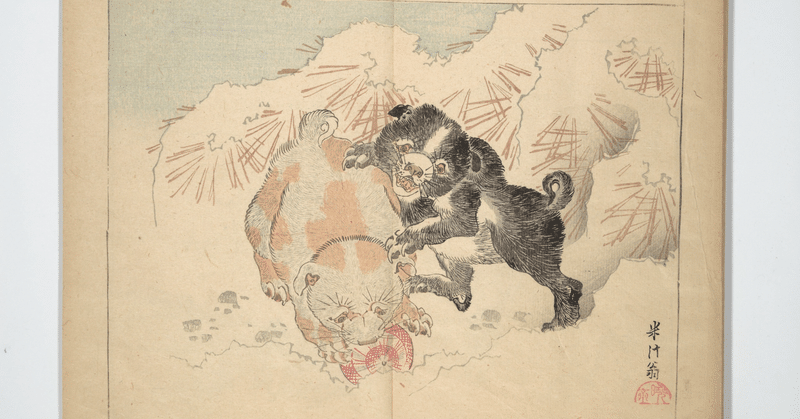
ベルナルド・ソアレス『不穏の書』
六月九日
所謂「思想家」たちの書く「私はなぜ何々主義者になったか」などという思想発展の回想録或は宣言書を読んでも、私には空々しくてかなわない。彼等がその何々主義者になったのには、何やら必ず一つの転機というものがある。そうしてその転機は、たいていドラマチックである。感激的である。
私にはそれが嘘のような気がしてならないのである。信じたいとあがいても、私の感覚が承知しないのである。実際、あのドラマチックな転機には閉口するのである。鳥肌立つ思いなのである。
正午起床、珈琲、個包装の貯古齢糖五つ、ドライアプリコット二つ。きのう湯浅が逆転サヨナラスリーランを打たれたらしい。やはりリリーフ投手がアキレス腱だったか。薄薄気が付いていた。毎度ランナーを出しているので九回を任せるには不安があるとベンチはもうすでに気が付いていただろう。昨夜の敢えての湯浅既用は、岡田流の「ライオンの子落とし」に思えなくもない。ともあれ、スアレスがいれば、と今頃どれだけのファンが思っていることか。
フェルナンド・ペソア『不穏の書、断章』(澤田直・訳 平凡社)を読む。
様々の「異名」で書いたペソア。リスボン在住の簿記補佐だというベルナルド・ソアレスよる散文手記『不穏の書』は、リルケ的内省色が濃く、倦怠臭が半端ない。こういうの好き。ことし最も多く付箋が付いた。訳者が原文でペソアを読みたいばかりにポルトガル語を勉強したというだけあって、その訳文は瑞々しい。きょうは二時には図書館に入る予定だからあまりだらだらと書くわけにはいかない。『不穏の書』の中からいくつか引いて、終わることにする。
なぜ芸術は美しいのか。それが無用だからだ。なぜ人生は醜いのか。それが目的や目標や利害を持つからだ。実人生のあらゆる道は、ある点から別の点に赴くためのものだ。誰もやってこず、誰も出て行く者もない道があったらどんなによいことか。
凡俗の人間は、たとえ人生が辛くても、少なくとも人生を考えないから幸せだ。人生を外から生きること、ただ日々を生きること、犬や猫がしているように、これが普通の人がしていることだ。そして、人生とはこのように生きるべきなのだ。猫や犬と同じように満足して生きたかったならば。
生きていると感じることの虚しさが、積極的なものの次元に達することがある。偉大な行動人である聖者は――というのも、彼らは情緒の一部ではなく、全感情をもって行動するのだから――人生は無であるという感情によって無限へと導かれる。彼らは、夜や星で飾られ、沈黙と孤独で聖別される。偉大なる非行動人は、――その中にはかく言う私も含まれるのだが――同じ内的な感情によって無限小へと導かれる。感覚をゴムのように引っぱり、その見せかけの緩んだ持続性に穿たれた孔を見るのだ。
私がしてきたことは、夢を見ることだけ。それが、それだけが、人生の意味だった。内なる生以外のものには関心が持てなかった。人生最大の苦悩でさえも、自分へとつながる窓を開け放ち、その動きを眺めて自分を忘れることができれば、すぐに薄れたものだった。
あらゆる快楽は悪徳である。――なぜなら、快楽を求めることは、人生において誰もが行うことだからであり、真に呪われた唯一の悪徳は、みなと同じようにすることだからである。
他人の会計と自分の不在の人生を記録していた帳簿からぼんやりとした頭を上げながら、ときに吐き気を感じることがある。それは前屈みの姿勢のせいだが、数字や幻滅を超越しようとしてのことである。生きることは無用な薬のように私をむかつかせる。そんなとき、私はきわめて明瞭に見てとるのだ。もし私に真に望む能力さえあれば、こんな倦怠を吹き飛ばすことなどいとも簡単なのに、と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
