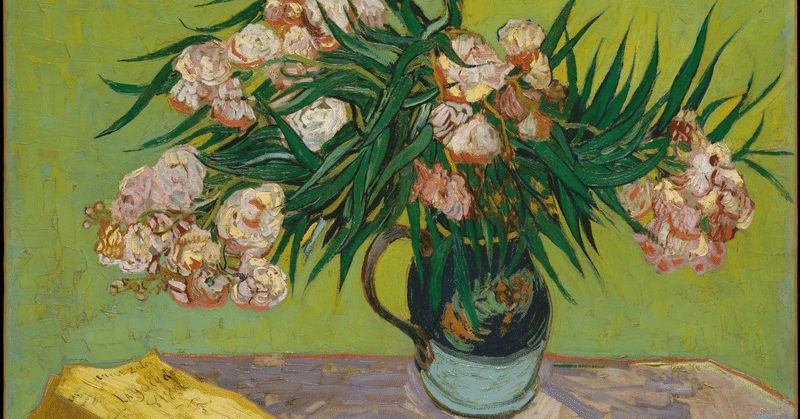
いつも忙しがっているやつにろくなやつはいない、たまにはいちにちじゅう広辞苑を読んで過ごしたい、
十二月四日
僕はね、基本的に人間として生まれたことが不満なんですよ。(ワインが入ったグラスを手に取って)これはガラスです。手でも触れるし、見て認識する。認識して生産もするようになって、我々の現代の文明になった。ところが一番困るのは、触覚ってものは必要だけど、一番使うのは視覚、目で物を見るってことです。人間は「見る」ってことが基本になっているためにですね、「見えない」ってことが不足になってるわけなんですよ。電灯が消えたとたん暗闇の部屋の中じゃ、もう歩けないんですよ。コウモリは暗い所でも、何にもぶつからないで飛ぶ。こう、自分で超音波を出しながら、どんなものでもくぐり抜けていく。人間は万物の霊長と思っていても、コウモリから言えば「バカな人間よ、何故お前は暗くなったら歩けないのか」。
午後十二時三五分起床。栄養菓子、緑茶。松井秀喜がコアラの大群に襲われている夢を見る。休館日。三時までにこれ書いて文圃閣行こうと思う。
嵐山光三郎『漂流怪人・きだみのる』(小学館)を読む。
きだみのる(本名・山田吉彦)の本は『東南アジア周遊紀行』の一冊しか読んだことがない。「なんだこのぎらぎらした老人は」と吃驚したのを覚えている。それいらい彼の名前を忘れられなくなった。彼の名声を高めた主著『気違い部落周游紀行』(今更だがなんてタイトルだ!)はまだ読んでいない。彼はいちおう社会学者ということになっているが、安定した職業的大学人とはおよそかけ離れた生き方をしている。一所不住の「無宿渡世人」で、インテリでありながら口をひらけば猥談炸裂、「野蛮」である。あえてそういう「人格」を演じていたのかしら。きだみのるの著作は古書店でもなかなか見かけることができない(少なくとも僕の通っている古書店では)。岩波文庫版の『ファーブル昆虫記』はよく見かけるけどね(訳者は山田吉彦と林達夫)。あればなんでも買うつもりでいる。なんとなくだけど夜這いの研究なんかで知られる赤松啓介と同じような体臭を彼に感じる。
茗荷オムレツだとかラム肉だとか食い物の話が本書にはやたら多く、読みながら俺もなにかワイルドな料理を作りたくなった。で、賞味期限切れのキャンベルのスープ缶で牡蠣と大豆入りのクラムチャウダーを作って食べた。


たいへん美味しかったんだが、三人前の二倍濃縮スープだったのであとで喉が渇いて大変だった。"Think rich, look poor."(考えは豊かに、見た目は貧しく)というアンディ・ウォーホルの「名言」をいまなぜか思い出した。
きだみのるといえばいつも連れている「謎の少女」ミミくんだ。学齢期にありながら学校に通っていなかった彼女は、きだみのるが高齢になってから作った子供だという。きだの没後、ある学校教員の養子になったり、小説のモデル(『子育てごっこ』)にされたりした。このへんの話は不快感なしには聞くことができない。なんというか、「親の業」というものを感じないわけにはいかなかった。もう何度か書いていることだけど、俺は「子作り」という行為を「端的な暴力」と考えている。きだみのるのように自由を愛する人間は他者の自由をも最大限に尊重しなければいかん。(生物学的な出来事としての)「子作り」はあきらかに「他者(子供)の不自由」の原因となりうる行為であり、どんな理由があっても認められるべきじゃない。たとえそれが「種としての人間」が存続する上で欠かせないことであっても。そこそこ頭がいいはずなのにそういうことにさえ無頓着な彼のうちに俺は「凡庸な無思索性」および「動物的不潔性」を見てしまった。がっかりしたよ。「男たるもの」といった調子の露骨で素朴な「マッチョトーク」にも微苦笑を禁じ得なかった。「やっぱ男って痛いな」「人間ってクズだな」という思いがまた強くなった。るるるるるるるるるるるるる、さくらんぼ、ぴんこぴんこ、ヤクザとサボテン、キツツキと盆踊り、さだまさし全集、白熊ゲーム、るるるるるる、おんどりゃあ、おんどりゃあ。ちゃうしぇすく。
もうそろそろ飯食う。レトルト親子丼。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
