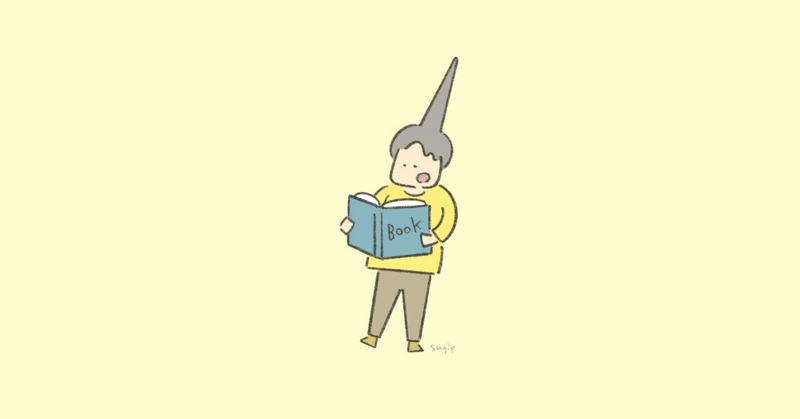
雑感記録(26)
【僕の原点回帰(高校編)】
先週、お盆真っ只中。僕にとって非常に嬉しい出来事がありました。それは高校時代の親友に5年ぶりに会えたことです。こうして「5年」と数字で表現してしまうと「さほど経過してねえんじゃあないかい?」と思われるかもしれませんが、この5年という月日は僕にとっては非常に長いものでした。
彼と色々と話をして、高校時代の想い出や今何をしているのか、そして今後どうなっていきたいのかなど種々雑多と話をしました。「やっぱり変わっていないなあ」と思いつつも「凄いやつを親友に持ったな」と少しばかし鼻が高くなりました。
僕にとって高校時代、とりわけ「放課後の時間」というのは原点であり、自身の根幹を作った非常に重要な時間でした。この親友と過ごした3年間の放課後はかけがえのない時間であったと思います。今回は僕の原点的な話をほんのちょと書いてみたいと思います。
〈過程への眼差し〉
僕は高校の時、帰宅部でした。本当は陸上部に入るつもりだったのですが、体験入部初日で主顧問と喧嘩して辞めました。原因は僕の入っていた陸上のクラブチームが気に入らないという何とも理不尽な理由でした。高校生となると、何というんでしょうか、「得も言われぬ力」とでも表現すればいいのでしょうか?力が有り余ってるんですよね。
それでその力のやり場を僕は初日に失った訳です。何とも理不尽な理由で。僕は途方に暮れました。「これから高校3年間どうすればいいんだろう」「この有り余った力をどこへ差し向ければいいんだろうか」と。それだったら他の部活の選択肢は?となる所なのでしょうが、入学して早々出鼻を挫かれた訳ですから、くそもへったくれもない訳です。「この学校の部活には期待しない」と頑なでした。さすが高校生。アホだ。
幸か不幸か、僕の通っていたクラスは進学クラスみたいなところだったので、やることがなかった僕は勉強に全振りしてやろうと思ったのです。結局3年間僕は「帰宅部のエース」として活動していました。365日毎日放課後、残れる日は必ず教室に残って下校時間が来るまでひたすら勉強していました。
そんな時、上述の親友も放課後、よく僕と残って一緒に勉強したり、色んな話をして過ごしてきました。特に僕は数学がからっきしダメで放課後残って問題集をやっていました。親友は数学が凄く出来たので、教えてもらっていました。懐かしの青チャート…。一応リンク貼っときます。
親友は勉強も出来たけれども、教えるのも凄く上手で非常に分かりやすかったのです。分からない問題は彼と一緒に「解法を考える」ということをしていました。これが僕にとっては非常に重要だった訳です。
彼は答えを教えてくれる訳では決してなく、何でこうなるのかということを常に教えてくれました。時に僕は納得がいかず、「いやこうした解法ではだめなのか」「この式に当てはめたらもっと簡単にできるんじゃないのか」等々話をすると、いつも「一緒に考えよう」と言って教室の黒板を使って二人で並んで式を書きなぐって双方の解法を吟味したりしていました。
ごく稀に二人して分からない問題も出てくる訳で、そういった時も同様の仕方で解決を図りました。この時間が僕は凄く愉しかった。「ああ学ぶことって面白いな」と思ったのはこれが1つのキッカケにはなったと思います。
こういったことがおおよそ3年間続く訳です。教科が数学以外にも国語や英語、社会…あらゆる教科に於いて同様の手順を踏んで僕は学びを深めていった訳です。
ここまで長ったらしく書いた訳ですが、僕がこの3年間の放課後の時間で得たものは大きく2つ。1つは真に学ぶことの楽しさ。そしてもう1つが過程への眼差しの萌芽。これは今の僕の根幹をなしていて、読書や芸術に触れ続けられている超重要なスタンスになる訳です。
学ぶことはその気があれば誰でも出来ることで意外と簡単なように見えるけど、しかし結構難しいと思うんです。例えば僕がもしこの親友と一緒に学ぶことをせず独りでただひたすら勉強していたらどうなっていたのでしょう。想像すると多分独りで勝手に自滅してたんじゃないかなと思います。
独りで勉強する、学ぶことも重要ですがそれをフィードバックすることも大事だと僕は考えています。結局独りで考えたことなど、所詮「井の中の蛙」。大海を知りもせず満足してしまって、広い世界がそこにあるのに、それを知らずして「俺は勉強したんだ」となってしまうのはよろしくない。
幸運なことに僕はその親友と常に一緒に考えることができていました。お互いの考えをぶつけ合って「ここはこうじゃないのか」「こうした方がもっとスムーズに解けるんじゃないのか」「そもそもその考え方が合っているのか」「他に何か手立てはあるんじゃないのか」と。こういうのって結構面白いし、愉しいんですよね。お互いの衝突ですら愉しい。
また、ここでお互いにやっているのは「答え」に対する考えでなく「解法」に対する考えについて学んでいることが大きい。つまり「過程への眼差し」というところです。これは本当に僕にとって重要で、人生的なテーマの1つでもあります。
皆さんも経験がある…というと些か変な表現になりますが、社会人になって非常に強く感じたことなのですが、常に結果を求められるんですよね。「〇〇件の獲得をしろ」「月に〇〇円稼げ」など色々とある訳です。それは所属している会社ごとによって異なりますが。
例えばです。Aさんは営業成績トップ。会社でも一目置かれている。Bさんは営業成績はあまりよくなく、取れない訳ではないがそれなりにやっている。しかしAさんは結構法令に引っ掛かるスレスレの方法で営業して獲得している。しかもお客さんにはそこそこの説明しかしていない。一方Bさんはお客さんに納得して貰えるようにしっかり説明し、信頼を得たうえで獲得している。納得したうえで契約して貰えればそれでいいやというスタンス。こうした場合、評価されるのはどちらでしょう。
一般的に考えればAさん一択でしょう。だって会社に貢献しているのは事実Aさんな訳ですから、実際に実績も出しています。どう獲得したなんかはどうでもよくて数字として表されているのだからそれでよし。でも僕はそれが嫌な訳です。だったら僕はまだBさんの方がマシな気がする。
これって結構自分でも綺麗ごとを言っているのは十分承知しています。稼いでいるのは確実にAさんですし、その会社を知らない人たちからしても「いやこいつは凄い」ってなるのは当たり前です。
しかし、あまりにもその過程を考慮されないとは何とも悲しい話ではないでしょうか。誰か、ほんの少しでもその過程の大切さを分かってあげられる人がいればいいなと僕は強く思っていますし、僕は少なくともそういう人間でありたいと考えています。
そういった意味で高校3年間の放課後、過ごしてきた時間は僕の人間形成に大きく関与している訳です。つまり「過程への眼差し」を常に持つということ。
この高校時代があったからこそ今の僕が居る。これは本当にそうだと思います。その親友には感謝しかない。直接言うのが恥ずかしいのでこの場を借りて感謝したい。また放課後の時間に僕に関わってくれた多くの友人たちにも感謝したい。
「ありがとう。これからもよろしく。」
どうぞよしなに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
