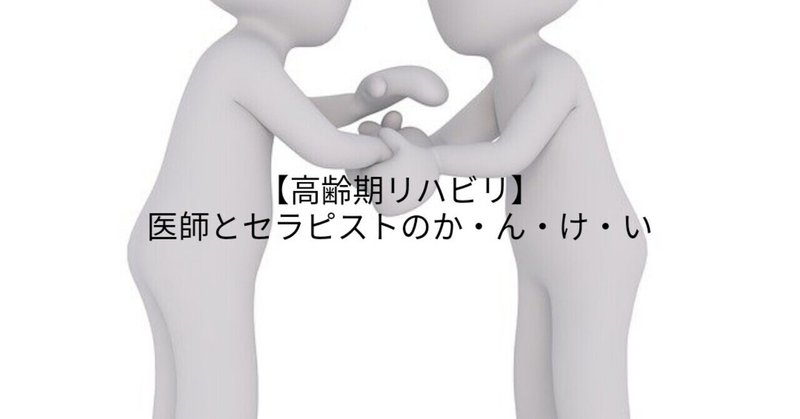
【高齢期リハビリ】医師とセラピストのか・ん・け・い
医師とセラピストは連携強化せよ
介護保険下の訪問リハビリは
医師の指示が必要でして
さらに
国は今年度の介護保険改正で
医師とセラピスト一緒に
リハビリの目標と計画を立ててくださいね
とメッセージを出してきました。
さもなければ…
収入を減額しますよ!
といった
強いメッセージです。
しかも
訪問リハビリ事業所と同じ施設の医師が
訪門リハ利用者を直接診察しないと
さらに収入を減額しますよ
とも。
つまり
医師との連携を強化しなさい
医師と連携を強化すれば
もっとリハビリ効果が出ますよ
といった感じですかね。
勘弁してくれ…、と思うセラピストは
多いのか少ないのか
皆さんどうでしょう?
今までなんとかうまくいってたじゃないか。
医師のリハビリ指示
ちなみに
医師からのリハビリ指示は
運動負荷
プログラムの指示
中止基準
が主です。
そんな中、リハビリ指示内容の質と量も
医師により様々です。
うすーい内容のものから
有益なものまで。
印象としては
うすーい内容が7割ですが。
所属医師以外からの指示を受ける場合
前述のように
基本的に所属している施設の医師に
指示書をいただかなければならないんですが
それが無理な場合は
外部のかかりつけ医に指示書を依頼して
いただきます。
費用は
250円(自己負担)
つまり指示書一枚
2500円
病院の収入ですね。
※後期高齢者医療保険の場合
薄い内容でも有益な内容でも
同じ値段。
わたしらセラピストがどれだけ詳細に
報告書や書類を作っても
0円、プライスレス。
連携を強めるには
もし今後
内外部問わず医師とセラピストの連携を
強めるのであれば
お互い理解する努力が必要ですよね。
医師はなにができるのか?
セラピストはなにができるのか?
職能団体レベル
地域レベル
個人レベル
で必要そうですね。
医療モデルの医師と生活モデルのセラピスト
そもそも
急性期、回復期での病院内チーム(医療モデル)
と
生活期介護保険チーム(生活モデル)では
性質が違うため
ギャップを埋めなければならないんです。
そのギャップを埋めるためか
前回の介護保険改正時にも話が出てましたが
訪問リハビリの指示を出す医師は
所定の研修を受けなければならないこと
になってました。
それが先送り先送りで
まだ保留状態でして。
その「研修」に関しても物議を醸し出してますが。
医師とセラピスト同じ土俵で話す機会は少ない
こちらから猛プッシュした場合や
退院前のカンファレンスなどでは
意見交換をする場があるのですが
それでもまだまだ足りない。
地域には
医療モデルが得意なセラピスト
生活モデルが得意なセラピスト
色々おります。
こちらのリハビリ報告書も
読んでくださっているのか?な?
※読んだ上で指示を出してくださる医師ももちろんおられます。
お医者さん、もっと生活期にも
目を向けていただければ…
お忙しいですかね。
介護保険下訪問リハビリの
医師とセラピストの連携
まだまだ壁は厚いですね。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
