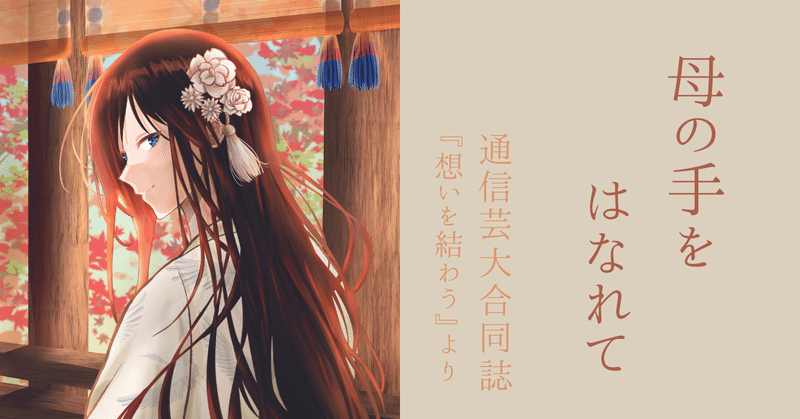
母の手をはなれて | 小説『想いを結わう』収録
お手本のような秋晴れだった。
私は手を借りてタクシーからゆっくりと降りる。雲ひとつない空のもとで、ひやりとした風が頬をかすめた。赤く染まり始めた葉が日の光にあたってきらきらと光っている。
朝九時とはいえ、浅草はもう観光客で賑わっている。何人かが私たちに気づいて、遠くから写真を撮っているのが見えた。
「ゆっくりで大丈夫ですからね」
付き添いの女性に声をかけられ、はい、と返事をしてそろそろと歩く。
体がずっしりと重く、足がなかなか前に進まない。足元の石がじゃりじゃりと音を立て、つんのめるようにして一歩、また一歩と踏み出した。駐車場からの移動距離は長い。十一月と思えない強い日差しから目を背けた。
「あ、お義母さんじゃない?」
夫の声に顔を上げる。ちょうど母が建物に入っていくところが見えた。口元は笑っているが顔全体の表情は固く、動きもぎこちない。緊張しているのだろうか。
こちらにまったく気づかない母の後ろ姿を眺めていたら、ふと幼いころを思い出した。
すぐに迷子になる子だったと、母はよく私に言った。
生まれ育った小さな田舎町のショッピングモールで、よそ見をする私と歩くのが早い母の間にひとり、ふたりと知らない人が通るともうだめだった。立ち止まり、母に似た後ろ姿を走って追いかけ、私はたちまち迷子になるのだ。母はやがて、どこへ行くにもしっかりと私の手を繋ぐようになった。私はそれが嬉しくて、でも少し窮屈だった。
迷子になるのは怖い。よく見知った楽しい場所が、初めて足を踏み入れる場所に見えてぞっとしてしまう。二度と母に会えず家にも帰れずごはんも食べられない、そんな想像が頭を駆け巡り私はその場で大泣きをした。何人もの大人の力を借りて母を見つけ出してもらっては、ひどく叱られたものだった。迷子になるのも叱られるのも嫌なのに、ついよそ見してしまう癖はなかなか直らなかった。
東京へ旅行にいくよ、と言われたのはたしか私が小学一年生ころのことだった。私はずっと、どうしても浅草に行ってみたくてたまらなかった。テレビで見る浅草は赤の提灯が大きくて綺麗で、仲見世通りは美味しそうなものであふれていた。天国みたいとはしゃぐ私を母は呆れ顔で見ていたのだろう。
家から車で五時間かけて辿り着いた浅草で、私は呆然と立ち尽くした。
人、人、人、人、人。どこを見ても、人。
さまざまな国の老若男女が、ひしめき合い、大声で話し、笑い、写真を撮っている。こんなに多くのいろんな人が同じ場所にいるのを、私は見たことがなかった。たくさんの人の笑い声や混ざったにおいで頭がガンガンとする。せっかくの仲見世も人の背中や足が壁になってよく見えない。私は、母の手をぎゅっと強く握った。
そのときの母の顔を、私はよく覚えていない。すぐ迷子になる私が命綱のようにその手を掴む姿は、母の目にどう映ったのだろう。実家の壁には、そのときの家族写真がまだ飾ってある。
雷門の大提灯の前で、顔をしかめて母の手を離すまいとしている私の姿。その表情からは、ここで迷子になってしまったらもう二度と見つけてもらえないとでもいうような、笑ってしまうほどの悲壮感が漂っていた。
そんな鮮烈な浅草デビューだったが、大学進学を機に上京してから私は何度も浅草に足を運んだ。浅草寺、浅草神社、仲見世通り、花やしき。簪の専門店、とろろの美味しいお店、かっぱ橋の食器屋さん。大学生の私には魅力的なものばかりで、友人や恋人とよく観光してはお気に入りの場所を増やしていった。
幼いころの記憶はあっさりと薄れて、いつの間にか浅草は楽しい思い出ばかりの場所になっていたのだ。
そんな昔のことを思い出しながら、たどたどしい足取りで夫に続いた。
白無垢は冬布団を着ているようなものだから、と着付を担当してくれた女性が笑っている。たしかに、ずっしりとした重み、汗が吹き出る暑さは、布団そのものだった。
慣れない下駄は足元の砂利に沈み込む。一歩踏み出すごとに体力を使い果たしていくような気がした。
「晴れてよかったな」
夫が笑顔で言いながら目を細める。照りつける太陽の光を私の全身の白が反射しているのだろう。ほかの人からはよく見えないだろうなと胸元にいる鶴を眺めた。外で撮る予定の集合写真では模様ひとつない真っ白な白無垢に見えてしまいそうだ。せっかく縁起のよい鶴の柄を選んだのに。
呑気に先を歩く夫をうらめしく眺める。黒の袴は、すらりと長身の彼によく似合っていた。数歩進んでは振り向くその姿に、歩きやすいでしょ、ずるいと文句を言うと、「歩きやすいけれど、お腹はしっかり絞められていて苦しいよ」と夫は笑った。
遠くのざわめきと時折聞こえる賽銭の音。簡単な親族紹介の後、浅草神社で私たちの結婚式は始まった。
境内を参進して雅楽とともに入場すると、両側にずらりと並んだ親族一同と友達が見える。
この日しか見ることのできない景色だ。なにかが胸に詰まり、見知った顔たちを直視できない。目を逸らしてまっすぐ前を向くと、鳳凰や麒麟、龍と目があった。明るい橙色を背景に部屋をぐるりと囲んで飛び交うように描かれているそれらは外からの光に照らされ、まるで生きているような迫力を湛えている。そういえば、天井画が修復されてその美しさを取り戻したのは、ちょうど私の生まれた年だったか。
豪華絢爛、という言葉しか思い浮かばないその鮮やかな空間は、ひりりとした空気で満ちていた。誰も笑わず息を殺してこちらを見つめているのが分かる。チャペルでおこなう式は皆が微笑ましく、また涙して見守ることが多いが、神社だとこうも緊迫感たっぷりの張り詰めた雰囲気になるのかと緊張が高まっていく。心臓が口から出そうという比喩は本当にそう感じるからなのだなと、胸で息をしながら思った。
神前結婚式は、新郎新婦がやらなければならないことが多い。耳打ちなどほとんどなく、リハーサルで習ったことをすべて間違えず実行しなければならない。
禁止事項が多い上に慣れないことばかりだ。非日常空間のなか粛々と進む式を強張った顔で、どうにかひとつひとつこなしていく。立つ、頭を下げる、祈る、座る、立つ、頭を下げる、座る、立つ、頭を下げる……。なぜこんなにも、動作が多いのだろう。私たちはひたすら、立っては頭を下げ続けた。
帯に締め付けられたお腹のせいで立っていても座っていても貧血のような苦しさがある。神妙な顔ばかり写真に残ってしまいそうな気がした。神に誓うため、笑うタイミングなどなくずっと頭を下げている状態になってしまう。和やかさなんて欠片もない重苦しい空気の中で、きりきりと胃が締め付けられていく。
なんでもいいから、どうか滞りなく済んでくれ。
そんな罰当たりなことを願っていると、細く畳まれた和紙が渡された。祝詞奏上——誓いの言葉だ。
「今日の良き日に浅草の大神の大前において」
夫の声が、しんとした本殿に響く。
普段は小さな声でゆったりと喋る彼が、人前で堂々と声を出す姿は珍しく見えた。
今日より後は 互いに 相和し 相信じ 苦楽を共にし 終生変ることなく 立派な家庭を築くことを 茲にお誓い申しあげます
その言葉は最後まで滞ることなく発せられた。
なんて大仰な誓いだろう。なんて重い誓いだろう。
実際に結婚したのはもう半年も前なのに、今さら結婚の重みが、ずん、と私にのしかかる。すべての苦楽を共にする覚悟は本当にあるのか。立派な家庭を、私たちは築くことができるのだろうか。
夫が名を言う。私はずっと閉じていた口を開いた。挙式で唯一、私が発する言葉は自分の名前だ。からからになった喉の奥から声を絞り出した。生まれてから今までずっと付き合ってきた私の名前は、静かな本殿に響き、奥へ吸い込まれていった。
指輪交換や玉串のお供えが終わり、親族固めの盃の合図があった。式次第のほとんどが終わったようだ。思わず安堵のため息が漏れる。
親が友人へ、友人が後ろへ御神酒をまわす。静まりかえっていた本殿に、どうぞ、すみません、ありがとうございます、という囁きがこぼれていく。全員に御神酒が行き渡るのを待つ間、張り詰めていた場内の空気が少しずつゆるんでいった。この場の皆でお酒を酌み交わし、この式は終わりとなる。
「乾杯の音頭をお願いいたします」
その声に、私の母が立ち上がった。茶道の師範でもある母は、黒留袖がよく似合っている。母は頭を下げ、口を開いた。
「本日は、」
その声がふつっと途切れる。
あれ、と様子をうかがうと、母はぎゅっと唇を噛みしめていた。目が真っ赤で、手は震えている。ふう、と息をついて次の言葉を続けようとしたが、途切れ途切れになったその声はよく聞こえなかった。
母は、私が幼いころからとても厳しい人だった。好奇心旺盛なのに怖がりな私に振り回されては怒っていた。とにかく心配性で、私が遠くに行くことをなにかと不安がっては口を出した。どんなに私に嫌がられても、いってらっしゃいとおかえりを言うために、家にいる日は必ず玄関まで出てきては薄着の私に小言を言った。
すぐに泣く人だった。悲しくても嬉しくても、感動しても悔しくても、目を真っ赤にしてぼろぼろと涙をこぼしては鼻をかんでいた。そんな母がぐっと堪えてまっすぐ前を見据え、私たちにお祝いの言葉を述べている。
目を落とすと、御神酒の入った盃を持つ自分の手が見えた。母の手を握らなくても、迷子にならなくなったのはいつからだろう。
「おめでとう」
母は最後に、はっきりとした声でそう結んで盃を掲げた。
おめでとう、おめでとう、と声があがり、皆で盃に口をつける。やがて拍手が起こって、無事に親族固めの盃は終了した。盃を返し、ゆっくり腰を下ろす。
終わった。これでやっと、私たちの結婚式は終了したのだ。
空気が完全にゆるみ、皆が和やかな笑顔を浮かべているのが見えた。今日一番の役目から解放された母は安堵した様子で、隣に座る姉たちと話をしている。
御神酒を全部飲むと胸の締めつけと相まって倒れる場合があるので気をつけてくださいね、という忠告をきちんと守った私は、唇に薄くついただけのお酒を舐めた。少し苦いアルコールの香りに、思わず顔をしかめる。そんな私を見て、夫がほっとしたように表情を和らげた。
そういえば夫は今日、私のほうばかり見ていたなと気づく。貧血を起こして倒れそうな私が不安だったのだろうか。よく転ぶ私が心配だったのだろうか。お互いの薬指にはめられたピンクゴールドが光る。
私と夫は顔を見合わせて、ふふ、と笑った。
すぐに迷子になる子だったと、母はよく私に言った。
浅草を迷子にならずに歩けるようになった私はまだ、やりたいことばかりにすぐ飛び付いては痛い目を見て、無計画に突っ走っては転ぶ毎日だ。
人間関係、仕事、学業、家庭、夢。これからだってきっと、迷い悩むことばかりだろう。それでも。
どんなときでも必要ならお互い鬼になろうと決めて、角隠しは被らなかった。なににも染められないぞという思いで、色打掛は何色もの糸で紡がれた派手なものにした。私は母の名が入ったこの名前で、母が命懸けで創った私のままで、夫と手を結び、迷っては軌道修正をするこの日々を生きていく。
立派な家庭であることよりも、そうありたいと願って努力を重ねることこそが尊いのだ。教えてくれたのは、何度でも話し合いをしてくれる夫だった。たったひとりで私を育てた母の背中だった。私のまわりで静かに私の命を支えるすべてだった。
秋の風がそっと私の頬を撫でた。
こちらを見ない母に、心の中で小さく呟く。
今日この場所で、その手を離れる瞬間を見届けてくれてありがとう、と。

読んでくださりありがとうございました!
こちら、KUA(京都芸術大学)通信教育部の学生17名による『想いを結わう』というアンソロジーの合同制作企画に寄稿した小説です。
浅草神社では実際に挙式をしており、その経験をもとに創作しました。いかがでしたでしょうか?
デザインを専攻している 藍沢紗夜 さんに主催いただいたこの企画は、以下のようなものでした。
「小説」「イラスト」「デザイン」の3部門から1人ずつ計3名のチームを組み、「結」というテーマに沿って、それぞれの内容がリンクした作品を共同制作したものを本にまとめました。
テーマである「結」には、企画のメインであるチーム制作と、異なるジャンルを結ぶことで、より深みのある新たな作品を創造する、という意味を込めました。それぞれのチームならではの「結」の解釈をお楽しみいただける一冊です。
初対面の方々と3人で制作を進めるのは初めての体験でした。
表紙イラスト担当の明月アツキさんと内容やモチーフの詳細を詰めながら、デザイン担当の鈴木心さんにアドバイスいただいて…。
正直、私はイラストというものがどのような過程でどのくらい手間がかかるものなのか、まったく分かっていませんでした。年末年始やテストも挟み、忙しい中たくさんの時間を費やしていただいたアツキさんには本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

また、青春ものや恋愛系を選ぶチームが多いのではないかと思い、悩みましたが、あえて結婚式という大人のテーマで挑みました。
入学して1年、通信制大学にはさまざまな方がいらっしゃいます。この1冊の中でもそれが見て取れたら面白いのではないかなと思っています。
制作中、詰まっては話し合い、何度もすり合わせをして確認を行って進めました。全員がこの形式での創作に不慣れな中、大きな揉め事もなくスムーズに完成まで運ぶことができたのは、齟齬のないよう丁寧な確認を重ねて素敵なイラストを描き下ろしてくださったアツキさん、適切な助言やサポートをくださり最後に世界観に合うデザインで仕上げてくださった心さんのおかげです。
改めて本当にありがとうございました!

アンソロジーには他チームの素敵なイラスト・小説が詰まっています。
ぜひぜひ、読んでいただけますと幸いです!
最後にはなりますが、主催の紗夜さん、素敵な企画をありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
