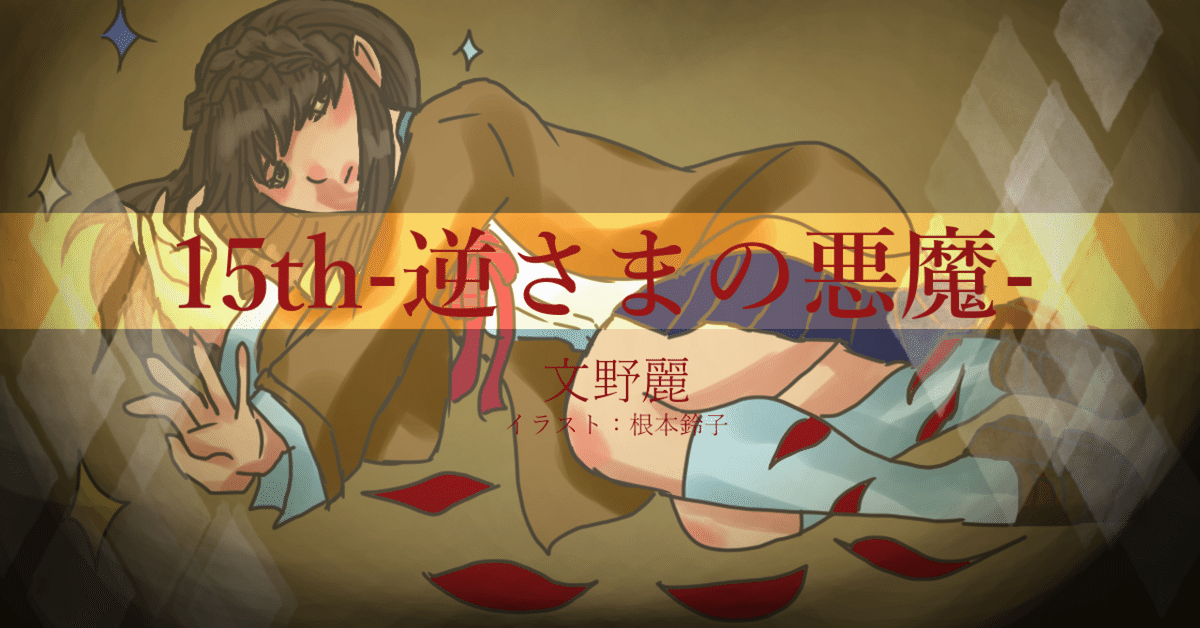
第七話「下された診断」長編小説「15th-逆さまの悪魔-」
「少しでいいから食べなさい」
「食べたくない」
「でも食べないと身体に悪いよ。お願いだから、一口だけでも食べて」
「食べたくない」
琴音はこの頃毎日母と食べる食べないの問答を繰り広げ続けていた。この日は父は残業のためまだ帰宅していなかった。母は自分の食事を終えた後、箸に触りもしない琴音を説得するようになった。
「食欲がなくても、少しだけ食べなさいよ。いくらなんでも、一口二口なら食べられるでしょう?」
琴音は返答に困って黙っていた。すると母は
「なんでそんなに頑ななの? 病気な訳でもないのに、食欲が全く湧かないなんてあるの?」
琴音はどっちつかずの態度を見せ、食べてほしいという母の懇願に打ち勝とうとして頑張っていた。今夜も母に諦めさせて、食事を下げてほしかった。
琴音は食事を拒むうちに、目に見えてやつれてきていた。鏡を見ると、顔色は暗く見え、肌は土気色で、頬がぺったんこになっていた。目の下には隈ができていて、唇は赤みを失っていた。肌にはニキビが目立ち、乾いて荒れている。
いつしか学校も休みがちになっていた。体力がなくて登校がしんどいし、慢性的に体調が悪い。頭痛胃痛腹痛はほとんどいつもであるし、身体に力が入らず、脚がもつれてしまってまっすぐ歩けないくらいだった。吐き気も頻繁に起こる。吐こうとしても何も出てこないのであったが。
それに学校へ行かなければ歌羽と向き合わずに済むのだ。話しながら常に少しずつでもエネルギーを削られるのはやはりつらくて、逃れられるならそれに越したことないのであった。
一度学校を休んでみたら体力的にも精神的にもあまりに楽で、学校に行かない生活を気に入ってしまった。一度楽な道を知るとどうしても苦しい日常を送り続けることができなくて、休む頻度が上がっていった。
当然両親は黙っていなかった。彼らは歌羽とのことは知らなかったが、体力面の問題で学校へ行けないのは明らかに食事を摂らないせいなので、問題は一つのように思われた。食事をすれば問題なく学校へ行けるのに、どうして娘が食事を拒んで学校生活も犠牲にしてしまうのか理解できない様子だった。
まさか麻理恵に対する罪悪感という自罰的感情、そして深い悲しみから食べる気持ちを失っているとは思いもよらなかっただろう。
ある日、また朝食の席に来ないで寝室にいた琴音のところへ母がやってきた。
「今日は病院へ行ってみない?」
「なんで?」
「なんでってご飯食べられないからだよ。どう考えてもおかしいじゃない。胃か腸に問題があるのかもしれない。診てもらおう」
食事しない原因は消化器官の異常でないことは琴音本人がよく知っていた。だが母に説明することはできない。琴音は病院行きに、無気力に同意した。
琴音は問診と血液検査を受けた。内視鏡検査は必要ないと判断された。
医師は血液検査の結果が出てから、母と娘に告げた。
「内臓機能に異常は見受けられません」
一呼吸おいて、医師は琴音に話しかけた。
「最近、学校や普段の生活で、ストレスになっていることはありませんか」
琴音は息を飲んだ。数秒考えてから、答える。
「勉強が分からなかったりして、ストレスなときはあります」
「ストレス、少しばかり強いかな?」
「えっと……」
「過度のストレスでご飯を食べられなくなることがあるんです。そういう症状、今若い女性に増えているんだけどね」
「ストレス性の病気なんでしょうか」
母が少し前屈みの体勢になった。
「心の不調、かもしれません。ここからだと少し遠いんですが、××市に〜病院っていう、大きい病院あるの、お母さんご存知ですか?」
「はい。駅からまっすぐの国道沿いにある……」
「そうですそうです。そこへ行って相談してみませんか? 紹介状書きますので、受診してみてください」
後ろで母が戸惑っているのを背中で感じながら、琴音は医師がパソコンで何事か打ち込んでいるのを眺めていた。
受付で渡された紹介状には、「精神科」の文字があった。
内科を受診した次の週に、予約を取って病院へ向かった。病院は車で一時間ほど掛かる場所にあった。精神科の予約は常にいっぱいですぐにはとれないものだが、内科医が緊急性をみとめて紹介状を書いてくれたおかげで優先的に診てもらえることになった。
琴音は二年前に入院した郊外の病院を思い出した。
待合室でかなり待った後、琴音の名前が呼ばれて、母と一緒に診察室へ入った。
医師は壮年の、恰幅がよい男性だった。角刈りの頭には白髪が混じっている。琴音にいくつか質問した。
「夜は眠れていますか」
「たまに眠れないときがあります」
「学校へは行けていますか」
「最近、疲れてて休んでます」
「身体が疲れてる感じ?」
琴音は迷ったが、少しだけ本当のことを言った。
「ふらふらして、体力が足りなくて、つらいです」
「ダイエットしたいとか考えたことはありますか」
「はい。今、しています」
今度は思いきり嘘をついてしまった。
「ダイエットは、どんな方法でしているの?」
「食べる量を減らしています」
「減らしているどころか、最近ほとんど水しか飲まないんですよ、この子」
母がじれったそうに口を挟んだ。
「そうですよね。そういう人、今多いんですよ」
医師はパソコンで電子カルテに何か打ち込んだようだった。
「摂食障害という病気をご存知ですか?」
「摂食障害というと、キョショクショウのことですか」
母が反応した。
「琴音さんは、聞いたことあるかい?」
「名前は……」
医師は顔を上げ、琴音と母、二人に説明した。
「ダイエットをしようとして、極端に食べる量を減らすうち、食べ物を食べられなくなってしまう人がいます。ほとんどが若い女性に見られる症状です。先ほどお母さんが拒食症とおっしゃいましたが、一般に言う拒食症は摂食障害の症状のうちの一つです。そして琴音さんにはそれが当てはまると思われます」
医師は琴音に話しかけた。
「食べられなくて、心も身体もつらかったでしょう。きちんと治せばよくなるので、頑張って治療していこう」
医師は再び母に向き合った。
「根気強く直していく必要がある病気です。ご家族の協力がどうしても必要になってきます。一緒に治していきましょう。こちら読んでみてください」
そう言いながら、机の上に置かれていた「摂食障害ってどんな病気なの?」と表紙に書いてあるパンフレットを手渡してくれた。
医師は心強いことを言ったが、琴音は全然治す気になれなかった。このまま食べないで、費やされて潰えていきたかった。跡形もなく消えてしまいたい。
帰りの車の中で、それまで何も言わなかった母が口を開いた。
「ちゃんとご飯食べなさいよ」
琴音が黙っていると、母はよい強い調子で続けた。
「ダイエットなんて嘘でしょう。そんなこと一言も言わなかったじゃない。何を意地張ってるのかわからないけど、まともに食べるってそれをすればいいだけでしょう? 全然難しいことじゃないよね」
母は右折しようとして一旦静かになった。右折が完了すると、一層キツい口調で続きを述べた。
「琴音に用意したご飯、毎回捨ててるんだよ? もったいないじゃない。それがどれほど罰当たりなことか、もう分かる歳だと思うんだけどね」
「私の分は用意しなくていいよ」
「は? 何言ってんの?」
「私は食べたくない。食べない分は用意しなくていいよ」
「ふざけたこと言ってんじゃないよ!」
母は大声を出した。
「そんなにママの作るものが気に入らないっていうの?」
「そういうわけじゃなくて、食べ物が全部嫌なの」
「もういいよ。パパに話すから。それで怒られたらいいよ。あんまりふざけたこと言ってると許さないからね」
それ以後、母娘は二人とも黙っていた。琴音は厳しい沈黙に母の怒りを肌で感じ取った。
帰宅して、琴音は部屋にこもっていたが、父が帰宅すると、母はさっそく診断結果と琴音の言っていたことを話したようだ。
琴音は廊下に出て、こっそり両親の話を盗み聞きした。
「そんなふざけたこと言ってんのよ。なんとか言ってやってよ」
少しの間の後、父の言うことが聞こえた。
「これはそういう単純な問題じゃないかもしれないぞ」
「どういう意味よ」
「精神的な病気だって言われたんだろ? 病気のレベルで食べる気が起きないのは、叱って食べさせたらいいってもんでもないんじゃないか?」
「じゃあどうしろっていうのよ、あんなに痩せてきてるじゃない」
「そう聞かれても、俺も今聞いたばかりだから分からない。俺は俺で調べてみるよ」
夕食時、琴音は部屋から出なかった。扉の外で、母が半狂乱になって琴音を叱りつけたが、ずっと布団にくるまっていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
