
#273 一流のマネージャーが考えること
「働き方改革」は今や全企業の課題となっている、
と言っても過言ではありません。
そんな中、
プレッシャーが増しているのは、リーダーやマネジャー。
✓ 個人目標とチーム目標を課せられる
✓ 上層部からは「残業削減」を求められる
✓ 現場からは「仕事は増えてるのに…」と反発を受ける
日々、板挟みになりながらも
自分の役割を果たそうと奔走している人を見かけます。
そのエネルギーたるや、相当なものです。
でも、そのままだといつか、その
当人が疲弊してしまいます。
そこで今回は、一流のマネージャーがやっている
自分もチームも疲弊せずに成果をあげる方法をお伝えします。
1.一流のマネージャーが意識していること

✓ 待つ姿勢が大事
✓ アドバイスよりフィードバックが効果的
✓ メンバーの「心理的安全性」を大切にする
この3点を理解し、
実行しているマネージャーは一流です。
もしかしたら、中には
「これだと部下が指導できないのではないか」
と思った方もいるかもしれません。
相手に指摘して「心理的安全性」を脅かしてしまえば、
メンバーとの「関係の質」が悪化するかもしれませんからね。
でも、一流マネージャーが実践しているのは、
「放置すること」と「厳しく指摘すること」
のちょうど真ん中をとった方法、
「客観的な事実をフィードバックする」という方法です。
2.客観的な事実を伝える
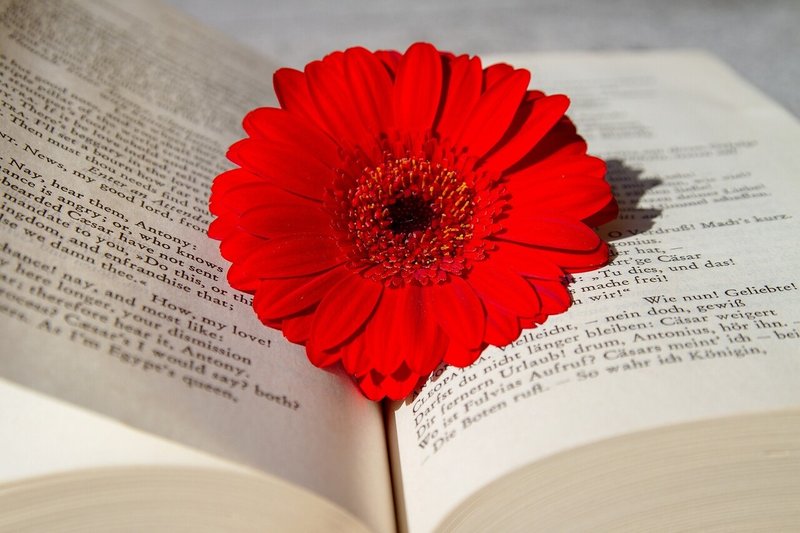
フィードバックとは、もともと軍事用語で、
「砲弾が目標地点からどれくらいズレていたかを射手に伝えること」
を指していたそうです。
ここで大切なのは、
客観的な事実を伝えるだけで、
主観的な価値判断が入っていないことです。
とても分かりやすい例を見つけたので紹介しますと、
「的から左に2mズレていましたよ」はフィードバック
「もっと右を狙って撃ったほうがいい」はアドバイス
相手により効果があるのは、
アドバイスよりもフィードバックです。
3.フィードバックが推奨される理由

フィードバックが推奨される理由は2つあります。
✓ 相手が抵抗感なく受け入れられる
✓ 本人が自発的に考えることができる
フィードバックは客観的事実を伝えるだけなので、
相手は抵抗感なく受け入れることができます。
先ほどの例で言うと、フィードバックでは
「目標地点からのズレ」を伝えるだけですから、
ズレをどのように修正するかを考えるのは本人です。
本人が自発的に行動を修正するのを促せると、
自分で考え、行動できる人にも近づけます。
一方で、アドバイスの場合は、
「上から目線」と受け取られることがありますし、
具体的に指示することで、本人が考える機会を奪います。
相手が自発的に行動できるようになるには、
アドバイスよりフィードバックの方がいい
と言われているのはこのためです。
4.フィードバックのポイント

フィードバックをする時のポイントは、
直後に・軽く・フラットに
「感じたこと」を伝える
ということです。
以前私がいた職場では、
お客様にカジュアルな口調で対応をするメンバーがいました。
(以降Aさん)
友達と話しているかのような言葉づかいなので、
「本当にそれでいいのか」とハラハラしていました。
そのお客様が帰られた後の上司とのやりとりが、
フィードバックなんだろうなと感じたので紹介します。
上司 「さっきのお客様はお知り合いの方なの」
Aさん「いえ、今日初めて会いました」
上司 「そうなんだ。私はてっきり友人かと思っていたよ。
初対面の人と対応しているようには見えなかったな。」
上司はダメな点を指摘したのではなく、
自分が感じたことをそのまま伝えていました。
上司は「私はそう感じた」という事実を伝えただけですから、
対応のダメな点を指摘していることにはなりません。
でも、このフィードバックを受けたAさんは、
「ちょっとフランクすぎたかな」
と自分の頭の中で考える機会がもてたと思います。
また、上司はお客様が帰った直後に
Aさんとこのような会話をしていました。
直後に伝えると本人も振り返りやすいですし、
なるべく軽く伝えたほうが受け取りやすいですからね。
今思えば、あの上司はフィードバックを意識して
本人に考える機会を提供していたんだな思います。
5.まとめ

いかがですか。
今回は一流のマネージャーが意識していること
実践していることについてお伝えしました。
実際に言葉にするのは簡単でも実践するのは難しい
ということが多かったかもしれません。
ですが、これが意識し、できるようになると
自分もチームも疲弊しないで成果をあげる
ことができるようになります。
慣れるまでは難しいかもしれませんが、
少しずつ、実践してみてくださいね。
今回はこれで終わりにします。
ではまた。
👉次に読むなら
過去のオススメ記事を紹介
・#267 部下が意見を言わない理由
・#261 上司の上手な見限り方
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
