
羊角の蛇神像 私の中学生日記⑰
死闘の果てに
不吉な弾力を頭部に感じた。
両手を封じられた絶命絶命の私は、そのままの体勢でジャンプして、Wくんの顔面へ頭突きをしたのだった。
Wくんは膝をつき、自分の口から溢れ出る赤いものに触れて、次にその手を某然と見つめていた。
私もまた、ぼんやりとしていたと思う。
状況を理解し、その恐ろしさを咀嚼するのに時間がかかった。受け入れ難い事実を受け入れなければならない時、私たちの体感時間は速度を落とす。
Wくんの前歯が数本折れたようだった。
血をだらだらと流れる口の中へ指を入れて、ぐらつく自らの歯にそっと触れて確かめる様子が恐ろしかった。
3年生が何かを言った。
どうやら、これからWくんと3年生の誰かが喧嘩をするというような話をしている。
よくわからない。
トーナメント的なものであれば、1回戦で勝ったのはおそらく私であり、私と誰かが戦うのではないのか。
勿論、そんな力も気持ちも無い。
早くこの場を立ち去りたかった。
Aくんが口から血を流し続けるWくんに冷たく言った。
「今からこの3人のうち誰かとケンカや。自分で決めてええで。自分で決められへんかったら自動的におれかCになるけどな」
私は死にかけのゾンビのような心でそれを聞いていた。
ゾンビは2度死ぬ。人は繰り返し地獄を味わう。
ゾンビの心に少し残った人間の部分が、Bくんの悲しみを嗅ぎ取って、私は彼の狼狽する顔を盗み見た。

踏み絵 あるいは蜘蛛の糸
第2ラウンドの挑戦者は再びWくんで、3年生の3人の中から指名するように命じられた。
Aくんは、Bくんが一番弱いイージーモードだから、自分で指名しなければハードモードの自分(Aくん)かCくんが相手になるから早く決めろ、という風に聞こえた。
私は子どもだったので、最弱扱いをされたBくんは、悔しさと恥ずかしさを感じたのではないかと思った。
今まで、ずっとそう思っていた。
Wくんは、Bくんを指名した。
私は、へとへとになった体で、ぼんやりとする頭を支えながら部屋を出た。
あるいは、しわしわになった風船のような頭に、紐のように体が垂れ下がっていたのかも知れない。
去りながら、既に始まっていたふたりの戦いを横目で見た。
Wくんを一方的に殴るBくんの方が、苦しそうに顔を歪めていた。泣く寸前の子どものように呼吸が乱れていた。
Bくんは、逃げ出したかったのではないだろうか。
本当は、Wくんのことなど殴りたくなかったのではないか。
好戦的なAくんと、知能犯でラスボス的なCくんと、いたずらが好きで、本当は優しくて、Wくんとも仲良くしていたBくん。
ヒエラルキーの頂上にいるような彼らだったが、本当は、お互いの顔色を見ながら、微妙な力関係に絡めとられて、つらかったのではなかったか。
Wくんを殴らなければ、Bくんが標的になっていたのだろうか。
わからない。
当時のことを文章化するために、記憶を何度も反芻する中で、私はそんな可能性について考えるようになっていた。
Aくんが、WくんにBくんを指名するような流れを作ったのには、ふた通りの可能性があったかも知れない。
本当はWくんを殴りたくないBくんに対して、「お前はどちら側か?」と踏み絵を迫ったパターン。
あるいは、Bくんが手加減することを見越して…。
それは無いか。
そんな情けを掛けるくらいなら、第2ラウンドは無かったと思う。
私は彼らの本当の気持ちがわからない。
わからないことは怖いし悲しい。

舌弁花
本来であれば、その時間は清掃をしなければいけなかったと思う。
私は玄関の下駄箱から一足ずつ靴を出しては、土や小石を掃き出していた。
死にたいような、世界のあらゆる物が無価値だと感じるような、無限のやるせなさを拭うように、無心に手を動かしていると、廊下にドタドタと人が走る音が響いた。
Wくんだった。
彼が、殺気だった目で私に襲いかかろうとしていた。
血走った目と、口から流れる血が恐ろしかった。
もう、ええ加減にしてくれ…と、投げやりな気持ちで彼を向かい入れたと思う。
私は彼が手にした折り畳み式の将棋盤で頭を何発も殴られた。
ええって…。わかったって…。
これも3年生にやらされてるんやろ…。
いつまで続くのこれ…。
畳んだ将棋盤で頭をバンバン叩かれるのが、何かもう、痛気持ち良いような感覚のエラーが現れていた。
怒りも悲しみよりも、呆れや可笑しさの感情が、ひらひらとハエ取り紙のようにまわる私の心を静かに満たしていた。
寮長先生が現れて、Wくんは制止された。
Wくんは、けしかけられたとは言え、前歯を何本かやられたのだ。怒りがあとから込み上げてきたとしても、それは仕方のないことだと子どもながらに思った。
将棋盤で殴っても、気が晴れることは無いだろう。
喧嘩慣れしていない私は、加減ができなかった。
彼に取り返しのつかない、ひどいことをしてしまったのだ。
一方で、現実感が急速に失われる感覚の中で、自分の意志や存在も、綿毛のように頼りのないものへ変わっていくのだった。
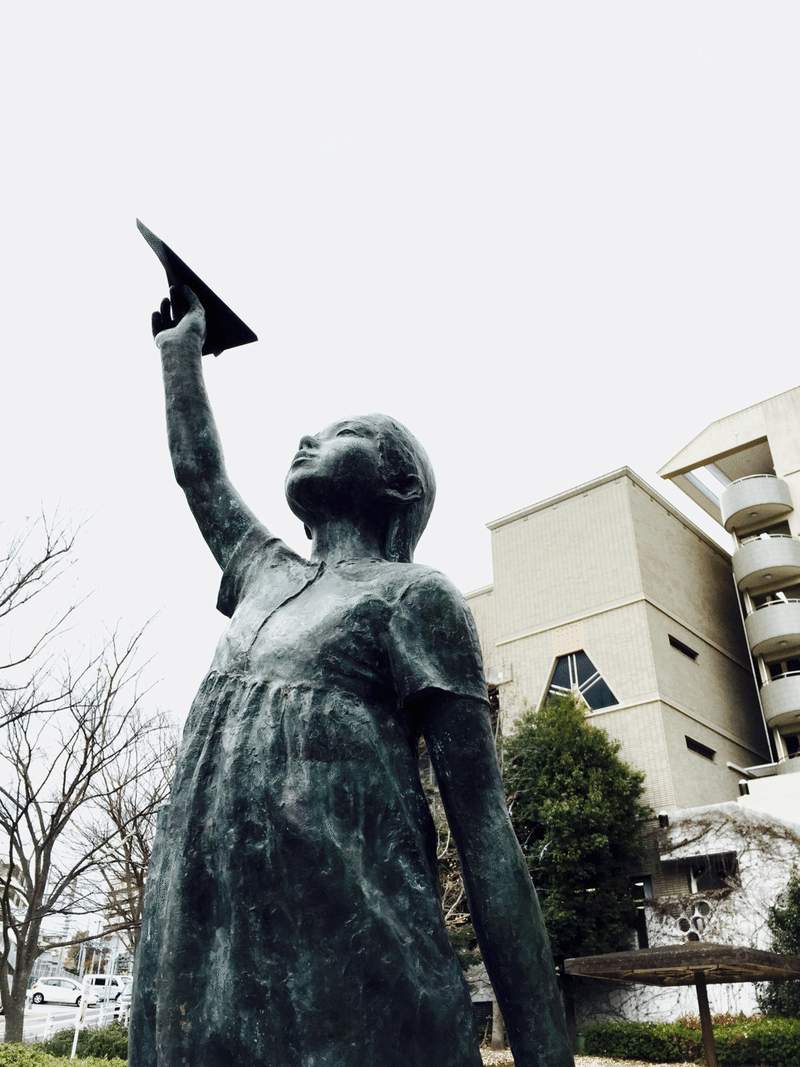
土と人間と生命
Wくんの上下の前歯は殆ど折れたようだった。
その頃、私とWくんがまともに会話することは無かった。
言葉の代わりに暴力で関わることしかできなかった私たちは、首のもげた獣のつがいのようなものだった。
そんな怖い比喩でも、私たちのいるナンセンスな世界の絶望は伝えられないだろう。
朝か昼か夜の、いつのことかは覚えていない。
息が詰まるような圧迫感と他人の匂いで目を覚ますと、私の胸の上にWくんが座り込んでいた。
彼は、歯を折られたことについて、「どうしてくれんねん」と抗議めいたことを言ってきた。
私は何と答えたか覚えていないが、またけしかけられたのだと思いながら、彼をなだめたように思う。
小突かれたりはしたかも知れないが、ひどく殴られたとか、そういうことは無かった。
私は今までずっと、彼の歯を折ったことを、3年生たちのせいにしていた。
なぜ私はあのくだらないブラッドスポーツに乗ったのだろう。
逃げるとか、先生に言うとかの選択肢は無かったのだろうか。
そういう逃げ場を失った、心理の袋小路に追い詰められていたのだろうか。
きちんと謝るべきだった。
今はそう後悔している。
その頃、確かマラソン大会を目前に、いつも以上に長い距離を走っていたと思う。
長距離を走っているとお腹が痛くなることがある。
走ることに随分慣れた私だったが、時にはお腹が痛くなることもあった。
しかし、お腹とは違う所が痛い。
脇?それとも胸だろうか。
走ってなくても鈍い痛みが続いていた。
私は肋骨が折れていた。
Wくんが座ったから折れたのだろうか。
私はサポーターを胸に巻いて1週間ほどすごした。
肋骨が折れてたのに走っていたことを自嘲気味に友だちに話すなどした。

炬燵は心を解かすもの
寮にはこたつがあった。
寮の空気が荒んでいなかったなら、私も先輩たちとこたつで暖を取りながら、楽しく話したりしたのだろうか。
本当ならば、こうだった。
本来ならば、そうだった。
そんな言葉は虚しいだけだ。
鍋は楽しく囲むもの。
出汁昆布は鍋をおいしくするもの。
ドレッシングは野菜を手軽に摂りやすくするもの。
将棋盤は将棋を指すためのもの。
そして、こたつは私たちの冷えた心を解かすものだった。
ある夜、上級生たち4人に不穏な動きがあった。
3室では、誰もがつらいはずのブラッドスポーツが、惰性だけで行われている気配がした。
私は蚊帳の外だった。
残酷な夜と絶望の昼があった。
ある時は傍観者で、ある時はアナグマいじめのアナグマだった。
そうして私の心は冷え切って、感情らしきものが希薄になっていた。
私たちの居室の畳のように、清々しい虚無が姿勢を正して私の側で寝息を立てていた。目を見開いて。
夜の薄闇の中で、廊下側の障子におばけのような存在を感じて、身動きできなかったことがあった。
あの恐怖、気配の正体を私は知らない。
そしてある夜、4人が足音を忍ばせながら廊下を歩いていた。
私の居室の前を通り過ぎて、私は安堵したと思う。
Aくんが、廊下の壁に立て掛けたこたつの足をくるくると回して本体から外そうとしていた。
錆びた音が、死にかけの猿のように悲しく響いた。
本体から抜いた金属製のこたつの足を、Wくんに手渡すのが見えた。
ゆっくりと手渡されたバトンの無情な重みを、私もなぜか感じることができた。
影絵のように、不思議に美しいその光景を布団の中でそっと見ていた。
まつ毛を鉄の檻にして。
彼らはノックした。
しばらくの沈黙のあと、ドアが開かれた。
こたつは、私たちの冷えた心を解かすはずのものだった。
決して、誰かを傷つけるための凶器ではなかった。
夜の底で鈍く響く音が、布団に潜り込む私に追い縋り、耳元で聴こえた。

羊角の蛇神像⑱へ続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
