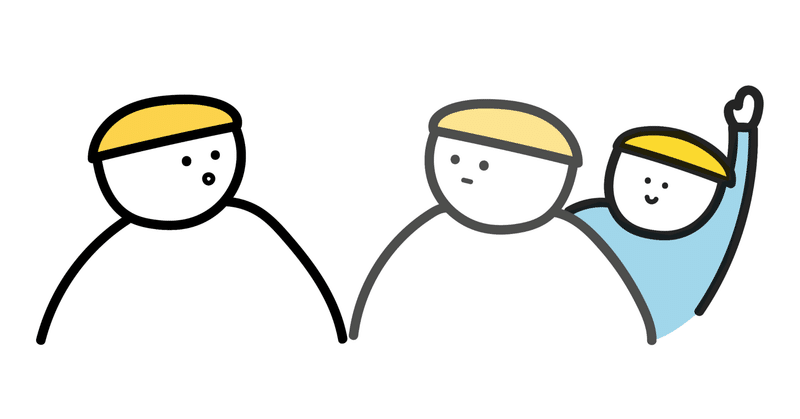
哲学カフェにはどんな意義があるのか?
レタスでは毎月1回、金曜夜、Rethink cafeという名の「ゆるい」哲学カフェを開催しています。
2022年2月から始めて、11月で21回目!楽しく続けています。リピーターさんも少しずつ増えていて有難い限りです。
◆過去開催したテーマの例◆
・この世以外のことを考える
・なぜ自分を傷つけるのか?
・なぜ『一汁一菜』に多くの人が感動したのか?
・AIが進化する中で、人間は何をするようになるのか?
・令和版 理想の読書感想文とは?
・ネガティブ思考がもたらす良いこととは?
(そのほかのテーマはこちら)
今回は活動のふりかえりを兼ねて、哲学カフェの意義はどんなところにあるのか、併せて考えたいと思います。
Rethink cafeで大事にしていること
日常生活には「こうあるべき」という暗黙知が溢れています。何かに取り組む時には、みんなが○○しているからといった理由で選択することも多く、「正解」を求める傾向が強いと思います。情報が溢れる中で、本当にこれで良いのか?と吟味する機会や、他の人とフラットに話す機会も少ないのではないでしょうか。
そんな問題意識から、普段ならスルーしてしまうようなこと、日常の身近なテーマについて、ちょっと立ち止まって考える時間を作るために開催しています。
また、同じテーマであっても人によって疑問に思うところ、ひっかかりポイントは様々です。だからこそ、言葉にすることで誰かの考えるヒントになることもあり、そういった他者との違いを感じ、楽しむことも大事だと考えています。
そして、答えを出すことは重視していません。1時間という短い時間ということもあり、まだ話したいな、もやもや残っているんだけどな…と思うこともあります。でも、そのもやもやを抱えながら明日からまた考えるきっかけになれば良いのです。これも大事にしていることです。
哲学カフェに関する研究
いろんな方と話をしたり、情報を見聞きしたりするなかで、最近哲学カフェ(哲学対話)って人気だなと思いました。
Rethink cafeに参加してくださった方に参加理由を尋ねると、「何度か哲学カフェに参加したことがある」「いろんな人と対話する時間を持ちたくて参加した」「哲学カフェを主催している」という方は何人もいらっしゃいます。
「哲学」に興味があるのか?いろんな人と対話したいのか?考えることが好きなのか?いろんな仮説が考えられます。
レタスはワークショップの開催以外にも、心理学の知見を活かした効果検証を事業の1つとして行っています。スタッフもそれぞれ自分が課題として捉えている領域の研究をしています。
そこで、自分たちの活動をふりかえるための材料として、学術的には哲学カフェをどのように捉えているのか、どんなことが研究されているのかを折角なので調べてみました。そのうち、印象に残った4つの研究を紹介します。
①授業の在り方としての哲学対話
大学生と小学生それぞれを対象に、「どうして勉強しなきゃいけないの?」という問いで哲学対話をすることで学習動機づけに与える効果を検証した研究があります(三和・青山・解良・山本,2022)。小学生の結果は「生活における価値(勉強ができれば、普段の生活に役に立つと思う)」のみ向上することがわかりました。
この結果だけですべてはわかりませんが、哲学対話は「生活」にまつわる問いを考える時には相性が良いのかもしれません。
②ケアの側面
緩和ケア専門看護師、がん患者とその家族との哲学対話の実践から哲学対話のケア的側面を考察したものもあります(高橋,2017)。死を前にした患者の苦悩を聞くこと、対話することは「アセスメント」のプロセスではなく、それ自体がケア、スピリチュアルケア的な意味を持っていると示唆されています。
自助グループ、サポートグループがあるように、同じ悩みを抱える人たちが集まって対話することが治療的な効果をもつことは納得できます。治療者(上記の研究だと緩和ケア専門看護師)にとって、アセスメント目的で患者や家族と対話することはできますが、そのような構造化された面接の場以外で見られる言動(ノンバーバルな様子も含む)も、相手を理解するうえではとても重要です。
デイケアのような生活の延長に位置するところで働いていると、日常のやりとりがケア的な関わりになっている、むしろその時間をケアとして活かせないかと考えることもあったなと思い出しました。
③公共性のある手法
森本(2013)によると、「生存確認のために来た」と冗談を言って参加している90代の参加者、普段は何も考えずぼーっとしているが哲学カフェに参加する時だけは昔と同じように頭が回転していると話す70代の参加者の言葉を例に、セーフティネットとしての哲学カフェの機能を考察しています。
確かに、バックグラウンドは知らないけどこの時間だけ出会う人という点で、公共性のある場として機能していそうです。定期的に考える時間として参加する、よく見る顔ぶれと一緒に考えたくて参加する、そんなつながりを意識する機能はあると思います。
④よくあるルールの功罪
「発言しなくてもOK」とする態度を検討した桂ノ口(2019)によると、「人やものごとを不可視化せずに問い考える」点が哲学対話の特徴だと主張しています。
オンラインだと特に感じますが、「発言していない=考えている」とは限りません。勿論1人1人が考えることは大事なものの、一緒に考えることも大事にしたいです。
もし、聞き専でチャットにもリアクションがない人が参加していた場合、発言している人からすると、相手からどう思われているのかと不安や怖さを感じることも考えられます。
発言が少なくなっている?と感じた場合、その人がどこにひっかかって考えが止まっているのかを少しだけ言葉にしてもらうことで、考えの一部を知ることができます。そこから、別の人の思考が拡がっていくことも考えられます。また、もやもやしているのに言うタイミングを逃しているのなら、その人にも言える時間を作ることで、その場にいる全員が一緒に考えることができます。思考の邪魔はしたくないですが、言葉にすることでみんなと一緒に考えることを大事にしたいという考えを言語化してもらった気がします。
毎月続けたことによる変化
哲学カフェという場を開くこと、そこで出会った人たちと対話することから感じた変化が2つあります。
1つは、日常生活で自分のひっかかりポイントがないか探すようになったこと。
本を読みながら、動画を視聴しながら、これってどういうことなんだろう?Rethink cafeのテーマにしたらどんな話ができるだろう?
そんなことを考えながらインプットするようになり、だらだら情報を取り込むことは随分減りました。
もう1つは、自分のひっかかりポイントにはグラデーションがあると気づいたこと。
今夏からリピーターの方と一緒に、翌月のテーマを考えるようになりました。(手伝っていただけて本当有難いです!)
その打ち合わせで、最近もやもやしたこと、考えていることを共有すると、みんなの考えているポイントが全然違うことを実感します。それがまた面白い。
自分がそこそこ衝撃を受けた体験にインスパイアされたテーマを提案することもあれば、提案してみたものの意外と「話が深まらないかも」と付くこともあります。自分のひっかかりにもグラデーションがあることを感じられる時間でもあります。
まずはひっかかりを探すことから
”正解を求める傾向がある”という問題意識を冒頭紹介しましたが、正解ありきで生きていくと、自分のひっかかりに気づけなくなってしまいます。
この記事を執筆している三宅の体験を少し話すと、開催当初は自分のひっかかりがいかに少ないか、ということを突き付けられることが多かったです。レタスで活動する前から、自分は正解至上主義に染まってしまった、それではまずいと気付かされた体験がありました。それに気づいてからは、何とかしようとチャレンジしてきたつもりでしたが、テーマが全然思い浮かばない事実を目の当たりにすると、そんなに自分は考えずに生きているのかと悔しくなることもありました。今でもそう思う。(考えすぎはしんどくなるので休息は大事。それにしてもな…という感覚が自分の体験としては強かったのでした)
ようやく、自分なりの価値観、倫理観、大事にしたいこと、そういうものが見えてきました。輪郭が見えてくると、ひっかかりポイントと出会いやすくなりました。なぜ怒りを覚えているのか?それは自分の大事にしたいことに反するからだ、というような感じで。
哲学カフェが人気な理由の1つに、普段話さない人と対話することも挙げられると思います。対話する時間は、発見が多くて私も面白いと感じます。でも、自分のひっかかりがわかっていないと、結果ふわふわした議論で終わるのではないかと思うこともあります。
だから、まずは自分のひっかかりを探すことから始める。そのためには、日常に溢れる情報、スルーしてしまうような出来事についてちょっと立ち止まって考える。「哲学する」「ひっかかりを探す」ための入口の場としての役割を果たせたらいいなと思います。
お知らせ
11月は、明後日17日(金)21時~開催します。
今回のテーマは、『謝るとは何をすることなのか?』
詳細はこちらをご覧ください。
過去の活動報告はFacebookよりご覧いただけます。
ちょっとでも興味を持っていただけたら、ぜひご参加ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
