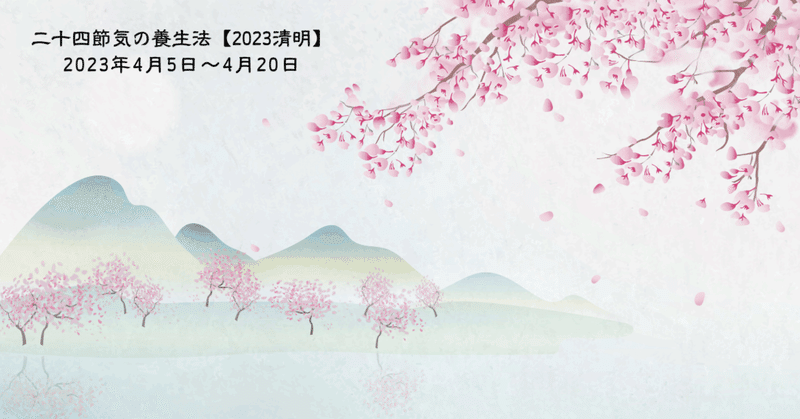
二十四節気の養生法【2023 清明】
今日から二十四節気「清明(せいめい)」ですね。清浄明潔の略で「空気は澄んで、陽光は明るく万物を照らし、全てがはっきりと鮮やかに見える」頃という意味で、 暦便覧には「万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれる也」とあります。日本では、春分の日(お彼岸)にお墓参りに行きますが、中国や台湾、沖縄などでは「清明」の日にお墓にお参りして先祖を敬うそうです。 北宋に描かれた「清明上河図」は、春たけなわの頃の賑わい栄えた様子が描かれています。朝晩はヒンヤリ涼しい日もありますが、日中は気温も上がって来て過ごしやすくなってきました。

中国では、春節、中秋節、端午節と清明節が伝統的な祝日とされます。またこの日は中国では「寒食節」とも言われ、火を使った料理を口にしてはならず冷たい物しか食べてはいけない日だそうです。決して冷たい物は口にしないという中国では珍しい日ですね。2600年も前からいわれのある行事で、昔は清明節の1日前で冬至の翌日から数えて105日目で「百五節」とも言うそうです。冷たい物を食べるというかこの日は日を使ってはいけない日ということで、実際には事前に十分に火を通して調理した物を、つめたいまま食べる習慣になったそうです。寒食節の伝説や風習を知ると、やはり中国の歴史は長いですね。
今月の癒しの庭園 「平安神宮 神苑」
各地で桜が満開ですね。今年は開花が早かったので、もう見ごろが済んで葉桜のところもあるようです。京都は桜の名所も多いのでどこにしようか悩みましたが、今月の「癒しの庭園」は『平安神宮 神苑』をご案内します。
平安神宮は平安遷都1100年を記念して、明治28年に創建された京都では比較的新しい神社ですが、神苑は明治の有名な造園家7代目小川治兵衛らによって平安京千年の造園技法の粋を結集して、社殿を囲む東・中・西・南の四つの庭がつくられ、春の紅しだれ桜、初夏の杜若・花菖蒲、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々どの季節に訪れても風光明媚な趣を見せてくれます。

平安神宮の正門応天門をくぐると白虎と蒼龍が迎えてくれます。


太極殿の左手に神苑入り口があります。南神苑、西神苑、中神苑、東神苑と広大なお庭が広がります。

受付を済ませ南神苑に入るとすぐに満開の八重紅枝垂桜がありますが、これは近衛家伝来の「糸桜」を津軽藩主が持ち帰り育てた桜が平安神宮創建時に仙台市長から寄贈されたそうで「里帰り桜」とも呼ばれ、谷崎潤一郎の「細雪」にも登場する京都の春を象徴する桜だそうです。

チンチン電車と呼んでいた、私たちの世代には懐かしい京都の市電が飾られています。

七代目小川治兵衛が手掛けた、龍が臥す姿を象った「臥龍橋」石材は、前回京都迎賓館の池にもあったのと同じ、天正十七年豊臣秀吉が造営した三条大橋と五条大橋の橋脚に使われたもの。以前は通れたそうで、この上を歩く人は「龍の背にのって池に映る空の雲間を舞うような気分」を味わっていただく」という小川治兵衛の作庭の意図が織り込まれています。
中神苑にある白虎池には6月になると「八ツ橋」が架かり一面を紫や白の花菖蒲が見事に咲き競います。

東神苑の栖鳳池から満開の桜越しに見た大平閣(橋殿)。向こうには東山連峰の華頂山を借景とした雄大な眺めが広がります。

大平閣(橋殿)の屋根の上には鳳凰が飾られています。
橋の中で腰を掛けて休んでいると穏やかな春の陽光に風が心地良く吹いてきます。小鳥のさえずる声にも癒されます。

大平閣(橋殿)から見ると栖鳳池の向こうに貴賓館尚美館があり、その横にも満開の紅八重枝垂桜がこの季節の絶景です。

一つ一つが可憐な桜の花。火袋の窓に蒼龍・朱雀・白虎・ 玄武の四神をあしらった釣灯籠も朱色の柱に映え厳かな趣。

平安神宮を出て岡崎公園から東山を見ると満開の桜越しに大文字山もくっきり。

岡崎の琵琶湖疎水の上にかかる慶流橋から東山の眺め。春爛漫の琵琶湖疎水をゆっくり巡る十石舟。のどかで風情がありますね。

お花見は行かれましたか?普段気づかないところにも満開になると、こんなとこにも桜があったんだと気づかされます。満開に咲く桜を見ると気分が穏やかに安らぎますね。やはりこの季節には日本に生まれて良かったなぁと思います。美味しいお弁当を持ってお花見に出かけてくださいね。
清明の養生法
さて、いよいよ新年度もスタートして、入社や入学、転勤などで環境が大きく変わる人もいらっしゃいますね。新しい出会いにウキウキする人もいますが、逆に不安になったり、引っ込み思案になったりする人もいます。
春の季節病ともいえる「木の芽時」や「五月病」など、人間も情緒が不安定になりやすい時期です。最近では「木の芽立ち症候群」などという病名もあるようですね。
陰陽五行の観点から春は肝が傷みやすい季節です。怒りやイライラなどストレスによって肝は傷められます。肝がストレスによって傷められると気が伸び伸びと全身に巡らなくなって鬱(肝鬱気滞)になったり、地面からメラメラと陽気が立ち昇るように春の肝気は上に上がり(肝陽上亢)、上昇し過ぎて興奮状態(肝火上炎)になります。
特に春は、セカセカしたり焦ってイライラしないよう心掛けましょう。この春の養生法を「疏肝理気」と言います。出来るだけココロを穏やかに保ち気の巡りを調えて肝を労わって過ごすようにしましょう。
女性の三大要薬
中医学では、女性の三大要薬と言われる漢方薬があります。
「23番、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」「24番、加味逍遥散(かみしょうようさん)」「25番、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」の3つで、聞いたことがあるかも知れませんし、もう飲んでるという方もいるかもですね。番号で表されることが多い漢方薬ですが、3つ連なって並んだこの漢方薬は、女性の不調や未病にはこの3つの漢方薬のどれかがあてはまると言われるほどです。

「23番、当帰芍薬散」は、血虚で冷え症、むくみ(水滞)タイプ。虚証で血を補する補血利湿薬。
「24番、加味逍遙散」は、ストレスで気滞、イライラ、怒りっぽい、ストレスで過食や少食になったり、胃炎や下痢などお腹が弱いタイプ。肝と脾を調える調和肝脾薬。
「25番、桂枝茯苓丸」は、肩こりや頭痛、生理痛などの血の巡りが悪い瘀血や足は冷えるのに汗がダラダラというような更年期など。実証で血を瀉する活血化瘀薬。
24番、加味逍遙散がオススメなのはどんな体質?

今回は、春で肝鬱を起こしやすい季節なので加味逍遙散についてお話ししたいと思います。
加味逍遙散は、逍遙散という漢方薬(当帰・芍薬・白朮・茯苓・柴胡・甘草・生姜・薄荷)に牡丹皮・山梔子が加えられた漢方薬です。
加味逍遙散を必要とする体質は、ストレスが溜まり肝鬱気滞になって、それが肝木剋脾土(相乗)となり胃腸を傷めるので機能性胃腸炎や下痢、過敏性腸症候群、食欲不振、消化不良など脾気虚となり、さらに進んで気血生化が出来なくなって血虚となりめまい、ふらつき、生理不順などが起こり、さらに精神不安や情緒不安定などを起こすタイプの方です。

起こりやすい症状は?
ストレスフルな毎日で煩躁(イライラ)、ほてりやのぼせ、怒りっぽい、心身疲労、ストレスによる過食や少食など食欲の乱れ、片頭痛、頭痛、不眠、脇肋痛(脇腹の脹痛)、生理痛や生理不順、月経前症候群(生理前の胸の脹痛、生理前の下腹部痛など)、めまいやふらつき、ゲップやオナラが多い、ため息をよくつくなど。
中医学の治療法は?
治療原則は疏肝解鬱、補脾気、養肝養血柔を行い肝脾を調和する。
漢方薬を薬膳で応援する
どんな薬膳茶や薬膳料理でも同じですが、1回や2回、薬膳茶や薬膳料理を飲んだり食べたりしただけで、痛いツライしんどいといった症状が消えてなくなることはありません。
薬膳茶や薬膳料理などは、しんどい症状があれば西洋医学にしろ中医学にしろ西洋薬(新薬)や漢方薬など専門医の診断をもとに処方されている薬がある場合は、それを応援する薬膳茶や薬膳料理を摂るという考え方です。
例えば、病院で「風邪(かぜ)」と診断されて風邪薬を処方されている場合、
中医学では、いわゆる風邪(かぜ)のことを「感冒」と言いますが、「風寒のかぜ」、「風熱のかぜ」など、ひと口に風邪(かぜ)と言ってもその元になる体質はいろいろです。
そして風寒の風邪(かぜ)の場合は辛温解表(しんおんげひょう)という治療法で主に麻黄湯(悪寒無汗)や桂枝湯(悪寒有汗)などカラダを温めて風邪(ふうじゃ)と寒邪を散らして治療します。
一方風熱の風邪(かぜ)の場合は辛涼解表(しんりょうげひょう)という治療法となりこの場合は銀翹散など風邪(ふうじゃ)を透し熱邪を冷まして治療します。
この体質の時に応援する薬膳茶や薬膳料理は、同じ風邪(かぜ)と言っても異なるのです。
風寒の風邪(かぜ)は、悪寒がひどくカラダを温めてもゾクゾクするといった症状で治法はカラダを温める薬で発汗させて風邪(ふうじゃ)を追い出します。
その時に飲んだ方が良い薬膳茶や薬膳料理(に限らず口にするもの全てですが)は、カラダを温める性質を持った物を摂った方が飲んだ薬を応援し効き目が増し早く治るということです。
逆に言うと、せっかくカラダを温めて発汗させて風邪(ふうじゃ)を追い出す薬を飲んでいるのに、アイスクリームやかき氷を食べたりビールを飲んだり(…なんていう人はいないでしょうし、またカラダも欲していないと思いますが…)、きゅうりやスイカ、なす、トマトなどカラダを冷やす性質の物を食べるのは薬の効き目を邪魔していることになり治りにくくなるのです。薬膳的な考えから行くとこの場合は、温熱性の性質を持った物が薬を応援する食材で、さらに咳が出るなら肺に帰経する食材、お腹が弱っているなら脾胃に帰経する食材がオススメということになります。
一方、風熱の風邪(かぜ)の場合は、高熱が出て、氷枕などで冷やしても熱が下がらず着ているものを全部脱いでも熱い、氷の入った冷たい物を飲みたい、喉が渇くなどの症状の時は、辛涼解表薬で風熱を冷ます薬を飲みますが、こんな時に生姜やネギ、羊肉やシナモンなどを食べたり、紅茶やお酒を飲んだりすると症状が治るどころか増々ひどくなりますね。
風寒の風邪(かぜ)で辛温解表薬を処方されて飲んでいる場合は、シナモン紅茶や生姜紅茶などで応援する。
風熱の風邪(かぜ)で辛涼解表薬を処方されている場合は、緑茶やトマトジュースなどで応援する、という感じで考えます。
寝込まなければいけないほどの症状がある場合は、どんなものも欲しくないほどに体力も気力も消耗しているでしょうから、しっかり寝ることが一番の薬だと言えますが、寝てられないとか寝込むほどの症状じゃない場合は、何か飲みたいなと思った時には、カラダのバランスを立て直す作用の物を選んで摂ることが大切です。
これが「薬膳」の基本的な考え方になります。
「私にオススメの薬膳茶はどれですか?」という質問を良く受けますが、今貴女の体質がどのようにバランスを乱しているのかがわからないと、おすすめの薬膳茶や食材は分かりません。「カラダの声」や「カラダからのお便り」」を良く観察して、今の自分のカラダがどのようにバランスを乱しているのかを把握し、それを立て直す作用のあるものを摂りましょう。
「なんか飲みたいな、とりあえずお茶でも」とか「コーヒーでも飲もかな」ではなく(どうしてもお茶やコーヒーが飲みたいのなら飲めばいいのですが)、なんでもいいというのならやはりカラダのバランスの乱れを少しでも調えてくれる作用のあるものを選んで摂ることがオススメなのです。
加味逍遙散タイプにオススメの薬膳
加味逍遙散が必要な人はストレスやイライラで肝が傷んで疏泄作用が低下し気の巡りが滞っているので、治療法は疏肝解鬱、補脾気、養肝養血でした。それなら食材なども同じ作用や効果があるものを選ぶと、より薬の効き目を発揮することが出来るということです。
食材では、
疏肝解鬱作用のあるもの
そば、あわ、エンドウ豆、なた豆、らっきょう、きゅうり、なす、トマト、苦瓜、大根、白菜、たけのこ、へちま、かぶ、ごぼう、里いも、からし菜、春菊、セロリ、セリ、スイカ、梨、ミカン、オレンジ、豆腐、ジャスミン、山査子、桑の実、緑豆、陳皮、緑茶など。
ポン酢や柚子、スダチ、レモン、オレンジなど柑橘系の味付けや大葉、三つ葉、香菜(パクチー)、みょうがなどの沿え野菜もオススメです。
補脾気作用のあるもの
うるち米、にんじん、長いも、じゃがいも、ぶどう、ライチ、落花生、栗、干ししいたけ、豚ハツ、鶏肉、牛肉、白身魚、イカ、蓮の実、なつめ、竜眼、百合など。
養肝養血の作用のあるもの
米、にんじん、ほうれん草、小松菜、やま芋、ジャガイモ、かぼちゃ、キャベツ、カリフラワー、インゲン豆、干ししいたけ、落花生、ぶどう、ライチ、ひじき、豚レバー、豚ハツ、イカ、タコ、赤貝、なつめ、竜眼、枸杞の実、金針菜、紅花など。
薬膳茶は
ジャスミン茶、柑橘系(柚子、レモン、オレンジ、スダチ)、マイカイ花、陳皮、桂花などをブレンドした薬膳茶など。

加味逍遙散が必要なタイプは、逍遙散タイプにプラスして便秘やニキビ、不眠など少し熱がこもってきているので、特に寒涼性で清熱出来るものを多めにとるのがオススメで、そこまでいってなかったり冷えを感じると言う人は温熱性がオススメになります。
疏肝解鬱はどちらかというと寒涼性がオススメになり、補脾気や養肝養血は平性または温熱性がオススメの食材が多いので、特に自分の体質が陽盛(熱がこもるタイプ)か陽虚(冷えを感じるタイプ)かどちらに傾いているのかをみて多めに摂るものを調整しましょう。
あまり極端に寒涼性ばかりや逆に温熱性ばかりを摂りすぎると、反対側にバランスを乱してしまうので少しずつ体調を見ながら加減していくのがオススメです。
薬の治療が必要な人も、まだそこまではいってないけど、イライラしたりストレスが多いなと感じる人は「未病」(黄色信号)にあるので、早めに薬膳で赤信号になる前に青信号に戻るように調えることが大切です。
毎日をリラックスして穏やかに過ごす
前にも書きましたが、生活習慣や生活環境のテーマは「リラックス」
どれだけリラックスして過ごせるかが大切なポイントになります。
リラックス出来る音楽を聴いたりリラックスする風景を見たり、ぬるめのお湯で半身浴、アロマやお香、リラックスできる服装で過ごす、ちょっと美味しいものを食べる、夕食はお粥など消化の良いものを食べる。早めに灯りを暗くしてスマホやパソコンなどは遅くまで見ないように心掛け、ストレッチやヨガでココロとカラダの緊張をほぐし、質の良い睡眠をとりましょう。
反対に、セカセカしない、分刻みで行動しない、イライラしない、カリカリしない、ムカムカしない、激辛、高カロリー、深酒、カフェインは避ける、特に寝る直前に胃に固形物は入れない、ベッドや布団に入ってからあまり物事を考えないなど出来るだけ神経を逆立てないようにして過ごすようににし、ハッピーホルモンと言われるオキシトシンがたっぷり分泌されるよう心掛けましょう

京都伝統中医学研究所の"清明におすすめの薬膳茶&薬膳食材"
1.「疏肝解鬱」におすすめ薬膳茶&食材
薬膳茶では、「気血巡茶」「理気明目茶」「麗香龍珠茶」「茉莉龍珠茶」「五望茶」「全部食べる薬膳茶 桑の実茶」「酸梅湯」など。
薬膳食材では、「山査子」「桑の実」「緑豆」「菊花」「マイカイ花」など。
2.「補脾気」におすすめ薬膳茶&食材
薬膳茶では、「そろそろダイエット茶」「プレママ応援健やか茶」「なつめ薬膳茶」「からだを温める黒のお茶」「なつめと生姜委のチャイ」「全部食べる薬膳茶 桂棗黒豆茶」「全部食べる薬膳茶 意棗紅豆茶」など。
薬膳食材では、「なつめ」「竜眼」「はと麦」「白きくらげ」「百合」など。
「いろいろお豆のスィーツセット」「白キクラゲのスィーツセット」
3.「養肝養血」におすすめ薬膳茶&食材
薬膳茶では、「増血美肌茶」「なつめ薬膳茶」
薬膳食材では、「金針菜」「枸杞の実」「黒きくらげ」「紅花」
薬膳スープ「四物湯スープセット」
中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。
薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。
薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式サイト正式オープンhttps://www.kyotorakurakudo.com
京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/
京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/
次回は、4月20日「穀雨」ですね。生温かい雨が穀物を育てる季節。日本のアチコチでは田植えの季節ですね♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
