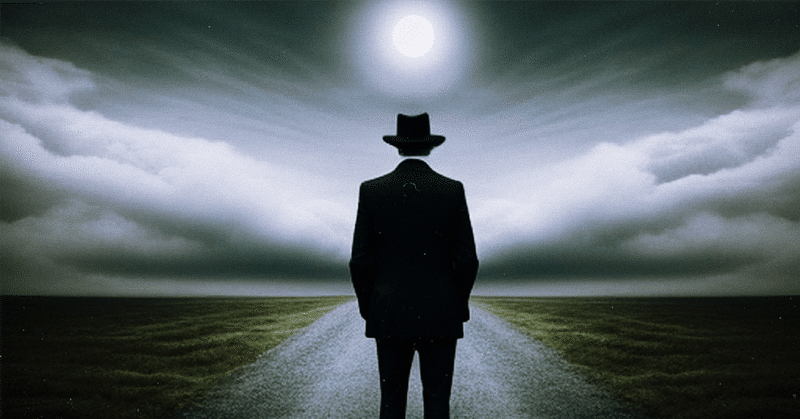
A Iが支配する、不確実性の増す世界。ではクリエイターはどう生きるのか
昨年は、生成AIが大きな話題でした。
これから世界はどうなるのでしょうか。
元Wiredの創刊編集長のケヴィン・ケリー氏は、これから「ミラーワールド」が訪れる、と言っています。彼は多くのIT起業家たちのインタビューを行ってきました。
そして実はこの本、私がアサヒパソコン時代にお隣の「PASO」の編集長だった服部桂さんが関わっています(読んで知った!)。
筆者の主張はこんな感じです。
AIなどのテクノロジーが進むと、これからは仕事の仕方が大きく変わると言われています。私の目に見えている未来は、いろいろなところで、百万人単位の人たちが一つのプロジェクトで同時に一緒に働くことが可能になるというものです。
ミラーワールドについて詳しく知りたい方は、Wiredの以下の記事がわかりやすいです。
ミラーワールドの建設はすでに始まっており、世界中のテック企業の科学者やエンジニアたちが、現実世界に重ねるヴァーチャル世界を建設しようとしのぎを削っている。何より重要なのは、こうして現れつつあるデジタル版ランドスケープが、本物のように感じられることだ──つまり、ランドスケープ設計者が言うところの「placeness(場所らしさ)」がある。Google Mapのストリートビューの画像はただ平面のイメージが連なったファサードだ。
ちょっとVRに似ていますが、注目されているのはARを使った技術ってことっぽいですね。
つまり、ポケモンGOで使われたような、現実世界にバーチャルを重ね合わせる技術です。今、Googleレンズを使うと、植物の名前を教えてくれたり、知らない言葉を自国語に翻訳してくれたりしますよね。あの延長です。
すでにインターネットの世界では、巨大コミュニティが生まれていますが、それがさらに拡張するイメージでしょうか。
例えばプログラミングの世界では、ギットハブやスタック・オーバーフローと呼ばれるコミュニティサイトで、協働するのが当たり前になっています。
ゲームの世界も同様です。今や世界中で大流行しているのがオンラインのチェス。チェスの世界的プレーヤーたちがYouTubeやTwitchなどで配信し始め、国境を跨いで絶大な人気を誇っています。
先日、ニュージーランドの藤井巌さんとお話ししたら、最近では大学間の共同研究が当たり前になっていて、例えば、ニュージーランドとデンマーク、アメリカの大学で、ネットで共同研究するのだそう。
協働の時代になりましたね。
クリエイターとしてどう働くか
ここから先は
これまで数百件を超えるサポート、ありがとうございました。今は500円のマガジンの定期購読者が750人を超えました。お気持ちだけで嬉しいです。文章を読んで元気になっていただければ。

