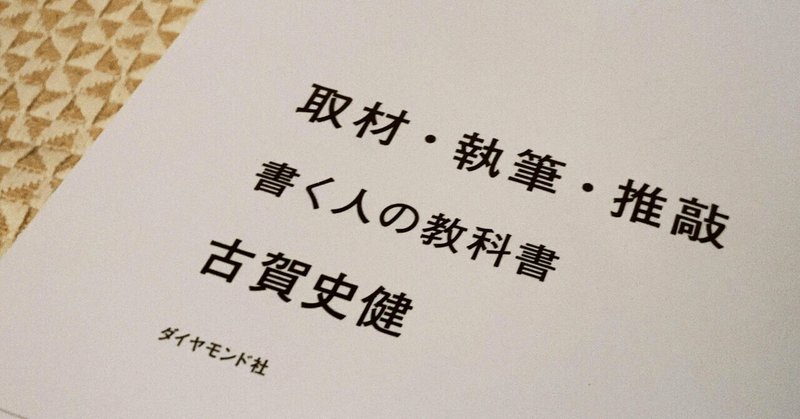
【読む】取材・執筆・推敲 書く人の教科書
もっと早く出会っていたかった。そんな1冊が先日、発売となった。
『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』(著・古賀 史健)だ。
先にお伝えするとまだ通読できていない。ビジネス書の中でもかなりボリュームのある一冊で、それでいうとまだけっこう序盤のところだ。でも現時点で「この1冊とはもっと早く出会いたかった…!」と心から思っている自分がいる。
いつもなら読み終えた本を紹介するところを、今日は例外として書き始めてしまっている。そして、もしかしたらこの先も何回か引用したり紹介したりするかもしれない、そのくらいにもうすでにこの一冊をすっかり信用している。
「もっと早く出会いたかった」というのは、素人ながら『取材・執筆・推敲』を手探りで行ってきたこの数ヶ月があったからだ。
ZINEをつくろうと決めて「農」にまつわる4組の方に「取材」をし、インタビューパートはもちろんのことエッセイパートも含めてすべて自分で「執筆」をし、ここ2週間くらいはひたすら「推敲」をしていた。誰かに教わった経験がないので、完全に見よう見まねでやってきた。
この経験を通じて、2つのことを思った。
1つは「もっとうまくなりたい」ということ。
取材やインタビューって奥が深いと思った。そして「書く」ということも。
最初に自転車にまたがったとき、全然うまく乗れない子供が悔しがるみたいに僕は「インタビューがもっとうまくなりたい」「もっと文章がうまくなりたい」と素直に思った。そこに打算とかはない。あったのは、すがすがしい悔しさと、難しさというおもしろさだった。
そして同時にもう1つのことを思った。
「でもどうやって学べばいいだろうか?」ということを。
ライターの学校もあるのだろうけど、もう少し手軽に基本を学べるものがあればと思った。そうすれば、「勉強」と「実践」のサイクルを回していけるのに…本屋には文章術の本がたくさんあるが何故だかピンとくるものがなかった。取材と執筆の両方のことが書いてある本も案外少なかった。
そのタイミングで本書が世に生み出された。
「これ!!」って思った。
「もう、これを待ってた!!」って。
著者の古賀さんが「ライターの学校」をつくろうとしているみたいで、そこで教えたいことをギュッと1冊に凝縮したのが本書だと後から知って納得した。「これ1冊を読めば大丈夫」感は、まさに教科書のあの感じに似ていた(でも単なるノウハウ本ではないことを念のため付け加えておきたい。まえがきを読んでいただけると分かるのだが、かなり熱い本だ。)
まだ読み始めたばかりだが、早速1つを実践している。
それは読書をするときに「この人に今度インタビューするつもりで読んでいく」というものだ。確かに、今回のZINEづくりでもインタビュー前にいろいろとその方にまつわるテキストを読んだが、ただ読むのと、今度インタビューすると思って「何を聞こうか」と読むのとでは、全然入ってくるものが違った経験がある。
僕の場合は実際にインタビューする予定があった人だが、これをインタビュー予定のない人の本でも実践してみるというのが発見だった。トルストイでもいいし、村上春樹でもいい。もちろんビジネス界隈だともっと考えやすいかもしれない。
例えば明日ユニクロの柳井正さんにインタビューすることになったら…それはもう…本気で柳井さんの本を読むだろう。
つまりは「問い」を持ちながら読むということなのだろうけど、実際に取材するようにと言われた方がグッとリアルになって緊張感が増す。本だけではなく、TVのドキュメンタリー番組でもいいかもしれないし、誰かの講演会でもいいかもしれない。
今日からできるトレーニングとして実践してみようと思った。
例えばこんな風に具体的に学ぶことがたくさんある。
インタビューはこれからも本業と関係なくてもやっていきたいと思っているので、この1冊は何度も読み返すことになるだろう。受験生のように何度もボロボロになるまで。
☟気になる方はぜひ!
1冊ができるまで日記 : 21/04/10
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
