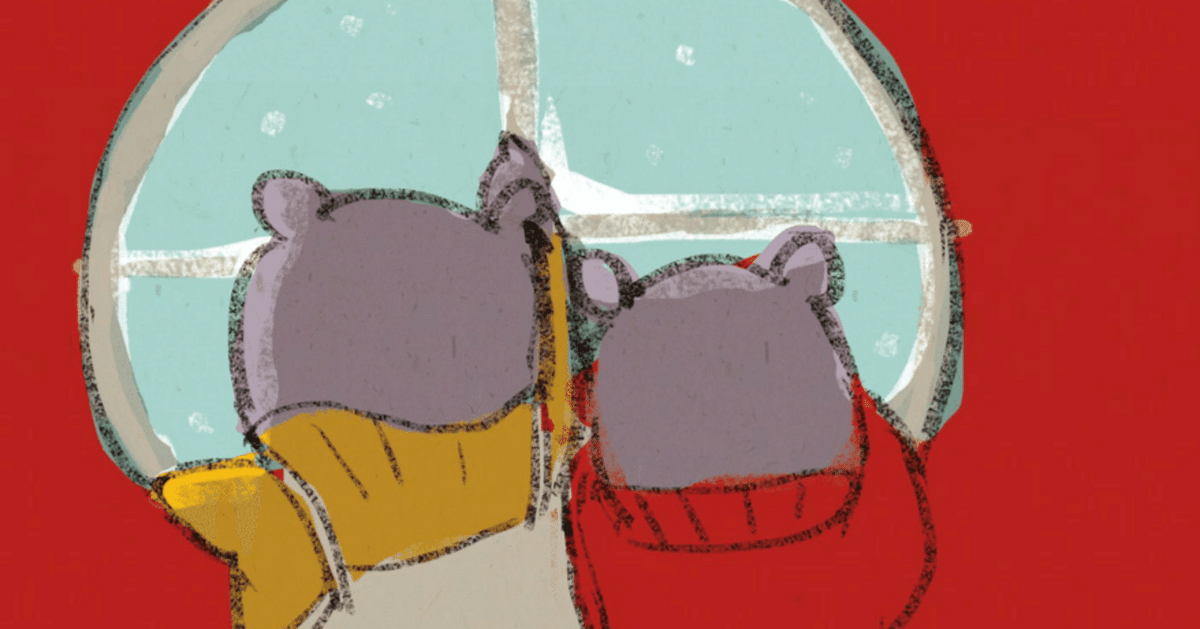
まだ閉じないでと願いながら《140字小説:2024年6月分②》
X(旧ツイッター)で書いた140字小説をまとめたものです。
猫が集会に行く準備をしている。「そういえば犬の集会って聞かないな」「そりゃ今じゃ、野良犬は少なくなりましたからね。集会かけるのは大体が野良なんでさぁ。野犬がいた頃なんて酷かったですぜ。よくドンパチやったもんです」「何か楽しそう」
猫が出かけた。仲間を呼ぶため、まずは遠吠えだワン!
『犬の集会』
池の中からオタマジャクシが顔を出し復讐を手伝ってくれと言った。「何への復讐ですか?」「私達の父が殺されました。きっとヤゴの親です。あいつらは凶暴です。兄弟も食われました」「善処する」池の中の子達は、池の外で立場が逆転することを知らないのだ。まあ、蛙は俺が車で轢いちまったんだけど。
『池の中のオタマジャクシ』
スカイドクターフィッシュは空中を泳ぐので、顔や身体の角質も食べさせることができる。自宅の一室で独り占めしていたが、うっかり外に逃がしてしまった。動きは素早く風のように過ぎ去る。貴方の側を旋風が横切って、肌がつるりとすることがあれば、それはスカイドクターフィッシュが通った後である。
『スカイドクターフィッシュ』
電車内の扉の前に立つ男は、停車駅で扉が開くと同時に、ザザッと一瞬右に動いた。乗車する人はいない。その後何事もなかったように男だけ降車した。見えない何かがいたのだろうか。よく見ると扉の左側に開閉ボタンがあった。男は扉が開かないと思って右側に移動しようとしたのだ。結局はそんなものか。
『ボタンを押したのは』
子供の頃は毎日怖い夢を見た。夢の中でお化けに追いかけられ、真夜中に起きて泣き叫んでいた。母が「まずは目を瞑って」と言って、それから耳元で幸せな童話やおとぎ話を朗読してくれた。すると怖い夢は見なくなるので、安心して眠りにつけた。本当は、母は夜勤でほとんど夜中はいなかったのだけれど。
『怖くない夜』
居酒屋で鬼と飲み比べをした。相変わらず日本酒や焼酎だったので、ワインはどうかと勧めてみた。鬼はいたく気に入り、ぐびぐびと飲んだ。悪酔いし、勝負は俺の勝ち。だが報酬は保留にした。そして数十年後の今日、報酬を貰う。「儂の方が礼を言いたい」「いや、価値があるだろうよ。鬼のソムリエ本は」
『鬼にワイン』
昨夜に妖の集いを見かけた。隅にいた顔無しに何事かと尋ねた。「明日は夏至なり、百鬼夜行の計画を立てている」「日が延びるのに」「日が延びれば夕刻が、つまり逢魔時が長くなる」襲うリストを見れば、今年の新入社員の名前があった。少し困るので雨女を買収。大雨となり、夏至の夜行は中止となった。
『夏至夜行の集い』
年に1度、6月の満月を収穫し、腐らないよう保存する。月は収穫するとイチゴ程の大きさになるから100個くらいは欲しいところ。100年かけて貯まったら、砂糖と一緒に鍋で煮込んでジャムにする。
こんなに手間がかかるのにね。うちの娘ときたら、朝食で90円のトーストに雑に塗って「普通」って言うのよ。
『満月ジャム』
不眠を訴える男に薬をやった。サントマンという妖精から貰った睡眠を誘う砂だ。男はよく眠れたらしく、全て寄越せと言いに来た。幾日かして使い切ってしまい、男はその砂がないと一切眠れなくなっており、そのうち気が触れて自害した。案の定。まあ結果が確認できたから良しか。今夜はよく眠れそうだ。
『良く眠れた男』
パイロットの友人を飲みに誘った。「UFOを見たことある?」「あるわけないだろ」「宇宙人の目的が存在を知らしめるものなら、未だに円盤型にすると思うんだ」「お、おう」「でも偵察が目的なら。溶け込む。その星の乗り物に」「…あの操縦士がいなかった飛行機、まさか」やはり見たのか。ああ残念だ。
『UFOを見たか』
交差点では『通りゃんせ』が流れていた。「口減しかな、今どき」縁日に紛れ、子の手を引く老人へ声をかけた。「あれは祝いの唄だ、口減しなら七つ前が妥当だろう」「確かに。それでその子は」「捨て子だ、今どき。親元へ」老人は笑みを浮べた。「ちょいとばかし祟るだけぞ」「お供しましょう。道真公」
『天神様が参ります』
露天風呂に浸かっていると河馬が入ってきた。「流石に困ります」「何故ですか」湯から上がろうとするが、何故か出られない。段々と熱くなり、頭に血が上りそうだ。「私は河馬ではありませんよ」河馬が言った。「私は獏です」夢から覚めた。汗でドロドロだ。ああ、温泉に行きたい。週末にでも行こうか。
『露天風呂に浸かって』
真夜中の駅前で街頭演説が行われていた。もう二時近く。条例違反じゃないのか。もちろん聞いている人は誰もいない。隣の人が「流石に普通じゃない。アレに耳を貸すんじゃないぞ」と言った。じわりと冷汗が流れた。すぐに通り過ぎようとした時、聞こえてしまった。『逃げろ!危ないの、お前の隣のヤツ』
『耳を貸すな』
母は私が三つの時に亡くなった。唯一の思い出は、商店街の喫茶店でプリンパフェを食べたことだ。その喫茶店が今日で閉店すると聞き足を運んだ。フレークの上にアイスと生クリームが乗って、中央に深い黄色をした硬めのプリンがころんといる。ゆっくりと口へ運んだ。食べている間だけ、母はそこにいた。
『最後の思い出』
その扉を開けば、少女が白兎を追いかけて、カカシと旅をし、青い鳥を探し、友達のキツネに会いゆける。街頭に灯りを灯しては消すのを繰り返す、だけの大人になってしまった私でも、幻想の星々を渡る。象を丸呑みにした蟒蛇を、帽子だと言い切るようになってしまうまでは、まだ閉じないでと願いながら。
『幻想の扉を開けば』
「湿気の多いところ通ってきたな」と小豆洗いが言った。「背中に仰山憑いとるよ」と俺の背中に小豆をかけた。落ちた小豆を拾って、勿体無いから貰っていいか聞くと、「いいぞ」と言った。持参した鍋で茹でて餡子にした。外郎の代わりに三角の餅にかけて、水無月擬きにした。今年はあと半年もあるのか。
『水無月擬き』
Xで140字を投稿しています。
こちらでも読んでいただけると嬉しいです。
月町さおり:Xアカウント
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
月町さおり
サポートしていただきました費用は小説やイラストを書く資料等に活用させていただきます。
