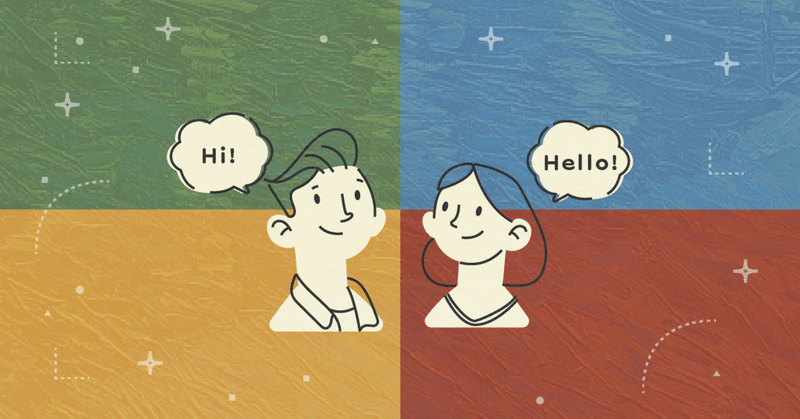
他人に誤解なく伝えるためには?
話が噛み合わないって、辛いですよね。
こんにちは、くつばこ+のうたです。怒涛のみうちゃんのnote更新が続いてますね。1年で50本を目標としていたのですが、残り年内11日の時点で41本。11日中9日も書かなきゃいけないと張り切ってますが、できるのでしょうか。ここではできると信じましょう(12/24付け)
(1/8追記 11日中10日書くという、オーバーキルを達成していました。信じてよかったです笑)
☆東工大生は話が噛み合わない?
東工大生というと、話が噛み合わないんじゃないか?とか思われていることが割とあります。個人的には、これ自体は基本的に偏見だと思っています。外部の人と話すときには、一般の大学生に擬態して話をすることも、基本的にはできるはずです。確かに、流行りのものをあまり知らないとかはありますけど、理系の言葉ばっかり使う、みたいなことは基本的にはありません。
☆時々いるけど…
逆に、東工大の中では時々話がかみ合わないことがあります。理系の大学生であるという意味では同質的な環境ですが、2年生以降に受けている授業は専門によってかなり違います。つまり、自分の専門的には常識のような内容であったとしても、全学的に常識とは限らないわけです。
例えば、僕は大学に入ってから、化学の授業は1年生の教養としての4単位以外はとっていません。つまり、化学の知識に関しては、ほぼ高校生までで止まっているといっても過言ではありません。しかし、化学を専攻している人たちは、何十単位も化学の色々な授業を受けていることもあって、沢山の知識を得ているのでしょう。
そんな環境だと、東工大生ならみんな知ってると思っていた知識が「そんなことはない」となることもかなり多いのか、意外にも東工大の中のほうが通じない気がします。これは、「常識」であり、言うまでもないから飛ばすね、という発想が関係してそうです。
☆発達障害者の悩みの一つは話が通じないこと
発達障害者の悩みの一つに、話が通じないこと、が挙げられることがよくあります。実際、僕も同じような経験があります。発達障害のひと急に話が飛ぶことが要因な気がしています。これは、東工大生同士の会話で時々おこる、「常識」を共有しているという誤解からくる、無理な省略と似ているかもしれませんね。一般的な価値観が少し違う発達障害者。当然「常識」が違うわけです。そうすると、当然ですが、「常識」という前提条件が違ってくるので、会話が通じなくなります。これが要因になっている気がするのです。
発達障害者と話が噛み合わない、は当事者も周りの人も困りがちなことなので、相互に相手の「常識」を理解したり、前提条件を事前に説明することが大事な気がしますね。例えば、何本か出すのはOKとか言うと、何十本も案を出すとかあり得ます。これの対処としては、事前に回答は1人5本までみたいに言ったほうがいいですね。つまり、具体的で、明らかな絶対的な数字を使ってお願いするのは、「常識」に頼らないので分かりやすいわけですね。
ということで、今日は伝え方の話でした。都合の良い解釈のする余地をなくすための、文章の書き方が求められてる気がしますね。文章力とか国語力って、このあたりを指すことかもしれないなと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
