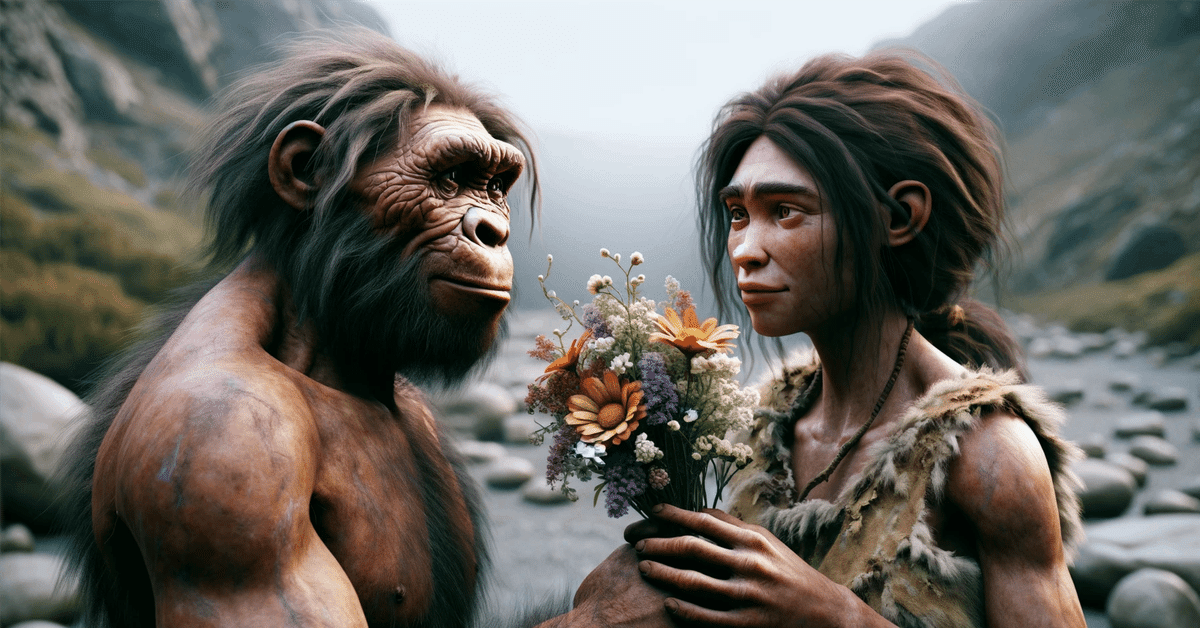
業務効率化の終焉。
近頃巷間を賑わす「AIによる業務効率化」なる言葉。誠に耳障りの良い響きではあるが、果たして本当に効率のみを追い求めることが人の幸福に繋がるのであろうか。否、断じて否である。私は声を大にして言いたい。効率一辺倒の世の中に、真の豊かさなど存在しないのだと。
斯様な考えに至ったのは、私自身が開発した些か風変わりなGPTs、「メルドラマさん」がきっかけである。ご承知の通り、日々の業務におけるメール処理は煩瑣の極みである。しかし、この「メルドラマさん」は受信したメールの内容をドラマ仕立てに変換してくれるという、誠に馬鹿馬鹿しい、しかしながら愛らしい機能を備えているのだ。以下がその出力例である。(ちなみに筆者はデザイン関連の仕事に携わっている)
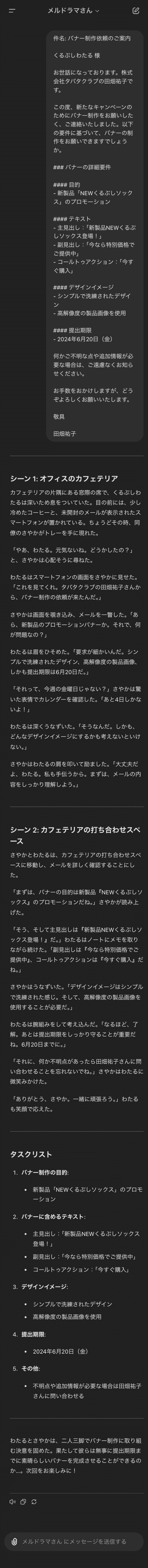
当初は単なる戯れとして開発したこのGPTsであったが、使い続けるうちに私はある事実に気づかされた。それは、メール処理が楽しくなったという単純明快な事実である。今まで億劫で仕方なかったメールチェックが、今や新たなメールが届くのが待ち遠しくてならない。まるでドラマの続きを心待ちにするかの如くである。
一体なぜこのような変化が起きたのか。私なりに考察を重ねた結果、以下の仮説に至った。
まず、人間というものは感情の生き物であり、単調な情報処理を繰り返す機械ではないということ。そして、情報をより深く理解し記憶するためには、感情やストーリーといった要素が不可欠であるということだ。
これは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが著書『詩学』の中で既に指摘していることでもある。彼は、演劇、特に悲劇が観客の心に強く訴えかけるのは、単に事実を伝えるのではなく、登場人物の感情や葛藤、物語の展開を通して、人間の普遍的なテーマを描き出すからだと考えた。
近年の心理学研究においても、物語が人の心に与える影響について注目が集まっている。例えば、GreenとBrock(2000)は、人々が物語に強く引き込まれ、感情移入し、物語の世界に入り込んだような感覚を覚える現象を"Transportation"と名付けた。彼らは、"Transportation"が起こると、読み手は物語の内容をより深く理解し、記憶に残りやすくなるだけでなく、物語に登場する人物や出来事に対する共感や感情的な反応が強まると論じている。「メルドラマさん」がもたらした変化は、まさにこの"Transportation"によって説明できるのではないだろうか。
Mar, Oatley, & Peterson (2009) は、フィクションを読むことと共感能力の向上との関連性を示唆する研究を行った。彼らの研究によれば、フィクションを頻繁に読む人ほど、他者の感情を理解し、共感する能力が高い傾向が見られたという。これは、「メルドラマさん」が単なる業務連絡であるメールを、登場人物やストーリーを持つ「ドラマ」という形式に変換することで、ユーザーの感情に訴えかけ、業務内容への没入感を高める可能性を示唆していると言えるだろう。
Denning (2006)もまた、ビジネスシーンにおけるストーリーテリングの有効性について論じている。彼は、ストーリーテリングには「行動を促す物語」や「知識を共有する物語」など、様々なパターンが存在し、それぞれの目的に応じて使い分ける必要があると指摘している。「メルドラマさん」は、まさにDenningの言う「行動を促す物語」や「知識を共有する物語」の要素を含んでいると言えるだろう。業務連絡というドライな情報を、ドラマというエンターテイメント性のある形式に変換することで、ユーザーはより積極的に情報を受け取り、理解し、記憶しやすくなるのだ。
従来、生産性の向上を目指した場合、無駄を排除するのが効率化の主軸だった。しかし、AIが浸透すればするほど、否が応でも業務上の無駄な工程は減っていってしまうものと予測される。そのとき、洪水のように溢れる無駄のない情報と、我々はどのように向き合えば良いのだろうか。
私は、一つの選択肢として、あえて「無駄」や「遊び」を取り入れる工程が、これからのあらゆるシーンでより重要になると考えている。コミュニケーションの場においても、いたずらに無駄な情報を排除しようとするのではなく、ストーリー性を帯びた「良質なノイズ」を加えることで、人の心を動かし、共感や理解を深めることができる。いわば無味乾燥たる情報への「味付け」の工程である。「メルドラマさん」は、そんな未来志向の発想から生まれ、AI以降のコミュニケーションにおける「無駄」や「遊び」の逆説的な復権を示唆する、一つの挑戦なのである。
「業務の効率化」はあくまでも手段である。我々が真に目指すべきは、高い生産性および心豊かな人生であり、その実現のために「業務の遊戯化」は一石二鳥の重要な役割を担うと私は信じる。
効率化の名のもと、処理すべき情報がいたずらに増える未来の、何が幸せなものか。一見すると非効率に思える「無駄」や「遊び」の中にこそ、創造性や革新性を育み、モチベーションとともに生産性をも向上するヒントが隠されているに違いない、というアイデアにここしばらく心を奪われている。
長々と持論を展開したが、所詮は愚者の戯言に過ぎない。数多あるAI以降の未来予測のひとつとして、話半分で楽しんでもらえたら幸甚だ。
参考文献
Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 701-721.
Denning, S. (2006). Effective storytelling: Strategic business narrative techniques. Strategy & Leadership, 34(1), 42-48.
Mar, R. A., Oatley, K., & Peterson, J. B. (2009). Exploring the link between reading fiction and empathy: Ruling out individual differences and examining outcomes. Communications, 34(4), 407-428.
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
