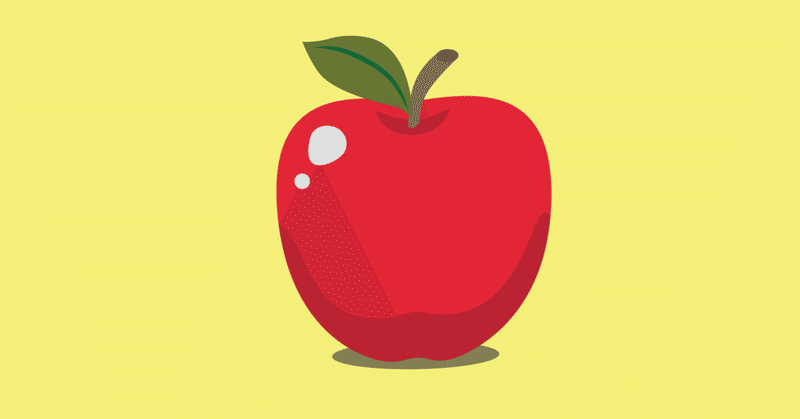
短編小説「男と子供とりんご」
とうとう食い詰めた男は、大道芸で金を稼ぐことを思いついた。元は都市に流れた貧農だ。たいそうな芸ができるわけもないが、この男は少々器用だったために、昔々、行商で見たお手玉くらいは、ぎこちないながらも何とか形にすることができた。
男は薪を二、三盗むと、それをナイフで削り出し、お手玉用の玉に仕立てた。とはいえ、球にする技術など持ち合わせないので、それは歪な形の玉になった。それが男にはりんごのように見えたので、今度は絵の具をくすねてきて、その木の玉を赤く塗った。すると、それは大きく甘いりんごに見えた。出来に満足した男は、早速、3つのりんごをぼろ布に包み、石畳の街角に立った。ひっくり返した帽子を地面に置くのも忘れずに。
初めはおっかなびっくり、徐々に調子よく、男はりんごをくるくると回した。ときどき取り落としてしまいそうになるのを何とか掴み、中断しながらも、日が暮れるまで回し続けた。しかし、蓋を開けてみれば、帽子には一ペンスも入らなかった。男は肩を落としたが、次の日も同じ街角に立った。
町は浮浪者で溢れていた。改革だか革命だか知らないが、あっという間に多くの人が貧困に突き落とされ、代わりに一握りの人間が大金持ちになった。男のいた田舎も同じだった。農民は突然、耕す土地を失い、食うにも困るようになり、働き口を探して都市へ流れた。
けれど、都市でも状況は変わらなかった。いや、目にする人間が多い分、都市のほうがひどくも見えた。この冬の一時だけで、男は煙突に詰まって死んだ煙突掃除夫《こども》を3人も見た。2人は窒息し、1人は誤ってつけられた火で、火あぶりになったのだった。そうでなくても人は飢え、盗み、殺していた。刑場は賑わいは増し、見物人が公開処刑に詰めかけた。絞首台で罪人がもがき、死んでいくのに、人々は熱狂した。
準備を終えると、男は昨日と同じように木のりんごを取り出し、くるくると回し始めた。しかし、やはり人々は足を止めることはおろか、コインを投げ込むこともしなかった。
もっとも男がお手玉だけでなく、もっとほかの芸ができれば、人も足を止めるのかもしれなかった。これはちょっと器用な男ができるくらいの簡単な芸。気の利いた口上もなしに、みすぼらしい男が淡々とりんごを回している——そんな見世物に金を払う余裕など、この町の人にあるはずもない。
人々が欲しいのは、もっと刺激的な何かだった。例えば、絞首台で人が死ぬような——。もし、あの公開処刑に見学料が必要ならば、人々はどんなことをしてでも金をかき集めただろう。盗みをし、殺しをし、例えそれが原因で自分が絞首台に吊されたとしても、まるで構わなかったかもしれない。そして、首に縄がかけられた瞬間、こう叫んだかもしれない。俺が死ぬところを見たいやつは、俺の棺桶にコインを投げろ、と。
しかし、幸か不幸か、男にできるのはお手玉だけだったので、彼はそれだけを根気よく続けた。手のりんごを投げては掴み、また投げては掴む——それを何十回、何百回と繰り返した。朝から何も食べていないので、次第に頭はぼんやりとし、うっかりりんごを掴み損ねそうになることもある。そんなときは気を取り直し、再びゆっくりとりんごを宙に放る。そんなことが続いたある日だった。男はふと、視線に気づいた。通りの向こうの路地から覗く、じっと男を見る視線。
そこにいるのは、まだ煙突掃除もできないような小さな子供だった。兄弟だろうか、2人いる。その2人が、男をじっと見つめている。
男は試しにりんごを放った。すると、二人の視線も宙へ向いた。高く投げると高いところへ、低く投げると低いところへ、面白いように二人の視線は上下する。
男はそれを喜んだ。こんな気持ちは、町へ来てから初めてのことだった。
生きることに精一杯の都会で、そこに人はたくさんいても、一人一人は孤独だった。誰もが他人を蹴落とそうとし、出し抜こうとし、盗み、殺す機会を狙っているのだ。そんな環境では、誰にも心は許せない。笑顔を見せるわけもない。それは小さな子供でも同じだった。
けれど、田舎で生まれた男は、貧しさの中でも心を許す相手を知っていた。それは雌犬のベラだった。臆病だったベラは番犬の役をせず、それに怒った父親に殴り殺されてしまったが、それでもベラのあの瞳は、男の心に残っていた。野原をひらひらと舞う蝶に飛びついていた、あの無邪気な喜びの光が。
その翌日から、男は街角に立つのが楽しみになった。あの2人の兄弟が、臆病なベラのように、路地から男を伺っている。お手玉を始めると、その視線が同じようにくるくると上下する。都会に生まれた子供なのだ。警戒心丸出しの顔つきで、決して近寄ってこようとしないのも、男にはなぜか好ましかった。
2人が自ら近づいてくるまで、男は素知らぬふりを続けると決めた。公開処刑帰りの、興奮した人々が通りを歩く。酔っ払い同士の喧嘩が始まり、野次馬が集まり、騒ぎに乗じて盗みを働く人がおり、貴族の馬車を引く馬が、糞をいくつも落としていく。それでも男の目に映るのは、路地の2人の兄弟だった。
ベラ、怖くないからこっちにおいで——時折、男は路地の二人を、本当にベラだと思うときがあった。そんなときは決まって朦朧として、立つのもやっとのときだった。大道芸を始めてから、男はろくにものを食べてはいなかった。少ない金もとうとう底をつき、店からは目をつけられて盗めなくなった。しかし、だからといって、働き口を探そうとは思わなかった。そもそも、それがないから食い詰めたのだし、だからこそ毎日街角に立っているのだ。
しかしそれも限界だった。とうとう男の手のひらから、りんごが一つ、転がり落ちた。男はそれを拾おうとしゃがみ込んだが、そのまま動けなくなってしまった。立ち上がることも出来ないほど、力は失われてしまったのだ。
それでもあの子たちのために——。男は力を振り絞り、りんごを拾おうと手を伸ばす。しかし、やはりだめだった。心臓の音が妙に大きく、息は荒く、懐に抱えたもう二つのりんごも、男の足元にころころと転がり出した。
と、そのときだった。霞む視界の向こうで、あの兄弟がこちらへ素早く走ってくるのが見えた。
男の目に、その姿はベラと重なった。やっと来てくれたのか——声にならない声を上げ、男は口角を上げようとした。ベラ、おいで。その温かい体を抱かせておくれ。
すると兄弟の手が、男のほうに伸びた。男もそちらに手を伸ばした。その指先が、いま触れ合おうとし——しかし、その小さな手は男の手をはね除けると、代わりに転がったりんごをかき集めた。
「早くっ、行くぞ」
兄弟は3つのりんごを抱えると、たちまち通りの向こうに走り去った。押された拍子に、地へと伏した男は、その小さな背中を見送った。
自分の大道芸が2人を楽しませていた——それは男の勘違いだった。そうではなく、悲しいかな、二人は男のりんごを見ていたのだった。おいしそうな赤いりんごを、いつかどうにかして盗んでやろうと、路地から狙っていたのだった。
石畳の埃を立たせ、男は泣くような息を漏らした。もちろん、泣けるわけがなかった。ここは都会、誰にも心を許してはいけない場所。あんな小さな兄弟にさえも警戒しなければならないのに、男はそれをすることなく、商売道具を盗まれたのだ。情けない、情けないが、そんな弱みすら、ここは見せてはいけない場所だ。
だから男は泣くのではなく、いまこそ笑うべきだった。あの馬鹿な盗人どもめ、あれが木でできたりんごとも知らず、腹を空かせて盗みやがったよ——。
笑えば、立ち上がることも出来ただろう。再び今度はしたたかに、都会で生きていけただろう。けれど、男は伏したまま、決して起きることはなかった。
赤く塗っただけの、歪な木の玉。それがりんごに見えるとは、どれだけ腹を空かせていたのか、ようやく手に入れたそれを囓り、どれだけ絶望を味わうのか。男の想像は遠くなり、やがて霞み、白く見えない果てへと消えていく。
伏した男の手の先へ、ぼろぼろの野良犬が小便をひっかけた。それをきっかけにして、空っぽの帽子を誰かが拾った。すり切れた靴を誰かが脱がし、夜には穴の開いたコートが消えた。朝には一つ増えた死体が、誰かの仕事を一つ増やした。誰かの手から誰かの手へと、りんご一つも買えないほどの、コインが数枚、移動した。
*
最後まで読んでくれてありがとうございます。よかったら「スキ」も押してくれると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
