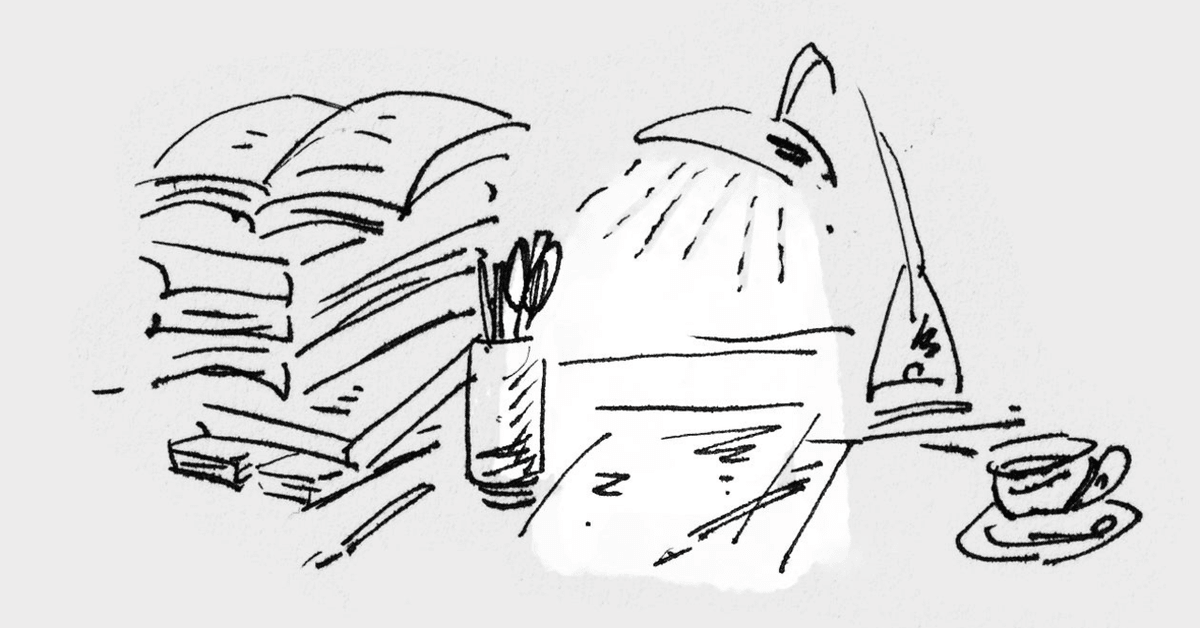
ライティングのキソ、丸わかり
こんにちは。フリーランスライターの黒木です。
今日は、ザザザっと(LayerX風に言えば、シュッと)ライティングの基本的なルールやお作法をまとめてみました。
媒体や会社ごとのルールもあるので、必ずしもこれらが正解という訳ではありません。ただ、一般的にライターや編集者が意識するポイントではあるので、参考までにご覧いただければ幸いです。
この記事は、こんな方におすすめです👇
ライターを志している方
駆け出してみたものの、基本的なルールがわからなくて困っている方
お仕事で文章を書くことが多く、文章のお作法を知りたい方
ライティングのルール
改行
媒体ごとにルールはあるものの、ウェブ記事なら2~4行に1度を目安に改行するのがベター。
改行したら、1行の空白行を入れて新たな行をスタート。スマホでの読みやすさも念頭に置くといいでしょう。
開く漢字
ライティングではひらく漢字(ひらがなで書く)と閉じる漢字(漢字で書く)があります。 開く漢字には一定のルールがあるので、覚えておきましょう!
補助動詞はひらく、動詞は閉じる:それを読んでください。 / その本を僕に下さい。
複合動詞の後半は開く(動詞が連なる場合、後半は開く):眠りつづける。 / 読みなおす。
副詞はひらく:もっとも~ / ほとんど~ / たとえば~
形式名詞はひらく、実質名詞はとじる:私のすきなことは運動だ / 事が起こってからでは遅い
いろんなウェブサイトで開く漢字がまとめられているので、それらを参考にするとよいと思います。
一文の長さ
一文一義の原則をできるだけ守りましょう。
一文の中に読点(、)は2つまでが読みやすいとされています。また一文は40字程度が目安です。
主語と目的語
日本語は主語や目的語を抜いても意味が成立しますが、省略しすぎると「これは何について言っているんだっけ?」と読者に伝わらず、誤解が生じる原因に。
「誰が」「何を」するかがわかりにくくなっていないかを常に見直し、必要に応じて主語や目的語を明記すると、より読みやすくなります。
主語と述語の関係
文章を書いていると途中で主語を忘れてしまうことがあるので、書き終わった後に「主語と述語は一致しているか」という観点でもう一度見返してみてください。(主述が不一致の文章が最近とても多くみられます!!!)
また、修飾語と被修飾語が離れていると文章がわかりづらいので、主語と述語、修飾語と被修飾語はできるだけ近づけると読みやすくなりますよ。
接続詞
接続詞が多いと文章が長くなり読みづらいため、使わなくても意味が伝わる場面では使わないようにしてみてください!
また、正しい接続詞を使えているか、書き終えたあと必ず見直すようにしましょう。
(ちなみに「なので」は本来は、正しい接続詞ではないので、記事上ではできるだけ使わないようにしましょう。「ですので」などに変えると◎です。ただし、インタビュー記事などの発話文の中で使うのはセーフです。)
特に、「順接の“が”」はほとんどの場合書き換えることが可能です。誤読の原因にもつながる使用法なので、極力使わないようにするのがベターです。
👇よくある例
先日ゴルフ大会がありましたが、そこで課長は次のように挨拶しました。
👇正しく書くと
先日のゴルフ大会で、課長は次のように挨拶しました。
こそあど言葉
「これ」「こちら」「この」「あの」「それ」「どの」といった「こそあど言葉」は誤読の原因となるため、できる限り使用を控えましょう。
言い換えられる単語やフレーズはないか、見直す際に気をつけてみてください。
約物
わかりやすくいうと、文章中の記号のこと。
「」→会話文、ドラマなどの一回のタイトルなど
『』→会話の中の会話、書面、映画などのタイトルなど
そのほかの括弧類は媒体ルールに沿って使用します。
最近多く見かけるのが、" ”ダブルクォーテーションマークがきちんと閉じていないケース。 (これを校正用語では「踊ってる」と言います)Google docsからの入稿で踊る現象がよく発生しているので、最後までよくよく見るようにしましょう。

これを見かけると編集者はちょっとテンションが下がります
また、三点リーダー(……)とダーシ(——)はふたつ重ねて使うのがルールです。
※三点リーダーはピリオド3つとは別物
※ダーシは全角ハイフンとは別物(辞書登録しておくのがおすすめです!)
文末の表現
同じ文末表現を使うと、文章のリズムが悪くなったり、繰り返しているような印象を受けて、読んでるときの違和感に繋がってしまいます。
同じ文末表現は連続して使わない、2回はギリギリOK、3回はNGと覚えておきましょう!
文末表現は「です」「ます」のほかにも、
過去形「でした」「ました」
体言止め
助詞で終わらせる「〜と。」
疑問形「〜でしょうか」
投げかけ「〜ですよね」
など、さまざまな表現があります。日頃から、いろんな記事の文末表現に目を配り、引き出しを作る意識を持っておくとよきです。
話し言葉
特にインタビューは書き起こしたままだと話し言葉が多くなり、カジュアルすぎる、稚拙な印象を受けてしまいます。
以下のような口語表現は文語表現に書き直すと良いでしょう。(もちろん、その人のキャラやメディアのカラーもあるので、適度に残すのは🙆♀️です)
〜って思いました→〜と思いました
〜だったんです→〜だったのです
だから〜→ですから
「〜という」の頻発
「という(こと)」は冗長表現になり、文章が間延びしたり、稚拙な印象になったりしてしまいます。
ほとんどの場合は使わなくても意味が伝わるので、できるだけ削ってみましょう!
文章の書き方
構成
よく使われる構成法は下記の2つ。迷ったら、このどちらかの型に当てはめると綺麗にロジックが通った文章になります。
PREP法
SDS法
PREP法
Point(要点)
Reason(理由)
Example(具体例)
Point(要点)
SDS法
summary (要点)
detail (詳細)
summary (要点)
読者をイメージする
どんな記事にも読者がいます。
書く前に「どんな人に読んでほしいか」を必ず想像し、「何を伝えるべきか」が明確にしましょう。
とりわけ、インタビューは一方的な「伝えるだけの文章」になりがちです。インタビュアーが伝えたいことよりも、まずは「読者が読みたいこと」を意識するようにしてください。
リード文
リード文は読者が「この記事を読みたい!」とワクワクするような内容にしてみましょう。
この記事を読みたい人はどんな人で、どんな情報を求めているのでしょうか?
その人に対してこの記事はどんな情報を与えられるのでしょうか?
リード文で読者に対する訴求ができていないと記事の離脱が増えてしまうので、一番気合を入れて書いてみてください。
記事のゴール
記事には必ずゴールが存在します。
記事のゴール=読者に行動を起こしてもらう(またはこんな気持ちにする)
です。
記事のゴールを決めないと、記事ではなく「ただの書き散らし」になってしまい、「結局何が言いたいのかわからない文章」で終わってしまいます。
記事を書く場合には、まずゴールを設定し、それを実現するために必要な要素は何かを因数分解し、執筆してみてください。
読者に持って帰ってもらいたい「お土産」は何ですか?
見出し(SEO記事)
見出し1が複数使われると、SEOで正しく評価がされにくくなってしましまいます。
👇正しい見出しの順序
見出し2(h2)
∟見出し3(h3)
∟見出し4(h4)
∟見出し4(h4)
最後に
「文章を書く」ことはある意味誰にでもできることです。ただし、「文章が書けること」と「読みやすく・伝わる文章が書けること」の間には大きな隔たりがあります。
今回お伝えしたライティングのお作法は、その隔たりを少しだけ埋めてくれる役割があります。
楽しく書いているのだから、ルールなんてわずらわしい!
そういう考えもよくわかりますし、私も仕事以外で書く文章はルールから逸脱している場合も多いです。
ただ、何かしらオフィシャルな文章を書かなければならないときには、これらのお作法が役に立つかもしれません。頭の片隅のさらに隅のほうに、これらを覚えておいてもらえたら、編集者冥利に尽きます。
楽しい、ライティングライフを!
この記事が参加している募集
ゆるゆると更新しているnoteですが、もしサポートしてもいいなと思っていただけたらポチッとお願いいたします。いただいたお気持ちとサポートは愛犬のおやつと私の元気になります🍪
