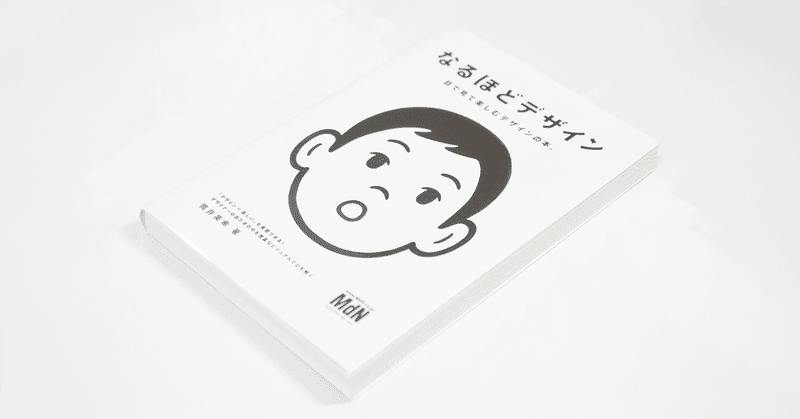
【読書備忘録#5】デザイナーの脳内を見てみませんか?
なるほどデザイン 目で見て楽しむデザインの本 を読んで 筒井美希
普段デザインに携わることが少ない人でも、世の中にはデザインがあふれかえっています。電車の中の広告、スマートフォンのバナー、Youtubeの動画、デザインはいたるところで使われています。そんな日常見かけるデザインを作るデザイナーな普段どんなことを考えているかを覗いてみましょう。
期間:2021.4.6~2021.4.8
時間:120min
著者:筒井美希
出版:2015.8.1
評価(5点満点)
おすすめ度:4点
読みやすさ:5点
タメになる:3.5点
おもしろさ:3.5点
対象者:大学生、クリエイターなど、これからデザインをしたい人
内容
デザインをする前に
まずデザインをすぐ行わないようにしましょう。最初に何のためにデザインするのかを考えましょう。
デザインには正解がないので、製作者のしっかりとした意図があれば良いとされます。
情報を整理する
制作する際にはどのような目的で制作するのかが大事になります。どうやって整理していくのか、順序を見ていきましょう。
1.どんな人に
・年齢、性別
・どんな知識レベルの人か
・どういう状況か(電車か、スマホか、歩いているか)
・ライフスタイル
・関心の高さ(専門的か、初心者か)
2.何を
・作り方
・バリエーション
・おいしさ
・美しさ
・品質
3.なぜ
・好きになってほしい
・楽しんでほしい
・理解してほしい
・正確に伝えたい
・商品を売りたい
4.いつ、どこで
・本屋
・コンビニ
・電車の広告
・巻頭、巻末
デザインの手順
STEP 0 図解とラフ
載せる情報を図で表し、優先順位を決めましょう。
ラフを作ることで、これからの迷いを減らします。黒一色でやってみるのが◎
STEP 1 方向性を決める
表現の方向性と構造の方向性を決めましょう。
STEP 2 骨格をつくる
タイトルをリードの配置、バランスの良さ、コラムの位置などをどこに何を置くかを考えましょう。ここで大事になるのが、近接、整列、反復、対比、強弱です。
STEP 3 キャラを立たせる
文字を中央揃えにしてみたり、文字の大きさを変えてみたり、行間や字間、フォントを変更してみましょう。
STEP 4 足し算と引き算
モチーフを追加してみたり、太字に、色の変更、背景や紙の質感を変えてみましょう。また、くどい表現になっているなと感じたら、逆にシンプルにしてみましょう。
STEP 5 ブラッシュアップ
余白の追加、文字の加工、図の追加、罫線の省略等今まで気になっていたことを一度俯瞰してみることで、少しずつ直していきましょう。
その時々で、目上の人や友人、クライアントに見せることで、アドバイスを逐一もらうことでより洗練されたものを作ることができます。
→自分では気づけない視点の意見をもらうことができます。
七つの道具
デザイナーには必須の七つの道具があります。これらを持つことでデザインがぐっと良くなります。常に意識して自分のものさしを意識しましょう。
TOOL 1 ダイジ度天秤
伝えたい内容、情報に優先順位をつけることで、強調する部分、そうでない部分を変えましょう。
TOOL 2 スポットライト
主役が埋もれないように見た目で差をつけましょう。これには一度物理的に離れて俯瞰してみることで、ちゃんと目立って見えるかを確認しましょう。色の足し算、引き算、下地を作ったり、図を作ったり。サイズ=重要度、余白をあえて揃えないなど様々です。
TOOL 3 擬人化力
書体を声色に変えてみましょう。文字組(行間の広さなど)を話したかに変えてみましょう。配置を人々に変えてみたり、あしたいを女性に例えてみたり、色を時代に例えてみましょう。
どういうイメージにしたいかで、採用する文字を決めましょう。
TOOL 4 連想力
デザインに必要なカタチ、フォント、色、質感を伝えたい内容やテーマから考えましょう。言葉の連想からイメージや写真の連想に変換してみましょう。
TOOL 5 翻訳機
言 語:言葉、文章などの文字による表現
非言語:写真、図番などのビジュアル表現
→バランスとメリット、デメリットを考えましょう。
TOOL 6 虫眼鏡
建築に神は細部に宿るという言葉があります。大きな路線変更をしない前提で、細かい部分に修正を加えていきましょう。
TOOL 7 愛
内容への愛、届ける相手への愛に寄り添ったデザインが良いデザインです。
文字組の基本
ここからはデザインの基本構成になります。脳内というよりこれからデザインをやるならこうしましょうという感じです。
行:一行で最大40~50文字、最小で13~15文字
行間:文字サイズの50~75%
字間:0が基本
文字サイズ:幼児20~32Q(14~22pt)、小学生16~24Q(11~17pt)、青年10~13Q(7~9pt)、幼児13~16Q(9~11pt)
デザインで差をつける
デザインにはすべて同じものを使ってはいけません。その中でそれぞれに差をつけることで色々幅広い表現を身に付けましょう。
1.字間
揃える:読みやすく美しく見える
空ける:読みづらく差別化できる
2.タイトルは主役感
最初に目が行くところで、一番大きく、文字量は少なく、差別化できるようなデザインにしましょう。
3.リードはイントロ感
タイトル後で本文の前で、やや大きめ、タイトルより文字量は多くして、改行しましょう。
4.本文は下地感
まとまった文量で、箱組で無個性、12~16Qくらいが妥当です。
5.キャプションは黒子感
目立たず、小さく、視認性の高く、コンパクトにしましょう。
グラフの使い方
グラフはそれぞれ使い道や使い方を誤ると全く別のように受け取ってしまいます。それぞれの表現方法を見極め、使い方や表現できるものを知りましょう。
「%」割合を表現→円グラフ
「≧」項目の大小を表現→横棒グラフ
「⇨」時系列の増減を表現→縦棒グラフ
「◯」分布を表現→折れ線グラフ
最後に
デザイナーって色々なことを考えているんですね。今まで建築の中でデザインをすることはありましたが、こんな感じで考えることはあまりなかったので、一から学ぶことができて良かったなと思います。
あとこれは見て楽しむものなので、文字データだけだと味気ないですね。ぜひ書籍を手に取ってみていただきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
