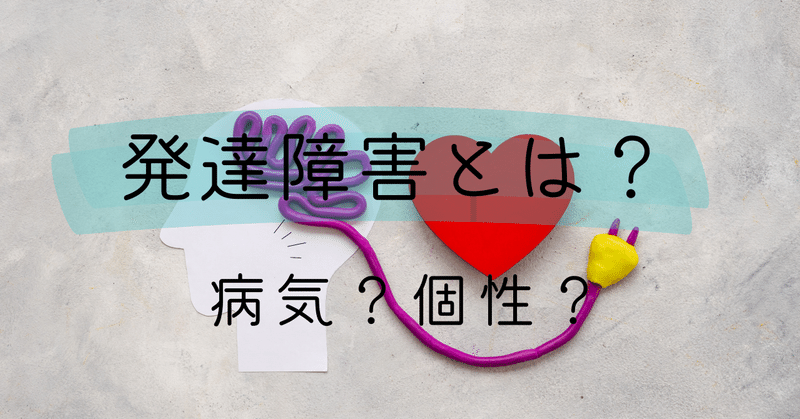
発達障害とは?
発達障害とは?わかりやすく解説
発達障害は、生まれつき脳の機能に違いがあるために、日常生活や学習に困難を感じる障害です。
近年、発達障害に関する理解が進み、多くの方が診断を受け、支援を受けるようになっています。
しかし、発達障害は複雑な障害であり、人によって症状や程度は様々です。
〇〇障害とは?現代社会における理解と意味
ちなみに〇〇障害は、現代社会において様々な議論を呼んでいる障害の一つです。
1. 〇〇障害とは何か?
「障害」とは、一体どういったものなのでしょう?
障害者基本法では、障害者を「身体障害、 知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。) がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受 ける状態にあるものをいう。」と定めています。症状の程度は人によって様々であり、軽度から重度まであります。
2. 〇〇障害の歴史と変化
障害に対する理解と認識は、時代とともに大きく変化してきました。
1. 古代・中世:排除と隔離
古代・中世の社会において、障害を持つ人々は、しばしば社会から排除され、隔離される対象とされました。
身体障害: 身体的機能に制限がある人は、労働力として認められず、乞食や奴隷などの扱いを受けることが多かった。
精神障害: 精神的な問題を抱える人は、魔女や悪魔に取り憑かれたとされ、迫害の対象となることもありました。
知的障害: 知的発達に遅れがある人は、社会の役に立たないとされ、家族から捨てられたり、施設に隔離されたりすることがありました。
2. 近代:医学モデルの登場
18世紀以降、医学的な視点から障害を捉える医学モデルが主流となりました。
障害は、医学的に診断・治療されるべき病状とみなされるようになりました。
障害を持つ人は、治療やリハビリテーションによって「正常」な状態に戻ることが期待されました。
しかし、医学モデルは、障害を個人の問題として捉え、社会的な要因を軽視する傾向がありました。
3. 現代:社会モデルと権利保障
20世紀後半以降、障害を社会的な問題として捉える社会モデルが提唱されるようになりました。
障害は、個人の身体的・精神的特性ではなく、社会が作り出したバリアによって生じるものであると主張されました。
障害を持つ人が社会で平等に参加するためには、社会のバリアを取り除くことが重要であると強調されました。
社会モデルに基づき、障害者権利条約などの国際的な枠組みが整備され、障害者の権利保障が進められています。
発達障害の特徴
発達障害には、主に以下の3つの特徴があります。
1. 脳機能の違い
発達障害は、脳の様々な機能に違いがあるために起こります。
具体的には、情報処理能力、運動機能、コミュニケーション能力、社会性などに違いが生じる可能性があります。
2. 発達遅滞
発達障害は、発達の過程で遅れが生じる場合が多いです。
例えば、言語の発達や運動の発達が遅れたり、社会的なルールや規範を理解するのが難しいなどの症状がみられます。
3. 一生続く障害
発達障害は、成長とともに症状が改善する場合もありますが、基本的には一生続く障害です。
しかし、適切な支援を受けることで、症状をコントロールし、社会生活を送ることが可能になります。
発達障害の種類
発達障害は、大きく以下の3種類に分けられます。
1. 自閉スペクトラム障害 (ASD)
ASDは、コミュニケーションや社会的な交流、想像力などに困難を感じる障害です。
ASDには、アスペルガー症候群、小児自閉症、非定型自閉症などが含まれます。
2. 注意欠如・多動性障害 (ADHD)
ADHDは、不注意、多動性、衝動性などの症状がみられる障害です。
ADHDは、集中力が続かなかったり、じっとしていられなかったり、思いついたことをすぐに口にしてしまったりするなどの症状が現れます。
3. 学習障害 (LD)
LDは、読む、書く、計算などの学習に困難を感じる障害です。
LDには、ディスレクシア、ディスカルキュリア、ディスグラフィアなどが含まれます。
発達障害の原因
発達障害の原因は、まだ完全には解明されていません。
しかし、遺伝的な要因と環境的な要因が複合的に関わっていると考えられています。
遺伝的な要因
発達障害は、家族内に発達障害を持つ人がいる場合に発症しやすい傾向があります。
これは、発達障害に関わる遺伝子が存在する可能性を示唆しています。
環境的な要因
妊娠中や出産時のトラブル、早産、低出生体重、脳への感染症などが、発達障害の発症リスクを高める可能性があります。
発達障害の診断
発達障害の診断は、医師や心理士などの専門家による問診や検査に基づいて行われます。
問診では、子どもの様子や発達歴などを詳しく聞き取ります。
検査には、知能検査、発達検査、行動観察などがあります。
発達障害の支援
発達障害には、様々な支援があります。
主な支援内容は次のとおりです。
療育: 専門家による個別指導やグループ指導
教育支援: 特別支援学級や通級指導教室での指導
医療: 薬物療法や心理療法
生活支援: 生活訓練や就労支援
発達障害と社会
発達障害は、社会生活を送る上で様々な困難を伴います。
しかし、適切な支援を受けることで、症状をコントロールし、社会生活を送ることが可能です。
近年、発達障害に関する理解が進み、社会のバリアフリー化も進んでいます。
発達障害を持つ人が、自分の能力を最大限に発揮し、社会の一員として活躍できるよう、社会全体で支援していくことが大切です。
まとめ
発達障害は、複雑な障害であり、人によって症状や程度は様々です。
しかし、適切な理解と支援を受けることで、発達障害を持つ人は、社会生活を送ることが可能になります。
発達障害について正しく理解し、発達障害を持つ人が社会の一員として活躍できるよう、社会全体で取り組んでいくことが大切です。
また今度「発達障害」の詳しい解説などもまとめたいなと思いますので、よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
