
Biotechビジネスアイデア創出の基礎-後半
前半では研究成果からビジネスアイデアにつなげる手法と、臨床関連の研究成果を実用化する前提で、技術タイプ別によくあるパターンとその解決の可能性を提示した。後半では基礎医学の研究成果実用化について、同様に技術タイプ別に実用化に向けてよくあるパターンと考えるべきポイントを述べる。
Biotech製品企画のシナリオー基礎医学研究者編
iPSC、siRNA、ゲノム編集などに代表される細胞の持つ能力の新発見の場合
筆者はここ10年ほど京都大学で仕事をしているので、この手の話はかなり現実味があるので、できるだけ特定のケースに寄り過ぎないように書く。まず、トップジャーナルに掲載される研究成果に寄せられる期待と、実用化の可能性は必ずしも一致しないことを意識してほしい。小さな発見でも非常に重要な技術は市場を席巻するし、それぞれの技術に合わせた対応が必要だ。この手の大きな新発見ではその時点で想定しうる未来と、それより大きな未来の両方を想定した議論が必要になる。例えばゲノム編集技術のときには論文発表前後にUCバークレーとBroad Instituteの両陣営から数十の特許が出願されており、当初から投資と実用化のチーム体制が組まれていたようだ。ただこの時点ではおそらく対象疾患に関する精緻な分析や市場予測はされていなかったのだと思われる。これはこの論文が発表された2012年以降の米国のアカデミアとTop tier VCの戦略の流れの中でエポックメイキングなケースだったかもしれないが、数名のトップサイエンティストが認めた技術については、連携しているVCが一気に関連する技術全体を囲い込み、アプリケーションを開発するためにありとあらゆる関連技術を抑えにかかっている。これは意外に知られていないが、編集のターゲットとなる疾患関連遺伝子や、地球上すべての生物のゲノム編集関連現象の探索に至るまでその構想は及んでおり、Juno TherapeuticsやMammoth Bioscienceと言うスタートアップとしてそれぞれ事業化されている。
さて、ここまで大きな事業化の計画は現実的には現状の日本の創薬エコシステムでは資金的にも人員的にも不可能だ。その場合の対策方法は2つ考えられる。一つはゲノム編集などを扱った西海岸、東海岸のエコシステムに持ち込むことだ。これには現地の研究者だけでなく、VCを始めエコシステムのインサイダーの協力が不可欠となる。2つ目は、現実的に日本の資金力で可能な特許出願だけを行い、論文発表で出す情報とそれ以外を緻密に使い分けて、自社内でプラットフォーム技術として囲い込むというやり方だ。当然同時並行で治療薬として大きなインパクトをもつ製品開発をメインで進める。裏では人脈の総力を尽くして日本の製薬企業か、場合によってはライフサイエンスへ参入を企図している他分野の企業に支援を求め、将来的な新規事業としてJVを提案する。
実際には最初の特許出願という早期の段階でこれほど大きな動きは簡単ではないし、それほどわかりやすい研究成果も稀だ。できればエンジェル投資家のバックアップのもとで、筆者と同様、あるいは米国ベースのプレイヤーが開発戦略を立てることが望ましい。

mRNAワクチンで実用化された核酸・タンパク質など生体分子の制御技術の場合
細胞の中や細胞間での生体分子の輸送(トラフィック)についての研究は基礎研究の中でも分子イメージングと高機能の顕微鏡の普及で90年代後半から急速に進展した研究分野だ。この手法は当初タンパク質の研究が牽引し、一分子イメージング技術までに発展した。一方で分子を精緻に制御する技術は細胞内がこれまでにないほどのダイナミクスを持っており、これまで機能を持たないと思われていたRNA配列にも注目が集まるようになっている。これらの技術の一端はmRNAワクチンとして日の目を浴びたものの、その本領を発揮するにはまだ夜明け前という状況が続いている。これらを医薬品として開発するには、規制も整っておらず、投資家を説得するための十分なコンセンサスが十分整っていない。これについては明確なガイドは提供できないが、研究向けのツールを提供しつつ、他社に先んじてこの分野に踏み出す先行者利益を追求するモデルが考えられる。2000年代にクレイグベンターがセレラジェノミクスで行った、ヒトゲノム計画とは独立してゲノム情報を解析した戦略だ。彼らは莫大なコストをかけてデータベースを作り、製薬企業から高額な研究費を得た(その後、薬になったかどうかはともかく)。見せ球としての治療用製品の開発も有効と思われるが、現実的には自社だけで全く新規のモダリティーのINDのためにFDAと交渉するのはかなりタフだ。場合によっては競合へのライセンス(あるいはクロスライセンス)を複数行い、一つの新しいモダリティを育てる戦略を保つ必要があるかもしれない。
今回は新規の遺伝子治療用のウイルス・ベクター技術にはあまり触れないが、DDS(薬剤送達技術)として重要であり、コンセプトとしては近い。
細胞周期、細胞分裂研究などをがベースにある、がんや細胞分化に関わる発見
この手の技術は非常に悩ましい。イメージング技術の発達でビジュアルに訴えるプレゼンがあるので一見すると魅力的な研究成果だが、新しい発見であっても既に治療薬が存在している疾患も多くあったりする(実際、その手の薬剤を使って実証実験をしていたりする)。根源的な生物学的な発見は治療法を開発するには一般的すぎるか、本気で既存薬剤を覆す新薬として開発するには大規模な臨床試験が必要となる。下手をすると1000億円規模での資金調達が必要だ。なので、論文の際に広げた風呂敷を少し小さくして、アンメットニーズの大きい疾患における治療法開発のターゲットとして検討をし直してみることを考えて欲しい。その際には当然論文で実施した動物実験データが使えないこともあり得るし、研究者の専門から遠い疾患領域となることも十分考えられる。その場合はVC側が研究体制を準備するか、あるいは別のビジネスモデルで考え直すことになる。
良くある別の応用例としては、がんをその性質で見分けることができるので診断技術に使うとか、新しいコンセプトの医療機器との組み合わせで治療を行うと言う形式の事業化だ。いずれも可能性はあるが、広く普及するには臨床現場での標準治療のフローに採用される必要があり、事業戦略は簡単ではない。安易に試薬や研究用キットとしての事業化をしても、売上は数億円規模までしか見込めないことから事業規模の拡大は簡単ではない。これも案件次第になるが、複数の特許を組み合わせて独自のプラットフォームを構築し、VC主体の創薬スタートアップの一部として実用化する方向性が期待される。
細胞研究、プロテオミクス研究からの酵素阻害剤・活性化剤、タンパク質分解促進剤(PROTACなど)の場合
キナーゼ阻害剤、その後はGPCR阻害剤などとして分子標的医薬品が市場を席巻したが、2000年代からユビキチンや細胞内分子の品質管理機構など、研究分野のトレンドにあわせていくつか新しいコンセプトの低分子や中分子化合物が出てきている。これは比較的製薬企業も得意な分野であり、学会などでも海外の事例も含めてネタになりやすい。最初に同定した分子を虎の子の一品として後生大事に開発するのではなく、論文用の見せ球の化合物で研究発表は行いつつ、裏では新しいコンセプトのパイプラインを複数貯めて、非臨床試験は外注ベースで突破して治験に進んでほしい。低分子医薬品であれば製薬企業OBでもまだ対応できるMedicianal Chemistの雇用も期待できるので、流行っている今のうちにサクッと進めてほしい。

細胞研究からの受容体、チャネル・トランスポーター阻害剤の場合
受容体については細胞外からの刺激を受けて細胞内シグナル伝達に関与する分子や、チャネル受容体があるが、ここでは低分子医薬品を想定して阻害剤に触れる。チャネル・トランスポーターについてもイオンなどの分子、特定のアミノ酸、ミトコンドリアやNPCなどのタンパク質輸送に至るまでいくつかパターンがある。いずれも比較的Conventionalな創薬といえるので、事業計画上ではいかにして「製薬企業ができないスピード」もしくは「製薬企業は挑まないリスクを超える」という差別化が必要になる。また、これらのモダリティは安全性試験に関する技術と関連することも多い。心毒性の指標であるhERGはカリウムチャネルだし、ABCトランスポーターは薬物動態研究でも重要だ。ただこの手の事例の場合では研究者が製薬企業の探索研究やADME-Tox、PK/PDに土地勘があれば比較的容易に製品設計ができるのだが、多くの基礎研究者はターゲットとしてのチャネル・トランスポーターと、その後の非臨床試験項目としてのそれらの試験の位置づけの違いを理解するまで時間がかかる。後者のほうが明らかに定常的な収入は見込めるものの、事業形態が全く異なるので、できれば新薬の開発に集中するか、上述したように別の技術と合わせ技で複数の創薬パイプラインを構成することをおすすめする。
あとは… セレンディピティを実現するまでの我慢
ちなみにだが、筆者の元ボスであるDaria Mochly-Rosenが最初に作ったKAI Pharmaceuticalsはエテルカルセチド塩酸塩というペプチド配列を基盤としたカルシウムチャネル阻害剤を実用化した。我々のStanfordのラボはペプチド創薬について研究はしていたが、カルシウムチャネルと言うターゲットは事業化後にスタートアップ側で苦肉の策で見つけ出したターゲットだ。彼らが独自に起死回生の策としてピボットした結果、成功につながっている。我々の大学のラボの中でそれを見つけても大して興味を持たなかったと思うし、発見が遅すぎたら会社の寿命が尽きていたかもしれない。タイミングとチーム構成いずれもマッチしたがゆえに実現したセレンディピティと言える。
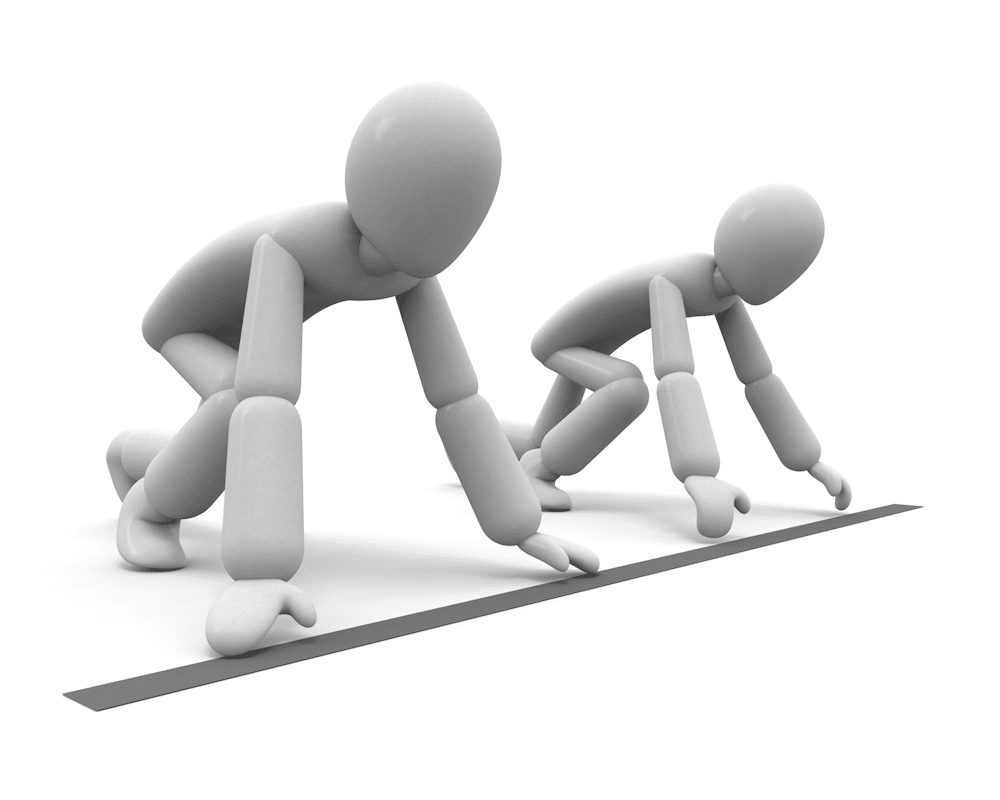
練習問題を解いて!
ここまで2回に分けて医学研究成果がBiotech製品として事業化に至る道筋を検討してきた。筆者の個人的な経験に完全に依存しているが、Stanford SPARKとの活動で得た知見、国内で合計1000回を超える支援セッションを通じて得た経験を元にしているので、少なくとも業界全体の3-4割はカバーできていると思うし、これらのシナリオを元にすれば残りの6割程度のケースでも十分に参考になると思う。この分野はとにかく情報がないし、セミナーで語れる成功事例はあと付けで参考にするには解像度が低すぎることが多い。これから事業計画を考える人には、ぜひこれらの文章を参考に練習問題をまず取り組んでみて、それから自分の事業計画を考えてみてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
